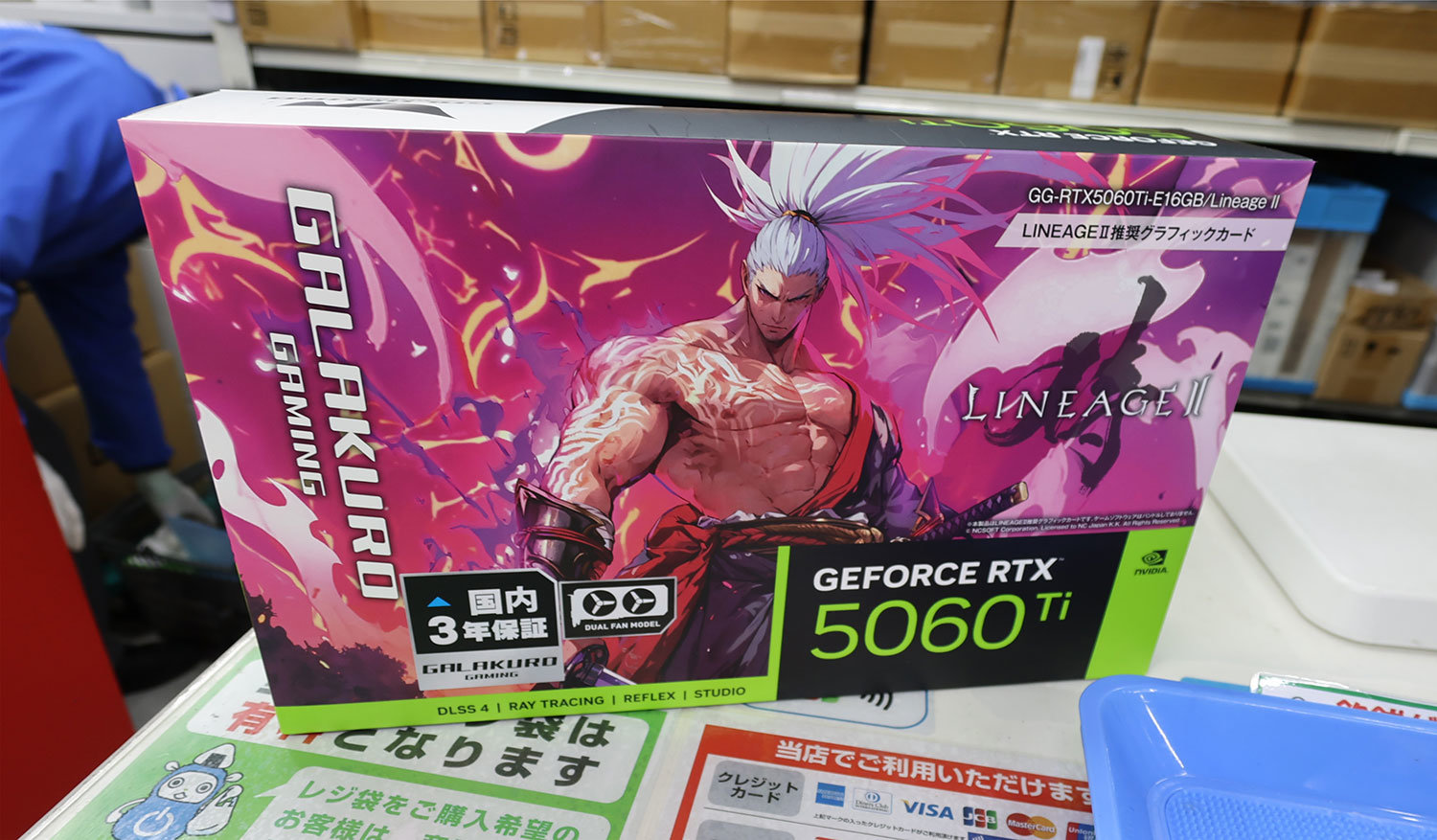「3Dプリンターのオープンソース設計」が中国企業によって勝手に特許申請されて業界全体が危機に陥っているという指摘

2009年から3Dプリンターの設計と構築を行っているエンジニアのヨゼフ・プルーシャ氏が、自身がオープンソースとして公開したハードウェア設計を無断で特許として承認されたことで、業界の未来が危ぶまれると指摘しています。
Open hardware desktop 3D printing is dead - you just don't know it yet | Josef Prusa / 3D printing
https://www.josefprusa.com/articles/open-hardware-in-3d-printing-is-dead/ プルーシャ氏によると、2016年にオープンソースとして公開した多色印刷ユニット(MMU)の設計がそっくりそのままコピーされたとのこと。この設計は中国とドイツで実用新案として承認されており、さらにアメリカでも特許出願されているそうです。プルーシャ氏は、2020年頃から中国企業による3Dプリンティング関連の特許出願が爆発的に増加したと指摘しています。プルーシャ氏が示したデータによると、業界で著名なわずか4社だけで、2019年には合計40件だった特許出願が、2022年には650件にまで急増しているとのこと。
この背景には、中国政府が3Dプリンティングを「戦略的産業」と位置づけ、「スーパー減税」と呼ばれる優遇措置を導入したことがあります。この制度では、研究開発費の200%が税控除の対象となり、その適用を受けるための「革新性の証明」として、承認される必要すらない特許出願が利用されているのです。その結果、既存のオープンソース技術や、ごく些細な改良を加えただけのアイデアが、有効性を十分に審査されることなく次々と特許として出願される「特許スパム」ともいえる状況が生まれています。 これに対して、「すでに公開されている技術なのだから、特許は無効にできるはずだ」という意見もありますが、プルーシャ氏は「現実はそんなに甘くない」と否定しています。
最大の問題は、特許に対抗するための圧倒的なコストの差です。中国での特許出願費用がわずか125ドル(約1万9000円)であるのに対し、アメリカやEUでその特許を無効化しようとすれば、簡単なケースでも約1万2000ドル(約180万円)、複雑な場合はその数倍の費用がかかります。一度承認されてしまえば、異議申し立てを始めるだけで7万5000ドル(約1100万円)以上を要することもあります。 また、たとえ有効な先行技術を持っていても、特許が存在する限り、企業は「侵害」を理由に製品の輸入や販売を差し止められる可能性があります。これを覆すには数百万ドル規模の費用と長い年月をかけた法廷闘争が必要となり、その間ビジネスは完全に停止してしまいます。このような訴訟リスクを前にすれば、メーカーがオープンソースハードウェアの製造や販売をためらうのは当然のことといえます。
こうした危機に対し、プルーシャ氏は特許出願を監視するチームを立ち上げ、コミュニティを守るための新たなライセンスを模索するなどの対策を進めていますが、この問題が3Dプリンティング業界に限ったものではないと強く警告。プルーシャ氏は「自分の専門分野周辺の特許出願に注意を払うようにしてください。後から対処するよりも、今行動を起こす方が比較にならないほど容易なのですから」と述べました。
プルーシャ氏の訴えに対して、ソーシャルニュースサイトのHackerNewsにもさまざまな意見が寄せられています。
ユーザーのsimpaticoder氏は「ここでの本当の問題は、本来あるべきではないのに、知的財産の所有が資本集約的になってしまっていることだ。このせいでオープンソースやコミュニティ主導の知的財産は著しく保護されず、資本を持つ者が一方的な捕食者となっている」と指摘し、司法制度全体のコスト問題を提起しました。また、AlexandrB氏は「欧米の特許を喜んで無視することを許容している中国での特許を真剣なものとして扱うのは馬鹿げています。この非対称性が中国企業に明らかな優位性をもたらしています」と述べ、国際的なIP制度の不均衡が問題であると論じています。
一方で、議論は3Dプリンターのユーザー層の変化にも及んでいます。RepRapプロジェクトの初期からの参加者であるCcecil氏はコミュニティの歴史を振り返り、「RepRapプロジェクトの真の価値は、プリンターを自作し改良するプロセスそのものにあったが、『既製品を買った方が良い』という風潮でその文化は停滞してしまった」と指摘。LeifCarrotson氏は、多くのユーザーの視点から「芸術家やエンジニアである多くのユーザーはプリンターの仕組みに興味はなく、単に『動作するツール』を求めているため、信頼性の高い市販品を選ぶのは合理的」と述べました。自作と市販の両方を経験したAurornis氏は、実用的な観点から「すぐに印刷を始めたい人には市販品の方がはるかに簡単で、プリンターのメンテナンスではなく本来の設計や印刷に集中できる」と語っています。
一方、一部のユーザーはプルーシャ氏の開発するプリンターが1000ドル(約15万円)と高額であることを指摘し、中国による不正な特許という話題は市場における敗北の言い訳に過ぎないという見方もあります。bdcravens氏は「かつては非中国製の方が高品質という固定観念が根強く、高い価格でも喜んで買っていました。しかし、3Dプリンティングをはじめとする業界で、その障壁は崩れつつあります。もちろん、政府の支援は不公平な価格優位性につながる可能性がありますが、プルーシャ氏の開発するプリンターよりも安価なBambu Lab A1は依然として性能面では優位性を維持しています」とコメントしました。
・関連記事 Nintendo Switch 2最大の問題を3Dプリンターを使って解決した話 - GIGAZINE
3Dプリンター自作銃「ゴーストガン」はどこまで進化したのか? - GIGAZINE
旧式の軍用機に「3Dプリンターで作った板」を接着剤で貼り付けるだけで年間22億円の燃料代が節約できることが判明 - GIGAZINE
切り餅を一瞬で「かがみ餅」にできる「かがみ餅アダプター」を実際に3Dプリンターで作ってみた - GIGAZINE
自宅用レーザーカッターを業務用レベル出力&10分の1の価格で実現した「Smart Laser CO2」を組み立てて使ってみた - GIGAZINE