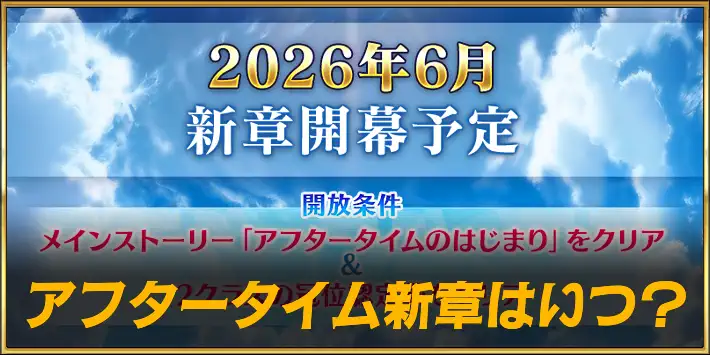AIの使用OKなクラスとNGなクラスで学習成果、比べてみた。意外な結果に

これなら学校でもAI使用を許可できるかも?
AIを使うべきか、それとも使わざるべきか。これは現代の学生と教育者全員が直面する問いかもしれません。
ChatGPTなどのツールを授業に取り入れることの是非について議論が続くなか、実際に経済学の学生を対象に実験が行なわれたところ、驚くべき結果が出てきました。
実際のクラスで実験
マサチューセッツ大学アマースト校の教授陣が、3、4年生向けの独占禁止法に関する経済学の授業を2クラス開講し、AIを使用するクラスと使用しないクラスの学習成果を比較しました。
両クラスにて、講義内容、課題、そしてノートやテクノロジー使用禁止という同じ条件下で筆記試験を行なったところ、生成AIを構造的に利用することにより、学生の学習意欲と自信が向上。一方で、試験の成績には影響しなかったのだとか。
研究チームが学術誌Social Science Research Networkに発表した論文では、「結果はシンプルです。AIの使用を許可し、段階的に活用させても、この授業では試験の点数は上がりませんでした。しかし、この取り組みは学生の学び方や学習への感じ方を大きく変えました」と記されています。
意外とポジティブな影響
研究では、一方のクラスにChatGPTのような生成AIツールを使用することを推奨し、AIの使い方に関するガイドラインが与えられました。もう一方のクラスではAIの使用を禁じ、その代わりにAIを使わない勉強方法についての指導・助言がなされました。
両クラスを担当したChristian Rojas教授と共同研究者たちによれば、AIを使うことが許された学生たちのほうが授業への参加意欲が高かったのだそう。
さらに、論文にはこうも記されています。
学期の終わりには、どちらのクラスの学生も他の授業では同程度にAIを使っていましたが、AI利用を許可された学生は、より長く(15〜30分ほど)中身の濃いセッションでAIを活用していました。
AIを使えた学生は、「効率」「自信」「主体的な関与」に関してより肯定的な印象を持ち、今後もAIを学び続けたい、またAI関連のキャリアを選びたいという意欲が強い傾向にあったといいます。
AIを使用した学生たちは、AIが生成した文章を編集したり、誤りを見つけたりと、自分自身の判断を優先したりする“内省的学習(過去の経験や考えから学ぶ)”に関する習慣をAIを使わなかった学生よりも多く身につけていたことが明らかになっています。
さらに、学生による授業の評価もAIを使わなかったクラスより高く、特に「講師が授業の準備がどれだけしっかりしていたか」と「授業時間を効果的に活用していたか」の項目で高評価をつけていました。
ただし、AIの使用が試験の点数や最終成績に直接影響した形跡は見られませんでした。
ズルではなく効率的なAI活用
「AIのおかげで学生がより多く学べたというわけではありません。より効率的に、より自信を持って学べるようにしたのです。学生たちは授業外での宿題や試験勉強にかける時間が短くなりました」とRojas教授は大学の声明で説明しています。
Rojas教授によると、この実験では教育者が学生にズルをさせることなくAIを授業に取り入れられることを示すことができたそうです。
ただし、今回の研究は少人数を対象としており、学生の自己申告に基づくデータも多いため、より大規模な調査が必要だとも述べています。
「全体として、ガイドラインを設けたうえでの構造的なAI利用は、学生の学び方や学びへの意識を変える可能性があるものの、試験の点数を上げるわけではないようです」と研究者チームは結論づけています。