“脳の多様性”を社会で活かす「ニューロダイバーシティ」の現在地
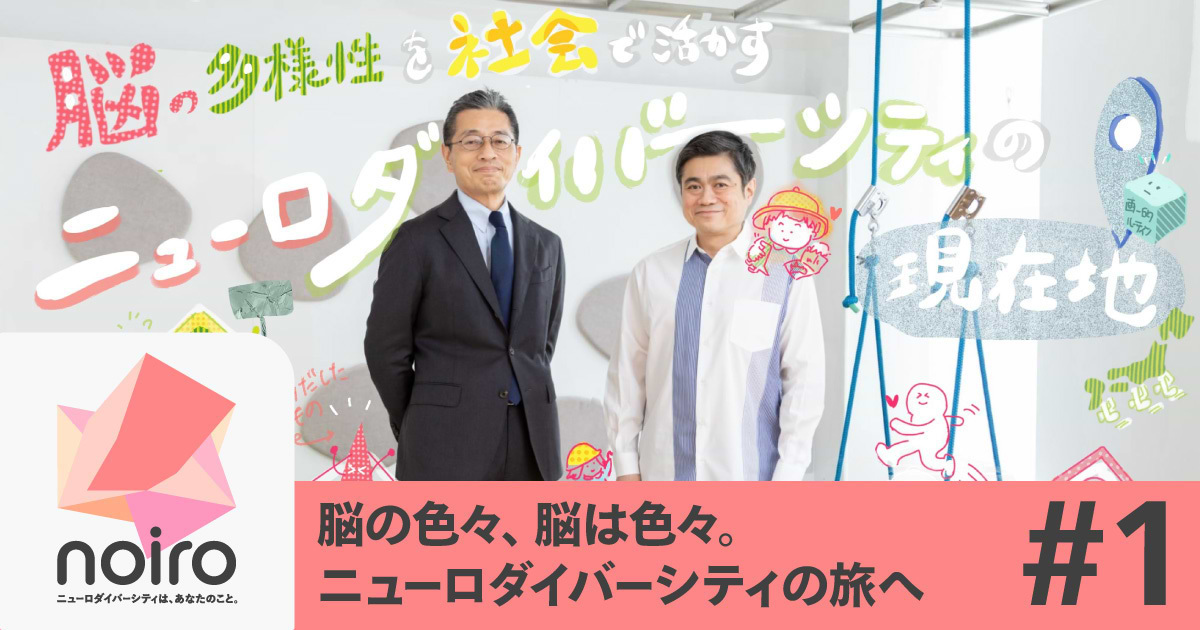
「ニューロダイバーシティ」(Neurodiversity:神経多様性)という言葉を知っていますか?
「脳や神経に由来する個人のさまざまな特性の違いを多様性と捉えて相互に尊重し、社会の中で活かしていく」考え方を表したこの言葉は、新しい概念やトレンドワードではなく、1990年代に生まれたものです。しかし近年、テクノロジーの発達や人材不足が相まって、ニューロダイバーシティを入口とした新たな未来の働き方、就業のあり方が、経済産業省や多くの企業であらためて模索されています。
2021年に、電通や電通総研などの電通グループ従業員有志によって、ニューロダイバーシティプロジェクト【noiro(ノイロ)】がスタートしました。本連載では、noiroメンバーが研究者や有識者、そして当事者の方々との対話を通じ、ニューロダイバーシティの考え方や現在地、未来の「働く」現場への活かし方について考えていきます。
第1回は、千葉工業大学学長および、「ニューロダイバーシティ・スクール・イン 東京」(東京都港区南青山2-5-17 ポーラ青山ビルディング5階 、以降NSIT)の共同創立者である伊藤穰一氏、電通総研グループの特例子会社「電通総研ブライト」前代表取締役社長の関島勝巳氏を迎え、noiroの北本英光がモデレートする対談を実施。教育と企業におけるそれぞれの立場・視点からニューロダイバーシティの現状、課題、今後についてお伺いしていきます。
ニューロダイバーシティとは: ニューロ(脳・神経)とダイバーシティ(多様性)を組み合わせた言葉。脳や神経、それに由来する個人レベルでのさまざまな特性の違いを多様性と捉えて相互に尊重し、それらの違いを社会の中で活かしていこうという概念。自閉スペクトラム症(以降ASD)、注意欠如・多動症(ADHD)など定型と異なる非定型的な発達(ニューロダイバージェント)を、障がいや、能力の欠如、優劣としてではなく人それぞれの『自然な違い』だと捉える。また、ニューロダイバージェントのみならず、すべての人を対象としている。オーストラリアの社会学者であるJudy Singer氏が1990年代に提唱し、2010年代から海外のIT企業を中心に、高い集中力や創造的思考力など発達障がい者が発揮する特性を生かす取り組みが広まった。
当事者の肉親としての経験を基に設立した、新たな学校
北本:「ほとんどの天才は自閉症である。ただし、ほとんどの自閉症の人は、天才ではない」
これは、ご自身もいわゆる自閉症と公表されている動物行動科学者のTemple Grandin氏の言葉です。ニューロダイバーシティを考える際にこの言葉は一つのカギだと考えています。ASDの中には先天的に高い知能や特異な才能を持つ方がいますが、ニューロダイバーシティはそのような限られた人々のみの話でも、さらには発達障がいと診断がついた人のみの話でもない。すべての人の「多様な特性の脳」に向き合う姿勢が大事です。電通グループのプロジェクトnoiroは、この考え方を前提として発足しました。
この連載ではニューロダイバーシティを理解していくために、多彩な視点や考え方と出合う“旅”をしたいと思っています。今回は伊藤さんが特に知見をお持ちのASDを中心としてお話を伺えればと考えていますが、最終的にはニューロダイバーシティが浸透した社会の姿や、そこに向けた期待感などをお伝えできればと考えています。
最初に自己紹介を兼ねて、お二人の経歴とニューロダイバーシティに興味を持ったきっかけや理由などをお聞かせください。まずは伊藤さんからお願いします。
伊藤:私自身が小さいころから少し変わっており、幼稚園時点で教育の仕方が合わず園を飛び出したり、本当に興味があることだけを勉強したりするタイプでした。また、化学者だった父は診断がなかったものの間違いなくASDで、妹も後からそうだと気づきました。
2011年に米国ボストンにあるマサチューセッツ工科大学(以降MIT)のMITメディアラボ所長に就任したところ、学生をはじめ多くのASD当事者に出会いました。同校の心理学の教授によれば、MITでは学生の6~7割は(医師によって診断された)自閉症だと。彼らを中心としたコミュニケーション方法ができあがっているため、当事者も誇りを持ってASDを受け止められる環境でした。
ボストン在住中に生まれた娘が3歳のときASDと診断され、帰国の際、日本でどのようなセラピーをするかを考える必要が生じました。娘の診断前から、ASD関連の活動を行っている方や研究者と交流し、メディアのリサーチ結果なども見ていた中で、親の立場から日本の状況とその中でニューロダイバーシティを推進するには何をしたらいいか考え始めたのです。
北本:当事者の肉親として関わってこられ、そこからさまざまな課題意識を持ちつづけられる中でNSITを設立されたのですね。NSITでは3歳~12歳の多様な子どもに向けてフロアタイム※1とレッジョ・エミリアアプローチ※2の手法を掛け合わせた教育を行っています。なぜこうした方針の学校を日本でつくろうと思われたのでしょうか?
※1:フロアタイム 個人の違いを尊重しながら、子どもの発達と、その家族をサポートする支援モデル。当事者の自然な興味や遊びに基づいて、他者との関係の構築やコミュニケーションスキルを高めることを助ける。
※2:レッジョ・エミリアアプローチ イタリアのレッジョ・エミリア市で考案された子どもへの教育法。環境は「第三の教師」であり、アートなどの活動とそのドキュメンテーションを通して、感性や可能性を引き出していくもの。
伊藤:娘に診断が出た後、まず日本でもよく行われているABA(応用行動分析)※3を行いましたが、彼女の反応はあまり良くありませんでした。そこで、自閉症専門病院の医学長から提案を受け、フロアタイムの認定機関ICDL(The International Council on Development and Learning)で5日間集中体験をさせたらポジティブな反応があったんです。しかし、日本ではフロアタイムを実践している場がなく、他の学校を調べてもぴったりの場所が見つからなかったため、新たな学校をつくることを考えました。
共同創立者の松本理寿輝(りずき)さんは、レッジョの教育法を実践していた方です。私もボストンでこの教育を見ており、体験型なところが良いと感じていました。そこでフロアタイムとレッジョを実験的に掛け合わせ、どんな教育ができるかを考えていけたらと思い双方の本社に相談したところ、互いに興味を持ってくれて話が進みました。
北本:伊藤さんの著書「普通をずらして生きる ニューロダイバーシティ入門」 を拝読しました。NSITが子どもたちを標準化して「普通」に近づけるのではなく、全ての子どもの個性を尊重する方向へ教育を変えていこうという実験的な取り組みをされていて、大変共感することばかりでした。
伊藤:ここでの取り組みをそのまま公教育に採り入れることは難しいかもしれませんが、NSITで育った子どもたちが社会に出ることで、少しずつ未来が変わっていくといいと考えています。
※3:ABA(応用行動分析) 発達障がいの子どもの「行動」のみならず、その「きっかけ」と「結果」に注目した支援方法。当事者にとってよい「結果」を生み出す行動は繰り返し行われるという考え方に基づき、子どもの行動にアプローチする。
障がい者雇用とニューロダイバーシティの現状とは
北本:関島さんはご自身の経歴と合わせて、企業で発達障がいに向き合う中での課題やニューロダイバーシティに興味を持ったきっかけを教えてください。
関島:私は電通総研に入社して ちょうど40年。最初の20年間はシステムエンジニアとして働き、その後15年間は人事部長、直近5年間は電通総研グループの特例子会社「電通総研ブライト」の社長を務めていました。障がい者雇用に約20年間関わったことになりますが、企業の障がい者雇用の現場は、もしかしたらこの後伊藤さんからお聞きする理想の教育の延長線上からは、ややずれたところにあるかもしれません。
なぜかといえば、日本では各企業に障がい者の法定雇用率が義務付けられており、現在は2.5%、2030年には3.0%になると言われています。「義務」という言葉から連想されるとおり、障がい者本人の希望と企業の思惑は必ずしも一致しないことが多いかもしれないからです。
北本:最近の障がい者雇用はどういった状況なのでしょうか?
関島:日本の障がい者数は約1200万人(人口の約10%)。内訳は身体障がい者400万人超、知的障がい者100万人超、精神障がい者約600万人超です。昨今、精神障がい者数の増加とともに企業が雇用する精神障がい者数も増えてきており、当グループでも精神障がい、特に発達障がい者の採用は年々増えてきています。
北本:2018年から精神障がい者も法定雇用義務の対象になりましたね。関島さんがニューロダイバーシティに興味を持つようになったきっかけを教えてください。
関島:こうした状況の中、発達障がい者の採用数が多いという理由で「電通総研はニューロダイバーシティが進んでいますね」と言われることが増えてきたのですが、私はその言葉に違和感がありました。なぜかというと「ニューロダイバーシティが進んでいますね」という言葉の中に「天才的DX人材が先端IT業務に携わっている」というニュアンスを感じるからです。
私は発達障がいの人が天才だとか天才ではないとか言いたいわけではありません。「普通とは何か」という議論はあるものの、ほとんどの発達障がい者は普通の能力の人です。なによりも「発達障がい=天才」という図式に、発達障がいの人自身が違和感を覚え苦しんでいることも見聞きし、ニューロダイバーシティについて関心を持つようになりました。
北本:なるほど、「発達障がい=特異な才能を持つ」というような狭義の解釈をしている人もまだまだ多いということでしょうか。
ニューロダイバーシティを推進するうえで大事なポイントの一つに、「一般的な大人を巻き込むこと」や、そうした誤解をしている人への啓発があると思います。NSITにおいてはこの点をどう考えられているのでしょうか?
伊藤:NSITに関わる大人を思い返すと、まず一つのコミュニティとして生徒の親たちがいます。現在はさらに関わる対象を広げようとしていて、ニューロダイバーシティのNPOをつくってワークショップをしたり、海外からアドバイザーを呼んだりしています。また、巻き込むという意味では、ニューロダイバーシティに関する特集を組んでいる大手メディアに取り上げてもらい、私たちの仲間を紹介するのも大事だと考えています。
「秩序」を尊ぶ日本の美学と教育は、多様性を許容しにくい
伊藤:今お話ししたようなアクションは、ある種「文化」のシフトを促すことだと思います。日本では特に産業革命以降、ダイバーシティ(多様性)を美学として捉えない傾向がある。どちらかといえばピシッとそろった秩序あるものや、標準化された人々が足並みをそろえて仕事をする方が美しいという美学と、その背景としてフェアネスを尊ぶ文化があるのではないでしょうか。ニューロダイバーシティで重要なのは標準化ではなく、各自がそれぞれの方法で取り組むこと。それは、日本のそうした美学や教育の仕方とはなかなか合わないんです。
北本:私は長らく教育に関する事業に関わっておりますが、いろいろな課題はあるものの、個人的には日本の公教育の本質は素晴らしいと思っています。しかしながら「普通」に合わせようとか、はみ出したものを正しくそろえるかのような意識やアプローチを変えていくことは、とても大事だと思います。
伊藤:標準化された社会において他者に言われたことをその通りに行う人は、突出した才能を発揮するのが難しい。教育には苦手分野や弱点を引き上げる方法と、強みの方を伸ばす考え方があります。日本の仕組みでは前者が主で、本人の得意分野に力を入れるのではなく苦手を一生懸命無くそうとする。けれども、特徴的な人材が育つのはやはり後者の方法です。例えば、日本のノーベル賞学者は2024年時点で28人ですが、MITでは105人います。
北本:大変共感します。確かに、日本では「苦手な教科を克服し、得意にするための努力を続けていく」という伝統的な教育観があります。探求学習の導入などで少しずつ景色が変わりつつありますが、「好き」や「得意」を伸ばすことで、個々の特性を活かした個性的な人材が育つと思いますね。
関島:企業で雇用している障がい者にも志向の多様性や得手不得手がありますので、本来は好きなことや得意なことを中心にアサインしたいと思う半面、仕事なので個々の希望をどこまでかなえるかに悩む企業も多いと思います。まさに伊藤さんがおっしゃる画一的な日本の教育の延長線上にある悩みかもしれません。また、現状多くの企業では障がい者にアサインできる仕事は限定的でルーティンワークが多いため、選択肢が少ないという事情もあると思います。
発達特性のある人々が力を発揮するには、親以外の理解者と手厚い愛情が必要
伊藤:ニューロダイバーシティと一言で言っても本当に難しく、同じASDの診断がついても、全員が本当にでこぼこ。彼らの長所を見つけ出したり伸ばしたりするには、手厚い愛情が必要です。ノーベル賞化学者などの話を聞いてると、「天才」と呼ばれる人の多くは、親以外の誰かに支援されて才能を開花させています。一番近くにいる親は、逆にそこを見いだすのが難しいケースがある。例えば、学生時代に化学の先生が「あなたは賢い、すごいよ」と背中を押してくれたことをきっかけに、興味のあることを掘り下げていたりします。
北本:NSITでもそのような経験をされた子はいますか?
伊藤:少し異なるかもしれませんが、NSITのセラピストには、すべての子どもを愛してる人がいます。本校に来た親御さんの中には彼が初対面なのに自分の子を愛してくれて、その子と“接続”し、楽しそうにコミュニケーションを取る姿を見てショックを受ける人もいますね。
関島:ショックというのは、自分たちの接し方が良くなかったという反省の意味ででしょうか?
伊藤:例えば自分の子どもが叫んでばかりで、言うことを聞いてくれないという親御さんがいました。その子がテレビの前で叫びながら大好きな電車のビデオを見ていたら、そばで観察していたセラピストも一緒に叫び出した。そこから楽しそうにコミュニケーションを取り、置いてある電車を2人で数え出したりしたんですね。その様子を見て親は「何で(自分たちにはしない)あんな反応を?」とショックを受けました。
親はそれまで叫ぶと「やめろ」と怒鳴っていたそうです。しかし、セラピストによればその子の叫びは「喜び」の発声だと。その子が喜んでいるときに自分も喜んでいる姿を見せると、気持ちが“接続”して信頼ができ、電車で遊ぶことで学びにつながっていく。親は「喜び」の声を止めて教科書で学ばせようとしていたのが、その子の好きなものを通じて学びにつなげる方法があるのだと気づいたんです。
伊藤:そんなふうに、親に対して自分の子とどうやって接したらいいかを見せるのも重要な支援です。コロナ禍に興味深かったのは、セラピストが対面で訪問できないからと、親のトレーニングをしたらとても効果があったこと。対応をわかってる人がたまに1時間だけ来るよりも、いつも一緒にいる親が学べる方が当然いいんですよね。
北本:子どもにとっては、親は一番身近な存在で大切なのはもちろんですが、セラピストの方のように、その子の可能性を信じて背中を押してくれるような大人が重要ということですね。企業にもそのような存在が共にいてくれることが、当事者の才能を開花させてくれるというような。
「内発的動機」が犠牲にならない仕組みづくりの重要性
伊藤:こうした教育方法は、すべての人に向いていると思います。私が従来のアプローチは合わないと思った理由は、子どもに与えるモチベーションが「褒められる」ことだったからです。
たとえばASDの子は目線をなかなか合わせられないので、合わせると褒めてご褒美のクッキーを渡すような方法を取ります。本来は目線を合わせるのはコミュニケーションのためですが、ASDの子は違和感があるからしない。そこでご褒美をもらえるからするというモチベーションを植え付けてしまうと、部屋に入るなり手を差し出すようになってしまいます。
これは当事者以外でも同じで、本来は自分の好きなことを一生懸命勉強すればいいのに、親や先生に褒められるために勉強するようになると、大人になったときには内発的動機がなくなってしまう。その結果、一部の人は他者に言われたことだけをきちんとこなす“褒められ中毒”になってしまう。
北本:やはりアメとムチだけで動くのではなく、内発的な動機、モチベーションが重要ということですね。
伊藤:アメとムチで一生懸命頑張らなくてはいけない場面もあると思いますが、人生全体はやはり「やりたいから」といった好奇心で動かすもの。嫌なことをする経験も重要な勉強なので全てなくせとは言いませんが、それをしすぎての好奇心やパッションが犠牲になるケースが多い気がします。2つの掛け算が大事なのではないかなと。
北本:企業においても従業員は、自分が何をしたいかより、評価されることや上司に認められるためにするといった外発的動機で行動するケースは多くありますよね。関島さんはこれまで発達障がいの人と向き合ってこられた視点から、どう感じられましたか?
関島:「内発的動機」「外発的動機」という観点で考えると、現状では多くの障がい者は法定雇用率、つまり「法律的な義務」をベースとした環境の中で仕事をしていることが多くあります。義務からは自由な発想は生まれにくいと思いますので、現在の状況では本来の「内発的動機」に基づく働き方が十分に実現されているとは限りません。
働くことの理想は、個人が自身の興味や適性を活かし、企業もその意欲を尊重しながら共に成長していくことです。障がいのある人が希望する仕事に挑戦でき、企業もその意欲や能力を活かせる環境が広がれば、より充実した働き方につながると思います。そして、この課題を乗り越えるヒントの一つとして、「ニューロダイバーシティ」の考え方があるのだと思います。
「支援する」「される」関係ではなく、当事者を現場に巻き込む発想を
伊藤:今千葉工業大学で関わっているリサーチャーはASD当事者なのですが、彼女たちは「まず当事者がデザインしないと駄目」だという考え方です。ニューロティピカル(定型的・標準的な神経発達)が想像するASDに向けたインターフェースと、当事者がしたいことは異なると。ただ、それをティピカルが想像するのは難しいため、当事者に一緒に考えてもらい、設計に参画してもらうための組織づくりをしていくのが最近のアメリカの動きにもなっています。
障がい者はフォローする対象という誤解を抱き続けて生み出したものが、実は合っていないといった状況も出てきている。その中でアメリカでは、デザインにおけるフィロソフィが変わりつつあります。この流れを広げていくためには、ニューロダイバーシティの考え方が重要です。
関島:多くの企業の障がい者雇用の現場では、支援する側が「支援される側に対して"普通の仕事の進め方"をサポートすること」が一般的です。しかしこの「普通」の定義が曖昧であり、その不確かさの中で双方が気を遣いながらコミュニケーションを図っているのが現状だと思います。この課題の解決策の一つとしても、ニューロダイバーシティの考え方は有用だと思います。「普通」というあいまいな基準にとらわれず、個々人の特性を生かした働き方を尊重することで、より柔軟な環境が構築できるはずです。
北本:支援する側が「普通」と思っていることが、支援される当事者にとってはそうでない可能性がある。その違和感をなくすためには、当事者であるニューロダイバージェントとともにつくり上げるという姿勢が求められるのですね。いわゆるインクルーシブデザインのようなアプローチでしょうか。もともとニューロダイバーシティという概念自体が、ASDでもあるJudy Singerさんの提唱によるものですし、当事者の主体性が大事だと感じます。
伊藤:アメリカでは当事者が自分たちの団体をつくって、初めて状況が大きく変わりました。また、DEIでもそうですが、アメリカの当事者団体は経営層に当事者がいない企業や団体とは取引をしないという動きがあります。こうした動きはいずれ日本にも来るのではないかと期待していますし、DEI同様日本の文化に合わせてうまく推進できるかもしれません。
後編では、教育と企業をつなぐ視点や、社会にニューロダイバーシティを浸透していくうえでのポイントについてお伝えしていきます。
【フォトスクライビングの制作:電通グラレコ研究所 代表 甲斐千晴】 電通グラレコ研究所は、グラフィックレコーディングを中心としたビジュアライゼーションサービスの提供と研究を目的とする電通グループ横断プロジェクトチームです。本記事では撮影写真に取材内容を描きこむ〝フォトスクライビング″という手法で制作しました。https://www.dentsu.co.jp/labo/grareco/index.html
Page 2
電通や電通総研などの電通グループ従業員有志は、2021年にニューロダイバーシティプロジェクト【noiro(ノイロ)】をスタートしました。本連載では、そのメンバーが研究者や有識者、そして当事者の方々との対話を通じ、ニューロダイバーシティの考え方や現在地、未来の「働く」現場への活かし方について考えていきます。
※ニューロダイバーシティとは ニューロ(脳・神経)とダイバーシティ(多様性)を組み合わせた言葉。脳や神経、それに由来する個人レベルでのさまざまな特性の違いを多様性と捉えて相互に尊重し、それらの違いを社会の中で活かしていこうという概念。自閉スペクトラム症(以降ASD)、注意欠如・多動症(ADHD)など定型と異なる非定型的な発達(ニューロダイバージェント)を、障がい、能力の欠如、優劣としてではなく人それぞれの自然な違いだと捉える。ニューロダイバージェントのみならず、すべての人を対象としている。オーストラリアの社会学者であるJudy Singer氏が1990年代に提唱し、2010年代から海外のIT企業を中心に、高い集中力や創造的思考力など発達障がい者が発揮する特性を生かす取り組みが広まった。
教育と企業における視点の違いやニューロダイバーシティの現状・課題についてお伝えした前回に続き、第2回となる今回も電通 未来事業創研/noiroの北本英光によるモデレートで後編をお届け。
千葉工業大学学長および「ニューロダイバーシティ・スクール・イン 東京」(東京都港区南青山2-5-17 ポーラ青山ビルディング5階 、以降NSIT)の共同創立者である伊藤穰一氏、電通総研グループの特例子会社「電通総研ブライト」前代表取締役社長の関島勝巳氏に、教育と企業をつなぐ視点や、社会にニューロダイバーシティを浸透していくうえでのポイント、ニューロダイバージェント(発達特性のある人)の活躍推進などについてお聞きしました。
ポイントは能力ある当事者の「発掘」とモチベーション変革をどうするか?
北本:伊藤さんは情熱を持ってNSITを設立され、フロアタイム※1とレッジョ・エミリアアプローチ※2の組み合わせによって、ニューロダイバージェント(ASDなどの発達障がい)の子どもの力を伸ばす教育を実践されようとしています。一方で企業における発達障がい者への対応の現状は、寄り添い理解するというよりは「支援する側/される側」に分かれてしまう状況です。せっかく当事者が自身の力を伸ばせるような教育を受けてきても、企業に所属することでその教育の成果が活かされない可能性も考えられます。
こうしたことを考えたときに、企業の対応で期待することや、伊藤さんが実践されてきた教育と企業に所属した後の連続性をどう考えていらっしゃるか、ぜひお聞かせください。
※1:フロアタイム 個人の違いを尊重しながら、子どもの発達と、その家族をサポートする支援モデル。当事者の自然な興味や遊びに基づいて、他者との関係の構築やコミュニケーションスキルを高めることを助ける。
※2:レッジョ・エミリアアプローチ イタリアのレッジョ・エミリア市で考案された子どもへの教育法。環境は「第三の教師」であり、アートなどの活動とそのドキュメンテーションを通して、感性や可能性を引き出していくもの。
伊藤:この点は私も重要な課題だと捉えています。そのうえで、もしかしたらカギはスタートアップにあるのではないかと。大企業でルールや社風を変えるのはなかなか難しいものですが、スタートアップ企業であれば、ある程度最初からカルチャーをつくれます。また、発達障がいで仕事ができないと思われている人でも、実は「アンロック」…つまり本人にとっての障がいを取り除いたり、枷と感じているものを外したりすると、急に特異な力を発揮できるようになることもある。仕事や企業における彼らを考えるうえで、難しくもありポイントでもあるのは、そうした「発掘」をどうするかです。
私の勝手なイメージですが、趣味の世界などではその片鱗が見えてくるケースがあります。たとえば以前にドバイでスキューバダイビングの先生をした時、学校ではできない子と思われていた生徒が一番意欲的に打ち込む例がありました。逆に学校で一番の優等生は「これって成績に関係あるの?」といったモチベーションになってしまう。つまり、企業の中で「変わっている」と言われ、力が発揮できていなくても、モチベーションさえ変えられればアンロックする人もいるのだと思います。
一方で、「企業側のモチベーション」を上げていく方法も難しいと思います。法定雇用率をベースとした障がい者雇用では、どうしてもコストを下げていく方向に話が進んでしまう。そこを本当は環境次第で特異な力を発揮できる「才能」を探していると考えれば、少しはモチベーションが変わるのではないでしょうか。
北本:法定雇用率は雇用の平等を担保するなど良い点もたくさんあると思いますが、今改めて考え直す必要もあるかもしれませんね。
伊藤:社会におけるこうした雇用の重要ポイントには、アンロックすると見いだされていない才能が発掘されるかもしれないといったポジティブな経済的モチベーションもあれば、フェアネスの視点でみんなをバリアフリーにしていくといった考え方もあります。会社としてどういう理由で雇用しているかによってKPIは全く異なる。そこがニューロダイバーシティプロジェクトの難しいところだと感じます。
全ての人がニューロダイバーシティの「中」にいる
関島:何社かのニューロダイバーシティが進んでいるIT企業の方にお話を聞いて、共通点があることに気が付きました。それは、そうした企業では、ニューロダイバーシティを「障がい者雇用」の一施策として行っているのではなく、あくまで「優秀な技術者の採用」という観点でとらえているということです。さらに、入社後も能力を存分に発揮できる仕組みや、働きやすい環境をさまざまな工夫をしてつくっています。
ある企業では従業員の約半数が発達障がいとその傾向のある方でしたが、当事者の人々も、残り半数の当事者ではない従業員も生き生きと仕事をしている。それを見て「障がい者の働きやすい会社はすべての人が働きやすい」のだと気づきました。つまり、ニューロダイバーシティが進むということは、障がいの有無にかかわらず、全ての従業員が能力を発揮でき、生き生きと働けることなのだと実感したのです。
北本:今後日本でニューロダイバーシティの話が広がっていくにしても、単なる障がい者雇用の話ではないという意識は持つべきですね。全員が当事者なのだと。
関島:障がい者雇用に携わっていると、「偉いですね」とか「大変なお仕事ですね」と言われることがしょっちゅうあります。確かに、障がい者にはさまざまな特性があり、サポートが必要な場面もありますが、すべての人にさまざまな特性があります。障がい者雇用をしているからといって特別に大変なわけではありません。むしろ、「大変でしょう」と言われると、理解されていないと感じて残念な気持ちになります。
伊藤:人にもよりますが、当事者の中にも本当は「かわいそう」だと思われたくない人は多いと思います。周りに「かわいそうだから」と手助けをする人がたくさんいる人ってどうしてもプライドを持ちにくいんです。
少し違うかもしれませんが、杖などの補助器具も日本ではどこかかわいそうな雰囲気の色合いが多いと思います。イギリスなどでは「ディスアビリティ デザイン(Disability Design)」と呼ばれる、非常にかっこいいデザインの杖や義足がつくられています。彼らがプライドを持てる状況をつくることは大事なのではないでしょうか。
北本:日本ではDEIの研修でも、「配慮する側」「される側」のような分け方で、配慮される側への思いやりを持とうといったアプローチが多く見られます。理解するのはもちろん大事ですが、どうしても「する側」「される側」の構造から抜けられない。繰り返しにはなりますが、ニューロダイバーシティは全ての人に関係する。全ての人が当事者という点がこれまでのDEIにはなかった重要な観点ですね。
伊藤:どんな人であっても不確実・不安定な環境では過ごしにくいものです。その中で発達障がいの人は特にその影響を受けやすい。そうしたセンシティブな人に良い環境を作ることができれば、すべての人も幸せになれます。
北本:確かに、近い概念で言えばユニバーサルデザイン。それをもっと心の方に寄せていくイメージですね。
現状ではティピカル(一般的)な人たちの、ニューロダイバージェントに対するリテラシーは圧倒的に低いように思います。身体障がいや知的障がいであれば、何となくわかるけれど、脳や心の多様性となるとなかなか難しい。仮に脳の話だとしたら、本来100人いれば100人とも異なるのが当たり前だと皆が認識できるかが重要ですね。「当事者」対「自分」という話ではなく、本当の意味で自分ゴト化させて、全ての人がニューロダイバーシティの中に入ってこられるといいですね。
伊藤:いわゆる「全てがノーマルの人」は存在しませんからね。以前に何かの論文で見ましたが、物理的にも平均的な体重で平均的な特徴があって、といった全てがアベレージ内の人というのは1人もいないそうです。なのに、そうした「普通の人」がいるような錯覚を起こしているのだと思います。
教育と“空気感”が育てた、若者の柔軟な感覚を活かしたい
北本:NSITで12歳まで主体性を持って学んできた子どもたちを、いかにうまく企業、あるいは仕事につなげていくのか。その接合点がこれから大事だとあらためて思いました。そのときのヒントとして、関島さんが以前に経験されたという、新入社員研修での話をお聞かせいただけますか。
関島:ここ数年、電通総研の新入社員研修で障がい者雇用について30分ほどのプレゼンを行っています。プレゼン後に新入社員には簡単なレポートを提出してもらうのですが、これがなかなか良い内容なんです。例えば、「特例子会社はインクルージョンに逆行していないか?」とか「農業などもとても良いが、本業に直接貢献できる仕事をアサインすべきでは?」というような意見が多くなってきています。これは本当に素晴らしいことです。同じ話を50代以上の従業員にしても、全く反応が違うんですよ。障がい者雇用を福祉的な観点のみでとらえ、経済合理性で解決しようとするなど、残念なことが多いです。
これはおそらく、最近の学校でSDGsや環境問題と並んでDEI教育が行われている成果が出始めているのだと思います。こうした感性を持つ若者が企業の中でどんどん成長していけば、世の中も変わってくるでしょう。だからこそ、インクルージョン、つまり障がいの有無を問わず、多様な人々を同じ場で教育していく必要性があるのかなと感じています。小さいときからの学びは本当に大切です。
伊藤:若い方たちの世界観が変わってきている。そこにはもちろん教育もあるけれど、音楽や漫画、日常的な空気が全体として変わってきているのではないでしょうか。そのどこまでが教育で、どこまでが今の“空気感”なのかは興味深いですね。またどの時代もそうですが、上の世代への違和感や反発もあるかもしれません。彼らは、今の環境問題や不安定な社会は上の世代の行動が生み出したものだと感じていて、そこから脱却したい。そのうちの一つに、肌感覚としてのダイバーシティがあるのかなと。
国連などが「上」からいろんな啓発をするよりも、実は若い人たちのそうした感覚を上手に育てる方が自然なムーブメントになるかもしれません。その意味で私も若い人にはすごく期待しています。「ポジティブデビアンス」(Positive Deviance=ポジティブな逸脱)というアプローチがあって、社会の中の小さなマイノリティによる、みんなと違う珍しい行動から解決法を見いだす方法です。上から変えようとするよりも、そうしたアクションを拡大できると良いと考えています。
技術者の社会的地位向上とAIの進化が広げる、ニューロダイバージェントの活躍の場
北本:電通グループはもちろん、多くの企業にニューロダイバーシティを広げていく取り組みは、そのための採用や受け入れ方法、マネージメントの検討も含めて今始まったばかりです。そのうえで、ニューロダイバージェントは、このテクノロジー社会でどんな貢献ができるのか。ASDに限らずADHDなど他の発達障がいの人も含め、伊藤さんはどんな職種や世界で価値を発揮できるとお考えでしょうか?
伊藤:コロナ禍では多くの企業に困難がありましたが、障がいがある人たちは逆に仕事へ参加しやすくなった面もありました。リモートワークであれば、目線を合わせたくない人や動けない人なども仕事がしやすかったからです。例えば1人だけオンラインで参加する会議だとその人の声は届きにくくなるけれど、全員がオンラインであればフェアになります。力の発揮しやすさでいうと、そうした環境が一つ考えられます。
また、ASDの人たちが特異な能力を発揮する場は、理工系が多い。そうした技術者の社会的地位が上がることは、ASDやニューロダイバーシティを考えるうえではとても重要です。アメリカでは、マサチューセッツ工科大学(MIT)のような理工系の大学のトップに理工系の人材がいますし、イーロン・マスクをはじめIT系企業のトップはASDだらけで、成功者としてのロールモデルが見えています。
関島:障がい者が自己実現でき、自身と会社がともに成長できるような社会が訪れることが理想だと思います。そしてその考え方の根幹にあるのがニューロダイバーシティだと思います。また、企業に就職するだけでなく、自律的に仕事ができる社会の実現も理想のひとつです。AIをはじめとする最先端の技術は、ニューロダイバージェントとニューロティピカルの曖昧な垣根をなくす有用なツールになることは間違いありません。
北本:現在の生産年齢人口7300万人が、今後どんどん減っていき、日本の国力が下がると懸念される中では、働き方もさらに変わっていくと思います。その中での企業による採用の視点を変え、ニューロダイバージェントが入社した段階での理解を広げ支持者を増やしていく方法も考えられます。いずれにしても活動を大きくしていかないとニューロダイバージェントが働く場からこぼれ落ちてしまう。そこを何とかしないといけないと切に感じました。
ニューロダイバーシティのカギは、日本独自のコミュニティにある
北本:繰り返しにはなりますが、ニューロダイバーシティは「障がい者の施策」ではなく、全ての人が特性を生かしながら働ける環境をつくること。結果的にそれがあらゆる人の働きやすさにつながるのだと感じました。同時に教育、例えば今NSITにいるASDの子どもたちが、未来にどんなふうにいられると日本が輝いていけるのか。この視点で、伊藤さんから今後の展望をお聞かせください。
伊藤:ASDにもいろんな子がいて、自立が難しい子ももちろんいます。ただ自立できないからって社会に貢献していないわけではない。コミュニティにはさまざまな役割があります。その中で「かわいそうだから」と手助けをしてもらう立場ではなく、「この人がいるとみんながハッピーになる」と何かしらの役割を担ってもらうような状況は、日本でも結構あったのではないでしょうか。例えば独立するほどの技術はないけれど、地域の草花の手入れなどをしてみんなに愛されている人などです。
また出雲にはコミュニティナースと呼ばれる人がいて、地域の集まりなどで高齢者と若い子や子どもが遊ぶ場に参加し、健康チェックなどをしています。そうしたコミュニティを使って地域住民の幸せと健康を活性化するような仕組みです。仕事をしていない高齢者も、子どもの面倒を見たり知識を伝えたりすることで、それぞれに役割ができる。そんなふうにコミュニティ内での役割があれば、互いにとって心地良い居場所になります。
北本:なるほど。私自身はニューロダイバージェントの力も、子どもの力も信じています。彼らは、われわれにはないものを持っている。必要なのは支援をするとかされるという意識ではなく、コミュニティの中で共に生きていくという姿勢なのではと強く思います。
伊藤:きちんと成立したコミュニティには多くのレジリエンスがある、その中で互いに気を配りあいファミリーメンバーになるという形も一つのあり方だと感じます。日本人の助け合いや地域共存のような考え方は、スタートアップや競争視点では弱いかもしれませんが、平和にはいい。私は、そうしたある種の“村落共同体”的な文化やコミュニティにキーがあると思います。
企業においてはどうしても「雇う人」が環境やプロダクトをつくります。その職場が変わらなければ始まらない。ですので、大きいレイヤーとしての結論はやはり今まさに皆さんがやっていらっしゃる活動を通して電通のような大企業の現場を変えることが重要。そちらをメインに「ポジティブデビアンス」のケーススタディをしていけると良いと考えています。
北本:ありがとうございます。お二人のお話をお伺いして、ニューロダイバーシティの概念が社会に広がることで、どんな子どもも楽しく生きていける、誰もが働きやすくなるという期待を感じました。NSITは「未来の子どもの環境の“New Standard”をつくること」を旗印にされていますが、ニューロダイバーシティが浸透する未来に向けて、まさに「未来の働く環境の“New Standard”をつくること」をご一緒に目指したいですね。
「個々の才能が輝く社会」
関島勝巳の色「はたらくをあざやかに。輝き方はひとつではありません」



![[プロモーション]【500人調査】片付けが進まない背景に 「捨てるかどうか」の判断疲れ 「片付け・整理整頓に関する意識調査」を実施](https://image.trecome.info/uploads/article/image/458d3fbb-219e-40fc-a458-1b7a90a07fa8)