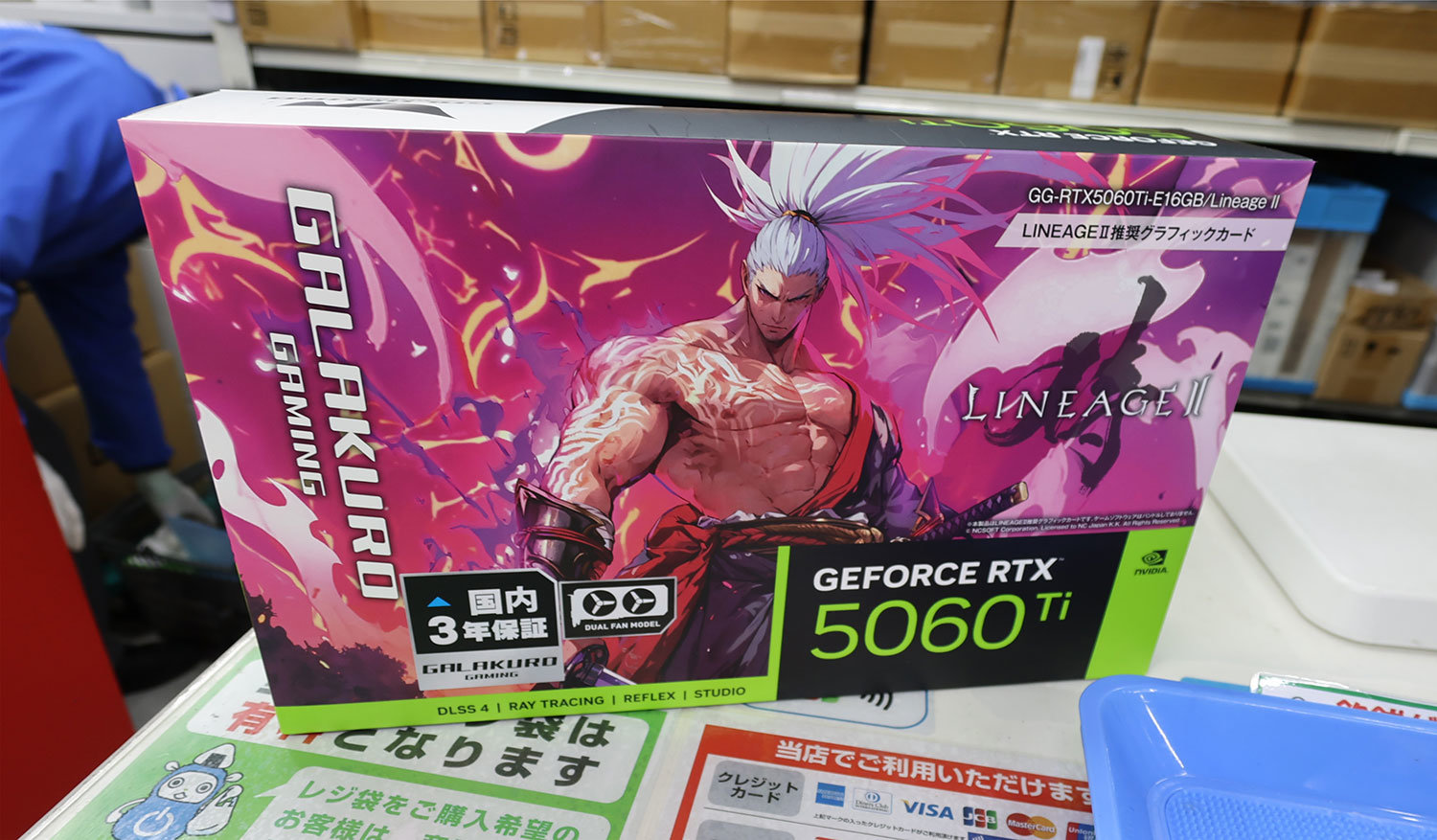「検索」の歴史、7万年遡ったら、AIがどんだけヤバいか見えてきた(ギズモード・ジャパン)

「調べたいことがあるんですけど…」 「はい、どうぞ」。手渡されたのは、分厚く重い、粘土板。 【全画像をみる】「検索」の歴史、7万年遡ったら、AIがどんだけヤバいか見えてきた 紀元前3000年ごろのメソポタミア。調べ物をするには、粘土板を集積した保管所に行き、たくさんの粘土板から必要な情報を見つけなければなりませんでした。 それから5000年もの時が流れた今、私たちは保管所の代わりに、スマートフォンからインターネットへと接続し、無限とも言える情報に、時間も場所も選ばずアクセスできるようになっています。 "知りたい"。その欲望が、粘土版からインターネットへと、人類の技術を進化させてきたのです。 そして2025年現在、その「調べる」という営みは、かつてない転換点を迎えているように思います。そう、AIの登場です。 すでにChatGPTやGeminiなどのチャット型AIツールで、日常的に調べ物をしている人も少なくないかもしれません。AIは、質問になんでも答えてくれるだけでなく、私たちの代わりに、"考える"ことまでしてくれます。 知恵を記録し、情報を得て、行動に役立てる。遥か昔から人類が続けてきた「調べる」という行為は、AIの登場でどう変わってしまうのでしょう? 今回は、7万年の人類の歴史を辿りながら、「人と知の行方」を考えてみたいと思います。
「肉じゃがの美味しい作り方」を知って、夕食がちょっと豊かになる。医者が論文から新しい知識を得て、患者の命を救う。私たちは「調べる」ことで、些細なことから重大なことまで、できなかったことを可能にします。 まずは改めて、「調べる」とはどのような行為なのか、言語化することから始めてみましょう。 デジタル大辞泉では、「わからないことや不確かなことを、いろいろな方法で確かめる。調査する。研究する」と定義されています。 人が「調べる」のはなぜ? ではそもそも、なぜ人は「調べる」をするのでしょう。 神経科学者のタリ・シャロットと法学者のキャス・サンスティーンは、「How people decide what they want to know(人はどうやって知りたいことを決めているのか)」という論文の中で、情報収集の動機を、以下の3つに分類しています。 実用的効用:情報を意思決定や行動に役立てるため 認知的効用:純粋な知的好奇心や理解への欲求 快楽的効用:気分を良くするため(または悪くしないため) 確かに、問題を解決するためにネット検索することもあれば、好奇心に突き動かされて本を読むことも、SNSで自分の投稿に「いいね」がついているか確認してちょっと嬉しくなることもありますよね。言語化するとハッとさせられます。 私たち人類は、7万年の間、そんな「調べる」を行なってきました。人間にとって切り離せない習性なのでしょう。 しかしそこには、幾重にも重なる、技術革新の連鎖があります。私たちがいかにしてこの大きな発明「AI検索」へと辿り着いたのか、悠久の歴史の流れを辿りながら、紐解いていきましょう。