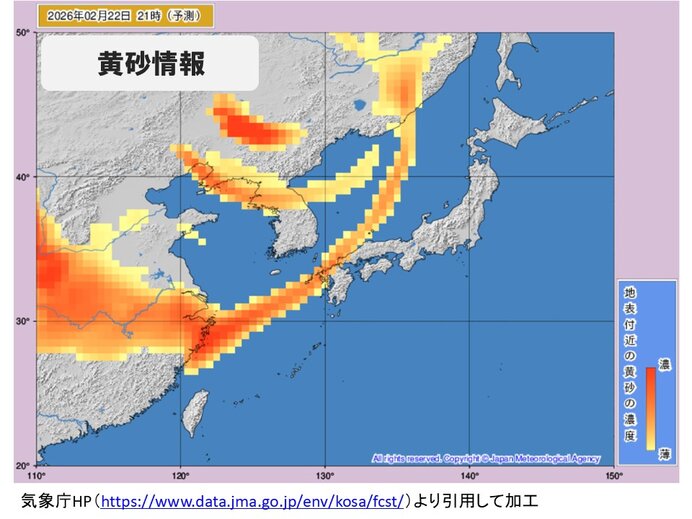ヒグマ駆除は米軍の特殊部隊と戦うようなもの!迫り来るクマの脅威…ドングリの凶作だけが原因か?人間が心得るべきこと(Wedge(ウェッジ))

北海道南部地域の福島町で2025年7月12日、新聞配達中の男性がヒグマに襲われて死亡した。その後に駆除されヒグマがDNA鑑定によって「加害個体」であることが特定され、4年前に町内で女性を死亡させた個体と同一だったことも判明した。 【図表】出没件数と許可捕獲数、死傷者数の関係 現在(25年8月2日時点)、道庁による「北海道ヒグマ注意報」が福島町、上ノ国町、平取町の一部地域、砂川市に発出されている。ツキノワグマによる人身事故人数(25年7月末時点の環境省による速報値)は、岩手県12人(死者1人)、長野県13人(死者1人)をはじめ16県で53人におよぶ。8月に入っても連日のようにクマ出没の報道がなされ、人の生活圏への出没が異状現象ではなく、もはや日常となっている。 この背景として、餌の凶作などが挙げられているが、注目すべきはそもそものクマ類の個体数が増え(、分布も拡大し)ていることだ。対策の基本的な考え方は人の生活圏とクマ類の生息域を区分(ゾーニング)し、すみ分けを図っていくこととされているのだが、維持すべき個体数水準を定めて、個体群管理を実施しているのは都道府県で兵庫県に限られている。 国は対策として、24年4月にクマ類(四国のツキノワグマ個体群を除く)を「指定管理鳥獣」に指定し、都道府県による計画的な捕獲や生息状況の調査などを国の交付金の対象とした。また、25年4月には鳥獣保護管理法を改正して「緊急銃猟制度」を創設し(9月1日施行)、人の日常生活圏にクマやイノシシが出没した場合、一定の条件を満たした時に、市町村長の判断により銃器を使用した捕獲等ができるようにした。 生活圏へのクマ出没が日常と化している今、私たちは何をすべきなのか。本論では、クマ類の被害を防ぐうえでの個体群管理の重要性とその課題について論考する。
ツキノワグマの大量出没の要因として、生息地における堅果類(ドングリ)の凶作により餌の供給が足りていないこと、里山の高林齢化と里地の耕作放棄地によって人里に近いところに好適な生息地となりつつあることが挙げられている(米田政明 『ツキノワグマ保護管理の課題-教訓を活かす JBN緊急クマシンポジウム&ワークショップ報告書―2006年ツキノワグマ大量出没の総括とJBNからの提言』)。兵庫県では、ドングリの豊凶把握により出没程度を高い精度で予測しており、ドングリの豊凶が出没に影響していることについては数多く報告されている。また、近年では夏季の果実の不作が夏の出没を招いていることが明らかにされている。 しかし、近年の出没頻度と規模の増加は、このドングリの豊凶に加えて、分布域と生息数の増加が影響していると考えられている(哺乳類学会 2024『今後のクマ類の管理に関する意見書の提出について』、日本クマネットワーク 2024『2023年度のクマ大量出没と人身被害 〜その実態と背景・今後に向けた課題〜 報告書』)。 ツキノワグマの出没件数と許可捕獲数および人の死傷者数の関係(2009〜23年)をみると(図1)、出没件数が増加するにつれて、許可捕獲数および人の死傷者数は直線的に増加している(図2、3)。 人との軋轢の指標である許可捕獲数(駆除数)は人の死傷者数と高い相関 (r = 0.8943, P < 0.001)がみられ(図4)、同様な関係は東北5県でも報告されている(日本クマネットワーク 2024)。すなわち、ツキノワグマの個体数増加が出没件数の増加を招き、それにともない許可捕獲数および人身被害の急増を招いたことが推測される。 ヒグマについても許可捕獲数と死傷者数は、1966年に開始された春グマ駆除が進行すると減少し、個体群回復のため春グマ駆除が廃止された90年以降に増加した傾向が読み取れる(図5、哺乳類学会2024)。ツキノワグマでは2023年に許可捕獲数(7858頭)と死傷者数(210人)、ヒグマでは23年に許可捕獲数(1684頭)、21年に死傷者数(14人)が過去最高記録を更新した。
Page 2
北海道奈井江町の北海道猟友会砂川支部奈井江部会が24年に町のヒグマ駆除への協力要請を条件面で折り合わず辞退した際、山岸辰人部会長は「ヒグマ駆除は、米軍の特殊部隊と森の中で戦うようなものだ」と危険性が軽視されていることを指摘している(朝日新聞 2024年5月26日)。そもそも、ヒグマの駆除でも専門的捕獲者は限定されている。ましてや、居住地へ出没したクマ対応は至難の業である。 米国でも市街地にクマが出没しているが、大学で野生動物管理学を学んだ専門家が州の正規職員として雇用されて対応している。米国にクマの取材にあたった朝日新聞の伊藤絵里奈記者は、米国の専門家に日本の状況を説明すると「民間のハンターが市街地に出たクマに対応するなんて、釣り人が人食いザメに立ち向かうようなものだ」とのコメントを紹介している(朝日新聞 2024年12月16日)。 日本には、管理を担う自治体に野生動物管理の枠組みをプランニングし、運用する人材を配置するという考えが不足している(横山真弓『【増えすぎたクマ】このままでは人間のコントロール不能なフェーズに?クマ対応の「地域力」向上に必要なこと』 )。そのため、高齢化と減少が進む狩猟者、個体数管理に踏み切れない政策、都道府県に野生動物管理専門職が不在な状況で、クマ類は増え続け、現場は管理不能な状況に陥っている。
人の生活圏へのクマ類による侵入は異常現象から日常になりつつある。まずは、あふれてくるクマの駆除はもとより、緩衝地帯でも個体数調整を進めて、クマを山に押し戻し、人への警戒心を高める必要がある。そのためには、クマの個体群管理にむけた体制整備と役割分担、その担い手育成と配置を進めるべきだろう。 今日、クマ類のみならず、イノシシやシカなども分布の拡大と個体数の増加によって、さまざまな軋轢が生じている。クマを含めた野生動物管理の専門職ならびに専門的捕獲技術者の養成を国は大学と連携して実施すべきである(日本学術会議 2019『回答 人口縮小社会における野生動物の管理のあり方』)。 近年になって、環境省・農林水産省の支援を受けて、大学間連携による野生動物管理教育カリキュラムが試行(宇野裕之, 小池 伸介,髙田 隼人2025『大学における野生動物管理教育カリキュラム 野生生物と社会』13:69-74.)、野生動物管理教育カリキュラムの認証制度の検討(鈴木正嗣,吉田正人 2025『野生動物管理学教育カリキュラムと認証制度』野生生物と社会学会13:65-68. )されている。また、知床自然アカデミーによるリカレント教育(中川元 2025『知床における野生動物管理者のリカレント教育〜知床ネイチャーキャンパス〜』 野生生物と社会 13:81-86. )、エゾシカ協会によるシカ捕獲者認証制度と大学の連携(伊吾田宏正 2025『北海道におけるシカ捕獲管理者制度と大学の連携〜酪農学園大学の事例〜』野生生物と社会学会 13:79-80.)などの取り組みが開始している。 これらの制度を活用しながら、特定計画の実現に必要な、都道府県レベルに科学行政官、市町村レベルに現場指導を行う鳥獣対策員を配置し、専門的捕獲技術者の育成を進める必要がある。
梶 光一
Page 3
クマの専門家からは、たびたびクマ類はシカやイノシシと違って繁殖力は弱いとの理由で、個体群管理には否定的な見解が唱えられることが多い。確かに環境省による「特定鳥獣保護・管理計画作成のためのガイドライン(クマ類編)」(環境省 2022)には、「クマ類は一般的に自然増加率がイノシシ及びニホンジカと比較して低いと考えられること、推定個体数も少ないことから、捕獲を強化することで個体数を急激に減少させることは個体群の存続にとって負の影響を与える可能性がある」と記述されている。 しかし、同ガイドラインで示すツキノワグマとヒグマの自然増加率は、スウェーデンで管理不能に陥るまで急増した増加率(年率16%)とほぼ同じである(梶光一・小池伸介編 2015『野生動物の管理システム クマ,シカ,イノシシとの共存をめざして』KS地球環境科学専門書、講談社)。兵庫県の2つのツキノワグマ個体群も同様の増加率(16%)を示し(兵庫県 2025)、クマ類は条件が整えば、5年程度で生息数が倍増する繁殖ポテンシャルを有していると言える。 したがって、クマ類の増加率はシカに比べて低いという思い込みを払拭し、増加中の個体群に対しては、個体数を確実に低減するためにモニタリングを基に個体群管理を順応的に行う必要がある。
環境省が7月、「緊急銃猟制度」を策定し、そのガイドラインを公表した(環境省 2025)。この制度によって、市町村長の判断で危険鳥獣の銃猟を捕獲者に委託し、安全確保が可能な場所(農地や河川敷等)での銃猟・クマが建物に侵入した場合の銃猟・夜間での銃猟などが可能となった。 これまでも日常的にクマが生活圏に出没している地域で、出没対応の経験が豊富で体制も整備されている市町村にとっては、より対応が迅速になるので評価できるだろう。また、「捕獲者」という用語を用いて、いわゆる「趣味で狩猟を行う者(ハンター)」と区別していることも、本制度が高度な専門性を有していることを際立たせている点で評価できる。 本ガイドラインには「事前に必要な役割分担を整理した上で、捕獲関係者も含め、役割に応じた人員をあらかじめ特定し、緊急時に実際に迅速かつ円滑に対応できる体制を整備することが重要である。その際、知識や技能を有する者が不在である場合には、訓練の実施等も体制の整備の一環として必要」と記述されている。また、これまでの狩猟や駆除とは異なるので、捕獲技術だけでなく、市町村職員と捕獲者をつなげるといった地域の鳥獣対策のリーダーでありコーディネーターを務められるような素養を育成していくことも必要と述べられている。 しかし、通常の山野の鳥獣被害対策ですら四苦八苦している市町村に、このような高度の専門性をもつ指揮官、コーディネーター、捕獲の担い手の育成と配置を委ねることができるだろうか?