ネアンデルタール人は「直系の祖先」ではなかった…ノーベル賞受賞者・ペーボ博士が解き明かした「人類の起源」(小林 武彦)
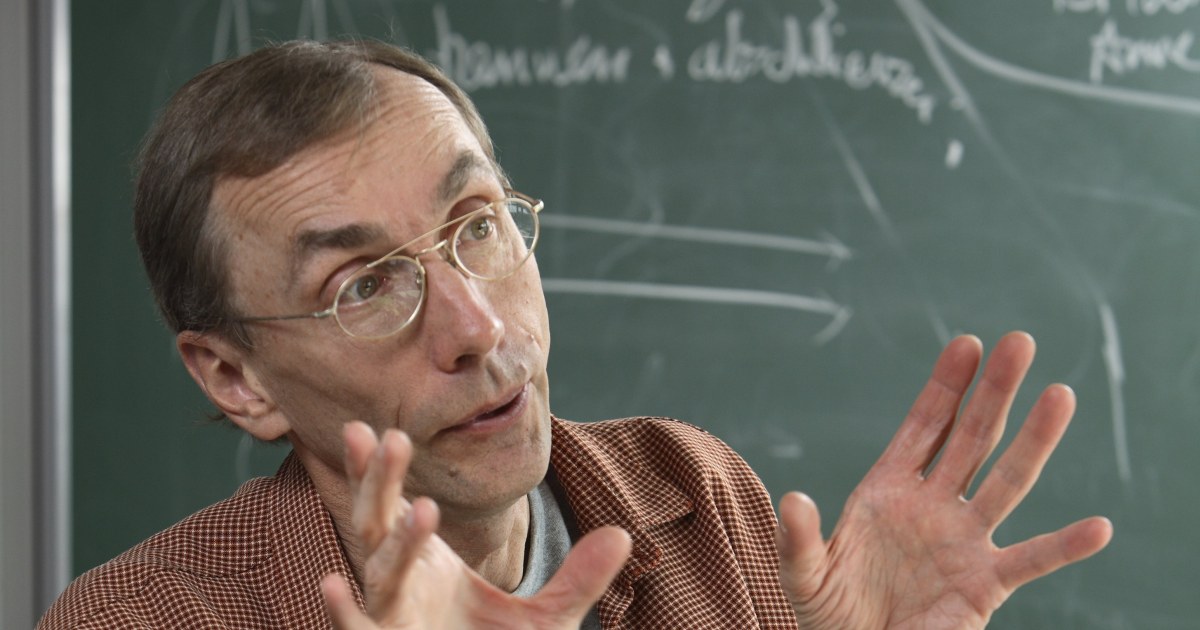
生物の中でも、ヒトは「ある変化」を機に幸せに生きにくくなったという。
その理由とはなにか。幸せに生きる方法はないのか。
小林武彦氏の新刊『 なぜヒトだけが幸せになれないのか 』では、生物学から「ヒトが生きる意味」を考える。
本記事では、〈「サルの進化は横並び」だったのに、「人類」が地上で生き残ることができた「重大な理由」〉に引き続き、ヒトの進化について詳しくみていく。
※本記事は、小林武彦『 なぜヒトだけが幸せになれないのか 』(講談社現代新書)から抜粋・編集したものです。
急に脳が大きくなった
猿人の時代は約500万年間続きました。このぐらい昔だと化石も少なく、この期間で体や暮らしがどう変化したのかよくわかりませんが、おそらく果物を主食とした複数種の猿人がいたと考えられています。いろんなヒトの種が現れては消えていったのだと思います。まさにヒトは「変化と選択」の真っ只中だったのでしょう。
少ない化石からの推察で、大きな変化が現れたのはおよそ200万年前と考えられています。脳の容積が1000mlと猿人の500mlに比べてほぼ倍増しました。
身長も猿人が110cm程度だったのに対し、165cmの化石も見つかっています。かなり視線も高くなり、名前も猿人から新たに「原人」に変わりました(図2-4)。まだ濃い結構な量の体毛はあり、若干の肉食も始まっていたようです。
また、彼らの一部がアフリカを出てアジアやヨーロッパに移動し始めるという変化もありました。インドネシアのジャワ島、中国の北京の洞窟でそれぞれジャワ原人、北京原人の骨が見つかっています。このような長旅を可能にさせたのも、一つは脳の容積が増えたこと、もう一つは、後でお話しするヒトの人たる性質のおかげだったのでしょう。



![[プロモーション]【500人調査】片付けが進まない背景に 「捨てるかどうか」の判断疲れ 「片付け・整理整頓に関する意識調査」を実施](https://image.trecome.info/uploads/article/image/458d3fbb-219e-40fc-a458-1b7a90a07fa8)