『都市高齢社会と地域福祉』の「縁、運、根」
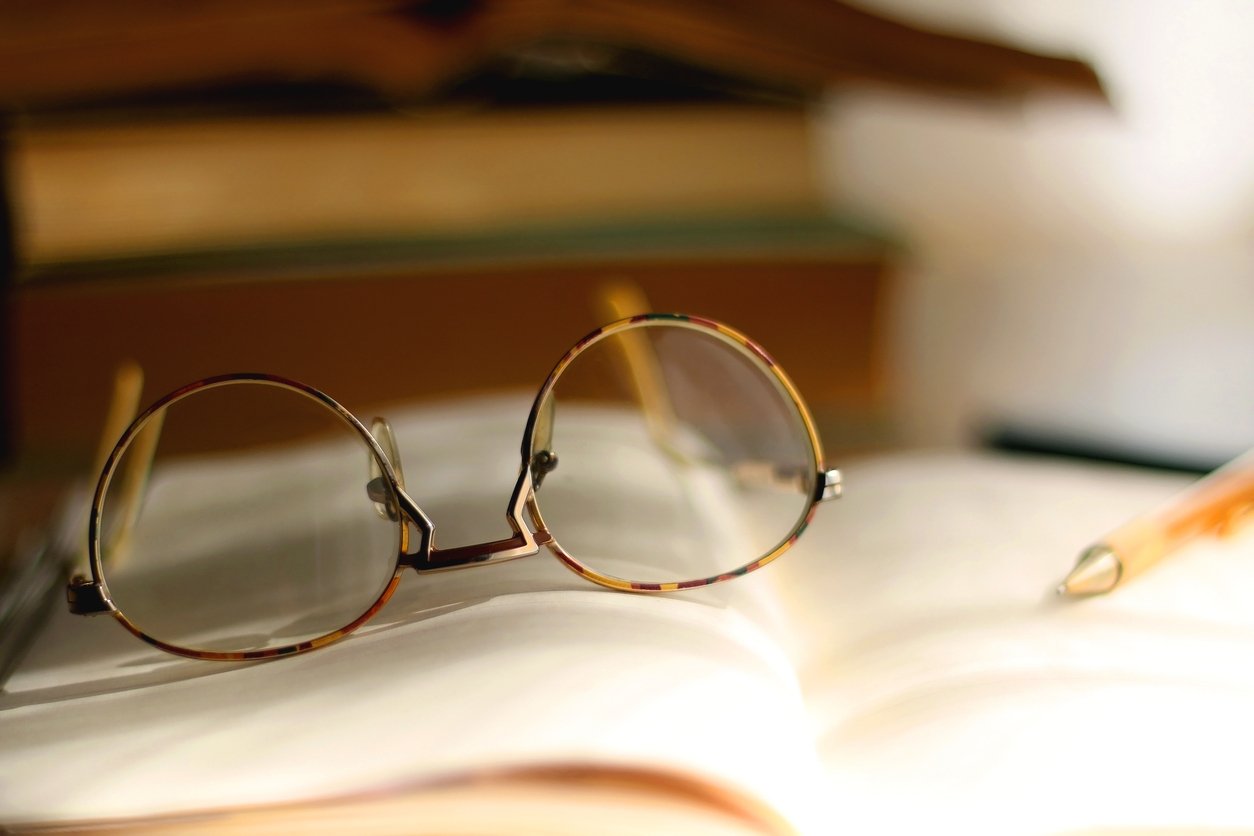
Jelena990/iStock
(前回:『高齢化の社会設計』の「縁、運、根」)
行動科学科の社会学講座
1984年10月に文学部の社会学担当として出発した際の著書は、『コミュニティの社会理論』と『高齢化の社会設計』の2冊であった。
ただ九大文学研究科の社会学専攻とは異なり、北大文学研究科では行動科学科のなかでの社会学専攻として、心理学、社会心理学、人類学、地理学などと共存するシステムになっていた。そのため、教授も助教授も含めて行動科学所属のスタッフ全員が、何らかの方法によるデータ処理の技術と統計学的基礎を踏まえた業績を出されているように感じられ、この2冊のデータ処理レベルでは不十分なのではないかと自問自答する数日が続いた。
データ処理技術が未熟
実際のところ、私の大学院時代も久留米大学でもコンピューターがなく、それまでに統計学の授業も受けたことがなかった。そのため調査データはIBMカードに穴をあけて、それを最新のカードセレクターで分類する作業をいくどか経験したに過ぎなかった。
それで、北大赴任後の心配事の筆頭は、行動科学に所属する社会学専攻で果たして実証研究者としてやっていけるだろうかという点にあった。かりに学説や理論への関心が強ければ、それなりに北大でも生きていけるだろう。しかし都市社会学を専攻して、都市の諸現象を科学的に解明するという専門家を指向していたのだから、どうしてもデータ処理の技術とそれを支える統計学の基礎だけは身につけたいと思うようになった。
コンピューター操作の個人授業
幸いに北大では大型コンピューターセンターに出かければ、そこでの端末装置を使い、データ処理の練習ができることを知り、授業の合間に15分歩いてそこに出かけて、端末装置の動かし方から使い方を学び始めた。
しかし、どうしても独学では無理な技術があり、その習得には社会学講座の二人の助手に個人授業をお願いした。数理社会学の盛山助教授(現・東大名誉教授)の教え子たちであり、諸事情を考慮して勤務時間外の夕方5時過ぎからや土曜日の午後などに、1回1時間で半年間に10回くらい教えてもらった。もちろん時間外の個人授業なので、薄謝だが毎回お礼をした。
統計学の独習
それによってデータ処理ソフトSPSSがかろうじて使えるようになり、コンピューターによる簡単なデータ処理の技術が身に付いた。
ところが、実際に打ち出されたデータの分布や記号が分からない。統計学の基礎がなかったために、せっかくのデータの分布を読み解けないことに気が付いたのである。そこで赴任後に親しくなった経済学部統計学の助教授に相談したところ、初等統計学のテキストとしてホーエル『初等統計学』(培風館、1970)を紹介してもらった。
ホーエル『初等統計学』の精読
昼間は授業やその準備や会議などでこの本を読めないので、自宅で本気で取り組むことにしたが、分からないことが多かった。
しかし、一方ではコンピューター操作によりSPSSでの簡単なデータ処理ができるようになったので、『初等統計学』のなかでの度数分布、標準偏差、正規分布、確率、ランダムサンプリングなどの章を少しずつ読み進めた。
理解不能であれば、翌日統計学の助教授の研究室に出向いて、直に教えてもらった。そして調査データの解析での基本である「クロス表」の作成に関して、そのχ2検定(カイ自乗検定)の方法と根拠までもしっかり学習した。ここまでで半年間はかかったように記憶している。
電卓でのχ2検定法にも習熟
SPSSソフトでは打ち出したクロス表の下に自動的にχ2値(カイ自乗値)が出るので楽であったが、社会学講義に含めていた「社会調査」の授業でも90分を使ってχ2検定法を受講生に実習をさせようと思い、電卓での計算式にも習熟した。これにより、自らのデータ処理や講義での実習にも自信が得られるようになった。
北大移籍後約1年間で、第1回で紹介したミルズの社会学公式(社会学=IBM+リアリティ+ヒューマニズム)のうち、IBMにすこし近づけたと思えるようになった。
コンピューターの操作も統計学の独習にも縁と運
コンピューター操作の練習では助手の二人に交替で教えてもらい、統計学では経済統計学の助教授によるアドバイスを受けたという縁と運により、自前のテーマでの計量的な社会調査を行えると判断した。
苦労が大きかったが、1年かけて学んだ知識と技術が、その後急速に普及した研究室でのパソコンでもそのまま活かせるようになり、北大定年退職までの科研費による収集した大量データの分析にも威力を発揮するようになった。パソコン技術も初歩統計学の知識についても、根性をいれて学習した甲斐があった。
ワープロの購入
北大に移って最初に購入したのは、当時発売されたばかりのNECのワープロ「文豪」であった。それまでの35年間は原稿用紙やノートに万年筆やボールペンで書いた経験しかなく、ワープロで「文字を打つ」行為も恐る恐る始めたに過ぎない。
講義ノートを手書きで作成するのではなく、ワープロの練習にもなるため、文字を打ってノートを作り始めた。これも私にとってはライフスタイルの大きな変化であり、適応するのには1カ月ほどかかった記憶がある。
「文部省科学研究費」への応募と採択
ワープロ作成書類の第一段階として、1986年~88年の3か年にわたる「文部省科学研究費」向けに「都市高齢者の生活構造の比較研究」という主題をまとめ応募した。初回ながら運よく採択されたので、86年夏に小樽市、87年夏は久留米市、88年夏は札幌市で60歳~80歳までの市民500人をランダムサンプリングして、ゼミ生による訪問面接調査をすることが可能になった。
調査時期を夏にしたのは、それまでの福岡県とは異なり北海道の冬は豪雪のために徒歩による訪問面接調査が不可能であるとの判断による。
前期の定期試験が7月末に終了することを前提にした調査プランを作成した。現地までの往復交通費、宿泊費、学生調査員への調査協力費(バイト代)支払い、ワープロによる作成した調査票の印刷代、3年目の終りの『報告書』印刷製本代などが科学研究費の内訳であった。会計係への入金を確認して、8月上旬の4日間にゼミ生による調査を行ったが、この日程は北大定年退職まで変わらなかった。
小樽調査
初年度の86年夏の小樽調査では試行錯誤の連続であった。北大に移って3年目だったので指導する院生はいなくて、助手にも頼みにくくて、結局はすべてを一人でこなしたからである。
調査員にはゼミ生を中心として20人が集まり、旧式の小樽市「海員会館」の宿泊予約、小樽市役所市民課への調査の挨拶と500人のランダムサンプリングの実施、20人の調査員への調査地点の割り振り、3泊4日の業務として一人25人の訪問面接の指導と実施、目標回収率は70%としたので、最低でも17~18人からの調査票の回収、毎日の夕食時における反省会の実施など、目まぐるしいほどの忙しさであった。
しかし、とりわけ事故もなく、無事に3泊4日の小樽調査を終えて、みんなで小樽駅から札幌駅に帰って、そこで解散した。その後夏休みのゼミ課題として、小樽調査の経験から何を学んだかについてレポートを9月末に出してもらった。1か月あとに21人分の宿泊費を始めとして、学生たちへの交通費や謝金が支払われた。
データ入力
小樽での実際の有効回収は321票(64.1%)であった。2年目の久留米調査では66.5%、3年目の札幌調査も60.3%であったので、都市での訪問面接調査結果としては満足できる回収率であった。
調査が終了して、回収した調査票の記入漏れや書き間違いなどのデータクリーニングも自分で行い、総回収334票のうち有効と判断した321票を北大生協がビジネスとして始めていたデータシートづくりに発注した。
2か月後にフロッピーディスクに入力されたデータセットを受け取り、大型コンピューターセンターの端末機にそのデータを入力して、そこからSPSSソフトを使ったデータ分析を開始したが、これは調査が終わった秋から冬にかけての業務となった。何しろ初心者マークの技術だから、データ分析がなかなか捗らなかった。
科研費『報告書』の刊行
当時は3年間の研究成果は、すべて『科学研究費報告書』として3年目の年度末までに印刷製本する義務があった。札幌調査結果がコンピューター入力できたのは最終年度の12月であったため、札幌データはあまり使えなかったが、小樽調査と久留米調査結果を使って科研費の領収書として『報告書』を出した。
それだけで止めてもよかったのだが、ともかくも自前の科研費の調査で3都市のデータを収集したのだから、1年間で身につけた初歩的なコンピューター操作と入門レベルの統計学の知識を活用して、科研費の『報告書』とは別に、半年毎に1本の論文を書きあげようと決意した。
「都市高齢者のネットワーク構造」から
まずは社会学の本流である「社会関係」や「集団参加」の実態を、3都市での比較分析を行なった。図1のように、これは前回紹介した「老人問題史観」を批判して、高齢者もまた一人の市民であり、いくつもの「役割」を担っているという前提で、その社会的ネットワーク構造を明らかにして、「老いと孤独」といった通説を見直したいという仮説で行なった。
図1 高齢者個人の社会的ネットワークの構造 (出典)金子、1993:118.
社会的ネットワークの実態、地域福祉、近隣関係
3都市の調査票は同じ内容だったから、そのままデータの比較ができ、その統計学的処理を基にして分析を行った。これは北大に移ってからの初めての体験であり、それまでとは異なる実証的な論文を書いているような気がした。
解明したい第二の課題としては、高齢者の社会的ネットワークの実態が、「地域福祉」の要件であるコミュニティ形成とどのような関連にあるかを明らかにすることであった。そのために高齢者個人の「近隣関係」やボランタリーアソシエション(V.A)としてのさまざまな地域関連の団体への参加状態を調べて、大都市札幌と中都市久留米と小樽の間の比較を試みた。たとえば3都市の近隣関係が図2のように確認できた。これは調査票でしか得られないデータであり、統計学的なχ2検定法により、この3都市間の「近隣関係」の量的相違が証明されたことを喜んだものである。
なぜなら図2から、大都市札幌市高齢者の「近所の友人数」の「なし」が、久留米市や小樽市よりもはるかに多いことが統計学的に裏付けられたからである。
さらに同じ中都市でも九州の久留米市の方が北海道の小樽市よりも「近所の友人」が多いことも証明されて、「地域福祉」の方向性を確認できた。小樽市に象徴される北海道都市は、明治期からの移住者の集合なので個人レベルでの自力路線が強いが、江戸時代からの定住者も多く、地縁や住縁が強い九州都市の久留米市とは明らかに異なった近隣関係を示していた。
図2 高齢者の近所の友人数 (出典)金子、1993:138
『社会学評論』第38巻第3号(1987年)に掲載
札幌市の調査は1988年だったので、1986年小樽調査と1987年久留米調査のデータを比較分析した論文を、学会編集委員会に送ったところ、査読の結果受理されて、学会誌『社会学評論』第38巻第3号(1987年)に掲載された。これが学会誌2回目の掲載になった。
「高齢者の都市アメニティ」
次に、当時の都市研究で盛んに使われはじめていた「アメニティ」を課題とした論文を書いた。アメニティとは「快適性」なのであるが、多くの先行研究では「場所、環境・気候などの快適性」というハードな文脈に収斂していて、社会学がテーマとするソフト面の人間関係の持つ「住み心地のよさ」への配慮が不足していると思われた。そこで、ハードとソフトの両面から「都市アメニティ」を測定しようと考えて、3都市の調査票に関連項目の質問文を入れていた。図3がその全体的なモデルである。
図3 都市アメニティの分析図式 (出典)金子、1993:182
「高齢者の都市アメニティ」のモデル
要するに、(Ⅰ)都市のハードパフォーマンス、(Ⅱ)集団活動への参加、(Ⅲ)高齢者の社会的ネットワーク、(Ⅳ)都市のソフトパフォーマンスに分けて調査票によりデータを収集して、最終的には3都市データそれぞれで「都市アメニティ」を被説明変数とする重回帰分析を行った。ここまでの技術はホーエルの『初等統計学』とコンピューター操作の延長上で身につけていた。
その結果、図4のような結果がいくつも得られて、「都市アメニティ」としての「住み心地よさ」を押し上げるのは、「安全環境」「体験環境」「地域の統合性」(まとまり)、「伝統的祭り・行事の継承」などであることが判明した。
図4 高齢者の都市アメニティ (出典)金子、1993:196
第1回の「日本計画行政学会賞」を受賞
「都市アメニティ」の比較結果は日本都市でのアメニティ政策にも寄与できると考えて、日本計画行政学会が編集発行する『計画行政』に投稿したら、無事に1988年の第20号に掲載された。全くの偶然であるが、その翌年の1989年に「日本計画行政学会賞」の制度ができ、本論文はその第1回目の受賞をしたのである。授賞式が行われた1989年(平成元年)11月11日は忘れられない記念日となった。
「高齢者の都市地域集団関係」
第3には、町内活動など都市の地域集団関係の比較やボランティア活動などの現状が大都市札幌と中都市久留米でどのように違うのかなどを明らかにするために、関連データを比較分析した。
老人クラブ活動、学習活動、趣味娯楽活動、奉仕活動、スポーツ活動、宗教活動などの実態を踏まえた比較分析だったが、久留米の高齢者の方が札幌高齢者よりも集団活動が熱心であるという結果を得た。この論文は倉沢・秋元編『町内会と地域集団』(1990)に寄稿した。
1990年まで3都市比較の論文を書き続けた
それら以外にも「都市化とボランタリーアクション」と「地域福祉と都市コミュニティ研究」を別々の雑誌論文として発表した。
何しろ独自の3都市の調査結果を得たのであるから、テーマを変えながら、先行研究を概観して、調査票に盛り込んだデータを比較しながらの論文執筆が1990年くらいまで断続的に続いた。
博士論文執筆を慫慂される
「計画行政学会賞」受賞を1989年12月に福岡に出かけ鈴木広先生にご報告した際に、先生から受賞のお祝いをいただき、そのうえでそろそろ学位論文を準備してはどうかというアドバイスをいただいた。
前回紹介したように、長い間九大の文学研究科での「文学博士」の学位は、かなりな年配の方が大きな業績をまとめたら授与するという「伝統」があったように思われてきたが、文部省は可能なかぎり全学部でも「博士学位」を出すように方針転換を変え、それが周知徹底され始めていた。そのような事情で「博士論文」執筆の話になったのであろう。
「博士論文」審査では、教授会で主査1人副査2人の3人体制の審査委員会を作り、半年かけて業績を審査して、教授会用、大学本部用、公開用の書類作成が義務付けられる。しかも主査も副査も通常の講義、ゼミ、会議はそのままであり、多忙になることは間違いない。これは私が北大で10名程度の主査を経験して分かったことであり、当時はこのような事情は何も知らなかった。
『都市高齢社会と地域福祉』を目指して準備を始めた
もちろん「博士論文」執筆のアドバイスは恩師のありがたいご配慮なので、ひとまず2年がかりで1冊の本を書き上げようと決意した。
調査データを使った論文をメインの第Ⅱ部にして、第Ⅰ部は先行研究の理論のまとめ、社会システム論に立脚した高齢者の「役割理論」を整備して、都市高齢者調査の仮説などを書き、第Ⅲ部は高齢者行政向けの研究成果を揃えようと構想を練った。
ただし、次回に取り上げる長谷川公一東北大学助教授との共著『マクロ社会学』の話がすでに出版社主導で同時進行していたので、博士論文の準備は自宅で行い、『マクロ社会学』関連は研究室でやることにした。
以後70歳ですべての大学業務から引退するまで、このような別々の本の準備を同時進行する作業をあと2回経験することになるが、この2冊の準備がその最初であった。
「博士文学」の学位取得
幸いなことに『都市高齢社会と地域福祉』の原稿は2年で書き上げて、ミネルヴァ書房から1993年2月に「都市社会学叢書3」として刊行された。北大移籍後3冊目であり、それにはほぼ10年を要したことになる。
本書をさっそく九州大学に博士論文として3月に提出して、文学研究科で最終面接を含む学位審査(主査は鈴木広教授)をしていただいた。その結果、10月13日付で「学位授与」が決定したという通知が本部の事務局長名で届いた。そしてその年の12月に九州大学の会議室で「学位授与式」があり、「学位記」をいただいたのである。44歳での学位であり、これによって翌年教授に昇進した。
博士論文が5刷になった
本来は「博士論文」なので、単著にしても売れないだろうというミネルヴァ書房の予想であったが、たまたま厚生省が地域福祉を強化する方針を打ち出した時期だったので、いくつかの「書評」でも好意的に取り上げていただけた。
なかでも一番驚いたのは、日本都市社会学会誌『日本都市社会学会年報』15号(1997)の特集号のテーマが「都市高齢化と地域福祉」になり、私の巻頭論文を加えて5本の論文が集まったことである。そのような「地域福祉」ブームもあり、本書はなんと5刷まで行ったのである(画像は5刷)。
※ 日本都市学会賞(奥井記念賞)受賞後の5刷
「日本都市学会賞」を受賞した
しかも、その年に北海道都市学会が「日本都市学会賞」の候補として本書を日本都市学会本部に推薦して、翌年の1994年の「日本都市学会賞」を受賞することになった。慶応義塾大学の塾長をされた奥井復太郎先生を記念した「奥井賞」であり、偶然にも授賞式は10月28日に三田の慶応義塾大学で行われた。
北大移籍後のコンピューター操作の練習、初等統計学の独習、科研費による3都市調査の思い出、データ処理とその解読作業、そしてテーマを決めての論文執筆、1冊にまとめ直す作業など10年間の「縁と運」の思い出が浮かんできて、授賞式では感無量であった。副賞の「オノト 万年筆」(丸善)は40年間使ったが、昨年その役割を終えた。
本書により2つ目の学会賞を受賞して、「博士文学」を取得した。その意味で苦労した甲斐があった本であり、その後の私の進路を決定付けてくれた。
一つは社会変動としての高齢化の延長にある『マクロ社会学』の応用、もう一つは高齢社会の到来にたいしてコミュニティ論を土台にした地域福祉で対応できるかどうかの模索であった。
これらもまたほぼ同時進行で準備することになった。
【参照文献】
- Hoel,P.G.,1966,Elementary Statistics2th, John Wiley &Sons,Inc.(=1970 浅井晃・村上正康訳『初等統計学』培風館).
- 金子勇,1987,「高齢者の社会的ネットワーク構造」日本社会学会編『社会学評論』第38巻第3号:32-46.
- 金子勇,1988,「高齢者の都市アメニティ」日本計画行政学会編『計画行政』第20号:84-93.
- 金子勇,1990,「高齢者の都市地域集団関係」倉沢進・秋元律郎編『町内会と地域集団』ミネルヴァ書房:109-128.
- 金子勇,1993,『都市高齢社会と地域福祉』ミネルヴァ書房.
- 日本都市社会学会編,1997,『日本都市社会学会年報15 都市高齢化と地域福祉』同学会.
【関連記事】
・時代解明の「縁、運、根」の社会学:問題意識と方法 ・『コミュニティの社会理論』の「縁、運、根」 ・『高齢化の社会設計』の「縁、運、根」



