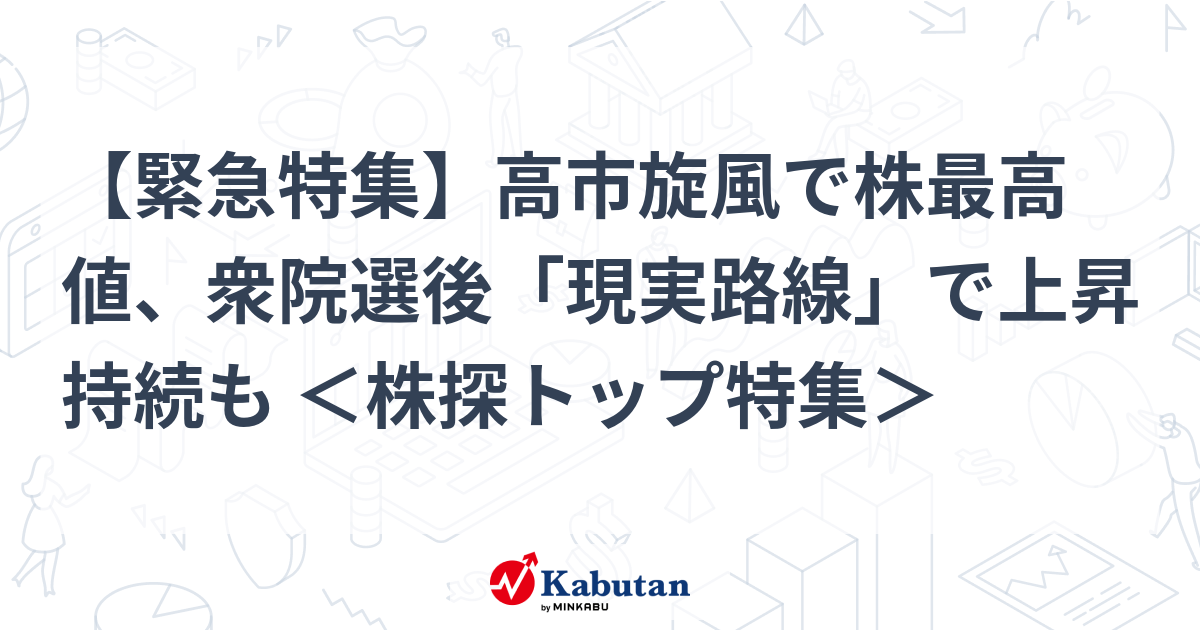「カシオペア」に「サロンカーなにわ」……鉄道車両の「引退ラッシュ」だった6月を振り返る

6月から7月に入り、2025年も折り返し地点を過ぎました。その6月には、鉄道ファン以外からも人気を集めた車両など、さまざまな鉄道車両が引退しました。長年の運用を終えた車両たちを振り返ります。
1999年7月に運転を開始した「カシオペア」は、6月30日に上野駅に到着した団体臨時列車をもって、営業運転を終了しました。
6月30日着の団体臨時列車をもって営業運転を終了した「カシオペア」「カシオペア」は、かつては上野~札幌間を結んでいた寝台特急でした。青函トンネル開通と同じ1988年に登場した「北斗星」よりもさらに上の寝台特急として誕生しており、客室はすべてA寝台個室という、当時としてはハイグレードな列車でした。2015年の北海道新幹線開通を機に、「カシオペア」は定期的な運転を終了。以降は「カシオペア紀行」などの団体臨時列車として運転されてきました。
「カシオペア」の引退は、それまで続いてきた、一般的な客車寝台列車の終焉と言えるかもしれません。実際には、2016年以降の「カシオペア」は団体臨時列車としての運転で、他方クルーズトレインではありますが、JR九州の「ななつ星 in 九州」は、客車列車として運転されています。しかし、(衰退期であったとはいえ)全国各地で寝台列車が運転されていた時期を知る寝台客車は、今回の「カシオペア」運転終了で、すべて現役を退くことになります。7月以降も残る寝台列車は、クルーズトレインを除けば、「サンライズ瀬戸」「サンライズ出雲」の2列車のみです。
なお、営業運転こそ終了した「カシオペア」ですが、7月12日には上野駅のイベントで展示される予定。旅客を乗せることはありませんが、車両の仕事はまだ残されています。
「カシオペア」最終営業日と同じ6月30日には、JR東海の311系も、一般列車での営業運転を終了しました。
1989年から名古屋圏で活躍していた311系311系は、1989年にデビューした近郊型車両。JR東海発足後、同社が新形式としては初めて投入した在来線一般車両です。当時は、721系、221系、6000系、811系と、3扉・転換クロスシート車両がJR各社(JR東日本を除く)で投入されていた時期。JR東海も311系を投入することで、東海道本線の車両快適性向上を図りました。
現在のJR東海では、2022年より315系を順次導入しており、211系、213系、そして311系の置き換えが進められてきました。同社の211系は2025年3月に運用を終了。そして311系も、6月末で定期列車の運用から退きました。
定期運転こそ終了した311系ですが、7月12日には臨時列車の運転が予定されています。これは車両基地から車両解体スペースがある場所までの「廃車回送」ですが、今回はツアー企画としてファンも乗車します。ツアーはすでに満員となっていますが、黎明期からJR東海で活躍してきた車両の、最後の花道を飾る旅となりそうです。
6月21日には、JR西日本の「サロンカーなにわ」が、ラストランを迎えました。
団体臨時列車向けとして改造された「ジョイフルトレイン」では唯一の生き残りだった、JR西日本の「サロンカーなにわ」(しげまろさんの鉄道コム投稿写真)「サロンカーなにわ」は、国鉄時代に登場した「ジョイフルトレイン」の一つ。ジョイフルトレインは、元々は団体輸送用に適した車両として製作されたもので、ほとんどが余剰となった客車や電車を改造したものでした。ただし、大きく改造された車両では、展望室や個室、お座敷などが設置されるなど、通常の車両とは大きく異なる設備となっていました。この「サロンカーなにわ」は、14系客車を改造し、1983年に登場。編成両端には展望室が設置されており、その他もグループ利用を想定した座席と、やはり一般的な車両とは異なる設備を持つ車両でした。
しかし、近年の鉄道車両は、一般的な車両と異なる設備を持つものは少なくないものの、そのほとんどは個人旅行をターゲットとした観光列車的なもの。かつてのように団体輸送用に製作され、かつ2020年代まで残った車両は、「サロンカーなにわ」が最後でした。
6月21日、「サロンカーなにわ」は、団体臨時列車「サロンカー晴れの国おかやま号」として、大阪~岡山間を往復。その後、6月23日には中間車が、25日~27日には車端側の1両が、それぞれ所属基地を去っています。
私鉄の車両で唯一、6月に営業運転を終了したのが、わたらせ渓谷鐵道のわ89-310形。最後に残った314号車が、6月30日にラストランを迎えました。
わ89-310形(右、今回引退した車両の同型車)わ89-310形は、わたらせ渓谷鐵道線の開業翌年、1990年に登場した車両。バスの部品(エンジン含む)を活用していることから、「レールバス」と呼ばれていたといいます。わ89-300形、わ89-310形、さらに両形式より小型だったわ89-100形は、いずれも富士重工業(現在のSUBARU)が製造した鉄道車両。当時の富士重工がローカル線向けに開発していた、バス部品の活用によって製作コストを抑制した車両群の一つでした。