米が不足するほど買い求める人は増える(田中淳夫)
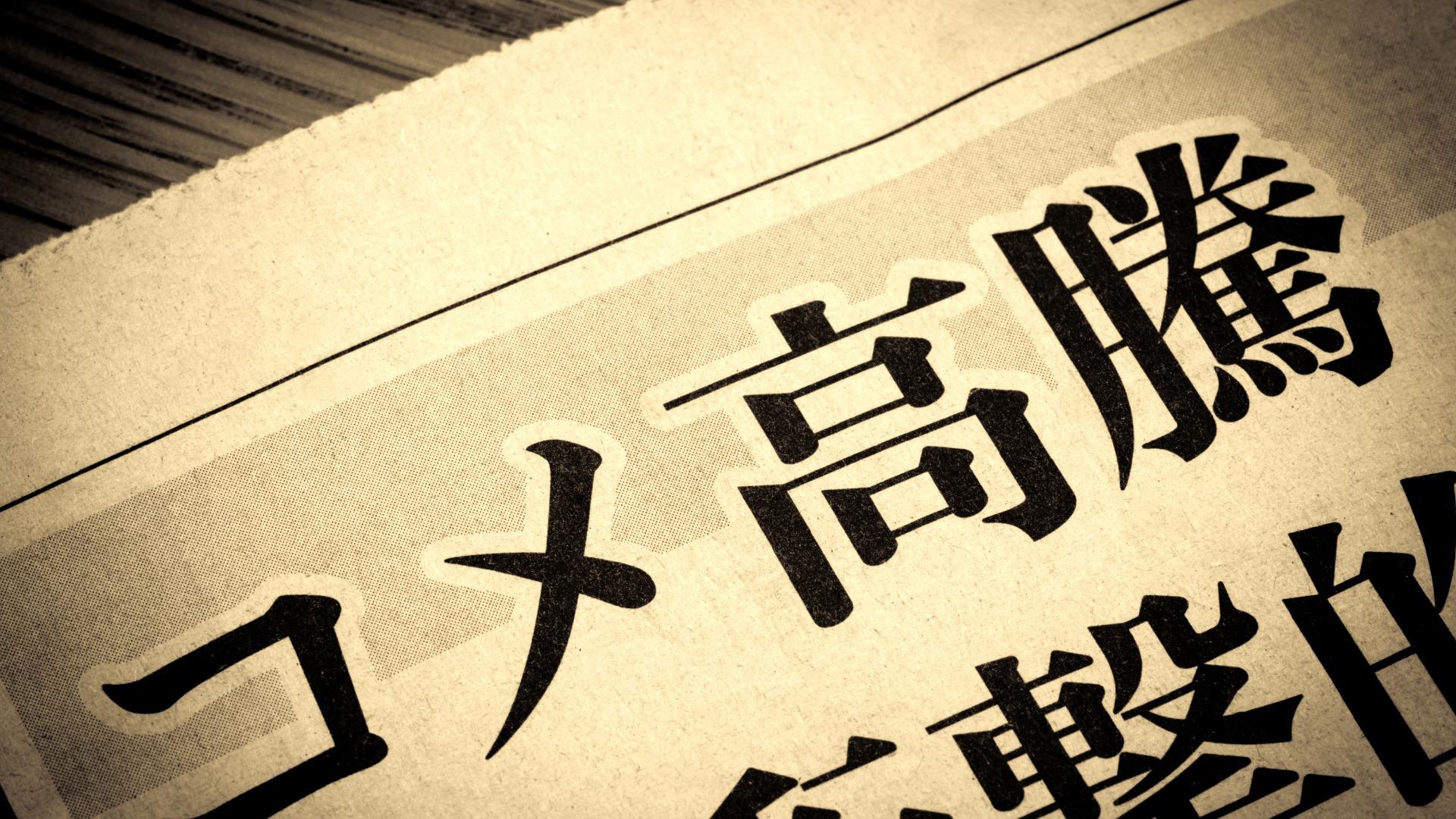
米の価格高騰が長引いている。
その理由として、さまざまな説明がされる。流通が目詰まりを起こした、投機的な買占めが行われている、そもそも米の絶対量が足りていない……なかには政府やJAの陰謀論まで登場している。
以前もよく似た話があったな、と記憶をたどれば、ウッドショック(2020年~22年)だった。木材価格の高騰が世界的に起きたが、その際もそんな言説が飛び交った。
結果として、木材は十分あったのに価格が上がっていた。そこには需給バランスの乱れや流通の問題だけでなく、木材業者の買い占め行動があったと言われている。
そこで今回の米不足と高騰問題を消費者の行動から俯瞰してみたい。そのため心理学的に人々の経済活動を読み解く行動経済学の理論を当てはめてみた。
まず米問題は「不確実性下での意思決定」に当たる。
人間は不確実な事態に直面した際、合理的な判断よりも感情や直感に基づいて行動する傾向が強い。加えて「損失回避バイアス」があり、利益を得ることよりも損失を避けることを強く求める。
米の品切れ状態を目にして不安が広がったため「損失」を避けるために、必要以上の購入を行う消費者が増加したことが考えられる。
通常の消費者行動なら価格が上がれば購入を控えるものだが、価格の上昇が今後も続くかもしれないと消費者が考えると、今のうちに買っておこうという心理が働く。しかも「ゼロリスクバイアス」もあった。米不足リスクを完全に排除したいという心理が強くなり、高くても必要以上の量を購入してしまうのだ。
不安感は集団内で増幅され、買いだめ行動が広がる「群集心理」もある。他者の行動に追随する「同調バイアス」も強まる。
結果的に購入者・購入量が増えて品不足を招き、また価格を上昇させる。
いわゆる「パニック買い」である。コロナ禍初期のマスクやトイレットペーパーの買い占めなども記憶に新しい。米も、食料という欠かせないものゆえに、よりパニックに陥りやすく、極端に走りがちなのだろう。
そしてメディアによる情報の拡散も無視できない。マスコミは、否定的な情報ほど重要と考えがちで、熱心に報道する傾向がある。それはテレビや新聞のニュースに留まらない。ワイドショーや週刊誌、街の情報誌でも取り上げる。
1993年に冷夏による作付け不良が原因の米不足が起きている。マスコミはそのニュースを連日流すとともに、雑誌では「美味しい米の食べ方」や「ご飯が美味しい店」といった特集が増えた。米不足がキーワードとなり、米に関する記事なら何でも載せればウケる、読者が飛びつくという意識も編集者には働いたのだろう。
実は私もそうした記事を執筆する最前線にいたから、よく記憶している。私の場合は、米が手に入らない場合はどうするか、という取材をしていた。外米の味まで解説した。
米不足が報道されることで、米が食べられないという危機意識が広まると、逆に米を求めるという倒錯した現象も起きがちだ。普段はダイエットなどを理由に米をあまり食べなかった人まで、ご飯を食べたがる。外食では大盛りを注文する。結果的に通常以上に米を求める消費者を増やしてしまった。
そうなれば家庭でも外食店でも、米を多く確保しようと動く。高値であっても必要以上の米を購入して在庫を抱えるのである。
どうやら米不足の一因として、一部の業者が投機的に米を買い占めたと見るよりは、流通業者や外食業界、そして個人までが自己防衛的に米を買い増して、それが米の流通を滞らせた可能性が高いように思える。
だが、ここで冷静になって考えてみよう。
昨年の作柄は、前年より良かったことが後に知られる。前年比で3%増の18万2000トン増えた679万2000トンだ。これは6年ぶりの増加だった。
一方で今年になって備蓄米が放出されている。現在も進んでいるので全体量はわからないが、おそらく30万トンを超えるだろう。さらに輸入米も増えている。潜在的に通年よりも多いコメが市場に流れ込んでいるのである。今年は、米の作付けも増やしているから、夏以降はさらに多くの米が収穫されるだろう。
一方で日本の人口は確実に減少し続けている。口が減っては、米を食べる量も増えない。インバウンド需要も量的にはコンマ以下だろう。だから総体で見れば、供給量が消費量を上回るのは間違いない。
つまり、いつかコメがだぶつく時は来る。
米の保管には冷蔵倉庫が必要で、品質を落とさず在庫するのは難しい。買い占めに走った人や業者も、遠からず在庫を放出することになるだろう。
1993年の米不足時は、中国やタイ、アメリ、オーストラリアなどから米を緊急輸入した。全体でざっと260万トン以上。しかし翌年約98万トンが売れ残った。タイ米が公園に捨てられていた事件も発生した。
またウッドショック後も、木材の在庫はだぶつき、価格暴落を引き起こした。山元は、拙速に伐採して森を荒らした後始末と、価格低迷に苦しむ。そうした後遺症は、今も続いている。
今回、同じことにならないように願いたい。
日本唯一にして日本一の森林ジャーナリスト。自然の象徴の「森林」から人間社会を眺めたら新たな視点を得られるのではないか、という思いで活動中。森林、林業、山村をメインフィールドにしつつ、農業・水産業などの一次産業、自然科学(主に生物系)を扱う。著書に『樹木葬という選択』『鹿と日本人 野生との共生1000年の知恵』(築地書館)『絶望の林業』『虚構の森』(新泉社)『獣害列島』(イースト新書)、『山林王』(新泉社)など。Yahoo!ブックストアには電子本『ゴルフ場に自然はあるか? つくられた「里山」の真実』。最新刊は、全国で頻発する森林犯罪を告発した『盗伐 林業現場からの警鐘』(新泉社)。



