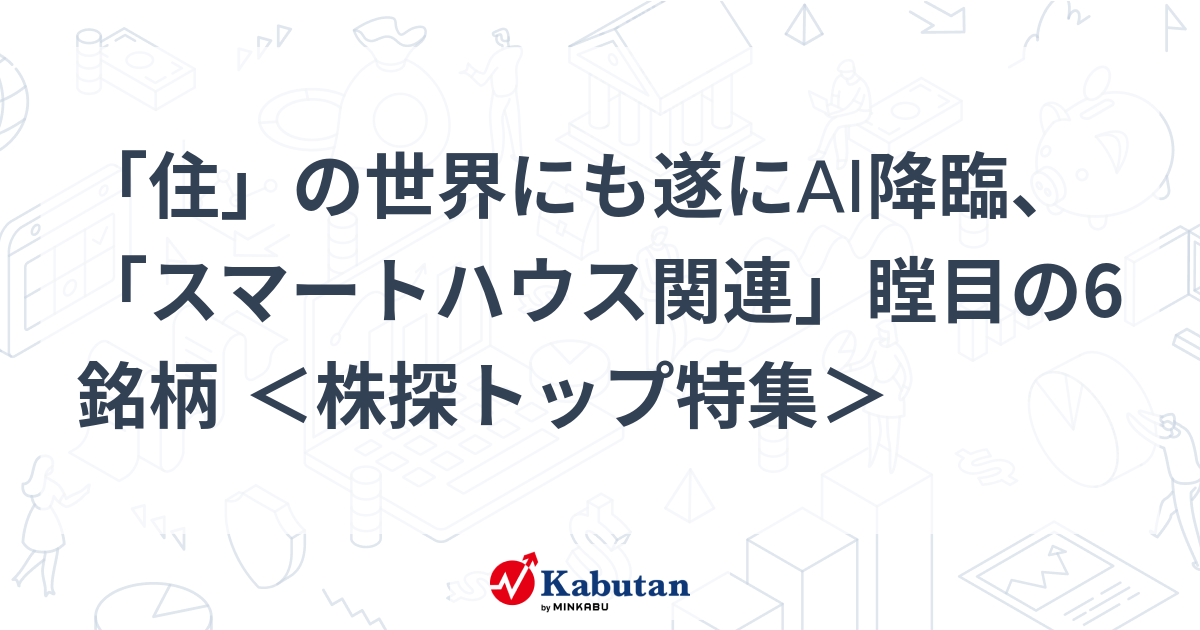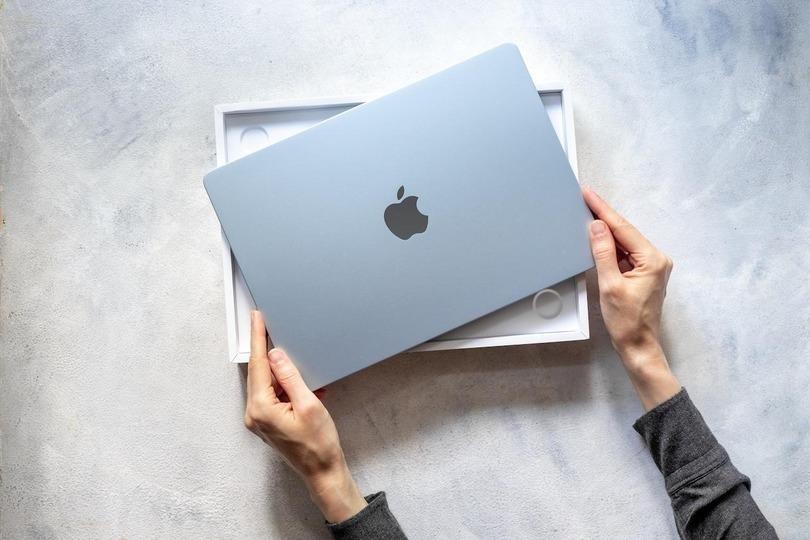GPT-5の影に隠されたOpenAIの「破壊的」新戦略。グーグルも勝てない方法で“AIのOS”になろうとしている(BUSINESS INSIDER JAPAN)
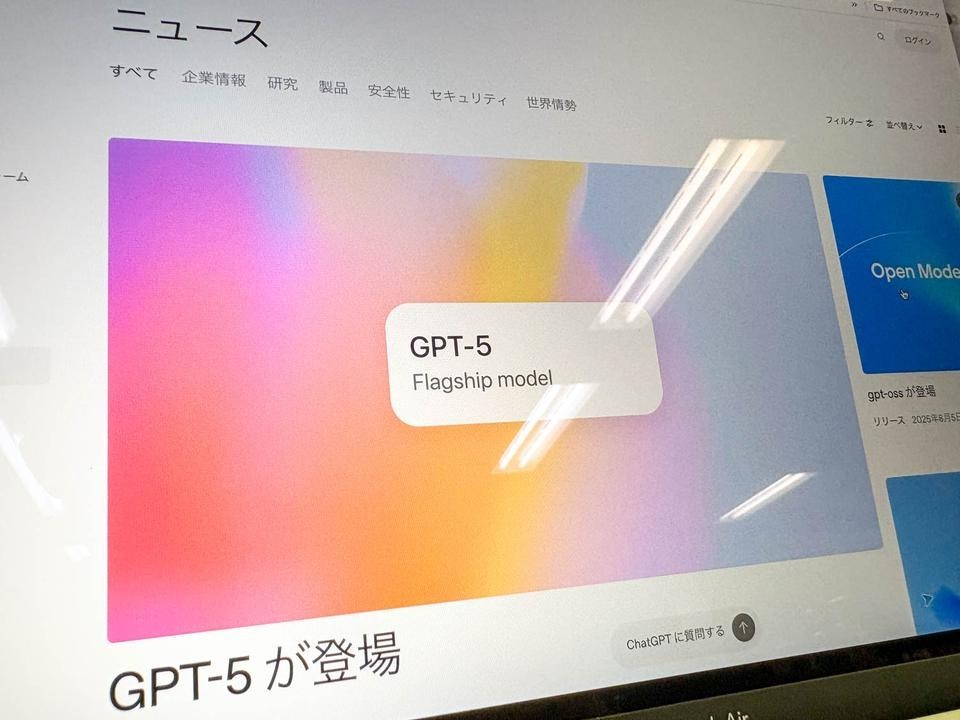
前編「gpt-ossはなぜ『事件』なのか」に続く後編では、OpenAIのオープン化に隠された破壊的インパクトについて掘り下げます。 【全画像をみる】GPT-5の影に隠されたOpenAIの「破壊的」新戦略。グーグルも勝てない方法で“AIのOS”になろうとしている gpt-ossでOpenAI、メタ(旧Facebook)の戦略はどう変わるか? 前編「gpt-ossはなぜ『事件』なのか」では、このレベルのLLMがローカル環境で動くことのインパクトをかいつまんで解説した。 gpt-ossは、AI業界の巨人が莫大なコストをかけて開発してきたLLMトッププレイヤーの戦略そのものに大きな影響を与えうると筆者は考えている。 清水亮 / Ryo Shimizu[経営者、研究者、プログラマー] ギリア株式会社ファウンダー・顧問。株式会社ゼルペム所属スペシャリスト。1976年長岡生まれ。米大手IT企業で上級エンジニア経験を経て1998年に黎明期の株式会社ドワンゴに参画。2003年に独立して以降19年間に渡り、5社のIT企業の創立と経営に関わる。2018年〜2023年まで、東京大学 客員研究員として人工知能を研究。主な著書に『よくわかる人工知能』など
この半年の間で、オープンウェイト(オープンソース含む)モデルは飛躍的に進歩した。これはAI研究者の間での共通認識と言っていい。 特にメタのオープンウェイトモデル(制限付きオープンモデル)の「Llama4」は、一般的なクラウドLLMよりもコンテキスト長で遥かに上回り(一般的なクラウドLLM=100万トークン、Llama4=1000万トークン)、一方推論性能に関しては、筆者のテストではアリババのQwen3が頭一つ抜きん出た印象だった。 しかし、gpt-ossが登場したことで、競争は次の領域に進んだと筆者は考えている。 これまでは、GPTシリーズという、「チャンピオン」に対して、Qwen3やLlamaなどが「挑戦者」として戦うという構図だったのが、gpt-ossの登場によって、「同じフィールド」での戦いに降りてきた。これは実はQwen3やLlamaにとって、苦しい戦いになることを意味している。 仮に今後OpenAIが、5月の発表のとおり本当に公益団体に徹し、今後常に無償でオープンソースのLLMを配布し続けることになるとすれば、OpenAIは最強の存在になってしまうからだ。アリババやメタ、そしてもちろんグーグルは、営利企業であり、最終的には研究開発費をどこかで回収しなければならない。