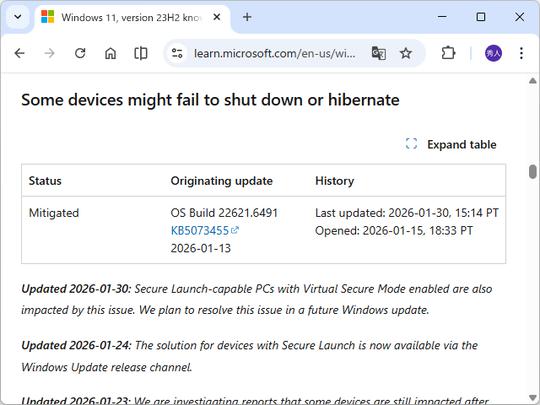愛知県豊明市の「スマホ1日2時間」条例可決にSNS「意味ある?」「同調圧力」…内容は医学的に妥当? 医師に聞く

愛知県豊明市で、余暇時間におけるスマホの使用時間について、「1日2時間以内」を目安とするよう市民に促す内容の条例案が9月22日に可決しました。この目安が医学的に妥当なのかについて、医師に聞きました。
愛知県豊明市の市議会で9月22日、「豊明市スマートフォン等の適正使用の推進に関する条例案」が可決されました。この条例は余暇時間でのスマホの使用時間について、「1日2時間以内」を目安にするよう市民に促す内容が盛り込まれており、10月1日に施行されます。罰則や強制力はありません。
市はこの条例の目的について「市民の皆さまの適切な睡眠時間の確保」と公式サイトで説明していますが、今回の条例の可決について、SNS上では「スマホ依存症からすればむしろありがたい」「スマホ2時間制限って本当に意味ある?」「同調圧力で縛るつもり?」「実際に守れる人はどれくらいいるんだろう」「わざわざ条例にすんな」など、さまざまな意見が上がっています。
余暇時間でのスマホの使用時間の目安を1日2時間以内としているのは、医学的に妥当なのでしょうか。スマホの過剰使用による心身への影響について、林外科・内科クリニック(福岡県宗像市)理事長で医師の林裕章さんに聞きました。
Q.愛知県豊明市の市議会で9月22日、「豊明市スマートフォン等の適正使用の推進に関する条例案」が可決されました。この条例では、余暇時間でのスマホの使用時間について、「1日2時間以内」を目安としていますが、これは医学的に妥当なのでしょうか。
林さん「結論から言えば、特に子どもにおいては『1日2時間』という目安は医学的にも妥当なラインです。
日本小児科医会は、以前から『すべてのメディアへの接触時間は1日2時間まで』と提言しています。これは、幼児期や学童期の子どもたちの健やかな発達には、実体験を通じた学びや、家族、友人との直接的なコミュニケーション、そして十分な睡眠が不可欠だからです。
WHO(世界保健機関)は2~4歳の子どもについて、座り込んだ状態でスマホやタブレットなどの画面を見る時間を1日1時間以内に抑えるよう勧告しています。
また学齢期から思春期の子どもに関して、米国小児科学会(AAP)は一律の分数ではなく、家庭ごとの『ファミリー・メディア計画』で時間と内容を管理する方針を掲げています。ただし『就寝の1時間前からはデバイスの使用を避ける』『寝室に持ち込まない』などの原則を推奨しています。
国や学会による数値例ですが、カナダの24時間運動ガイドラインでは5~17歳の子どもについて、余暇におけるスマホやタブレットなどの視聴時間を1日2時間以内に抑えるよう推奨しています。成人については、国際的な統一分数は設定されていません。
豊明市の条例が示す『2時間』は、こうした小児科的な知見と一致する、子どもの健康を守るための合理的な目安と言えるでしょう」
Q.スマホを使い過ぎると、心身にどのような影響を与える可能性があるのでしょうか。
林さん「スマホの過度な使用は、私たちが考える以上に心身にさまざまなリスクをもたらします。例えば、スマホの画面を長時間見続けると、目に大きな負担をかけるとされています。また、不自然な姿勢でのスマホ操作は、首や手首に大きな負担をかけます。主な症状は次の通りです」
・スマホ老眼(調節緊張) スマホの閲覧時に近い画面にピントを合わせ続けることで、目のピント調節機能が凝り固まり、一時的に遠くが見えにくくなる状態です。
・近視の進行 特に成長期の子どもが近くの物を見続ける「近見作業」は、近視を進行させる主要な要因の一つです。
・ブルーライトの影響 ブルーライトは、網膜へのダメージや、睡眠を促すホルモン「メラトニン」の分泌を抑制し、体内時計を乱す可能性があると指摘されています。対策として「20‐20-20ルール」が推奨されています。これは、20分画面を見たら、20フィート(約6メートル)先を20秒間見て目を休ませるという取り組みです。
・ストレートネック(テキストネック) 本来は緩やかにカーブしている首の骨(頸椎<けいつい>)が、うつむき姿勢を続けることで真っすぐに近い状態になります。これにより、首や肩の凝り、頭痛、めまい、吐き気などを引き起こしやすくなることがあります。その他にも、狭窄性腱鞘炎(きょうさくせいけんしょうえん、ドケルバン病)や肘部管症候群などのリスクがあります。
・スマホ依存(嗜癖<しへき>) 「スマホがないと不安になる」「使用時間をコントロールできない」などの状態です。
・睡眠障害 寝る前のスマホ使用は、ブルーライトの影響と、コンテンツによる脳の興奮作用で寝付きを悪くし、睡眠の質を著しく低下させます。
・うつ、不安障害 SNSなどで他者と自分を比較し、劣等感を抱いたり、ネット上の誹謗中傷に心を痛めたりすることで、うつ病や不安障害のリスクが高まることが指摘されています。
Q.余暇の時間にスマホの1日当たりの使用時間を2時間以内に収めることは可能なのでしょうか。
林さん「現代生活において、スマホの使用時間を2時間に収めるのは容易ではありません。しかし、意識的な取り組みで実現は可能です。重要なのは『目的のないダラダラ使いをなくす』ことです。スマホの使用時間を減らすのに効果的な取り組みを順番に紹介します」
■現状把握 まず、スマホのスクリーンタイム機能で、自分が何にどれだけ時間を使っているかを確認しましょう。「こんなに動画を見ていたのか」と驚くかもしれません。
■ルール作り 「食事中はスマホをテーブルに置かない」「寝室に持ち込まない」「午後9時以降は通知をオフにする」など、具体的なルールを家族で話し合って決めましょう。
■デジタルツールの活用 アプリの使用時間を制限する「アプリタイマー」や、一定時間スマホを操作できなくする「フォーカスモード」などを活用するのも有効です。
■物理的に距離を置く 勉強や仕事中は、スマホを別の部屋に置くなど、物理的に遠ざけることで、無意識に手に取ることを防げます。
■代替活動を見つける 読書や運動、音楽など、スマホの代わりに楽しめる趣味を見つけることが、最も本質的な解決策です。特に、体を動かす活動は心身の健康に多くの好影響をもたらします。
(オトナンサー編集部)