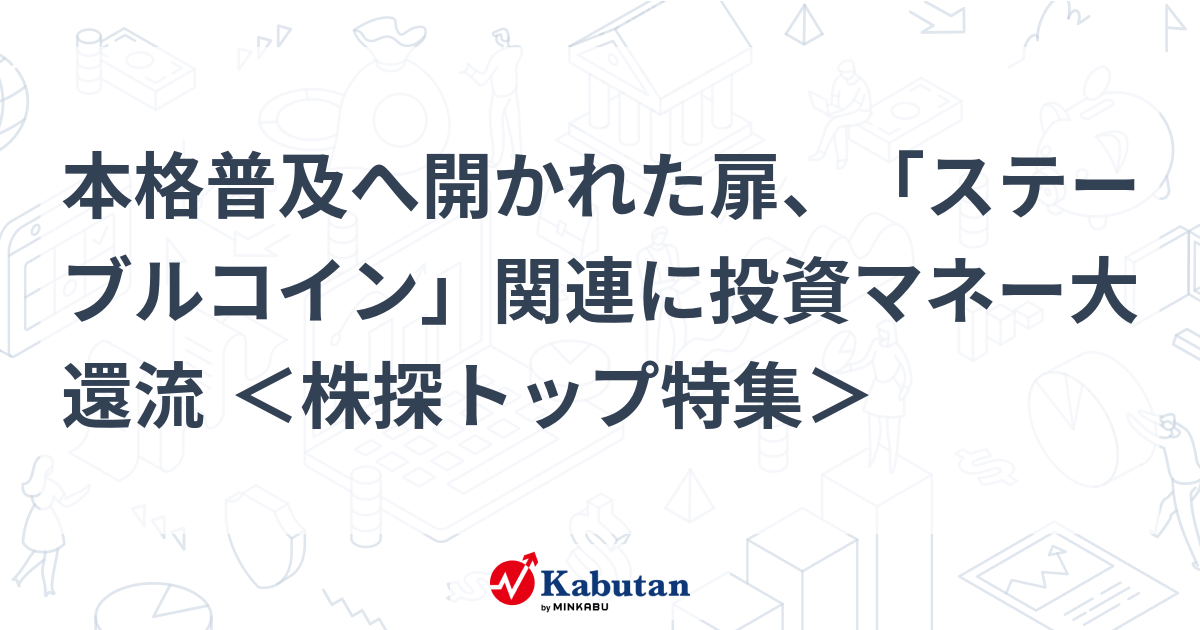国債市場救えぬ日銀、「風殺」買いオペ連発の異様-長期金利高を助長

本来は国債相場を下支えするはずの日本銀行による買い入れオペが、むしろ市場の不安要因になり始めた。一部投資家の大口売却で買い入れ枠が全て埋まる異例の事態が立て続けに発生し、日銀に対し売却できなかった投資家が流通市場で処分するため、10年債利回りの上昇に拍車がかかっている。
定期的に国債を買い入れ、市場に資金を供給する日銀オペでの最初の異変は14日だ。5年超10年以下のゾーンで単独かごく少数の金融機関の売却で予定額を消化し、他は応札しても売却できない「風殺」と呼ばれる状況が10年ぶりに起きた。20日も同様の事態が繰り返され、ブルームバーグの調べでは2回連続の風殺は異次元金融緩和策を導入した2013年以降初めてだ。
世界的にインフレ対策や景気刺激の必要性から財政支出拡大への懸念が強く、米国の30年債利回りは7月に一時5%を回復し、ドイツも11年来の高水準を付けた。日本でも30年債は過去最高利回りを付け、金利上昇の勢いは超長期から長期ゾーンにも波及。10年債は08年以来となる節目の1.6%を超えた。
国内金利が急上昇する背景には根強い日銀の追加利上げ観測がある。金利ある世界に戻る中、長年続いた超緩和策のひずみが流動性の低下やボラティリティーの上昇に加え、風殺という形でも表面化してきた。日銀の植田和男日銀総裁は米カンザスシティー連銀主催のシンポジウムでの討論会で、賃金上昇圧力は続き、労働市場の変化を踏まえて政策運営を行う考えを示した。
関連記事:植田日銀総裁、賃金上昇圧力続く-労働市場の変化踏まえて政策運営
パインブリッジ・インベストメンツ債券運用部の松川忠部長は、債券市場で売り圧力が強いのは日銀利上げ観測の高まりだとし、「利上げをする前に債券を売ってポートフォリオを軽くしようとしている」と述べた。
3メガ銀行の一角である三菱UFJフィナンシャルグループの決算説明資料を見ると、6月末の国債保有額は15兆4300億円と3月末時点から27%減少した。生命保険会社なども、含み損が出ている国債の処理を進めている。
関連記事:大手生保4社、国内債含み損9.8兆円に拡大-長期金利上昇が直撃
全取りレート
日銀の買い入れオペは、利回り水準が高い(価格は安い)国債から予定額に達するまで買う仕組みだ。通常、落札結果では平均落札利回りと最低落札利回りの双方が公表されるが、14日と20日の5年超10年以下は落札利回りが一つになる「全取りレート」と、異次元緩和後では初のケースとなった。
特定の金融機関の売却で他の市場参加者がオペで保有債券を売却できない場合、市場で売りを出す必要が生じる。さらに同レートが実勢よりも高かったため、金利の先高観が強まる一因となった。
オリックス生命保険資産運用部の嶋村哲マネジング・ディレクターは「一本値で決まったことは偶然の一致ではなく、1社で占めたことではないか」と推測。「売りたい投資家が実勢より高い金利水準で売却したことで、長期金利に対して高い水準を見通していることの表れではないか」と指摘した。
日銀は異次元緩和で大量に購入した国債買い入れオペを減額しており、7-9月の月間3兆7000億円程度から26年には3兆円程度に減らす計画だ。財務省の資料によると、日銀は依然として国債全体の51.7%を持つ最大の保有者であり、買い入れ減額による需給の緩みも金利の上昇圧力となっている。
日銀が22日に発表した銘柄別保有国債残高によると、10年物の378回債で前回の残高と比べ、5年超10年以下のオペ予定額に当たる3500億円増えていた。
27日には今月4回目の買い入れオペが予定され、残存期間5年超10年以下も対象だ。今週は長期ゾーンの国債入札がなく、残存期間15.5年超39年以下の流動性供給入札のみで、需給面で日銀オペへの警戒感が高まりやすい状況にある。
みずほ証券の大森翔央輝チーフ・デスク・ストラテジストは「ポジション調整か日銀の政策金利期待の金利上昇か、あるいは双方か決めつけるのは難しい」としつつ、「大量の長期債売りを警戒して海外投資家の売りが発生した可能性がある」との見方も示した。