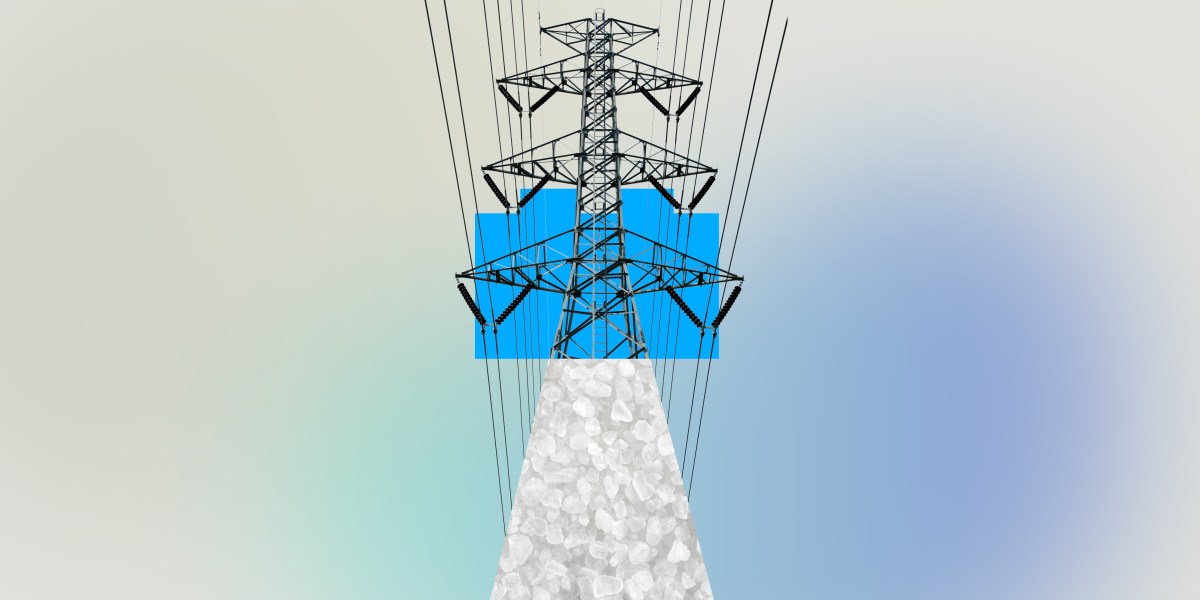「地球を冷やす6つの大作戦」効果とリスク

それでも、その前にできることがあると思うの…。
地球温暖化が現在のペースで進んだ場合、2030年から2052年の間に世界平均気温が産業革命前の水準と比較して1.5℃上昇すると予測されています。
専門家は、この1.5℃というしきい値を超えると、人間社会と地球環境に深刻な影響をもたらし、取り返しのつかない生態系の損失や、極端な気象現象のリスクが高まると考えています。
排出量削減だけでは足りない
温暖化を解決する最も直接的な方法は、温室効果ガス排出量の抑制なんですけど、現時点で最低限の削減目標にすらまったく届いていません。
国連の『排出ギャップ報告書2024』によると、1.5℃の温暖化を回避するために、国際社会は2023年までに排出量を2019年比で42%、2035年までに57%削減する必要があります。
報告書は、目標達成には、各国が「これまで以上に野心的な行動をとる必要がある」と述べています。
科学者: ジオエンジニアリングしかなくね?
このような厳しい状況を踏まえ、一部の科学者は排出量削減だけに頼るべきではないと主張しています。気候変動の最も深刻な影響を緩和するには、地球を人為的に冷却する大胆な取り組みが必要なのだとか。
研究者は、理論的に地球の冷却が可能な複数のジオエンジニアリング(気候工学)を調査中です。しかし、ジオエンジニアリングは依然として激しい論争の的になっており、ほとんど実証されていません。
ここでは、最も奇抜なジオエンジニアリング案を6つ紹介します。
1. 成層圏にエアロゾルをまいちゃえ(火山噴火のモノマネ)
Image: Hughhunt / Wikimedia Commons1991年にフィリピンのピナトゥボ山が噴火した際、観測史上最大とされる二酸化硫黄の噴火雲が発生しました。
成層圏に放出された大量のガスと火山灰が、太陽光を宇宙に反射したことによって、翌年にかけて地球の平均気温が0.5℃低下しました。
科学者は、成層圏エアロゾル散布(SAI)を行ない、人工的に火山噴火と同じ効果を再現しようと提案しています。SAIは、太陽光を反射する微細な硫黄粒子を成層圏に大量散布します。理論上では、これらの粒子が太陽光を反射するバリアとして機能し、地球の気温を下げると考えられています。
これまでに大規模な実験は実施されていませんが、研究者は砲撃による粒子の打ち上げから航空機による散布まで、複数の方法を提案しています。しかし、成層圏への粒子の散布は、想定外の深刻な結果を招くおそれがあると警告する声もあります。
最近の研究では、SAIが気象のパターンやジェット気流、地球規模の大気循環を乱すおそれがあると指摘しています。さらに、実際にSAIを効果的に実施するのは極めて難しいと述べています。
2. 雲をもっと明るくしちゃえ
成層圏エアロゾル散布(SAI)と同様に、海洋雲増光(海洋の雲を明るくする: MCB)も、エアロゾルを大気中に散布する技術で、海洋上空の低層雲に塩の粒子を散布します。
理論上、MCBは雲の反射率(アルベド)を高めるため、海洋が吸収する熱量を減少させることができます。SAIとは異なり、極めて厳しい規制の下で、MCBの小規模な実験が行なわれていますが、本格的な実用化にはまだ何年もかかるとのこと。
そんな段階なので、MCBの効果も影響もまだよくわかっていません。研究結果によると、オゾン層が増える地域もあれば減る地域もあったり、予期せぬ大気の連鎖反応を引き起こしたりする可能性があるそう。
さらに、MCBは温暖化が進むにつれて効果が薄れるどころか、むしろ暑さの影響を悪化させるおそれもあるといいます。
3. スーパー光合成植物をつくっちゃえ
Image: ekrem sahin / Shutterstock植物は、最前線で温暖化から地球を守ってくれています。植物は光合成によって二酸化炭素を吸収し、エネルギーやバイオマスを生み出すことで、大気中の炭素を取り除きます。
しかし、人類の排出する二酸化炭素の量があまりにも多いため、光合成だけでは追いつかないのが現状です。そこで一部の科学者は、光合成の効率を高めるために、植物や藻類を遺伝子操作しようと提案しています。そうすることで、より多くの二酸化炭素の吸収と代謝ができるようになるといいます。
スーパー光合成植物を推している人たちは、世界の食料安全保障にも有益だと主張しています。世界人口が増加するなか、光合成の効率を高めれば、食料やバイオ燃料の生産量を効果的に増やせるとのことです。
とはいえ、植物の遺伝子組み替えには多くの不確実性が伴います。新たに作り出した生物を自然環境や農業システムに組み込むことで、思いがけない副作用が起こる可能性もあると懸念されています。
4. 大量の海藻を養殖して海底に沈めちゃえ
海藻の大規模養殖によるジオエンジニアリングも、光合成の炭素吸収力を利用する手法のひとつです。この手法では、海水中の二酸化炭素を除去するために、海藻を工業的に養殖します。
養殖した海藻を海底へ沈めると、理論上は炭素を数百年にわたって隔離できるとされています。または、海藻のバイオマスをバイオ燃料や肥料、家畜の飼料などの製品として活用する選択肢もあるようです。
いいね、効果的な解決策になりそうじゃんって思ってしまいますが、世界平均気温を下げるほどの効果をもたらす規模で海藻を養殖するなんて無理と批判されています。
また、研究結果によると、海藻は二酸化炭素を発生させる海洋生物のエサになるため、ヘタすると炭素の吸収源ではなく排出源になっちゃう可能性があるそうです。
5. 軌道上に巨大な鏡や日よけを建設しちゃえ
Image: Mikael Häggström / Wikimedia Commonsお次は、最もぶっ飛んでるジオエンジニアリング。いちおう、SAIやMCBと同じ太陽放射管理技術なのですが、こちらは軌道上に巨大な鏡や日よけを打ち上げて、太陽光を反射させちゃえばいいじゃんっていう宇宙レベルのアイデア。
SF映画みたいな話を実現するにはめちゃくちゃ時間がかかりそうですよね。なんでも、宇宙空間で太陽光を反射させるには、中規模の国と同じ大きさの鏡や日よけが必要になるため、建設費が数十京円に達しちゃうそうです。だれが払うの?
技術的にも財政的にも無理筋な感じしかしないにもかかわらず、複数の研究組織が試作モデルの開発に取り組んでいるといいます。
しかしながら、温暖化による最悪の影響を防げる時期までに実用化できるわけがないと批判されています。
6. 地表をもっと明るくしちゃえ
宇宙に巨大な鏡を設置できないなら、地表を鏡みたいにすればいいじゃんっていうのが、お次のアイデア。
この、地表のアルベド(光の反射率)を高くする手法(SAM: Surface Albedo Modification)は、地球表面を広範囲にわたって明るくし、太陽光の宇宙への反射量を増やすことで、平均気温を下げるのが目的です。
SAMには、アルベドが高い作物の栽培や、雪が多い地域の北方林の伐採(緑を減らして白い表面を増やす)、山頂や屋根を白く塗るなど、さまざまな方法があります。いずれも、地球規模でアルベドを高くすることを目標にしています。地球規模でってところが非現実的に感じますけど、コミュニティレベルでの効果は期待できそうな気がします。
ここで紹介した6つの手法の中には、比較的無害に思えるものもありますが、地球を人工的に冷やそうとする試みによって生態系を変えてしまうことで、良い効果以上の深刻な影響を及ぼすおそれもあります。
いちばん心配なのは、これらの技術はまだ大規模な実験が行なわれていないため、実際にどれほど効果があるのか、あるいはどれほど被害が出るのかさえ、だれにもわからないところです。
テックにロマンを求めるのもわからなくはありませんけど、ジオエンジニアリングの技術開発にかけるお金を、確実に排出量を削減できる技術に回したほうが気温を下げられるのでは、とも思ってしまいます。