用もないのに東京・博多を往復するワケ…出不精の作家・長倉顕太さんが語る「移動」の絶大な効果 凡人こそ「フッ軽」になれ
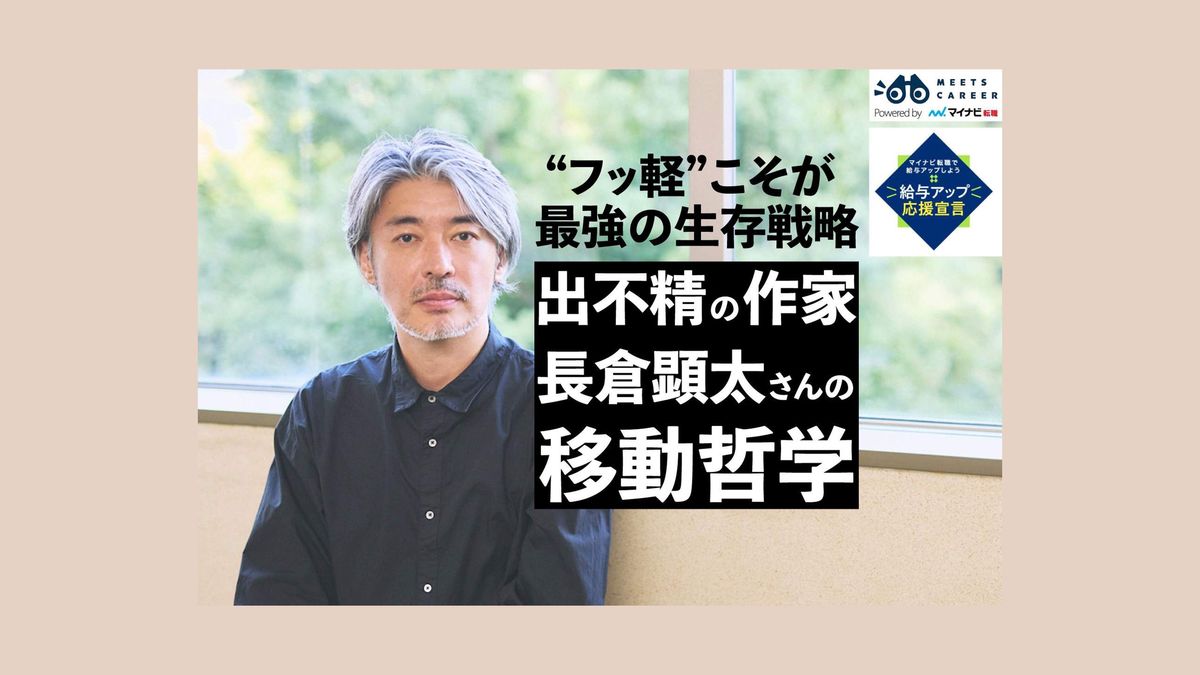
――では、なぜ長倉さんは目的のない「移動」をそこまで重視されているのでしょう?
長倉:僕は常々、人は環境を変えることでしか自分を変えることはできない、と思っているんです。そのことに気づいてから、無理やりでも仕事に移動を組み込むようになりました。
――世の中は「自らの意思で行動を変えよう」と説く本であふれていますが……。
長倉:脳科学や心理学など、これまでさまざまなアプローチのビジネス書をつくりましたが、その過程で疑問に感じていたのが「なぜ皆、頭で分かっていることができないんだろう」ということ。「健康を維持するためには野菜を食べて運動すればいい」と分かっているのに、それができない。
でも、暑かったら涼しい場所に行くし、水の中に放り込まれたら泳ぐしかないですよね。そう考えて気づいたんです。「環境→感情→行動」の順番だと。多くの人は「感情」、つまり意思の力で「行動」を変えようとするけれど、そのアプローチだと「環境」の引力に負けてしまうかもしれない。でも、「環境」を変えれば、自動的にマインドセットも「行動」も変わるのではないかと。
――なるほど。自分も仕事をするためだけに場所を移動することがあるので、その説には納得感があります。
長倉:あとは、講演会などでさまざまな人と会話するなかで「人は『環境』を受動的に受け入れると、感覚が麻痺してしまうのではないか」と感じて。
例えば、朝起きて、何も考えず電車に乗って、YouTubeでレコメンドされた動画を見ながら、自然と会社に着く、みたいな受動的なルーティンをなんとなくやり続けると、自分の意見もなければ自分が何をしたいのかも分からない人になってしまう可能性があるんじゃないかと。
でも、通勤のルートを変えるとか、主体的に日常から外れてみたら、周囲の「環境」を冷静に分析する機会が生まれて、やるべきことも明確になるかもしれない。「移動」には自分の立ち位置を否が応でも浮き彫りにする効果があります。海外に行けば、日本の良いところも悪いところも見えてくるように。
そういえば、哲学者のハイデガーも「日常は感覚を麻痺させる」といった趣旨のことを指摘しています(編注:代表作『存在と時間」にて、人間は日常のなかで主体性を見失い、世間一般の価値観や行動様式に埋没して生きていると説いた)。
――「環境」を変えると感覚を取り戻すことができるという考え方には、共感する人も多いのではないでしょうか。旅行だけでなく転職にも当てはまりそうですね。
長倉:明確なエビデンスはないんですけどね(笑)。でも、僕自身、28歳までまともな仕事をしていなかったのに、編集者になったことでアメリカに移住して、現地で子どもを育てられています。それはひとえに、著者の皆さんをはじめとする優秀な人たちと一緒に仕事をするという「環境」があったからこそです。人間関係は究極の「環境」ですからね。
店を変える、読書する……もっと「フッ軽」になるための日常アクション
――先ほど「通勤のルートを変える」みたいな話も出ましたが、長倉さんが日常的にやっている「移動」には何がありますか?
長倉:例えば、特に用事はないけれど新幹線で博多駅まで行ってそのまま東京に戻ってくるとか。
――博多駅で降りず、そのままUターンするのですか?
長倉:もちろん、規定の運賃は払ったうえで、ただ駅まで行って観光せずに帰ってきます。新幹線の車内をオフィスとして使う感覚ですね。なぜそんなことをするのかというと、移動している間にアイデアが生まれやすいからです。
画像提供=MEETS CAREER by マイナビ転職
――たしかに、最近の新幹線には仕事をするための座席(東海道新幹線の「S Work席」など)もありますし、新幹線と仕事は相性がいいのかも。移動中にひらめくというのはよく聞く話ですが、やはり「セレンディピティ(偶然性)」と移動は関係があるんですかね?
長倉:大いに関係があると思います。例えば、行き慣れていない本屋さんでAmazonにレコメンドされない良書と出合えるかもしれない。あと、僕は音楽ライブも好きなのですが、東京公演はほぼ行かず、あえて地方公演にばかり行きます。そうすると、現地で「こんなところにこんなものがあるのか」といった思わぬ出合い・発見があったりする。
Page 2
――とはいえ、大きな失敗をしたらどうしようと不安になる人もいます。
長倉:やってみてダメならやめればいいし、帰ってくればいいんです。そもそも、今はSNSやオンラインスクールなどで、どこにいても新しい情報を得たり、学んだりすることができるので、東京に住むメリットは相対的に下がっているのかもしれません。
だからこそ、移動や移住で、あえてコントロールできない環境に身を置いてみる。そこで起きるコントロールのできない出来事に対して、自分はどうするのか。その問いに答えることで、人生はより楽しくなります。
僕の好きな本『それでも人生にイエスと言う』のなかで、著者のヴィクトール・E・フランクルは、人生を悲観する人々に「ものごとの考えかたを一八〇度転回することです。その転回を遂行してからはもう、『私は人生にまだなにを期待できるか』と問うことはありません。いまではもう、『人生は私になにを期待しているか』と問うだけです。人生のどのような仕事が私を待っているかと問うだけなのです」と述べています。つまり、人生に意味づけができるかどうかは自分次第だと。
技術のトレンドや市場環境が目まぐるしく変わり、今いる会社もあと何年あるか分からない。そんな世の中だからこそ、仕事もキャリアも面白くする方法を「主体的に」考えなければならないと思うんです。僕にとってはAIよりも、慣れで「なんとなく」仕事をすることのほうが恐ろしい。「移動」とは僕にとって、主体的に物事を考えるためのレッスンなのかもしれません。
画像提供=MEETS CAREER by マイナビ転職
取材・文:はてな編集部、山田井ユウキ 写真:関口佳代 編集:はてな編集部 制作:マイナビ転職



![[プロモーション]【500人調査】片付けが進まない背景に 「捨てるかどうか」の判断疲れ 「片付け・整理整頓に関する意識調査」を実施](https://image.trecome.info/uploads/article/image/458d3fbb-219e-40fc-a458-1b7a90a07fa8)