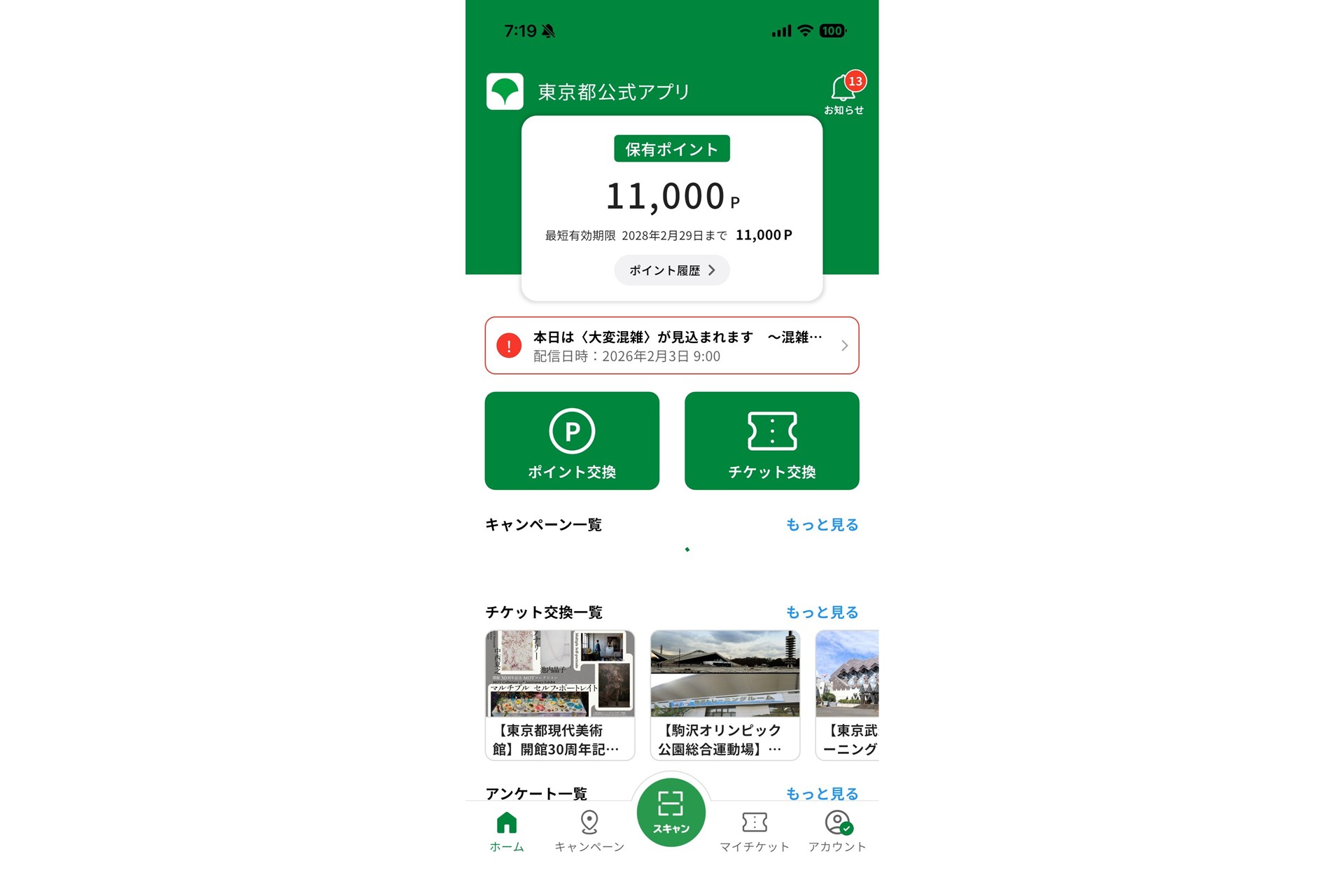【コラム】異例のFOMC、光ったのはパウエル氏の統率力-ダドリー

今週の米連邦公開市場委員会(FOMC)から読み取るべきことは何か。
第1に米連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長が、FOMCを確実に掌握しているという点だ。FOMCは17日、フェデラルファンド(FF)金利の誘導目標を25ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)引き下げ、4.00-4.25%とした。
FOMC会合前には金利据え置きを支持するFOMCメンバーと、50bpの大幅利下げを主張するメンバーがそれぞれ存在し、双方から反対票が出るとの観測があった。また、第1次トランプ米政権下で任命されたウォラー理事と、ボウマン副議長(銀行監督担当)が就任したばかりのマイラン新理事とともに、大幅利下げを支持して反対票を投じるとの観測もあった。
しかし、そうはならなかった。据え置きを望んだとみられるFOMCメンバーも最終的にはパウエル議長の判断に従った。金利の方向性ではなく、タイミングをめぐる見解が異なっていたことを踏まえれば、この結果は意外ではない。こうした状況では、反対票を投じる理由は見当たらなかった。
ボウマン、ウォラー両氏の意図を読み解くのは容易ではないが、より大幅な利下げがトランプ氏の強い意向であっても必ずしもそれに従うわけではないことを示している。トランプ氏の主張によれば、FF金利は1%に近い水準にあるべきだ。両氏の行動はFRBの使命への誠実な姿勢、そして中央銀行の独立性を守ることの重要性を物語っており、歓迎すべき展開だ。
第2に、経済予測の中央値が示す年末までの利下げ幅が75bpと、6月時点の50bpから修正されたことは重大な変化ではない。市場は当初この修正を好感したが、詳しく見れば明確なコンセンサスがなかったことが分かり、株価の上昇は一時的にとどまった。おそらくマイラン氏によるとみられる今年150bpの大型利下げ予測を除けば、他のFOMCメンバーは今後1回または2回の利下げで意見がほぼ二分されていた。
第3に、パウエル議長の記者会見では、FOMCが経済成長とインフレ見通しの中央値を引き上げた一方で、FF金利を引き下げたことについて、矛盾ではないかとの質問が相次いだ。だが筆者は、この点に大きな矛盾は見られないと考える。いずれも予測の上方修正幅は2026年に0.2ポイントの小幅にすぎない。より重要なのは、今回の利下げは予測の中央値に基づくものではなく、労働市場の弱さを示す雇用統計、具体的には過去3カ月の平均雇用者数の伸びが2万9000人に急減速したことを受けた措置である点だ。
では、今後の見通しはどうか。
FOMCの今後の政策判断は経済指標に左右される。緩和の可否は、労働市場の下振れリスクがさらに強まるかどうか、トランプ政権の関税が物価にどう波及するのか、それによるインフレの根強さが長期的なインフレ期待を押し上げるのかにかかっている。力強い雇用統計の継続、安定した失業率、根強いインフレが示されれば、追加緩和への支持は弱まる可能性がある。
パウエル氏が説明したように、現在の金融政策の運営は極めて困難だ。第1に、FRBの二重責務である完全雇用と物価安定がしばしば相反するため、両目標に対するリスクバランスの均衡を取る政策が求められる。パウエル氏が述べたようにリスクのない道は存在しないのである。第2に関税政策はなお不透明という点だ。価格転嫁は従来の予想よりも緩やかかつ控えめにとどまっているが、これは影響が小さいことを意味するとは限らない。むしろ、企業が明確な見通しを得るまで対応を控えている結果、転嫁が単に遅れているだけの可能性もある。
では、FRBの独立性に対する脅威はどうか。
パウエル氏は、クック理事の住宅ローン申請に関する虚偽申告疑惑や、ベッセント財務長官が要求するFRBへの独立した調査に関しては慎重に回答を避けた。代わりに、最近実施された金融政策の枠組み見直しや、連邦準備制度全体で10%の人員削減を計画していることなど、米金融当局としてすでに取り組んでいる改革を挙げた。
金融政策における「第3の責務」とされる長期金利の安定に関しては、FRBがこれまでこの点に重点を置いてこなかったのは当然であり、それは、完全雇用と物価安定という2大目標を達成すれば、長期金利は自然に安定すると考えられているからだとパウエル氏は強調した。
FRBの独立性をめぐる脅威は依然として現実的だ。トランプ政権はクック理事を正当に解任できない可能性がある一方で、トランプ氏が任命したFRB理事(副議長含む)が全員ホワイトハウスの意向に従うとは限らない。とはいえ、政権側がFRBの掌握を試みている意図は明らかだ。さらにトランプ政権は目的達成のために他の手段を模索したり、新たに考案したりする可能性もある。
今回、マイラン氏の金利見通しが他のFOMCメンバーと大きく離れていたことから、トランプ氏寄りの当局者が完全に金融政策の舵を取った場合にどれほど政策が急変するかがうかがわれる。金融政策がマイラン氏の方針通りとなれば、経済はすぐに過熱し、インフレが加速するだろう。FRBが議会に定められた責務に基づいて金融政策を運営するうえで、その独立性が引き続き守られることを願いたい。
(ウィリアム・ダドリー氏はブルームバーグ・オピニオンのコラムニストです。このコラムの内容は、必ずしも編集部やブルームバーグ・エル・ピー、オーナーらの意見を反映するものではありません)
原題:The Three Takeaways From the Fed’s Rate Decision: Bill Dudley(抜粋)