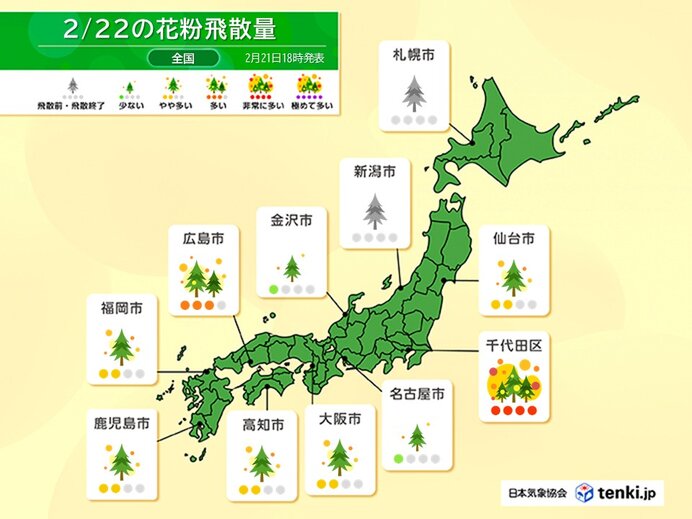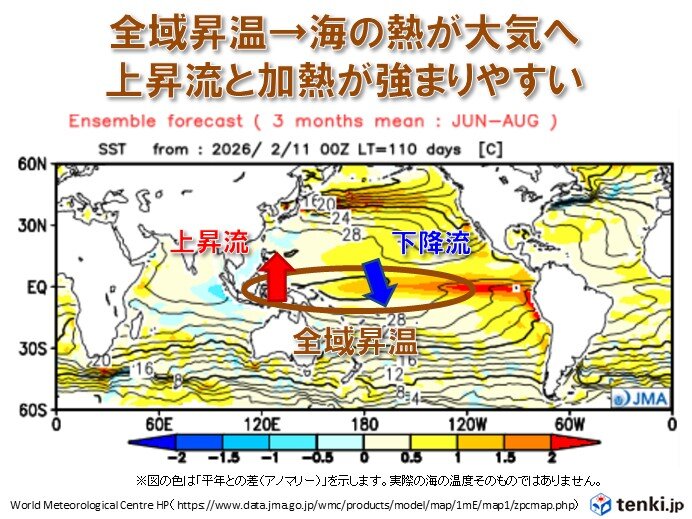「1日2食以下」の子どもが2.5倍に増加…支援団体が明かした“夏休みの食事”のリアル 「子どもが『給食以外でコメを食べていない』ケースも」

物価高やコメ価格の高騰が食卓を直撃する中、給食がない夏休みに、子どもの食事が危機に陥っている。
【映像】「とんでもないことを…」支援団体に寄せられた母親の声
支援団体の、認定NPO法人グッドネーバーズ・ジャパンの調査によると、学校がある期間と比べ長期休みの期間は、子どもの食事が1日2食以下の割合が約2.5倍に増加する。
長期休みの期間に食事の回数が減ると答えた人の理由としては、「経済的に余裕がない」という回答が約4割、仕事などで忙しく「時間に余裕がなく家庭で十分な食事の用意が難しい」との回答が約3割近くを占める。
同団体の浅野綾希子氏は、以下のような声が寄せられたと話す。
「あるお母様から『金銭的に厳しくて食事の栄養バランスよりかさ増しを優先せざるをえない状況で、去年の夏なんとかやり過ごしていたけれど、秋に子どもの体重が減っていることに気付き、成長期の今しか体を作れない期間なのにとんでもないことをしてしまった、本当に申し訳ないという気持ちでいっぱいだ。今も物価高に追いつけず、食費を工面するのにとても苦労している』といった声が寄せられていて、親御さんも頑張って食費を捻出し食事を用意されていると思うが、間に合わずご自身やお子さんにも影響が出ざるをえない状況に置かれている」(認定NPO法人グッドネーバーズ・ジャパン 浅野綾希子氏)
追い打ちかける「物価高」と「コメの価格の高騰」
同団体が食品を配付しているひとり親家庭の世帯数の推移を見ると、今年6月の配付世帯数は、前の年の同じ月と比べて約7割増え、7月も前の月と同じ水準となっている。
さらにこの夏、特に追い打ちをかけているのが、「物価高」と「コメの価格の高騰」である。利用者への調査では、「コメの価格高騰が夏休みの食事にどう影響すると思うか」との質問に、58.0%の保護者が「自分が食べるコメの量が減る」と回答した。
「成長期の息子が2人いるので自分はあまりコメを食べないようにしているが休みになるとコメの消費が倍になるので、経済的にコメが確保できるかかなり心配」(保護者の声)
支援団体によるとコメ価格が高騰する以前、コメを食べることでお腹を満たしていた家庭も少なくなかったということだが、今年の夏休みは状況が異なる。
「コメ(価格)が高騰し経済的に購入が難しくなっている中で、『子どもには給食でコメを食べてもらっている』『給食以外でコメを食べていない』ケースもある。夏休みは給食がないため、主食であるコメを食べられなくなる状況も見られる。かなり深刻だ」(浅野綾希子氏)
地域の飲食店を“こども食堂化” 「こどもごちめし」とは?
コメの高騰と物価高を受け、各地の自治体も相次いで夏休みの子どもの食事を支援している。
山梨県は「緊急的に実施」として、困窮世帯の小中高校生を対象に乾麺や肉・魚の缶詰、野菜ジュースやゼリーなど31食分、夏休みの1カ月分を配送している。
また八王子市は、夏休みの一部期間中に給食センターを開放し、一食300円で昼ごはんを提供、合わせて食育も行った。延べ参加者は去年の夏は約410人だったが、この夏は延べ約960人と倍増している。
備蓄米で夏休みの子どもの食事を支えるプロジェクトも。認定NPO法人フローレンスなど4法人は共同で、計12トンの備蓄米や企業から提供された食品を、支援団体などを通じて全国の子育て家庭約1.2万世帯に届けている。
ほかにも、大手飲食チェーン「吉野家」「モスバーガー」「はなまるうどん」が支援団体と共同で5.4万食を無償で提供。地域の飲食店をこども食堂化するサービス「こどもごちめし」のサイトから利用者登録をすると、中学生以下の子どもが無償で食事を食べることができる。
現在、「こどもごちめし」公式ホームページでは、支援者の募集を受け付けているとのことだ。
夏休みの子どもへの食料支援について、教育経済学者で慶應義塾大学の中室牧子氏は、次のように指摘する。
「海外では『フードスタンプ』という食料しか買えないような仕組みがある。これは低所得者世帯の食料を支援すると同時に農産物の需給調整に使われている部分も。例えば、今年はニンジンがたくさん取れたがブロッコリーが全然取れませんでした、という時は、フードスタンプで供給するニンジンの量が多くなる、などの形で、農家さんの所得変動を抑える効果もある」「子どもに対する食料支援と農家さんへの支援を両立させる仕組みなので、ひょっとすると日本でも夏休みの間だけはそういう子ども向けフードスタンプみたいなのがあってもいいのかもしれない」
(『ABEMAヒルズ』より)