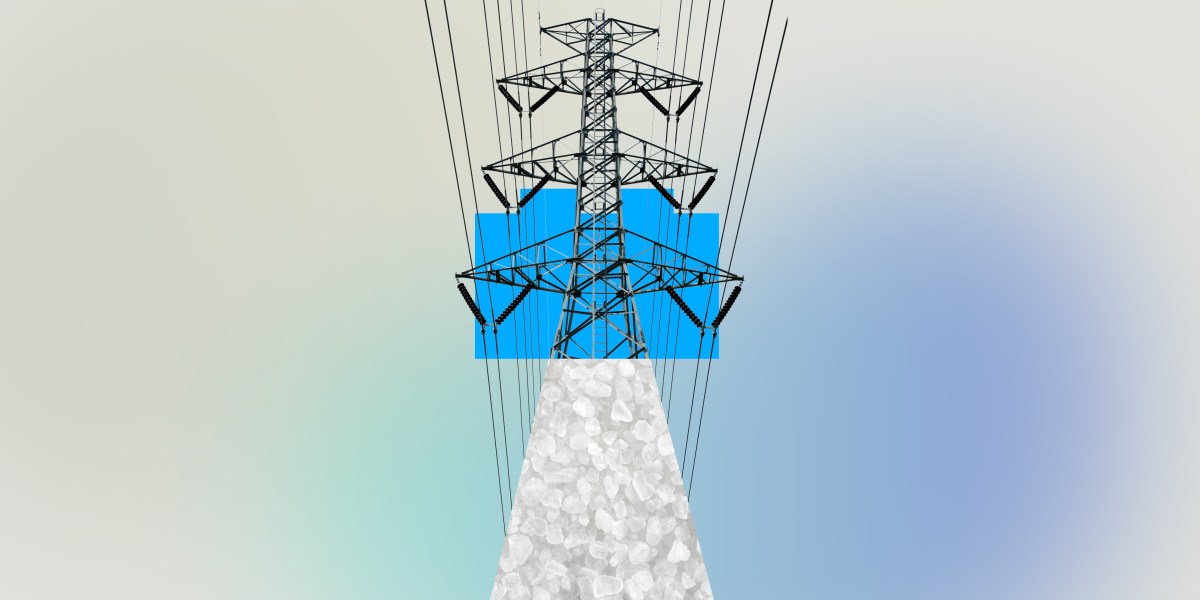自称仕事ができる人に困ったら、改善のカギは「メタ認知」(日経BOOKプラス)
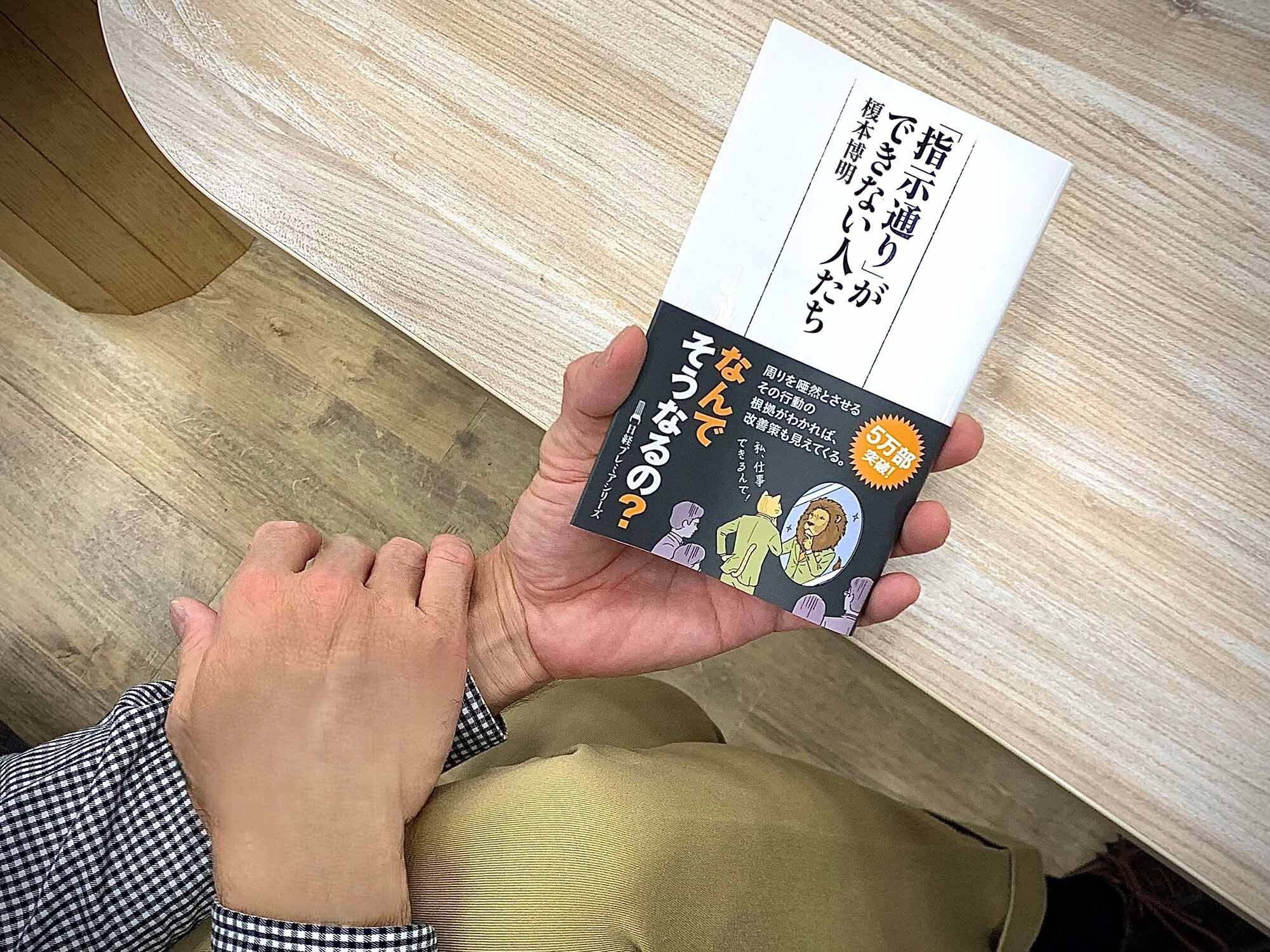
業務上の指示を受けた際、その内容を理解し、集中して取り組み、報告する、ということができない人たちがいます。決して不真面目なのではなく、前向きな態度で仕事に臨んでいるのに──こうしたケースについて、心理学博士の榎本博明さんは著書『「指示通り」ができない人たち』で詳しく解説。著書で取り上げている3つの能力を軸に、お話を伺います。今回は2回目。(聞き手は、「日経の本ラジオ」パーソナリティの尾上真也) ●なぜ「指示通り」にできないのか 尾上真也・「日経の本ラジオ」パーソナリティ(以下、尾上) 前回は、『「指示通り」ができない人たち』の著者である榎本博明さんに、著書の中で取り上げられている「認知能力」「非認知能力」「メタ認知能力」という3つの能力について解説していただきました。 今回はそれらの能力の改善が必要な人について、具体的にお伺いしていきます。同書の第1章「認知能力の改善が必要な人」では、指示通りができない人の話が出てきますね。 榎本博明(以下、榎本) 世間では「指示待ち人間は困る」と言われますが、指示待ちであっても指示通りにやってくれるならマシじゃないか、という声も現場にはあるのです。つまり、こうしてくれと仕事を頼んだのに、その指示通りにできない人がいて手を焼いているケースがあるということです。 榎本 例えばあるケースでは、部下に「データを入力して整理したら、それをある部署に持っていく」ように指示したのに、持っていっていない。これを分析すると、「データを入力して整理する」と「ある部署に持っていく」という2つの指示になります。2つの指示が与えられた際、1つ目の課題に集中しているうちに2つ目の課題が抜けてしまうのですね。この場合には、2つ目の課題は紙に書いてパソコンの横に貼っておくなど、外部記憶装置に任せることが必要になります。 記憶能力は認知能力の1つですが、人によってかなり差があるものです。昔の思い出話をすると、人によって覚えていることが違い、家族でも言った・言わないのすれ違いが起こりますよね。それほど人の記憶というのは飛んでしまうものなのです。 ですから、職場で電話を受けたときなど、取引先から何らかの伝達用件があったのに、メモするのを忘れ、そして電話を受けたことまで忘れてしまう、という事態が起こるのです。用件の内容を忘れることはよくあると思いますが、電話を受けたことまで忘れてしまうと、周囲は困ってしまいますよね。そういう人には即座にメモを取ることまで指示しなければなりません。 尾上 メモを取ることを促す他に、何か気を付けることはありますか。 榎本 認知能力に関してよくあるのはコミュニケーションギャップで、こちらが言ったことと相手が受け止めたことの内容がズレている、ということがたびたび起こります。 ちゃんと言ったから伝わるはずと思いがちですが、中学校や高校の国語の試験を思い出してみてください。「著者が言いたいことを次の5択から選べ」という問題で、間違える人もいますよね。つまり、日本語できちんと伝えても、その通りに受け止められない人もいるわけです。ですから、言ったからと安心したり、いきり立ったりしても仕方がないわけで、相手の読解力や理解力に合わせて、その人にとって分かりやすい言い方を工夫しなければなりません。 例えば、複雑な言い方は避けてポイントをいくつかに絞って区分けしながら伝える、ちょっとしたメモを添える、などですね。指示が伝わらないのには、理解できないことと、記憶が定着しないことの2段階があるので、「メモを渡して説明する」などしないと、相手に理解されず記憶に刻まれないこともあると思います。 ●テスト問題の内容を理解できない学生たち 尾上 伝えた内容を部分的にしか理解していない人も、少なからずいそうですね。 榎本 相手の言っていることをすべてきちんと理解できないから、何か文句を言われたと感じてしまうこともあるわけです。職場でお客さんとのトラブルが多くて、「お客さんが訳の分からないことを言う」と報告してくるけれど、両者の言い分を聞いてみると、お客さんのほうの筋が通っていることもある。読解力の問題ですね。 尾上 お客さんの言うことを理解せず、お客さんがおかしいと捉えてしまう、と。これはどうしたらいいのでしょうか。 榎本 本を読まない時代になり、論理的な文章を読む習慣がなくて、ちょっと感情が揺さぶられたことをつぶやくだけというコミュニケーションになっていると、読解力は身に付きません。私が学生と話していても、当たり前に知っているだろうと思っていた言葉が理解されていないと感じることもあります。 また、今、大学などで心理テストをやりづらいという話も聞きますね。テストをしようとしても、例えば「引っ込み思案」や「内向的」という言葉を学生が分かっておらず、テスト項目の内容を理解できていない。学生に聞いてみると、友達との日常会話やSNSでそんな単語は使わないから、と。 尾上 読解力だけではなくて、言語能力も失われつつある感じなんですね。この認知能力の改善には、社会から少しずつ失われている要素が関係しているような気がします。 榎本 そうですね。新聞に目を通したり、分厚い本でなくても簡単な本を読んだり、何かちょっとした習慣づくりをしてみる必要があると思います。 尾上 活字メディアを日常的に読む習慣を持つといいのですね。 ●メタ認知が働かないと、どうなる? 尾上 では続いて、第2章の「メタ認知能力の改善が必要な人」について、教えてください。 榎本 メタ認知というのは、つまり自分の認知活動を振り返る力です。例えば、仕事をしていて何らかのまずい点があるとします。すると能率が悪い、間違ったやり方をしているなど、周囲から注意やアドバイスをされ、人はそれを糧にし、修正しながら成長していきます。しかし、最近よくあるのは、アドバイスをされると自分が否定された、意地悪されたと受け止めてしまう人がいること。注意だけでなく、やんわりとしたアドバイスさえしにくい場合もあります。 そういったケースでは、メタ認知が働いていないのかもしれません。自分がまずいことをしたという意識がなく、周囲から感じが悪いことを言われたと思ってしまう。そういう人にはメタ認知を働かせるように導かなければいけないし、「あなたを否定したわけではなくて、もっと成長できるようにアドバイスしている」と、うまく説明しながら伸ばしていくことが大事ですね。 それから、同じミスを繰り返していることに気付かない人や、自分は仕事ができるつもりなのに実際はできていない人も、メタ認知が働いていないと思われます。つまり、自分の仕事を改善するための気付きを得る能力が開発されていないのです。このメタ認知能力、つまり振り返る力を開発していくだけで、成長していくと思います。 尾上 本書を読んで、私も思い当たる節がありました。最近は忙しさにかまけて、きちんと振り返ることをなおざりにしていたかもしれません…。 榎本 自分の足りない点を振り返って見つめ直すのは、誰だって嫌ですよね。しかも、仕事が忙しく疲れているときに、またどっと疲れが出るような振り返りをするのはきついでしょう。常に振り返るのは、難しいことです。でも、例えば仕事帰りの電車のふとした瞬間に、SNSや情報収集はやめて、今日一日どうだったかなとちょっと振り返る習慣を漠然とでも続けてみることが大事なのだと思いますよ。 尾上 なるほど、そうですね。ぼーっとしていると手元のスマホを触りがちですが、その時間に、その日一日を少しでも振り返ってみることはできそうな気がします。 文/佐々木恵美 構成/市川史樹 編集協力/山崎 綾