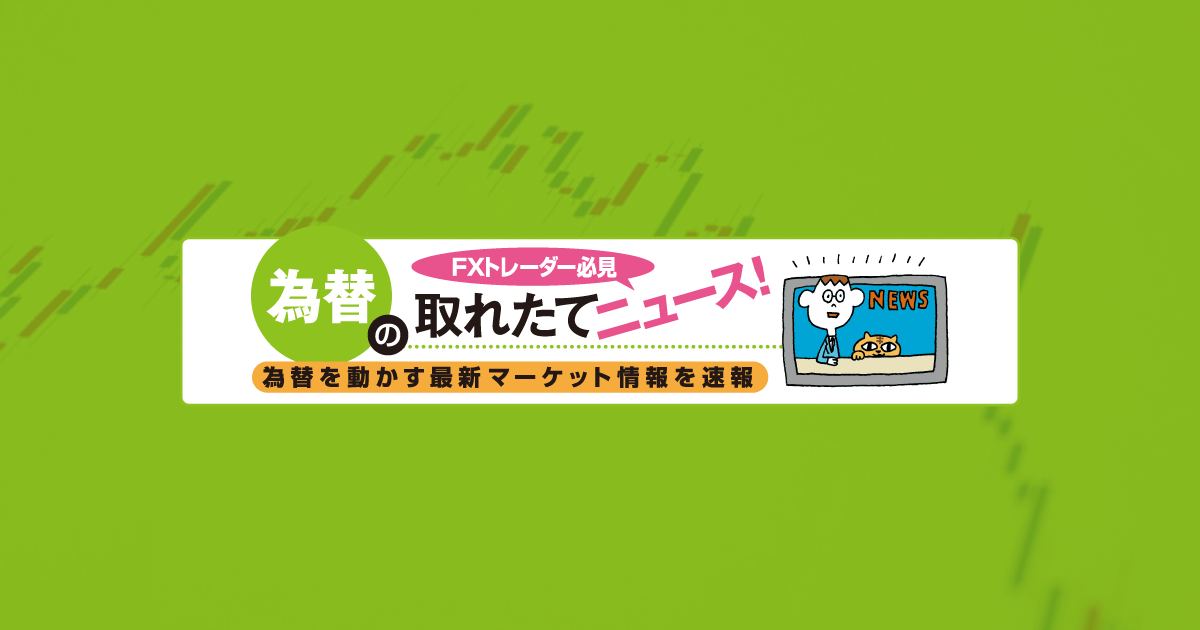子どもの学歴は「生まれ」で決まる…低学歴の親が目を背けたくなる学歴データが示す不都合な真実 学歴による格差は解消されるどころかさらに進んでいる

「学歴がなくても能力があれば活躍できる」など、学歴とその後の活躍を切り離して考える声がある。しかし、組織開発専門家の勅使川原真衣氏は「親と子どもの学歴には相関関係があり、学歴による分断は進んでいる」という――。
※本稿は、勅使川原真衣『学歴社会は誰のため』(PHP新書)の一部を再編集したものです。
写真=iStock.com/nirat
※写真はイメージです
「あなたは仕事ができるのか?」に反論できるか
たとえば中卒でニートの人が、25歳になってはたと、まったく畑の違う、仮に日本銀行に就職したい、と思い立ったとしたら。おそらく少なくない人が、こんなことをその人に暗に明に言うのではないでしょうか。
「へ? あなた仕事できるんですか? 本当にできる人はとっくに努力してきてますけど、大丈夫ですか? 学歴である程度のあなたの頑張りと実績がわかりますけど、うーんあなたがやれるようには思えない。何か力量を証明するものありますか?」
学歴社会とは平たく言えば、こうした主張に社会的なコンセンサスが生まれている状態です。それを私は肯定も否定もしていない点は繰り返しお伝えします。私自身の視座についてはさておき、ここでは、学歴がないと、「あなたが仕事ができるのかどうなのか、信用できない」と言われてしまうことに反論がしにくいのが学歴社会である点を頭に置いておきましょう。
さて、これの何が問題か? は次の問いに続きます。
不公平な「成功」への切符
次なる疑問。そもそもいまの仕事に水路づけた立役者は学歴ですが、その学歴を手にしたことは、本当に本人の努力と実力(能力)の賜物だと、言い切れるのだろうか? という点です。
先の例の中卒で社会に出た人は、本人の希望で義務教育で学校と決別したという人もいれば、当然のことながら、事情により高校以上の学校教育を受けることができなかった場合も大いにありますよね。
学歴社会は、個人の自由意志で、未来のためにいま精一杯の努力をし、実力を磨くことがさも皆が「(やれば)できる」前提に見えますが、じつはここですでに、捨象された議論が隠れているわけです。
本人の自由意志、合理性が働かない、選択の余地がないケースもあるよね? と。なのに、いま「もらいの少ない人」は、子どものころからの継続的な努力と実力の研鑽が足りないのだから、仕方がない──そう切り捨てることは、やはり結果の不平等を放置する意味において不公平ではないか? という議論が学歴社会の学術的研究の一義です。
専門的な議論はぜひ当該の書籍や論文に当たっていただければと思います。ここでは、一般書として平易に骨子を描くことに注力しますと、
多くをもらう人は、過去からいまもずっと頑張ってきて実績を残している人である
──これを体現した学歴社会のもとでは、高い学歴を得られなかった人は、まさに努力と実力不足という判定がされてしかるべきと考えられるわけです。ですが先に述べたように、したくてもできない環境下にあることも十分に考えられるのです。
Page 2
家庭ごとの社会階層(社会的な立ち位置。職業の威信や年収、居住地などで社会科学の研究では指標とされる)は再生産されるものの、その事実は機会の平等を盾にとり、あくまで本人の努力・実力の問題であるとされます。ひいては異議申し立てを許さない社会を盤石なものとするわけです。
勅使川原真衣『学歴社会は誰のため』(PHP新書)
この、学校教育という機会の平等で覆い隠された、結果の不平等という問題。教育社会学が実証的に世に知らしめてくれるまで、世間はおよそ、学歴社会で勝ち残るか否かは、本人の「能力」の問題だと信じて疑いませんでした。しかし、教育社会学者が「学校システムや就労のシステムを含めた、社会システムが、構造的な公平性を失っているのに、世間は問題を個人化しているじゃないか!」というのは、じつに的を射た指摘です。
とはいえ、その後もなかなか再分配の議論や、結果の不平等にも目配りをした公平な仕組みに向けたアファーマティブな介入(より踏み込んだ積極的介入)というのは、残念ですがあまり進んでいないことも付言しておきましょう。
「学歴による分断は一層進んでいる」論
学歴社会の是非はさておき、その傾向は強化されていると言えるのか否か。ここに焦点を合わせる研究の代表格が、『暴走する能力主義』の中村高康氏や、吉川徹氏でしょう。吉川氏の『学歴と格差・不平等 成熟する日本型学歴社会』『学歴分断社会』は、格差が断絶レベルまで進んでいることをデータでわかりやすく読ませます。濱中淳子氏も『検証・学歴の効用』において、はっきりこう記しています。
「学歴の効用が増大している」
繰り返しですが、学歴を媒介した所得格差は増大しています。それを知らないふり、世のなかそんなものだろうと、学歴を媒介にした所得格差に目もくれないでい続ける限り、「能力」による学校から職業への正当な采配だと信じて、実際には不公平な競争を生涯にわたって続けさせられる……教育費の公的な負担の議論も後回しになる……。非常に暗澹とした気持ちになりますが、こうした研究も連綿と続いています。
加えて、『高学歴難民』や『高学歴ワーキングプア』、『ルポ高学歴発達障害』などの、「学歴がすべてではない説」も枚挙に暇がありません。
写真=iStock.com/CYCLONEPROJECT
※写真はイメージです
Page 3
と、さらにここで、次のような意見もありましょう。
「いや、逆境にも負けず、自分で道を切り拓ける人もいる」 「経済的な逆境なら、安価な公教育もあるし、奨学金制度だってある。チャンスは『平等』にあったのだから、本人の問題じゃないか」
と。えぇ、さもありなんといった主張です。
しかし、これらの言説についても、教育社会学は毅然として、実証研究をもって反論します。ランダムサンプリングによる大規模調査および精緻化された統計手法の発展により、次のような、世代をまたぐファクトが抽出されました。
(1)学歴はまずもってその人の所得(稼ぎ、もらい)との相関がある (2)本人の学歴は親から子へと再生産される(親子の学歴に相関がある)
(1)については図表1のとおりです。学歴が高いほど平均賃金も高いのです(ここでは主旨ではありませんから男女格差については言及しません)。
そして問題は(2)。大卒の親の子供は大卒に、非大卒の親の子供は非大卒になるという、いわゆる親子の「学歴再生産」の傾向が、実証的に示されています。『教育格差 階層・地域・学歴』の松岡亮二氏の見解を参照しましょう。
(1)と合わせて考えると、賃金の傾向は学歴を媒介して世代を超えて再生産されやすいのです。極端な言い方をすれば、高学歴でハイソ(ハイソサエティ=上流の)、裕福な子はやはりそのハイソな界隈で裕福になりやすい。家が貧しいと、なかなか実家以上の暮らしになりにくい、というわけです。
学校は「平等に機会を与える場所」のはずなのに
その配分装置が、平等に機会を与えるとされている学校教育であることが特筆事項です。そこを媒介して、あたかも正当に「能力」を測ったと見せて、職業へと振り分けていく学校。これでは、生まれの違いが解消されないどころか不問に付されたまま。ゆえにその結果にはさらなる差が生まれます。そしてそれは世代を超えて、
「もともとラッキーな人はさらに強くしてもらい、もともと社会的なリソースが不足がちな人も、同等のチャンスはあげたのだからあとは頑張ってなんとかしなさいよ」
──で済まされてしまう。松岡氏が『教育格差』で述べたとおり、
「この社会に、出身家庭と地域という本人にはどうしようもない初期条件(生まれ)によって教育機会の格差がある(中略)この機会の多寡は最終学歴に繫がり、それは収入・職業・健康など様々な格差の基盤となる。つまり、20代前半でほぼ確定する学歴で、その後の人生が大きく制約される現実が日本にはあるのだ」というわけです。
Page 4
就職コンサルタントである福島直樹氏の『学歴フィルター』も、企業による学歴差別の実態を暴くルポであり、学歴(主に学校歴)によって就職という人生のフェーズにしかと分断が存在する様相を描いています。学歴フィルターないしは「ターゲット大学」=「特定の大学層の学生に対して特別な施策を行なう重点採用を実施している企業」と呼ばれるスクリーニング(選抜)が行なわれている割合で言うと、この本のなかでも参照されている、日本最大級の人事ポータルサイト「HRPro」の実施した調査(2017年実施)によれば、社員数1001名以上の大企業ではじつに56%だと言います。
というわけで、学歴論争のなかでも、学歴で賃金に差がつけられることの正当性を検討する議論は、先行研究も踏まえて、大枠が見えてきたでしょうか。学歴というものが、本人の努力と実績=「能力」だけでは獲得可能なものではない以上、世間で言われるとおり、学歴でその後の「もらい」を割り振っていくことに疑いをもたない社会というのは、どの道、問題があると言えそうです。