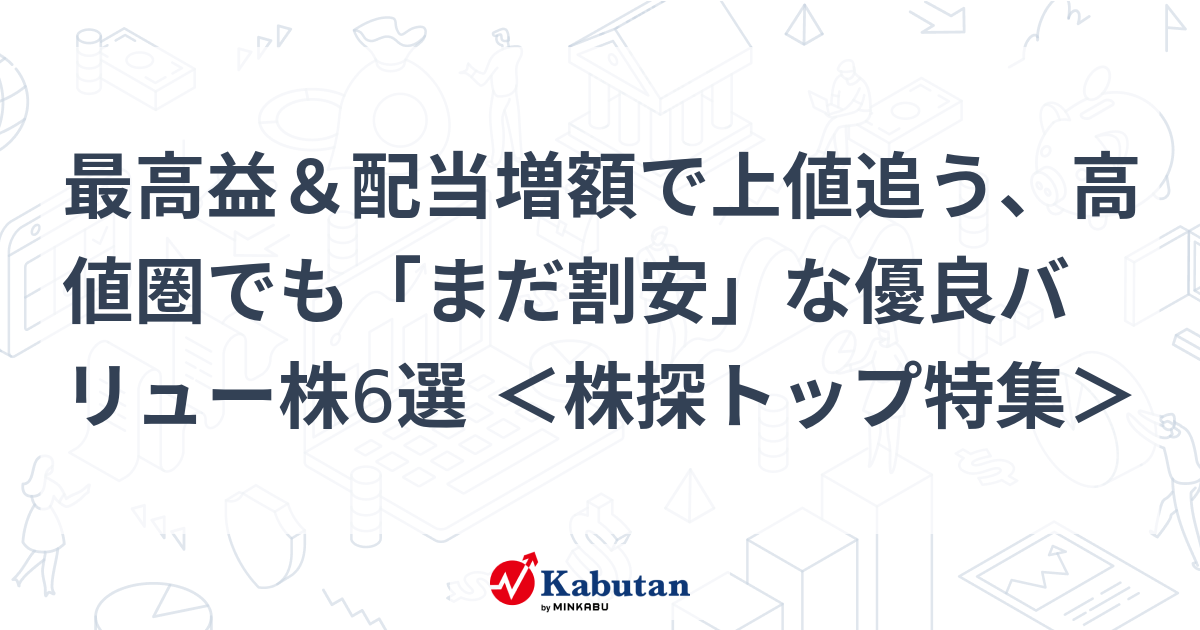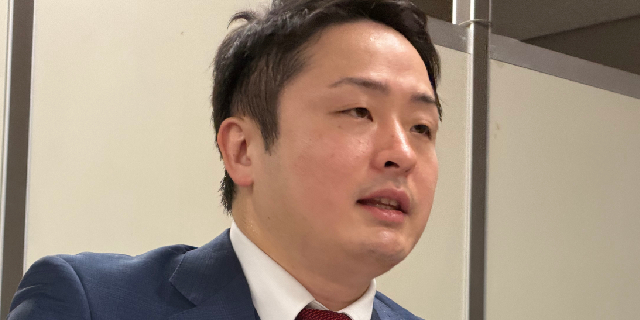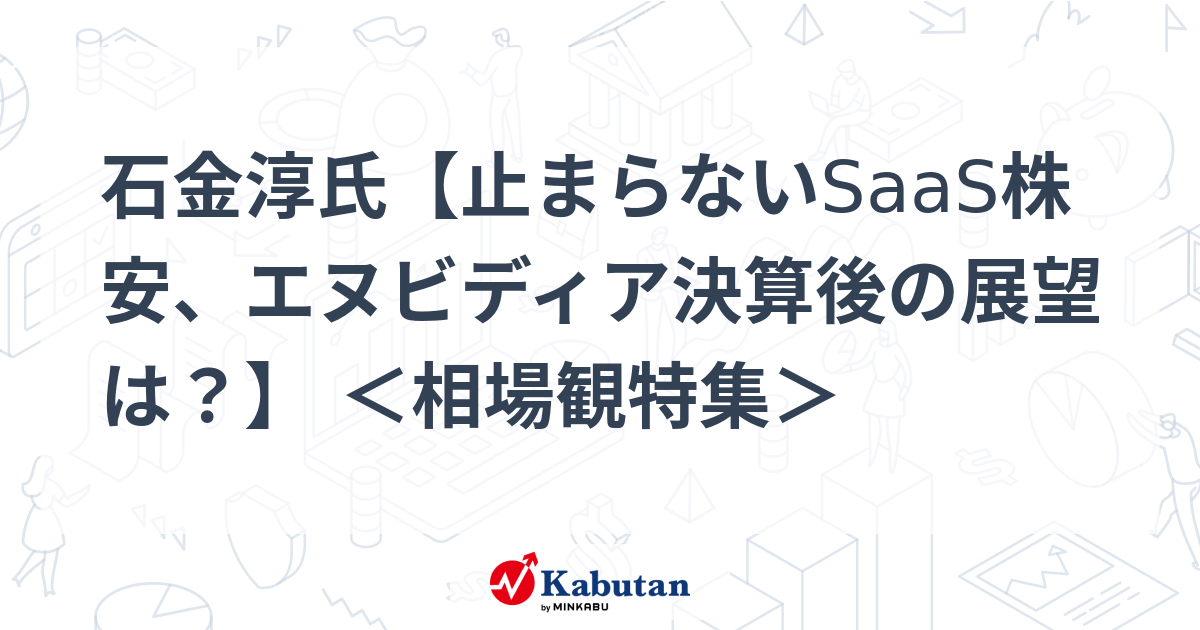【梅仕事2025】会社で梅干し漬けてみた:その3「干し」 → 完成

6月23日に開始した2025年度の梅仕事。今年の舞台は自宅ではなく会社! うまく漬かるかどうかは未知数だが、とりあえず第1次工程「梅の塩漬け」は無事に終えることができた。
その後7月4日に第2工程「赤しそ漬け」に着手。そして先日の7月29日から第3工程である「干し」を開始し、昨日8月1日、無事に全作業を終えることができたので情報共有しておきたい。
「梅干し」の制作においてクライマックスとなるのが、名前の通り「干し」の作業。亡き祖父の教えによれば「土用の丑の日の頃、三日三晩、干す」とのことで、ある意味では最も大切な工程。
雨が降りそうなら取り込むのは無論、状況によって臨機応変に対処せねばならない。このあたりはキャリアがモノを言うので、熟練者であればあるほど美味い梅干しが出来上がるのかもしれない。
私の梅干しキャリアは2021年からなので、まだ5年目。梅干し師匠である祖父に比べたらペーペーもペーな青二才であるが、今年は以下のような感じで干してみた。
〜1日目〜
まずはよく晴れた7月29日(火)の午前から干すことを決意。編集部のシンクの中で眠らせておいた漬物樽の中身を確認すると……
いい感じで浸かってる!
んで、家から持参したのは、ダイソーで買った「多目的ネット」3連発。今回は約2kgの梅を漬けたが、だいたい1kgでネット1つが目安。あとの1つは、紫蘇を干すためだ。
埃などがつかないよう、事前に入念に掃除した会議室のベランダに多目的ネット3枚を連結して設置し、
よ〜く浸かった梅と紫蘇を……
くっつかないよう間隔をあけつつ、丁寧に丁寧に干す!
梅酢も、ゴミが入らないよう、ネットなどでカバーしつつ、消毒の意味を込め、できるだけ日が当たる場所に置いておく。
午後、1粒1粒ひっくりかえしたり面倒を見つつ……
この日は一旦取り込むことにした。赤紫蘇はそのままにして、梅だけ、梅酢の中に戻し、ヒタヒタになるよう漬けて……(この時は、漬物石などは使わない)
もとの場所で一晩寝かす。
〜そして2日目である翌日(7月30日)〜
午前中に、ふたたび干す。
午後にひっくりかえしたりして、
この日は取り込まず、そのまま放置。しっかりと熱帯夜の夜露を梅に吸わせる。
〜3日目(7月31日)〜
午前中にひっくり返して、
午後にも1度ひっくり返す。ちなみに2025年の丑の日は2回あり、2回目がまさにこの日、7月31日である。(1回目は7月19日)
で、「丑の日に、三日三晩」なので、この日の夜も夜通しで干す……のだが、天気予報は翌日が雨。しかし、干しているのは、すぐに対処できる自宅ではなく会社のベランダ。
う〜む、これは一か八かの賭けになるぞ……。かくして私は「干し続ける」ことを選択し……
〜4日目(8月1日)〜
翌朝、早起きして会社に行くと、ギリギリセーフでまだ降っていない!
念のため、もしもの雨に備えて少し内側に干しておいたが、その心配は杞憂に終わった。
で、ネットの中身を確認してみると──
超絶いい感じ!!!!!
すぐさま取り込む。ちなみに、取り込んでいる最中に雨が降ってきた! 本当に神がかり的なギリギリセーフ!!
紫蘇もジップロックに取り込み、梅酢も、茶漉しなどを使いつつ瓶に入れて……
収穫完了!
うほぅ!
いい感じすぎる!!!!!
んで、一応もう食べられるのだが、私の経験上では、数ヶ月ほど(半年くらい?)寝かせたほうが味が落ち着いて美味しくなると思っているので、
梅干しは、涼しい暗所で寝かせることにした。来年の春ごろに食べてみたいと思う。
一方の梅酢と紫蘇は冷蔵庫へ。梅酢に関しては、大根を漬けたり、生姜を漬けたり(まさに「紅しょうが」)して食すのもヨシ。いろいろ楽しむぞ〜!
そしてジップロック内の紫蘇は、除湿剤(シリカゲル)を入れつつ、カラッカラになったところでミキサーなどで粉末にしたら「自家製ゆかり」の出来上がりだ。
ちなみに、ちょうどこの日、梅仕事の後、埼玉奥地の「100万円の古民家」に向かったのだが、その際に持参したおにぎりは……
まさに過去、私が作った「自家製ゆかり」を使った「2023年度版GO羽鳥うめぼしおにぎり」であった。
なお、ゆかりに関しては、なるべく早めに制作して使ったほうが、できたての香りを感じて良いと思う。来週あたり、粉末にしちゃおう。
──てな感じで、自宅ではなく会社で梅干しを作ってみた2025年の梅仕事は、思いのほか無事に完了の大成功! 春の味見が楽しみだ〜\(^o^)/
【完】
執筆:GO羽鳥 Photo:RocketNews24