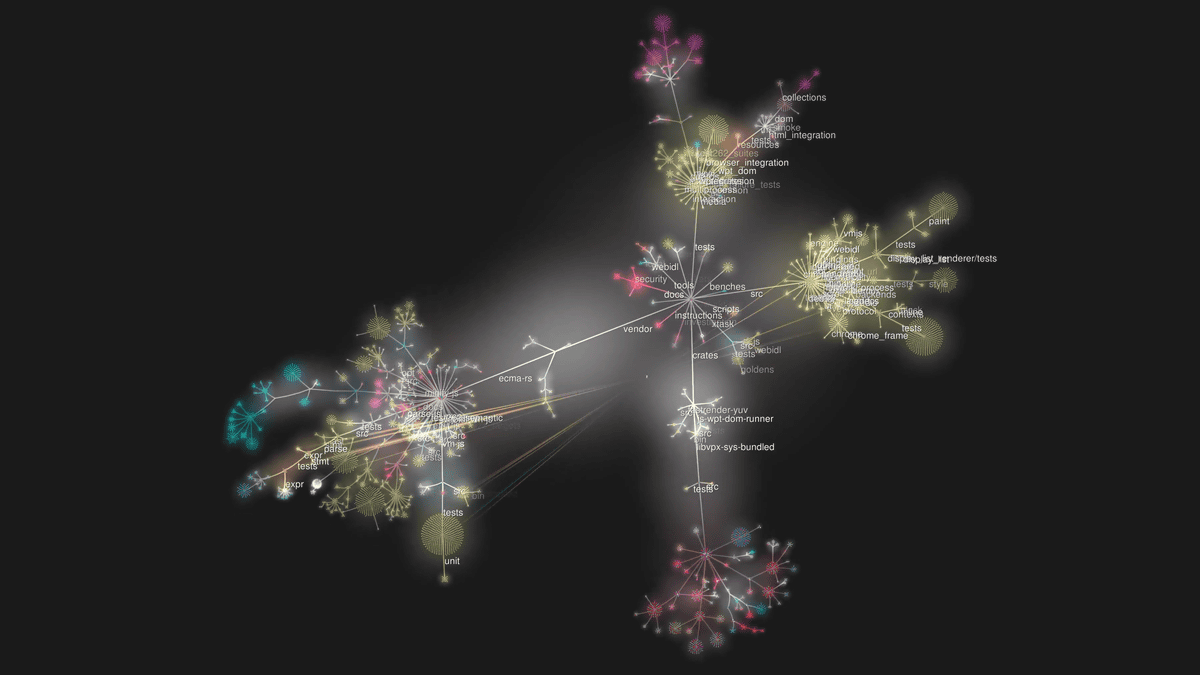カメラ沼の新たな選択肢、ハイエンドコンデジソニー「RX1R III」で動画を撮る

写真が好きという人は、カメラも好きである。写真好きとカメラ好きの人数を比較したら、むしろカメラ好きの方が人数が多いのではないかという気がする。カメラを愛でているだけで写真は撮らないという人も、実は結構いるんじゃないかと思う。
カメラ好きな人はいろんなカメラを手に入れるわけだが、いつかは手に入れたいカメラというのがあるだろう。ある人にとってはLeicaだろうし、ある人にはHASSELBLADかもしれない。これまでそうした「最後に行き着くカメラ」にあまり日本メーカーの名前が上がってこなかったが、昨今は富士フイルムやリコーのコンデジが入ってきている。
8月8日に発売が開始されたソニー「RX1R III」は、前作からおよそ10年ぶりに投入される、ハイエンドコンパクトデジカメだ。単焦点レンズにフルサイズセンサーを搭載し、市場想定価格は66万円前後。
そもそもRXは、ソニーのコンパクトデジカメブランド「サイバーショット」の中で、高級路線のシリーズだ。もっともよく知られているのは小型化を推進したRX100シリーズで、最新モデルは2019年発売のM7まで続いている。一方コンデジではなくネオ一眼スタイルのRX10もシリーズ化しており、2017年にM4が出ている。
RX1はサイズ的にはRX100とRX10の中間ということになるが、小型ながらフルサイズセンサーを搭載したことで、フラッグシップモデルに位置づけられる。初号機は2012年のRX1で、その半年後にはローパスフィルタなしのRX1Rが発売され、物議を醸した。「半年でローパスなし版が出せるなら、なんで最初から出さないんだ」というわけである。
そして2015年に発表されたRX1R IIは、本来ならその年に出るはずだったが、諸事情で発売が延期され、翌年の2月に登場している。ローパスフィルタのありなしが切り替えられるという画期的な機能を搭載し、ある意味ローパス論争に決着をつけた格好だった。
元々RX1Rシリーズは写真での評価が高く、すでにRX1R IIIも多くのメディアで評価されているが、動画性能はあまり語られていないところである。今回はこの動画性能について検証してみたい。
RXシリーズ、特にRX100は長年ボディは同じで中身だけ最新という手法を採用しており、設計工数を減らすとともに、買い替えてもアクセサリ類はそのまま使えるといったところをメリットとしていた。
一方RX1R IIIのボディは、さすがに10年経てば同じというわけにもいかず、サイズ感としては前作とほぼ同じだが、完全に新設計となっている。
大きなところでは、ディスプレイ関係がかなり違う。前作は液晶ディスプレイが縦方向にチルトし、自撮りにも対応したが、今回はディスプレイが埋め込み固定となっている。すでに前作から、ハイエンド機でディスプレイがチルトするのは安っぽいのではないかという意見もあったのは事実だ。
ただそこから10年、多くの人は自撮りするようになり、ディスプレイが前を向く設計が必須となった。そもそもVlogカメラブームを仕掛けたのがソニーなわけだが、それに逆行する……というか、そうしたブームとは関係なく、なるべく可動部を減らして長く使えるものを、という強い意思を感じる。
ビューファインダも、以前はRX100M3で初搭載して好評であったポップアップ式であったものが、今回は固定になり、可動部を減らしている。内部設計が小型化したことで、光学部がそのまま埋め込めるスペースができたということだろう。小さいながら、アイカップも取り付けられる。
レンズは前作と全く同じで、「ZEISS ゾナーT* 35mm F2」。前作での評判が良かったことから、あえてそこは変えなかった。絞りリングはF2から22まで、1/3段刻みのクリッカブルとなっている。最前面にマニュアルフォーカス用のリングを備えるほか、通常撮影とマクロ撮影の切り替えリングがある。
レンズ部にもデザイン的な変化は見られる。前作はレンズの根本部分にメタルオレンジのリングの差し色が大きく入っていたが、今回はそのリングがものすごく細くなっている。αシリーズにも通じるソニーフルサイズカメラの共通イメージをもたせつつ、あまり主張しないのが今風である。
センサーは静止画最大約6,100万画素、動画時最大約5,080万画素の35mmフルサイズExmor R CMOSセンサー。ローパスフィルターレスである。動画記録は4KおよびフルHDで、それぞれ10bitか8bitが選択できるほか、10bitではIntraフレーム記録にも対応する。
【動画フォーマット一覧】
23.98p (50Mbps)
1,920×1,080 (4:2:0, 8bit) 119.88p (100Mbps/60Mbps) 59.94p (50Mbps/25Mbps) 29.97p (50Mbps/16Mbps)23.98p (50Mbps)
XAVC S-I HD 1,920×1,080 (4:2:2, 10bit) 59.94p (222Mbps) 29.97p (111Mbps)23.98p (89Mbps)
前作では前面にフォーカスモードの切り替えダイヤルがあったが、これがなくなり、前面はシンプルになった。同じくなくなったものといえば、動画の録画ボタンがある。
以前はグリップ部も脇に小さく存在したが、本機ではそこはC2ボタンになっている。かといって動画撮影機能を奥へ引っ込めたわけではなく、メニュー内部に動画記録用ボタンを配置することで、どのモードからでも動画撮影に入れるようになっている。
軍艦部は、モードダイヤルやシャッターボタンの突起構造をやめて、本体埋め込みになった。ビューファインダも埋め込みになったことで、全体的に軍艦部をフラットにするというまとめ方になっている。こちらも出っ張りがあるとバッグの中でものが引っかかって曲がったり取れたりするので、なるべく故障がないように、という考え方なのかもしれない。
ボディ左側の端子類は、上からアナログマイク入力、USB-C、MicroHDMI端子となっている。バッテリーとメモリーカードスロットは底部にあり、このあたりは定番の作りだ。
では早速撮影してみよう。本機は35mm単焦点ではあるが、写真撮影に関しては50mmと70mmでも撮影できるよう、センサークロップモードが付いている。
一方動画にはそのような機能はなく、代わりに超解像ズームが使える。ただデフォルトではボタンに割り当てられていないので、パッと使えるような機能ではない。
一方電子手ブレ補正を入れると画角が狭くなるので、それを一種のセンサークロップとして使えば、2サイズが撮影できることになる。具体的に何mmになるのかは資料がないが、写真の画角と比較すると、40~45mm程度ではないかと思われる。
手ブレ補正は、写真撮影では搭載されていない。レンズ部に光学補正機構がないようだ。一方動画撮影時には、アクティブ(電子)手ブレ補正のみが使用できる。画角はだいぶ狭くなるが、補正力はかなり強い。
動画画角としての35mmは、それほど広角というわけでもない。人物撮影では、思ったよりも後ろに下がらないと構図が決まらないケースが多かった。ただ本機の本質は「写真としての標準画角35mmの良さ」だと思うので、動画撮影はある意味なるようにしかならないとして受け入れるべきだろう。
今回はせっかくなので、絞りを開け気味にして被写界深度を浅くしている。絞りを開けるためにND4を装着して撮影している。深度が浅いとフォーカスが不安になるところだが、AFでもかなり狙ったところに合焦する。このあたりはアルゴリズムがかなりこなれている印象だ。
動画撮影機能としては、Flexible ISOによるLog撮影にも対応しているが、昼間の映像はすべて非Log撮影である。後述する夜間撮影がLog撮影だ。
マクロモードも試してみた。マクロなしではレンズ前30cmまでしかフォーカスが合わないが、マクロモードにすれば20cmまで接近できる。とはいえ、35mm画角での20cmなので、超マクロという感じでもない。
美肌モードは、OFF、Lo、Mid、Hiの切り替えになっている。おもに写真で使われる機能ではあるが、そのまま動画でも使用できる。効果を上げても輪郭がぼやけることもなく、さりげなく処理している。
音声収録に関してもテストしてみた。マイクは軍艦部上面にあるが、微風でもかなりフカレが発生する。このあたりは、Vlog向けZVシリーズとは違うようだ。風音低減を入れると改善されるが、かなり大胆にローカットするようで、音質が硬くなる。
先週レビューしたDJI Mic 3がまだ手元にあったので、これもテストしてみた。アダプタを使えば、アナログ入力にケーブルを回す必要もなく、アクセサリーシュー経由で直接接続できる。
こちらはウインドスクリーンを付けただけのノーマル録音だが、かなり良好に集音できた。ソニーカメラとDJIマイクの相性はいいようだ。
次に特殊撮影機能を見てみよう。エフェクト系の機能としては、2021年以降のソニーの他のカメラ同様、「クリエイティブルック」が搭載されている。この機能は写真でも動画でも同様に使用できる。
ただ、長く使うハイエンドカメラとして、本当にこのような機能が必要だったのかは、意見が分かれるところではないだろうか。フィルム系とモノクロ系のバリエーションを増やすなど、このカメラなりのこだわりが見たかったところである。
写真にはない機能としては、「ピクチャープロファイル」がある。これはガンマカーブやカラーモードなど、動画にしかない規格に対応するためである。HLGやBT.2020対応のほか、FX系に搭載されているSーCinetoneや、LUTを読み込ませて使用できるPPLUTといった機能を搭載している。またLog撮影機能はここで設定するのをやめて、メニューの中に独立した。そのため、PP7~9までは欠番となっている。
スロー&クイックモードはソニーのカメラでは定番の機能である。ただ4K解像度では最高フレームレートが30fpsなので、クイックは可能だが、スローはあまり倍率は高くない。
一方HD解像度では最高120fpsなので、24pで撮影すれば5倍スローが撮影できる。SNもよく、AFもちゃんと効く。
次に夜間撮影をテストしてみる。Flexible ISOによるLog撮影で、S-Gamut3.Cine/S-Log3撮影してみた。Log撮影ではISO感度が200からのスタートとなるので、そこから倍々に上げていった。シャッタースピード1/30、絞りF2である。
レンズが明るいこともあり、ISO 6400ぐらいですでに十分だが、最高のISO 32000ではすでに奥の建物は白とびするほど明るい。ただSNは次第に下がってくるので、ISO 12800以上ではグレーディングのついでにノイズリダクションをかけた方がいいだろう。
単焦点コンパクトデジカメで、60万円超えのカメラとして登場したRX1R III。写真としての表現力に注目が集まるところだが、昨今のソニーのカメラにしては、動画撮影についてはやや大人しい印象を受けた。4K解像度で最高フレームレートが30pというのも、そこで無理して動画のためにリソースを割かないということだろう。
液晶モニターがチルトしないので、ローアングルやハイアングルでの撮影はやりにくい。視野角は広いので上下から覗き込めば確認はできるのだが、フレーミングはやはり正面から見たいところだ。腰が悪いオジサンにとっては割とキツいカメラである。ストリートスナップのような目線位置なら、楽に撮れる。
また対面自撮り撮影も、モニターが見えないので難しいだろう。マイク性能も普通で、ある意味Vlog的ではない。一方でSーLog3撮影はカバーしており、FXシリーズなど他のカメラとマルチで使っても色が合うようにはなっている。
写真のハイエンドカメラではあるが、動画でも同様にハイエンドというわけでない。かといって動画を完全に捨てるわけにもいかなかったところに、今のソニーの立ち位置がわかる。