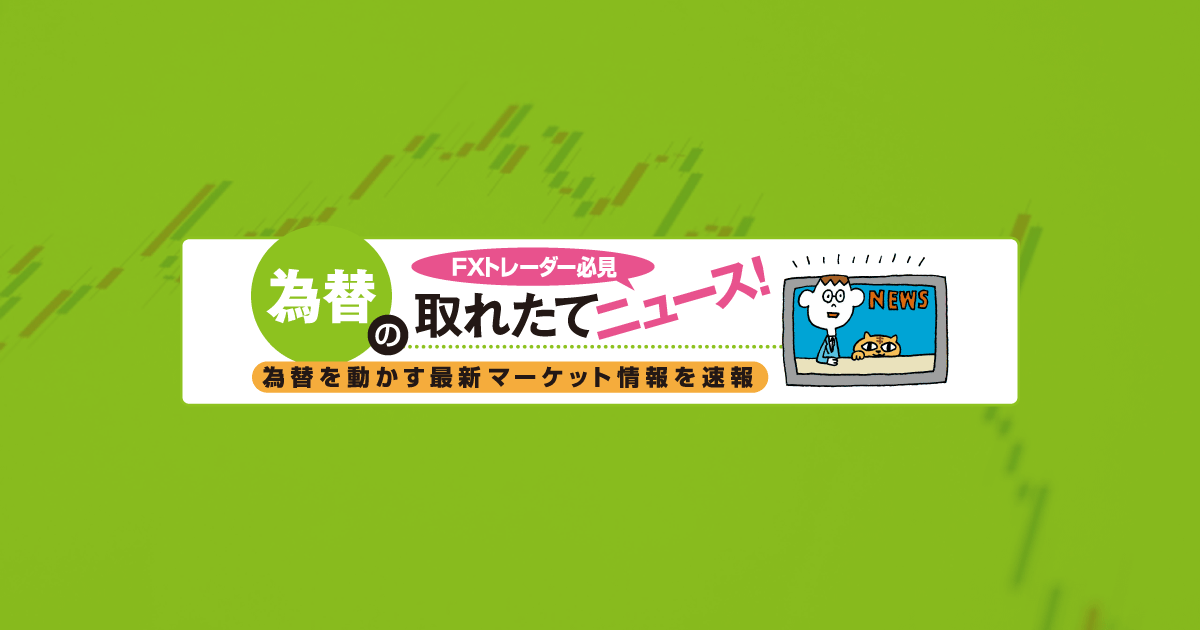コラム:ベセント米財務長官の「日銀利上げ」発言とドル/円相場=尾河眞樹氏
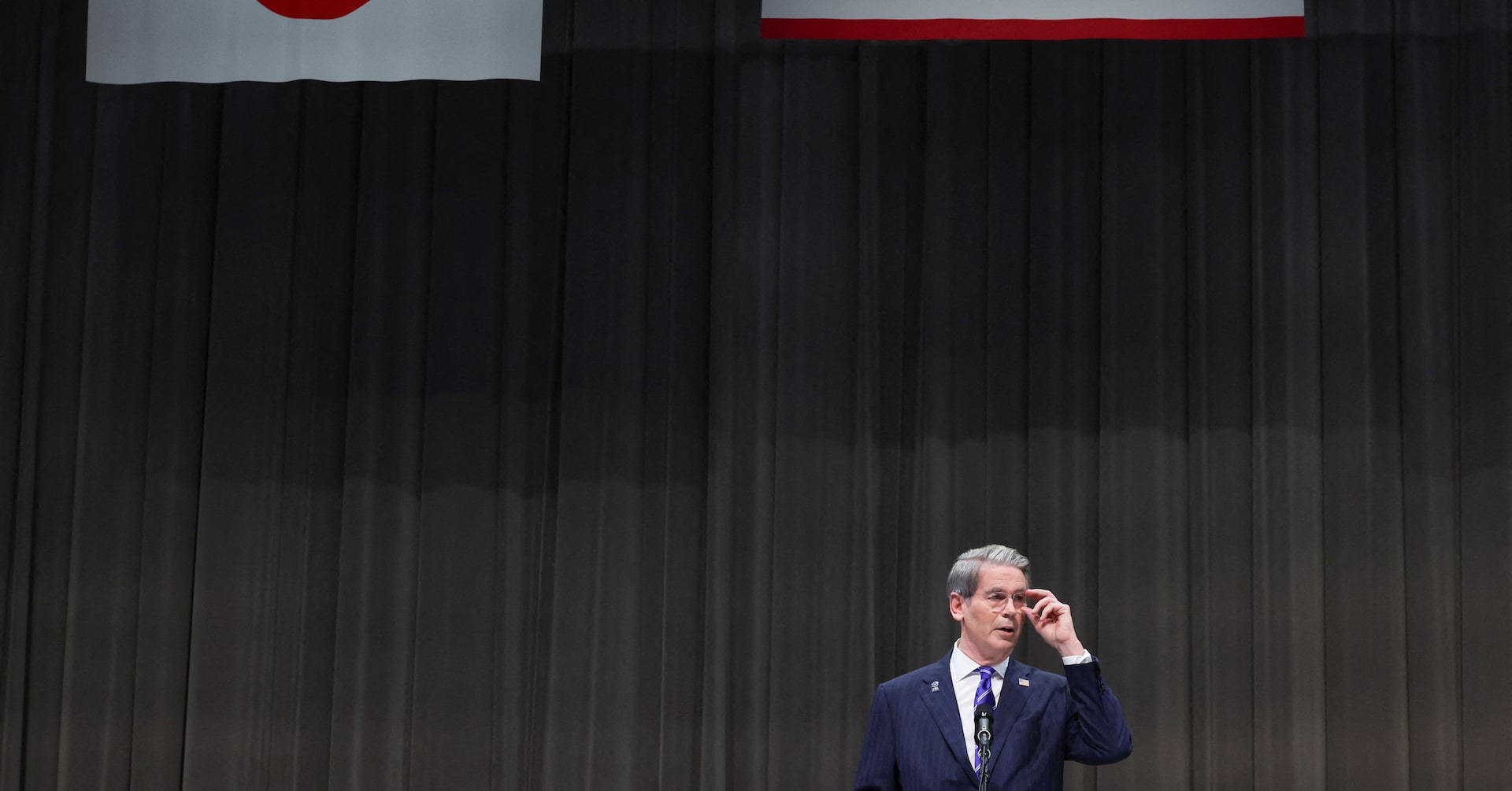
[東京 20日] - 「日銀はビハインド・ザ・カーブに陥っている。そのため日銀は利上げを行い、インフレを抑制する必要があるだろう」――ベセント米財務長官は8月13日のインタビューでこのように発言した。これを受けて日本の10年債利回りは1.57%台まで上昇した。「米長期金利は日本や欧州の長期金利の影響を受ける」という文脈での発言であり、「あくまで私見」と断ってはいるものの、米財務長官が日銀の金融政策について直接的に発言するのは異例だ。
トランプ政権は米連邦準備理事会(FRB)による早期「利下げ」の必要性を主張しており、仮に日銀が早期「利上げ」に踏み切れば、ドル/円は大幅に下落する公算が大きい。財務長官として米国債市場を守る立場のベセント氏は「強いドル政策の維持」を掲げてはいるものの、あえて深読みすれば、日銀に利上げを迫ることで間接的にドル安を促しているように見えなくもない。
翻って日本経済を点検してみると、8月15日に発表された今年4-6月期の実質国内総生産(GDP)成長率は、前期比年率1.0%増と、5四半期連続のプラス成長となり、0.5%前後とみられる潜在成長率を上回った。寄与度をみると、内需が実質で0.1ポイント減と2四半期ぶりのマイナスとなった一方で、外需は0.3ポイント増と、プラスに寄与している。日銀短観にもみられる通り、家計と企業の景況感のギャップは大きく開いたままで、食品価格高騰などによる節約志向から、個人消費は伸び悩む一方、企業部門は好調だ。足下で懸念されていたほど米関税引き上げによる日本経済への影響が深刻化していないのは、日米合意により関税率が15%に引き下がり、4月の相互関税発表時に比べて不透明感が後退したことなどに加え、為替レートが円安水準で推移していることも背景にありそうだ。
内閣府の「企業行動に関するアンケート調査(令和7年2月)」によれば、輸出企業の採算円レートは、製造業が1ドル127.1円、非製造業は138.7円となっており、現状の147円前後であれば十分採算が取れるうえ、円高方向への変動にも多少のバッファーがあることがわかる。ただし、4-6月期GDPでは輸出物価が12%も低下した点には注意が必要だ。日本企業が値引き輸出で関税負担を吸収したことが数字に表れており、円安効果で値引き輸出をどこまで続けられるか、今後注目していきたい。
ソニーフィナンシャルグループは今月、日米合意などを踏まえて、日銀の次回利上げ時期の予想を2026年7月から同年4月に前倒しした。7月31日に行われた日銀金融政策決定会合後の記者会見で、植田日銀総裁は「一気に霧が晴れることはなかなかないと思う」「特に各国の通商政策等の今後の展開やその影響を受けた海外の経済・物価動向をめぐる不確実性は高い状況が続いている」などと述べ、幾分ハト派的な印象を受けた。米国の日本に対する15%の関税率は、米政府が日本政府に送った「書簡」に記されていた25%よりは低いとはいえ、トランプ政権発足時の平均関税率は2.5%だったことを考えると、関税率が大幅に上昇していることに変わりはない。これらの影響がいつ頃日本経済に反映されるのかされないのかも含め、しばらく様子を見たいとの意図はあるだろう。したがって年内の利上げの可能性は高くないとみており、ベセント氏が利上げの必要性に言及したからといって、日銀が早々に利上げを決定するとは考えにくい。ただし、日本の景気は上振れの可能性は低いものの、先述した通り下振れリスクも後退しており、企業もドル/円の円高にはある程度耐え得る環境であることや、日経平均株価が連日高値を更新している現状などを踏まえると、米国の景気減速の可能性さえ後退すれば、年内の利上げの可能性もあり得るかもしれない。
一方、FRBにとっても舵取りが難しい環境は続いている。ベセント氏は先述した13日のインタビューでFRBの金融政策について、「9月の0.5%の利下げを皮切りに、そこから一連の利下げを実施できるだろうと考えている」などと述べた。これにより市場では9月の大幅利下げへの期待が浮上しドルが下落する場面もあった。しかし、ベセント氏は翌14日に前日の発言について、金利を中立水準にするには1.5%の利下げが適正という意味で、「FRBに利下げを要求したわけではない」と発言を微妙に修正し、ドルも持ち直した。
これらの発言に先立ち発表された7月の米消費者物価指数(CPI)は、総合指数が市場予想を下回ったものの、変動の激しい食品とエネルギーを除いたコア指数は前年比3.1%と市場予想の同3.0%をわずかながら上回ったうえ、このうち財は前年比1.2%と、前月の同0.7%から伸びが加速。サービスも前年比3.6%と高止まりだ。7月の米生産者物価指数(PPI)で、コア指数が前年比3.7%と、市場予想の同3.0%を大きく上回る伸びとなったことなども考慮すれば、今後米インフレが加速する可能性は徐々に高まっているようだ。
フェデラルファンド(FF)金利先物でみると、本稿執筆時点では、市場では9月の米連邦公開市場委員会(FOMC)で、0.25%の利下げが84%織り込まれている状況だ。7月の米雇用統計の弱い結果を受けて、利下げに踏み切る可能性は高いものの、上述したCPIやPPIを踏まえて、0.5%の大幅利下げへの期待は萎んでいる。22日にはパウエルFRB議長がジャクソンホール・シンポジウムで「経済見通しとフレームワークレビュー」というテーマで基調講演を行う。今年の同シンポジウムのテーマは「移行期の労働市場:人口動態、生産性、マクロ経済政策」となっており、米労働市場が減速傾向にあるなかで、9月の利下げ再開への道筋をつけるべく、利下げについて何等かの示唆がある公算が大きい。
とはいえ、9月の利下げ自体はすでに市場に織り込まれているなかで、パウエル議長が今後の利下げの可能性に触れる程度であれば、ドル/円相場への影響は限られるのではないか。仮に、今後の大幅利下げを示唆するようなことがあればドル/円急落もあり得るが、前述した米インフレの状況を見る限り、可能性は低いだろう。反対に「今後の金融政策はデータ次第」を繰り返し、利下げを一切匂わせないようであればむしろ、ドル高が進行する可能性がある。
ソニーフィナンシャルグループは、9月と12月、年内2回の利下げを予想しており、利下げは3.875%で打ち止め、27年には再利上げを予想している。中立金利まで利下げできるほど、米インフレは減速しないというのが見通しの背景だ。26年初から発動する「一つの大きく美しい法案」の減税・規制緩和による景気再加速の効果も来年の米景気を押し上げよう。目先はFRBの利下げと日銀の利上げ観測などで、ドル/円が下落する場面もありそうだが、それでも今年4月の「相互関税ショック」直後の140円ちょうど付近を大きく下回る可能性は低いと予想している。
反対に、当社の見通し通り、FRBの利下げが2回にとどまり、日銀も年内の利上げを見送るようであれば、年末にかけてはドル/円がじわり反転上昇すると予想しており、年末予想値は148─150円付近に据え置いている。他方、本稿で取り上げた通り、ベセント氏が日米の金融政策に言及するようになってきたのは気がかりだ。特にFRBの中立性が保たれないと市場が判断した場合には、140円を下回るドル安も想定しておく必要があるだろう。
編集:宗えりか
*本コラムは、ロイター外国為替フォーラムに掲載されたものです。筆者の個人的見解に基づいて書かれています。
*尾河眞樹氏は、ソニーフィナンシャルグループの執行役員チーフアナリスト。米系金融機関の為替ディーラーを経て、ソニーの財務部にて為替ヘッジと市場調査に従事。その後シティバンク銀行(現SMBC信託銀行)で個人金融部門の投資調査企画部長として、金融市場の調査・分析を担当。著書に「〈最新版〉本当にわかる為替相場」、「ビジネスパーソンなら知っておきたい仮想通貨の本当のところ」などがある。
*このドキュメントにおけるニュース、取引価格、データ及びその他の情報などのコンテンツはあくまでも利用者の個人使用のみのためにコラムニストによって提供されているものであって、商用目的のために提供されているものではありません。このドキュメントの当コンテンツは、投資活動を勧誘又は誘引するものではなく、また当コンテンツを取引又は売買を行う際の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。当コンテンツは投資助言となる投資、税金、法律等のいかなる助言も提供せず、また、特定の金融の個別銘柄、金融投資あるいは金融商品に関するいかなる勧告もしません。このドキュメントの使用は、資格のある投資専門家の投資助言に取って代わるものではありません。ロイターはコンテンツの信頼性を確保するよう合理的な努力をしていますが、コラムニストによって提供されたいかなる見解又は意見は当該コラムニスト自身の見解や分析であって、ロイターの見解、分析ではありません。
私たちの行動規範:トムソン・ロイター「信頼の原則」, opens new tab
筆者は「Reuters Breakingviews」のコラムニストです。本コラムは筆者の個人的見解に基づいて書かれています。