「脳のお掃除機能」を高め認知症を予防! 効果が実証された3つの対策
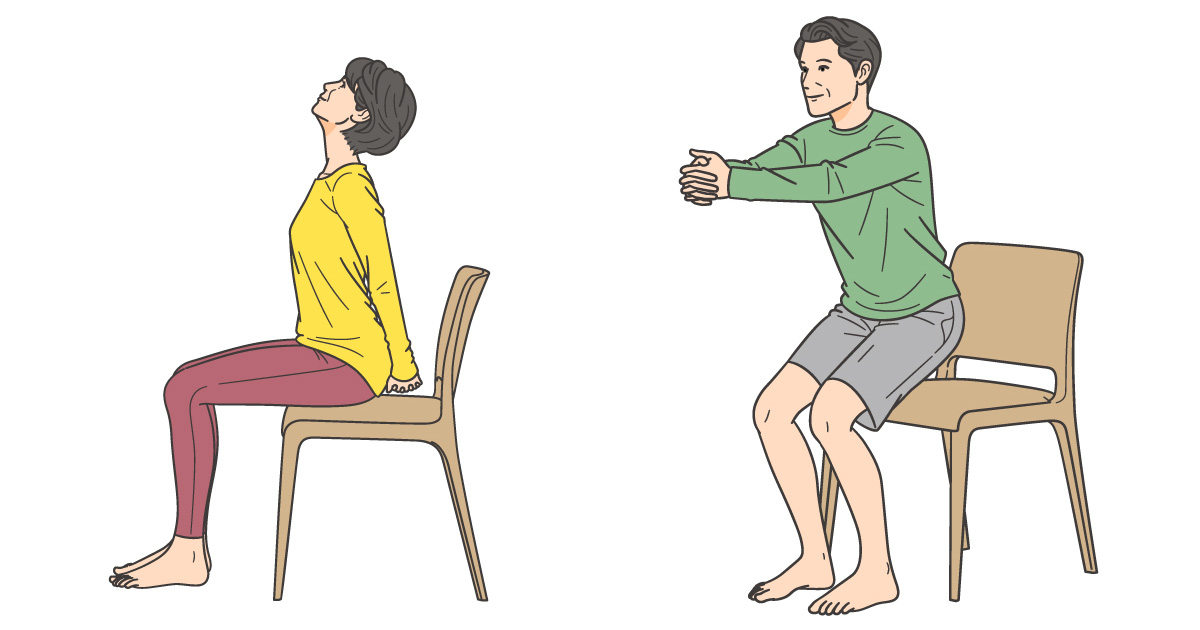
-
- シニアこそ「たんぱく質」で筋肉づくり 健康長寿をかなえる摂取術
-
シニア世代が特に意識したい栄養素が「たんぱく質」。近年、健康的に長生きするにはたんぱく質が重要だという認識が広がりつつあります。しかし、実際に何を、どのくらいとればいいのかについては、まだ十分に知られていません。一体、どのように摂取するとよいのでしょうか。過去の人気記事を基に、たんぱく質のとり方を見ていきましょう。
-
- 体のサビ防ぎ、老化を遠ざける! 「抗酸化生活」の極意
-
老化を進めるさまざまな要因が明らかになっている中で、大きく注目されているのが「酸化」だ。酸化によって細胞が傷つき、細胞や組織の機能を低下させ、老化を進行させてしまう。できるだけ老化を遅らせ、健康に過ごすためには、活性酸素を除去する力「抗酸化能」を高めることが肝要だ。
-
- 血管の若さが寿命を決める 100年元気に過ごす血管若返り術
-
人生100年時代をすこやかに過ごすためには、若々しくしなやかな「血管」を長く保つことが不可欠です。血管の老化予防に役立つ最新の知見を紹介しましょう。
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 2
記憶、判断などの脳の機能が低下していく「認知症」。15年後の2040年には認知症とその前段階のMCIを合計すると患者数は1200万人近くになると推計される。実は近年、科学的に正しい認知症予防に関するエビデンスが蓄積され、「認知症リスクは45%減らせる」という時代が到来している。認知症予防学の第一人者である日本認知症予防学会前代表理事で鳥取大学医学部教授の浦上克哉氏に、認知症予防に役立つ、認知症発症リスク因子に関する最新研究について詳しく聞いていく。
浦上克哉(うらかみ かつや)氏 日本認知症予防学会 前代表理事、鳥取大学医学部保健学科認知症予防学講座(寄附講座)教授
有料会員になると、鍵つき記事が全て読める&医療専門家に電話相談や名医紹介も!
-
- シニアこそ「たんぱく質」で筋肉づくり 健康長寿をかなえる摂取術
-
シニア世代が特に意識したい栄養素が「たんぱく質」。近年、健康的に長生きするにはたんぱく質が重要だという認識が広がりつつあります。しかし、実際に何を、どのくらいとればいいのかについては、まだ十分に知られていません。一体、どのように摂取するとよいのでしょうか。過去の人気記事を基に、たんぱく質のとり方を見ていきましょう。
-
- 体のサビ防ぎ、老化を遠ざける! 「抗酸化生活」の極意
-
老化を進めるさまざまな要因が明らかになっている中で、大きく注目されているのが「酸化」だ。酸化によって細胞が傷つき、細胞や組織の機能を低下させ、老化を進行させてしまう。できるだけ老化を遅らせ、健康に過ごすためには、活性酸素を除去する力「抗酸化能」を高めることが肝要だ。
-
- 血管の若さが寿命を決める 100年元気に過ごす血管若返り術
-
人生100年時代をすこやかに過ごすためには、若々しくしなやかな「血管」を長く保つことが不可欠です。血管の老化予防に役立つ最新の知見を紹介しましょう。
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 3
記憶、判断などの脳の機能が低下していく「認知症」。15年後の2040年には認知症とその前段階のMCIを合計すると患者数は1200万人近くになると推計される。実は近年、科学的に正しい認知症予防に関するエビデンスが蓄積され、「認知症リスクは45%減らせる」という時代が到来している。認知症予防学の第一人者である日本認知症予防学会前代表理事で鳥取大学医学部教授の浦上克哉氏に、認知症予防に役立つ、認知症発症リスク因子に関する最新研究について詳しく聞いていく。
浦上克哉(うらかみ かつや)氏 日本認知症予防学会 前代表理事、鳥取大学医学部保健学科認知症予防学講座(寄附講座)教授
有料会員になると、鍵つき記事が全て読める&医療専門家に電話相談や名医紹介も!
-
- シニアこそ「たんぱく質」で筋肉づくり 健康長寿をかなえる摂取術
-
シニア世代が特に意識したい栄養素が「たんぱく質」。近年、健康的に長生きするにはたんぱく質が重要だという認識が広がりつつあります。しかし、実際に何を、どのくらいとればいいのかについては、まだ十分に知られていません。一体、どのように摂取するとよいのでしょうか。過去の人気記事を基に、たんぱく質のとり方を見ていきましょう。
-
- 体のサビ防ぎ、老化を遠ざける! 「抗酸化生活」の極意
-
老化を進めるさまざまな要因が明らかになっている中で、大きく注目されているのが「酸化」だ。酸化によって細胞が傷つき、細胞や組織の機能を低下させ、老化を進行させてしまう。できるだけ老化を遅らせ、健康に過ごすためには、活性酸素を除去する力「抗酸化能」を高めることが肝要だ。
-
- 血管の若さが寿命を決める 100年元気に過ごす血管若返り術
-
人生100年時代をすこやかに過ごすためには、若々しくしなやかな「血管」を長く保つことが不可欠です。血管の老化予防に役立つ最新の知見を紹介しましょう。
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 4
健康診断や人間ドックは、病気を早期に見つける大切な機会。だが「なんとなく受けているだけ」で、その価値に気づいていない人も多い。加えて、人間ドックではどのオプション検査を受けたらいいか分からないという人もいる。本特集では、健診や人間ドックをより賢く活用するためのポイントを解説していく。
安田聖栄 (やすだ せいえい)氏 医療法人社団あんしん会 四谷メディカルキューブ 理事長、東海大学医学部 客員教授、医学博士
有料会員になると、鍵つき記事が全て読める&医療専門家に電話相談や名医紹介も!
-
- シニアこそ「たんぱく質」で筋肉づくり 健康長寿をかなえる摂取術
-
シニア世代が特に意識したい栄養素が「たんぱく質」。近年、健康的に長生きするにはたんぱく質が重要だという認識が広がりつつあります。しかし、実際に何を、どのくらいとればいいのかについては、まだ十分に知られていません。一体、どのように摂取するとよいのでしょうか。過去の人気記事を基に、たんぱく質のとり方を見ていきましょう。
-
- 体のサビ防ぎ、老化を遠ざける! 「抗酸化生活」の極意
-
老化を進めるさまざまな要因が明らかになっている中で、大きく注目されているのが「酸化」だ。酸化によって細胞が傷つき、細胞や組織の機能を低下させ、老化を進行させてしまう。できるだけ老化を遅らせ、健康に過ごすためには、活性酸素を除去する力「抗酸化能」を高めることが肝要だ。
-
- 血管の若さが寿命を決める 100年元気に過ごす血管若返り術
-
人生100年時代をすこやかに過ごすためには、若々しくしなやかな「血管」を長く保つことが不可欠です。血管の老化予防に役立つ最新の知見を紹介しましょう。
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 5
白内障手術は日本で年間180万件以上も行われる、最も多い手術だ。治療が進化した今、手術により近視・遠視・乱視・老視も治り、メガネなしで快適な生活を送る人もいる。しかし、そうしたことを知らない人はまだ多い。知識不足や医師とのコミュニケーション不足から、手術で期待通りの効果を得られない人もいる。また、意外な原因が白内障を進めることが分かっており、日常生活で注意するべきこともあるという。「白内障手術なんてまだ関係ない」と思っても、人は高齢になれば必ず白内障になる。一生に一度の手術だからこそ、後悔しないための基礎知識を備えておこう。
佐々木洋(ささき ひろし)氏 金沢医科大学眼科学講座 主任教授
有料会員になると、鍵つき記事が全て読める&医療専門家に電話相談や名医紹介も!
-
- シニアこそ「たんぱく質」で筋肉づくり 健康長寿をかなえる摂取術
-
シニア世代が特に意識したい栄養素が「たんぱく質」。近年、健康的に長生きするにはたんぱく質が重要だという認識が広がりつつあります。しかし、実際に何を、どのくらいとればいいのかについては、まだ十分に知られていません。一体、どのように摂取するとよいのでしょうか。過去の人気記事を基に、たんぱく質のとり方を見ていきましょう。
-
- 体のサビ防ぎ、老化を遠ざける! 「抗酸化生活」の極意
-
老化を進めるさまざまな要因が明らかになっている中で、大きく注目されているのが「酸化」だ。酸化によって細胞が傷つき、細胞や組織の機能を低下させ、老化を進行させてしまう。できるだけ老化を遅らせ、健康に過ごすためには、活性酸素を除去する力「抗酸化能」を高めることが肝要だ。
-
- 血管の若さが寿命を決める 100年元気に過ごす血管若返り術
-
人生100年時代をすこやかに過ごすためには、若々しくしなやかな「血管」を長く保つことが不可欠です。血管の老化予防に役立つ最新の知見を紹介しましょう。
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 6
早ければ40代から始まり、80代になると100%近い人が発症する「白内障」。今では全国あちこちで、濁った水晶体を人工の眼内レンズに入れ替える手術が行われている。眼内レンズにはいくつか種類があり、手術後の見え方や費用も違ってくる。こうした情報に関する病院やクリニック側の説明が不十分な場合もあって、手術後の満足度は人によりさまざまだ。どんな視点で白内障手術を受ける眼科を選べばいいのだろうか? よくある事例を交えて、押さえるべきポイントを見ていこう。
眼内レンズの進化により、白内障手術が広く普及
視界が白くモヤがかかったようにぼやけて見える、まぶしく感じる、老眼や近視、乱視が進んでメガネが合わなくなった…こんな自覚症状があれば「白内障」の可能性が高い。白内障は、目のピント調節を行う「水晶体」が濁っていく、進行性の病気(前回参照)。唯一の根治療法が、濁った水晶体を人工の「眼内レンズ」に交換する手術だ。現在、白内障手術は年間180万件以上行われている。
白内障は加齢とともに進むため、手術が広まった背景には間違いなく高齢化が影響している。金沢医科大学眼科学講座主任教授の佐々木洋氏によると、それ以上に大きな要因が「眼内レンズの劇的な進化」だという。1カ所にピントが合う眼内レンズに続き、2カ所、3カ所と複数箇所にピントが合うタイプが登場。さらに、乱視を矯正するレンズも選択可能に。20年前までの白内障手術は「矯正視力を改善するための手術」で、術後は老眼の状態で乱視が残ることも多かったが、今ではレンズの選び方次第で近眼や老眼、遠視、乱視の改善が期待できるようになった(詳しくは後述します)。
佐々木氏は、白内障治療の進化についてこう語る。「以前は近くを見ることがそれほど重視されなかったので、遠くだけにピントを合わせる眼内レンズを入れ、手術後に近くを見るときは老眼鏡を使う方法が主流でした。しかし現在は、パソコンやスマートフォンを使う人が増え、『遠くも近くも裸眼で見たい』と思う人が多くなりました。その希望をかなえるようなレンズが登場し、選択肢が広がったことも白内障手術が増えた要因です」
患者の知識不足、医師の説明不足が手術を後悔する理由に
読者の皆さんの身近にも、白内障手術を受けた人はたくさんいるだろう。その人たちから、「こんなに見えるようになるなんて!」「もっと早く受ければよかった」と感激する声を聞いたことはないだろうか? 手術後は視界がクリアになり、生活の質が格段に上がったことを喜ぶ人が非常に多い。
しかし、手術後に、「後悔していることもある」「もっといいレンズの選択肢があったのではないか」といった不満を漏らす人も少なくない。以下に紹介する70代後半女性がその一例だ。
79歳で手術を受けた女性Hさんの例
「夫は白内障手術でメガネいらずに。でも私はメガネが手放せません」
(写真はイメージ:PIXTA)
Hさんは70代半ばから視界がまぶしくなり、白内障と診断されて手術を受けることにした。すると、「遠くがよく見えるように」と希望した通り、手術後は遠くがクリアに見えるようになったが、近くを見るときは老眼鏡を使っている。
どんな眼内レンズを選んだのかと聞くと、「レンズに選択肢があるの? 『裸眼で遠くを見たいですか』と聞かれて『はい』と答えただけです」とHさん。
その後、Hさんの夫も83歳で別の眼科で手術を受けた。その眼科では複数のレンズについて説明があり、夫は少し奮発して選んだという。「夫は手術後にメガネを使うことなく、『裸眼で遠くも近くも見えるようになった!』と喜んでいます。手術後の見え方がレンズによってこんなに違うとは思いませんでした」とHさん。視界がくもらなくなった点は満足だが、自分だけメガネいらずにならなかったのは心残りだという。
この事例は決して珍しい話ではない。佐々木氏も、医師の説明不足により同じような例が多く起きていると指摘する。例えば、歯科で歯に詰め物をするときと比べてみよう。歯科ではセラミックか金属か、患者の状態や希望に応じて素材を吟味するのが常だ。「セラミックを入れたかったのに、金属になった」という話は聞いたことがない。「しかし、白内障手術ではどんな眼内レンズがその人に合うか、選択肢を説明されないまま手術を受ける人も多くいます」と佐々木氏。そうやって手術後に、「想像していた見え方と違う」と思う人が後を絶たないのだ。
基本的に白内障手術は一生に一度きり。情報不足のまま手術に臨むことは避けたいものだ。今回は、白内障手術で後悔しないために知っておくべき眼内レンズの選択肢、かかる費用など、手術に関する基本情報を整理したうえで「眼科選びのポイント」を紹介しよう。
-
- シニアこそ「たんぱく質」で筋肉づくり 健康長寿をかなえる摂取術
-
シニア世代が特に意識したい栄養素が「たんぱく質」。近年、健康的に長生きするにはたんぱく質が重要だという認識が広がりつつあります。しかし、実際に何を、どのくらいとればいいのかについては、まだ十分に知られていません。一体、どのように摂取するとよいのでしょうか。過去の人気記事を基に、たんぱく質のとり方を見ていきましょう。
-
- 体のサビ防ぎ、老化を遠ざける! 「抗酸化生活」の極意
-
老化を進めるさまざまな要因が明らかになっている中で、大きく注目されているのが「酸化」だ。酸化によって細胞が傷つき、細胞や組織の機能を低下させ、老化を進行させてしまう。できるだけ老化を遅らせ、健康に過ごすためには、活性酸素を除去する力「抗酸化能」を高めることが肝要だ。
-
- 血管の若さが寿命を決める 100年元気に過ごす血管若返り術
-
人生100年時代をすこやかに過ごすためには、若々しくしなやかな「血管」を長く保つことが不可欠です。血管の老化予防に役立つ最新の知見を紹介しましょう。
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 7
白内障手術は日本で年間180万件以上も行われる、最も多い手術だ。治療が進化した今、手術により近視・遠視・乱視・老視も治り、メガネなしで快適な生活を送る人もいる。しかし、そうしたことを知らない人はまだ多い。知識不足や医師とのコミュニケーション不足から、手術で期待通りの効果を得られない人もいる。また、意外な原因が白内障を進めることが分かっており、日常生活で注意するべきこともあるという。「白内障手術なんてまだ関係ない」と思っても、人は高齢になれば必ず白内障になる。一生に一度の手術だからこそ、後悔しないための基礎知識を備えておこう。
佐々木洋(ささき ひろし)氏 金沢医科大学眼科学講座 主任教授
有料会員になると、鍵つき記事が全て読める&医療専門家に電話相談や名医紹介も!
-
- シニアこそ「たんぱく質」で筋肉づくり 健康長寿をかなえる摂取術
-
シニア世代が特に意識したい栄養素が「たんぱく質」。近年、健康的に長生きするにはたんぱく質が重要だという認識が広がりつつあります。しかし、実際に何を、どのくらいとればいいのかについては、まだ十分に知られていません。一体、どのように摂取するとよいのでしょうか。過去の人気記事を基に、たんぱく質のとり方を見ていきましょう。
-
- 体のサビ防ぎ、老化を遠ざける! 「抗酸化生活」の極意
-
老化を進めるさまざまな要因が明らかになっている中で、大きく注目されているのが「酸化」だ。酸化によって細胞が傷つき、細胞や組織の機能を低下させ、老化を進行させてしまう。できるだけ老化を遅らせ、健康に過ごすためには、活性酸素を除去する力「抗酸化能」を高めることが肝要だ。
-
- 血管の若さが寿命を決める 100年元気に過ごす血管若返り術
-
人生100年時代をすこやかに過ごすためには、若々しくしなやかな「血管」を長く保つことが不可欠です。血管の老化予防に役立つ最新の知見を紹介しましょう。
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 8
誰もがいつかは「白内障」を発症すると言われ、日本では年間180万件以上の白内障手術が行われている。濁った水晶体と交換する人工の「眼内レンズ」が次々と開発され、裸眼の生活を取り戻すことも夢ではなくなった。さらに、左右の目に異なるタイプの眼内レンズを入れるなど、新しい方法も出てきている。今回はそんな眼内レンズの種類と特徴を紹介しよう。眼科選びに苦労した患者による体験談も必読だ。
白内障手術は「目の若返り手術」と言っても過言ではない
80代になると100%近い人が発症する「白内障」。印象派の画家、クロード・モネも患者の1人で、代表作「睡蓮」のぼやけた描写が、まさに白内障の見え方だと言われている。モネが手術を受けた1920年代は現在と大きく異なり、手術後は分厚いメガネをかけて生活したそうだ。
今や白内障手術は広く普及し、視界をくもらせる「水晶体」を人工の「眼内レンズ」に取り換える手術が全国で行われている。眼内レンズには、1カ所にしっかりピントが合う「単焦点レンズ」と、複数箇所にピントが合う「多焦点レンズ」がある(下表)。新しい眼内レンズが次々に開発され、老眼や近視、乱視も一度に改善し、メガネいらずの生活を取り戻す人もいる。
眼内レンズの主な種類とメリット・デメリット
単焦点レンズ 多焦点レンズ 遠くに焦点が合う場合 近くに焦点が合う場合 3焦点・連続焦点 焦点深度拡張型 メリット
- ピントが合う1カ所のコントラストが良く、鮮明に見える
- 単焦点レンズと同様に鮮明に見える
- 遠くから近く(50cmくらい)まで裸眼で見える
- 夜に不快な光が見えることは少ない
ト
- 単焦点レンズほど鮮明度が高くない
- 夜、不快な光が見える現象が出やすい
- 近く(30~40cm)が少し見えづらく、老眼鏡を使う人もいる
方
遠く ◎ ✖ 〇 ◎ 中間 △ △ 〇 ◎ 近く ✖ ◎ 〇 △5万件以上の白内障手術を行ってきた金沢医科大学眼科学講座主任教授の佐々木洋氏は、70~80代の人が白内障手術を受けた場合を例に、レンズの違いを次のように説明する。
「70~80代の人が白内障手術を受けるとすれば、従来の単焦点レンズは、白内障のない60代の見え方に戻るイメージ。具体的には、『遠くは鮮明に見えるが、近くは見づらい状態』になります。最近スタンダードになってきた新しいタイプの単焦点レンズは、従来の単焦点レンズより近くが見えやすく、50代後半の見え方のイメージ。そして、最新の多焦点レンズなら、老眼になり始めた40代の見え方になることも可能になりました。手元はやや見にくいものの、遠方から50cmくらいまでは裸眼で見える状態です。こう見ていくと、白内障手術は目の若返り手術と言ってもいいでしょう。メガネが不要になれば地震などの災害時も安心です」(佐々木氏)
見え方のイメージ
レンズの選び方によっては、遠くから近くまで鮮明に見えるようになる。(元画像:PIXTA)
-
- シニアこそ「たんぱく質」で筋肉づくり 健康長寿をかなえる摂取術
-
シニア世代が特に意識したい栄養素が「たんぱく質」。近年、健康的に長生きするにはたんぱく質が重要だという認識が広がりつつあります。しかし、実際に何を、どのくらいとればいいのかについては、まだ十分に知られていません。一体、どのように摂取するとよいのでしょうか。過去の人気記事を基に、たんぱく質のとり方を見ていきましょう。
-
- 体のサビ防ぎ、老化を遠ざける! 「抗酸化生活」の極意
-
老化を進めるさまざまな要因が明らかになっている中で、大きく注目されているのが「酸化」だ。酸化によって細胞が傷つき、細胞や組織の機能を低下させ、老化を進行させてしまう。できるだけ老化を遅らせ、健康に過ごすためには、活性酸素を除去する力「抗酸化能」を高めることが肝要だ。
-
- 血管の若さが寿命を決める 100年元気に過ごす血管若返り術
-
人生100年時代をすこやかに過ごすためには、若々しくしなやかな「血管」を長く保つことが不可欠です。血管の老化予防に役立つ最新の知見を紹介しましょう。
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 9
白内障手術は日本で年間180万件以上も行われる、最も多い手術だ。治療が進化した今、手術により近視・遠視・乱視・老視も治り、メガネなしで快適な生活を送る人もいる。しかし、そうしたことを知らない人はまだ多い。知識不足や医師とのコミュニケーション不足から、手術で期待通りの効果を得られない人もいる。また、意外な原因が白内障を進めることが分かっており、日常生活で注意するべきこともあるという。「白内障手術なんてまだ関係ない」と思っても、人は高齢になれば必ず白内障になる。一生に一度の手術だからこそ、後悔しないための基礎知識を備えておこう。
「老眼」の始まりは、白内障の始まり
高齢になるにつれて患者が増える「白内障」。50代になると約半数、80代では100%近い人が発症するほど一般的な病気だ。
白内障といえば、「視界に白いモヤがかかって見える」というイメージを抱く人が多いだろう。だが実際は、近くが見えづらいといった「老眼(老視)」のような症状から始まることも多い。老眼は、目のピント調節を担う「水晶体」が弾力性を失って硬くなり、近くの焦点が合わなくなる状態。40代から自覚する人が増え始め、徐々に手元の小さな文字が読みづらくなる。やがて硬くなった水晶体は白く濁り、常に汚れたメガネをかけているように視界がぼやけてくる。こうして起こるのが白内障だ。
白内障が進むと水晶体が濁り、光が通りにくくなって視界が悪くなる。(原図:PIXTA)
見え方のシミュレーション画像を見てみよう(下の写真)。老眼になると近くのピントが合わなくなり(写真上)、腕を伸ばして新聞やスマートフォンなどを遠ざけて見るようになる。そこに白内障が加わると、全体的に見えづらさが増し、生活の質が低下していく(写真下)。
老眼と白内障による見え方の違い
老眼が進むと近くのピントが合わず、ぼやけてくる。そこに白内障も加わると視界が白くかすみ、近くだけでなく遠くも見えづらくなってしまう。図中の「cm」は目からの距離、その右側の数字は「その距離でどのくらいの視力が出るか」を示す。(写真は佐々木洋氏より提供)
これまで5万件以上の白内障手術を行ってきた金沢医科大学眼科学講座主任教授の佐々木洋氏は、「多くの人は、このように老眼を経て白内障を発症します。老眼は白内障の初期症状なので、老眼が始まった時点で初期の白内障も始まっていると考えてください」と指摘する。
白内障手術で目の若返りが可能 だが中には後悔する人も
現在のところ、白内障を根治する唯一の手段は手術だ。手術では白濁した水晶体を取り出し、人工の「眼内レンズ」に交換する。「高齢の人であっても、最新の眼内レンズを選べば見え方が40代の見え方に若返ることも可能です。『こんなに見えるようになるなら、もっと早く手術を受ければよかった』とほとんどの人が喜ばれます」(佐々木氏)
だが、中には手術後に後悔する人もいる。「メガネいらずになると思ったが、手術後もメガネを使っている」「医師が勧めるレンズにしたが、もっと合うものがあったのではないか」などとモヤっとした気持ちを抱える人も少なくない。
現時点では、白内障手術は原則一生に一度きりとされている。手術後はレンズが目の中で癒着し、時間が経つとレンズの入れ替えが困難になるからだ。白内障が進めば、多くの人は手術を受ける日が来る。そのときに向けて基礎知識を備え、悔いのない手術にしたい。
本特集では、佐々木氏への取材を基に白内障手術に関する最新情報を解説する。どんな症状が出たら受診するべきか? 白内障の進行を予防することはできないのか? どんな種類の眼内レンズがあって費用はどのくらいなのか? 白内障手術のエキスパートに具体的なアドバイスを聞いていこう。
-
- シニアこそ「たんぱく質」で筋肉づくり 健康長寿をかなえる摂取術
-
シニア世代が特に意識したい栄養素が「たんぱく質」。近年、健康的に長生きするにはたんぱく質が重要だという認識が広がりつつあります。しかし、実際に何を、どのくらいとればいいのかについては、まだ十分に知られていません。一体、どのように摂取するとよいのでしょうか。過去の人気記事を基に、たんぱく質のとり方を見ていきましょう。
-
- 体のサビ防ぎ、老化を遠ざける! 「抗酸化生活」の極意
-
老化を進めるさまざまな要因が明らかになっている中で、大きく注目されているのが「酸化」だ。酸化によって細胞が傷つき、細胞や組織の機能を低下させ、老化を進行させてしまう。できるだけ老化を遅らせ、健康に過ごすためには、活性酸素を除去する力「抗酸化能」を高めることが肝要だ。
-
- 血管の若さが寿命を決める 100年元気に過ごす血管若返り術
-
人生100年時代をすこやかに過ごすためには、若々しくしなやかな「血管」を長く保つことが不可欠です。血管の老化予防に役立つ最新の知見を紹介しましょう。
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 10
健康診断や人間ドックは、病気を早期に見つける大切な機会。だが「なんとなく受けているだけ」で、その価値に気づいていない人も多い。加えて、人間ドックではどのオプション検査を受けたらいいか分からないという人もいる。本特集では、健診や人間ドックをより賢く活用するためのポイントを解説していく。特集の1回目は、健診の重要性や結果の読み解き方を見ていこう。
(写真:PIXTA)
意外と多い「根拠のない健康過信」
「会社からうるさく言われるから毎年受けている」「妻がどうしても受けろと言うから」――。大切だと分かっていながら軽視しがちなもの。その代表的な存在の1つに、健康診断がある。健康診断は「受けるべきだ」と頭の中では分かっていても、実際にはなんだかんだと理屈を付けて避けたがる人が少なくない。では、果たして、健康診断は本当に必要なのだろうか。
「必要だと分かっている人も多いのですが、あまり意味がないと考える人も一定数います。結果がどうであれ、『これまで健康だったから大丈夫』と根拠のない自信を持っている人がいますが、そういう人が一番危ないんです」
そう語るのは、健康診断や人間ドックサービスを提供し、医師も数多く受診する四谷メディカルキューブの理事長、安田聖栄氏だ。
安田氏が知る例でも、70歳になっても健康であることを誇り、「詳しい健診はしなくても私は大丈夫」と公言していた人がいたという。その人は、その数カ月後に脳梗塞を発症して入院。長期療養することになってしまったという。
「これまで健康だったからといって、これからも大丈夫とは限りません。たとえ自覚症状がなくても、加齢とともに体内では確実に変化が進んでいます。かといって、体内の変化は、外から透視することはできません。健診は気づきを与えてくれるのです」と安田氏は強調する。健診は、体内で起きている変化を「可視化」する大切な機会なのだ。
「健診」「検診」「人間ドック」の違いとは?
ひと口で健康診断といっても、その内容によって「健診」「検診」「人間ドック」という呼び方をすることがある。この3つにはどのような違いがあるのだろうか。
安田氏は「実は明確な定義が存在しない」と話すが、あえて言えば、次のように分類することができるという。
- 健診(健康診断) 全般的な健康状態を調べるもの。英語では「ヘルスチェックアップ」
- 検診 がん検診や糖尿病検診など、特定の疾患を調べるもの。英語では「スクリーニング」
- 人間ドック 日本独自の用語で、入院して詳しく調べる検査のこと。船が「ドック入り」して点検することに例えている。
(※安田氏による分類解説を編集部で編集)
これはあくまでも便宜的な区別だ。企業健診や住民健診などの公的な枠組みを「健診」と呼ぶことが多いものの、自費で受ける人間ドックを「総合健診」と呼ぶ場合もある。また、最近の人間ドックは入院しなくても、日帰りで行うケースも多い。このため、言葉の使い分けは別として、「何を調べるものなのか」を理解することが大切だ。
広い意味での健康診断は、費用補助があるかないかで大別できる。職場健診、住民健診、医療保険組合の健診の3つには、会社や自治体などからの費用補助がある。その点が、病院の健診や人間ドックと違う点だ。
では、健診では何を検査するのか、検査結果をどのように理解したらいいのか。詳しく見ていこう。
費用補助がある健診
- 職場健診 労働安全衛生法という法律に基づいて、事業主が実施主体となって行う健診。企業には定期的な健診が義務づけられており、労働者にも受診義務がある。
- 住民健診 健康増進法に基づいて、自治体(市区町村)が実施主体となって行う健診。努力義務となっており、自治体から住民へ通知が届く。費用補助の金額は自治体によって異なる。
- 医療保険組合の健診 健康保険組合が実施主体となり、保険加入者やその家族を対象に行っている健診で、労働安全衛生法と高齢者の医療の確保に関する法律(高齢者医療確保法)に基づいている。企業の職場健診に加えて、40~74歳を対象にした特定健診(いわゆるメタボ健診)がある。
-
- シニアこそ「たんぱく質」で筋肉づくり 健康長寿をかなえる摂取術
-
シニア世代が特に意識したい栄養素が「たんぱく質」。近年、健康的に長生きするにはたんぱく質が重要だという認識が広がりつつあります。しかし、実際に何を、どのくらいとればいいのかについては、まだ十分に知られていません。一体、どのように摂取するとよいのでしょうか。過去の人気記事を基に、たんぱく質のとり方を見ていきましょう。
-
- 体のサビ防ぎ、老化を遠ざける! 「抗酸化生活」の極意
-
老化を進めるさまざまな要因が明らかになっている中で、大きく注目されているのが「酸化」だ。酸化によって細胞が傷つき、細胞や組織の機能を低下させ、老化を進行させてしまう。できるだけ老化を遅らせ、健康に過ごすためには、活性酸素を除去する力「抗酸化能」を高めることが肝要だ。
-
- 血管の若さが寿命を決める 100年元気に過ごす血管若返り術
-
人生100年時代をすこやかに過ごすためには、若々しくしなやかな「血管」を長く保つことが不可欠です。血管の老化予防に役立つ最新の知見を紹介しましょう。
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 11
健康診断や人間ドックは、病気を早期に見つける大切な機会。だが「なんとなく受けているだけ」で、その価値に気づいていない人も多い。加えて、人間ドックではどのオプション検査を受けたらいいか分からないという人もいる。本特集では、健診や人間ドックをより賢く活用するためのポイントを解説していく。
安田聖栄 (やすだ せいえい)氏 医療法人社団あんしん会 四谷メディカルキューブ 理事長、東海大学医学部 客員教授、医学博士
有料会員になると、鍵つき記事が全て読める&医療専門家に電話相談や名医紹介も!
-
- シニアこそ「たんぱく質」で筋肉づくり 健康長寿をかなえる摂取術
-
シニア世代が特に意識したい栄養素が「たんぱく質」。近年、健康的に長生きするにはたんぱく質が重要だという認識が広がりつつあります。しかし、実際に何を、どのくらいとればいいのかについては、まだ十分に知られていません。一体、どのように摂取するとよいのでしょうか。過去の人気記事を基に、たんぱく質のとり方を見ていきましょう。
-
- 体のサビ防ぎ、老化を遠ざける! 「抗酸化生活」の極意
-
老化を進めるさまざまな要因が明らかになっている中で、大きく注目されているのが「酸化」だ。酸化によって細胞が傷つき、細胞や組織の機能を低下させ、老化を進行させてしまう。できるだけ老化を遅らせ、健康に過ごすためには、活性酸素を除去する力「抗酸化能」を高めることが肝要だ。
-
- 血管の若さが寿命を決める 100年元気に過ごす血管若返り術
-
人生100年時代をすこやかに過ごすためには、若々しくしなやかな「血管」を長く保つことが不可欠です。血管の老化予防に役立つ最新の知見を紹介しましょう。
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 12
日本人が一生のうちに「がん」と診断される確率は、男女ともに2人の1人の割合に達する。がんは何より早期発見、早期治療が重要だ。そして、そのために必要になってくるのは、「がんの疑いがあるかどうか」を調べるがん検診である。そこで本特集の3回目はがん検診について詳しく見ていく。
(写真:PIXTA)
かつては不治の病と恐れられた、がん。今では、医療技術の目覚ましい進歩によって完治・寛解の可能性が高まり、がんサバイバーとして社会復帰する人も増えてきた。そこで大切なのは早期発見である。検診によって早期の状態でがんが発見できれば、それだけ体に負担のない治療が可能になる。
自治体から、「がん検診のお知らせ」という郵送物を受け取ることがあるだろう。きちんと中身を見ているだろうか。国の指針のもと、胃がん、肺がん、大腸がん、女性には子宮頸(けい)がんと乳がんの検診も、年齢に応じて届くようになっている。
しかし、今でも、がん検診を避けたがる人は少なくない。「忙しくて時間がない」「面倒だ」「がんと診断されるのが怖い」などが主な理由だ。
果たして、がん検診はどこまで有効なのか。受診すべきなのか。
人間ドックの施設として、医師も数多く受診する四谷メディカルキューブ理事長の安田聖栄氏は、がん検診を受けるべき理由として以下の3つを挙げる。
- 日本人が一生のうちでがんと診断される確率は、男女とも2人に1人の割合に達する(*1)
- がんは死因の第1位となっており、男性は4人に1人、女性は6人に1人ががんで死亡する(*2)
- 治療の技術も日進月歩で、がんはもはや不治の病ではなくなった
①と②は、がんは多くの人にとって「ひとごとではない」ということだ。その上で、③について、安田氏は次のように説明する。
「現在は治療技術が進み、がん検診の重要性が高くなっています。もし治療が困難ならば、いくら検査をしても意味がありません。しかし、今は内視鏡治療の進化に加え、ロボット手術の導入、がん治療の新薬の登場などで、より体に負担が少なく、効果的な治療法が開発されています。その恩恵を十分得られるのも、早期に発見できればこそ、です」
これは逆に言えば、いくら治療技術が進歩しても発見が遅れれば、肉体的にも経済的にも負担のかかる治療が必要になってくるということ。早期発見によって負担の少ない治療で済めば、その後の人生も元気に生きられる可能性が高まる。
*1 国立がん研究センターがん情報サービス 最新がん統計より(2021年のデータ) *2 厚生労働省「令和5年(2023年)人口動態統計」より
ひと口にがん検診といっても、さまざまな種類がある。どのような検診を受ければよいのだろうか。
「年齢や生活習慣、家族歴などを考慮に入れて、検診効果の高い検査を、適切な頻度で受けることが大切です。国が推奨しているがん検診は、大腸、肺、胃、乳、子宮頸(けい)がんの5つ。少なくともこの5つには検査の有効性に科学的根拠があり、早期発見の効果が証明されています」と安田氏は語る。
「検査の有効性」というのは、検査することによって命が助かる可能性が高まるかどうかを指している。
「科学的に有効であると示されたがん検診ですが、残念ながら日本の受診率は依然として低い水準にあります。大腸がん、乳がん、子宮頸がんに限ってみても、欧米では6〜7割の人が受診しているのですが、日本では4割程度にとどまっています」と安田氏は話す。
-
- シニアこそ「たんぱく質」で筋肉づくり 健康長寿をかなえる摂取術
-
シニア世代が特に意識したい栄養素が「たんぱく質」。近年、健康的に長生きするにはたんぱく質が重要だという認識が広がりつつあります。しかし、実際に何を、どのくらいとればいいのかについては、まだ十分に知られていません。一体、どのように摂取するとよいのでしょうか。過去の人気記事を基に、たんぱく質のとり方を見ていきましょう。
-
- 体のサビ防ぎ、老化を遠ざける! 「抗酸化生活」の極意
-
老化を進めるさまざまな要因が明らかになっている中で、大きく注目されているのが「酸化」だ。酸化によって細胞が傷つき、細胞や組織の機能を低下させ、老化を進行させてしまう。できるだけ老化を遅らせ、健康に過ごすためには、活性酸素を除去する力「抗酸化能」を高めることが肝要だ。
-
- 血管の若さが寿命を決める 100年元気に過ごす血管若返り術
-
人生100年時代をすこやかに過ごすためには、若々しくしなやかな「血管」を長く保つことが不可欠です。血管の老化予防に役立つ最新の知見を紹介しましょう。
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 13
健診や人間ドックは、病気を早期に見つける大切な機会。だが「なんとなく受けているだけ」で、その価値に気づいていない人も多い。人間ドックでは、検査項目を「選ぶ力」が健康寿命を延ばすことにつながる。そこで特集の2回目は、人間ドックの賢い利用法を見ていく。
(写真:PIXTA)
「人間ドック」という言葉は日本特有のものだ。船が定期的にドックに入り、時間をかけて綿密に修理や点検を行うことに例えている。第1回で紹介した一般的な健診(職場健診、住民健診、医療保険組合の健診)が、“病気の義務教育”だとすると、人間ドックは“高等教育”と呼べるだろう。人間ドックは基本の検査項目が健診より多く、さらに任意に選択できるオプション検査では、より多様で詳細な検査が可能になっている。
健診は生活習慣病の早期リスクを見つけるために大切だ。対策型がん検診(対象は大腸がん、肺がん、胃がん、乳がん、子宮頸がん)のように、各市区町村で対象として特定された年齢の住民が、無料か少額の自己負担で受けられる検診もある(がん検診については第3回で詳しく紹介する)。
健診や対策型がん検診は手軽に受けられる利点がある一方、自分が不安視する病気のリスクを、自分の意思とタイミングで受けられない欠点もある。その点、人間ドックは、自分が必要だと思った検査を、自分のタイミングで好きに選んで受けることができる。
健診では見つからなかった、がんなどの重篤な病気を早期発見できることもメリットとしては大きい。例えば肺がんの場合、健診で行う胸部X線検査では、小さな腫瘍や異常を見落とすことがある。だが肺CT検査を受ければ、そうした見落としのリスクを避けられる。
- 健診(健康診断) 全般的な健康状態を調べるもの。英語では「ヘルスチェックアップ」
- 検診 がん検診や糖尿病検診など、特定の疾患を調べるもの。英語では「スクリーニング」
- 人間ドック 日本独自の用語。入院して詳しく調べる検査を、船が「ドック入り」して点検することに例えて呼ばれたが、日帰りもある。
(※四谷メディカルキューブの理事長・安田聖栄氏による分類解説を編集部で編集)
悩ましいのは、数ある検査内容の理解と選択
人間ドックは、病気を予防するために任意で2日ないし1日で受けることが多い。検査項目は、「基本コース」や「スタンダードコース」などと呼ばれる「基本検査」に、必要に応じて選べる「オプション検査」がある。基本検査やオプション検査のメニューは、医療施設によってさまざま。多くの施設がオプション検査として扱う検査を、基本検査に加えているところもあるため、選ぶコースや選ぶオプション検査により、総費用も数万円から数十万円と異なる。このため、費用については、検査する医療施設のホームページで確認してほしい。
人間ドックは、公的医療保険(健康保険)の適用対象外となり、基本的に費用は全額自己負担だが、会社が福利厚生の1つとして費用補助をしているケースもある。そういった費用補助があるなら、ぜひ活用したいところだ。
そんな人間ドックだが、悩ましいのが数ある検査内容の理解と選択だ。「この検査は自分に必要か。いや、念のため、調べておいたほうがいいかもしれない。でも、気になる検査を加えて行ったらどんどん料金が高くなる…」――。このように複雑に感じる人も少なくない。だからこそ、人間ドックは賢い選択を踏まえた利用が必要になる。
人間ドックの施設として、医師も数多く受診する四谷メディカルキューブの理事長、安田聖栄氏は、「人間ドックで重要なのは基本検査の内容をよく理解すること。どんなオプション検査を受けるかもしっかり検討しましょう」と話す。そこで本特集の第2回は、人間ドックの検査内容や受診する際の押さえておきたいポイントを解説していく。
-
- シニアこそ「たんぱく質」で筋肉づくり 健康長寿をかなえる摂取術
-
シニア世代が特に意識したい栄養素が「たんぱく質」。近年、健康的に長生きするにはたんぱく質が重要だという認識が広がりつつあります。しかし、実際に何を、どのくらいとればいいのかについては、まだ十分に知られていません。一体、どのように摂取するとよいのでしょうか。過去の人気記事を基に、たんぱく質のとり方を見ていきましょう。
-
- 体のサビ防ぎ、老化を遠ざける! 「抗酸化生活」の極意
-
老化を進めるさまざまな要因が明らかになっている中で、大きく注目されているのが「酸化」だ。酸化によって細胞が傷つき、細胞や組織の機能を低下させ、老化を進行させてしまう。できるだけ老化を遅らせ、健康に過ごすためには、活性酸素を除去する力「抗酸化能」を高めることが肝要だ。
-
- 血管の若さが寿命を決める 100年元気に過ごす血管若返り術
-
人生100年時代をすこやかに過ごすためには、若々しくしなやかな「血管」を長く保つことが不可欠です。血管の老化予防に役立つ最新の知見を紹介しましょう。
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 14
記憶、判断などの脳の機能が低下していく「認知症」。15年後の2040年には認知症とその前段階のMCIを合計すると患者数は1200万人近くになると推計される。実は近年、科学的に正しい認知症予防に関するエビデンスが蓄積され、「認知症リスクは45%減らせる」時代が到来している。本特集第1回では、認知症予防学の第一人者である日本認知症予防学会前代表理事で鳥取大学医学部教授の浦上克哉氏に、認知症予防に役立つ、認知症発症リスク因子に関する最新研究について詳しく聞いていく。
超高齢社会が進む中、認知症患者数は増加の一途をたどっている。国内推計では、2025年の65歳以上の高齢者における認知症有病率は12.9%、認知症の前段階のMCI(軽度認知障害)は15.4%となっている。認知症とMCIの有病者数を合わせると2022年時点で約1000万人。2040年には1200万人近くに増えることが予想されている(図1)。
図1 2040年に認知症患者とMCI患者の合計は1200万人に
2022年に認知症の地域悉皆(しっかい)調査(調査率80%以上)を実施した4地域(福岡県久山町、石川県中島町、愛媛県中山町、島根県海士町)の推計。年齢が高くなるほど認知症とMCIは増えていく。2025年の高齢者における認知症有病率の推計は12.9%、MCIは15.4%だった。有病率が今後も一定であると仮定した場合、2040年の認知症有病率は14.9%、MCIは15.6%とさらに増加。認知症有病者は584.2万人、MCIは612.8万人と推計される(データ:「認知症及び軽度認知障害の有病率調査並びに将来推計に関する研究」(令和5年度老人保健事業推進費等補助金)、厚生労働省より)
世界においても認知症有病者の増加は課題となっている。WHO(世界保健機関)の2025年の報告によると、2021年時点での世界の認知症有病者数は約5700万人で、毎年約1000万人が新たに認知症を発症している。
医療、予防においても新たな知見が相次いでいる認知症
認知症になると、数分前のことを忘れる、同じことを何度も聞くといった記憶障害に加え、着替える、お金を扱う、目的の場所に行くといった日常生活や社会生活を行うことが難しくなる。身内や知り合いの中に認知症の人がいる、という読者もいるかもしれない。また、自分自身もこの先、発症する可能性がある――そう思うと、不安になるだろう。
(写真はイメージ:PIXTA)
高齢化が進む中、認知症は誰もがかかる可能性がある病気といえる。しかし、できることなら認知症を予防し、発症を遅らせて、発症する前に天寿を全うしたい――というのは多くの人が願うことではないだろうか。
以前は予防ということすら夢物語だった認知症だが、近年では医療の進歩により予防が現実的なものになってきた。認知症になる前に天寿を全うすることも、中年期以降の生活習慣の改善などにより可能になりつつある。
認知症の専門医としてこれまで延べ13万人以上の認知症患者を診てきた、日本認知症予防学会の創設者で鳥取大学医学部 認知症予防学講座(寄附講座)教授の浦上克哉氏は、ここ数年で認知症予防の研究が進んでおり、悲観することはないと話す。「医学雑誌『Lancet』の最新報告では、認知症を引き起こす複数の要因が特定され、これらをしっかり管理することで最大45%の予防効果を得られることが明らかになっています」(浦上氏)
認知症の薬物治療にブレイクスルーが起こっているのも大きな追い風だ。レカネマブ、ドナネマブといった新薬(抗アミロイドβ抗体薬)が登場していることをご存じの方も多いだろう。以前は、症状を抑える薬しかなかったが、新薬ではアルツハイマー病の症状の進行のスピードを抑える効果が確認されている。「アルツハイマー病の原因に直接働きかける新薬が登場したことは画期的です。現在は症状悪化のスピードを3割程度抑制することが確認されています。その効果は限定的であるという指摘もありますが、まだ登場したばかりであり、今後さらに効果的な薬の登場が期待されます」(浦上氏)
認知症は、軽度認知障害(MCI:Mild Cognitive Impairment)という前段階を経て進行していく。詳しくは後述するが、このMCIの状態から健常な状態に回復することも可能なことが分かっている。「MCIにいち早く気づき、適切な対策に着手することが大切です」(浦上氏)
認知症の発症を遅らせると期待される要因が次々と明らかになってきた
- 最新研究から、認知症のリスク要因が明らかになり、最大45%の予防効果
- 認知症の前段階・軽度認知障害(MCI)で気づけば、健常な状態に戻れる可能性がある
- 新薬(抗アミロイドβ抗体薬)の登場でアルツハイマー型認知症の進行を遅らせることができるようになった。今後、更なる進化も期待できる
認知症対策は、早くスタートするほど成功率を高めることができる。私たちは、今から認知症のリスクとなるターゲット因子を正しく知り、ライフスタイル全体で予防対策を実践することで、10年、20年先の認知症予防を実現できるかもしれない。認知症予防について考える本特集の第1回では、世界で注目される最新事情を浦上氏に聞き、知識をアップデートしていこう。
-
- シニアこそ「たんぱく質」で筋肉づくり 健康長寿をかなえる摂取術
-
シニア世代が特に意識したい栄養素が「たんぱく質」。近年、健康的に長生きするにはたんぱく質が重要だという認識が広がりつつあります。しかし、実際に何を、どのくらいとればいいのかについては、まだ十分に知られていません。一体、どのように摂取するとよいのでしょうか。過去の人気記事を基に、たんぱく質のとり方を見ていきましょう。
-
- 体のサビ防ぎ、老化を遠ざける! 「抗酸化生活」の極意
-
老化を進めるさまざまな要因が明らかになっている中で、大きく注目されているのが「酸化」だ。酸化によって細胞が傷つき、細胞や組織の機能を低下させ、老化を進行させてしまう。できるだけ老化を遅らせ、健康に過ごすためには、活性酸素を除去する力「抗酸化能」を高めることが肝要だ。
-
- 血管の若さが寿命を決める 100年元気に過ごす血管若返り術
-
人生100年時代をすこやかに過ごすためには、若々しくしなやかな「血管」を長く保つことが不可欠です。血管の老化予防に役立つ最新の知見を紹介しましょう。
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 15
シニア世代が特に意識したい栄養素が「たんぱく質」。近年、健康的に長生きするにはたんぱく質が重要だという認識が広がりつつある。しかし、実際に何を、どのくらいとればいいのかについては、まだ十分に知られていない。一体、どのように摂取するとよいのだろうか。過去の人気記事を基に、たんぱく質のとり方を見ていこう。
テーマ別特集「たんぱく質」この記事の主な内容 シニアになると、若いころより筋肉がつきにくい! 60代は若い頃に比べて筋肉が約30%も減る たんぱく質は認知機能や寿命にも影響 筋肉を増やすために必要なたんぱく質の量は? 中高年以降は朝のたんぱく質摂取が大事 昼食はたんぱく質摂取量がばらつきやすい シニアが優先的に選びたい食材は? たくさん食べられない人はプロテインで補完、注意点は 慢性腎臓病の人は、たんぱく質のとり過ぎに注意シニアになると、若いころより筋肉がつきにくい!
いくつになっても十分な筋肉量を保ち続けることができれば、丈夫な足腰を維持し、そして、さまざまな病気を予防することが期待できる。筋肉づくりのためには、筋トレなどの運動をすることはもちろん、食事にも気を使うことが大切だ。筋肉を増やすために重要な栄養素が「たんぱく質」。たんぱく質は筋肉の材料であり、筋合成のスイッチを押す役割もある。
特にたんぱく質をとる上で気を付けたいのがシニア世代だ。この世代で筋肉量やたんぱく質摂取量が少ない人は、より積極的にとっていきたい。というのも、高齢になると若いころより筋肉がつきにくくなるからだ。筋肉がつかないわけではないが、シニアは若い人と同じ量のたんぱく質を摂取しても、同じだけの筋肉を合成することができない。筋肉不足になると、フレイル(虚弱)が進行してしまう。そうした事態はなんとしても避けたい。
60代は若い頃に比べて筋肉が約30%も減る
そもそも、シニアになると若いときと同じようには筋肉がつくれなくなるのはなぜなのか。
ポイントは、必須アミノ酸の一つである「ロイシン」にある。ロイシンは、必須アミノ酸の中でも特に強く筋合成のスイッチを押してくれる。しかし、高齢者はロイシンに対する抵抗性を持っているため、若い人と同じ量のたんぱく質を摂取しても筋合成を高めにくい。立命館大学スポーツ健康科学部教授の藤田聡氏は「高齢者はより多くのたんぱく質を摂取しないと食後の筋合成を最大化できないことになります」と話す。
筋肉量は、年齢を重ねるとともに低下していく。筋肉量は20~30代ごろをピークに、10年ごとに約8~10%ずつ減少し、40代ではピーク時と比べて約10%、50代では約20%、60代では約30%も減ってしまう。
「筋肉量が低下すると、歩行や階段の上り下りといった日常生活の動作に困難をきたしやすくなります。それにより活動範囲が狭くなり、1日の運動量が少なくなる。すると、さらに筋肉量が少なくなる…といった悪循環が生まれます」と藤田氏は話す。
さらに転倒や寝たきりのリスクも出てくる。「歩行速度が遅くなることによって転倒のリスクが高くなります。筋肉はクッション材の役割もしているので、筋肉量が低下すると骨折する可能性も高くなり、骨折すると寝たきりのリスクも高まるのが怖いところです」(藤田氏)
図1 筋肉量低下の悪循環
加齢による筋肉量の減少は避けられないものではあるが、減少の程度はなるべく最小限にとどめたいもの。筋肉量が減少していき、かつ筋肉がつきにくいシニアは、より意識的にたんぱく質摂取や筋トレをしたい。
本記事では、筋肉をつけるためのたんぱく質のとり方のコツを、過去の人気記事を基に紹介しよう。
-
- シニアこそ「たんぱく質」で筋肉づくり 健康長寿をかなえる摂取術
-
シニア世代が特に意識したい栄養素が「たんぱく質」。近年、健康的に長生きするにはたんぱく質が重要だという認識が広がりつつあります。しかし、実際に何を、どのくらいとればいいのかについては、まだ十分に知られていません。一体、どのように摂取するとよいのでしょうか。過去の人気記事を基に、たんぱく質のとり方を見ていきましょう。
-
- 体のサビ防ぎ、老化を遠ざける! 「抗酸化生活」の極意
-
老化を進めるさまざまな要因が明らかになっている中で、大きく注目されているのが「酸化」だ。酸化によって細胞が傷つき、細胞や組織の機能を低下させ、老化を進行させてしまう。できるだけ老化を遅らせ、健康に過ごすためには、活性酸素を除去する力「抗酸化能」を高めることが肝要だ。
-
- 血管の若さが寿命を決める 100年元気に過ごす血管若返り術
-
人生100年時代をすこやかに過ごすためには、若々しくしなやかな「血管」を長く保つことが不可欠です。血管の老化予防に役立つ最新の知見を紹介しましょう。
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 16
日経Goodayでは日々、新しい健康・医療情報をお届けしています。その中で、読者のみなさまが今、最も気になっているテーマ、例えば、「大腸がん」「脂肪肝」「痛風・尿酸値」「男性ホルモン」などに関する多数の記事の“エッセンス”をすばやく知りたい――。そんなニーズにお答えする新サービスを開始します。
それが「テーマ別特集」です。毎月、読者のみなさまの関心が高かったテーマをチョイスし、特に好評だった記事のポイントを編集部でピックアップしてお届けします。そのテーマ、ジャンルについて知っておくべきことが、この記事を読むだけですべて把握できます。さらに、そのテーマに関する記事一覧もご用意しました。ご活用ください。
有料会員になると、鍵つき記事が全て読める&医療専門家に電話相談や名医紹介も!
-
- シニアこそ「たんぱく質」で筋肉づくり 健康長寿をかなえる摂取術
-
シニア世代が特に意識したい栄養素が「たんぱく質」。近年、健康的に長生きするにはたんぱく質が重要だという認識が広がりつつあります。しかし、実際に何を、どのくらいとればいいのかについては、まだ十分に知られていません。一体、どのように摂取するとよいのでしょうか。過去の人気記事を基に、たんぱく質のとり方を見ていきましょう。
-
- 体のサビ防ぎ、老化を遠ざける! 「抗酸化生活」の極意
-
老化を進めるさまざまな要因が明らかになっている中で、大きく注目されているのが「酸化」だ。酸化によって細胞が傷つき、細胞や組織の機能を低下させ、老化を進行させてしまう。できるだけ老化を遅らせ、健康に過ごすためには、活性酸素を除去する力「抗酸化能」を高めることが肝要だ。
-
- 血管の若さが寿命を決める 100年元気に過ごす血管若返り術
-
人生100年時代をすこやかに過ごすためには、若々しくしなやかな「血管」を長く保つことが不可欠です。血管の老化予防に役立つ最新の知見を紹介しましょう。
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 17
日経Goodayでは日々、新しい健康・医療情報をお届けしています。その中で、読者のみなさまが今、最も気になっているテーマ、例えば、「大腸がん」「脂肪肝」「痛風・尿酸値」「男性ホルモン」などに関する多数の記事の“エッセンス”をすばやく知りたい――。そんなニーズにお答えする新サービスを開始します。
それが「テーマ別特集」です。毎月、読者のみなさまの関心が高かったテーマをチョイスし、特に好評だった記事のポイントを編集部でピックアップしてお届けします。そのテーマ、ジャンルについて知っておくべきことが、この記事を読むだけですべて把握できます。さらに、そのテーマに関する記事一覧もご用意しました。ご活用ください。
有料会員になると、鍵つき記事が全て読める&医療専門家に電話相談や名医紹介も!
-
- シニアこそ「たんぱく質」で筋肉づくり 健康長寿をかなえる摂取術
-
シニア世代が特に意識したい栄養素が「たんぱく質」。近年、健康的に長生きするにはたんぱく質が重要だという認識が広がりつつあります。しかし、実際に何を、どのくらいとればいいのかについては、まだ十分に知られていません。一体、どのように摂取するとよいのでしょうか。過去の人気記事を基に、たんぱく質のとり方を見ていきましょう。
-
- 体のサビ防ぎ、老化を遠ざける! 「抗酸化生活」の極意
-
老化を進めるさまざまな要因が明らかになっている中で、大きく注目されているのが「酸化」だ。酸化によって細胞が傷つき、細胞や組織の機能を低下させ、老化を進行させてしまう。できるだけ老化を遅らせ、健康に過ごすためには、活性酸素を除去する力「抗酸化能」を高めることが肝要だ。
-
- 血管の若さが寿命を決める 100年元気に過ごす血管若返り術
-
人生100年時代をすこやかに過ごすためには、若々しくしなやかな「血管」を長く保つことが不可欠です。血管の老化予防に役立つ最新の知見を紹介しましょう。
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 18
健康・医療に関するホット・トピックスをお伝えします。
有料会員になると、鍵つき記事が全て読める&医療専門家に電話相談や名医紹介も!
-
- シニアこそ「たんぱく質」で筋肉づくり 健康長寿をかなえる摂取術
-
シニア世代が特に意識したい栄養素が「たんぱく質」。近年、健康的に長生きするにはたんぱく質が重要だという認識が広がりつつあります。しかし、実際に何を、どのくらいとればいいのかについては、まだ十分に知られていません。一体、どのように摂取するとよいのでしょうか。過去の人気記事を基に、たんぱく質のとり方を見ていきましょう。
-
- 体のサビ防ぎ、老化を遠ざける! 「抗酸化生活」の極意
-
老化を進めるさまざまな要因が明らかになっている中で、大きく注目されているのが「酸化」だ。酸化によって細胞が傷つき、細胞や組織の機能を低下させ、老化を進行させてしまう。できるだけ老化を遅らせ、健康に過ごすためには、活性酸素を除去する力「抗酸化能」を高めることが肝要だ。
-
- 血管の若さが寿命を決める 100年元気に過ごす血管若返り術
-
人生100年時代をすこやかに過ごすためには、若々しくしなやかな「血管」を長く保つことが不可欠です。血管の老化予防に役立つ最新の知見を紹介しましょう。
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 19
直近1~2カ月の平均的な血糖値の推移を示す中長期的な指標であるHbA1c(ヘモグロビンA1c)。血糖コントロールにおいて重要視されている指標だが、変動してもほとんど自覚症状はないので、健康診断の結果を基に持続的な対策を取る必要がある。管理栄養士である麻生れいみ氏にHbA1c対策に有効な食事や生活習慣のコツを聞いた。
世界初(*)!ヘモグロビンA1cの低下をサポートする乳酸菌入りヨーグルトが登場
病気の早期発見や対策推進のために欠かせない血糖レベルのチェック。空腹時血糖値、食後血糖値、HbA1c(ヘモグロビンA1c)の3つの指標があり、このうち空腹時血糖値と食後血糖値は採血時の瞬間値だが、HbA1cは直近1~2カ月の平均的な血糖値の推移を示す中長期的な指標だ。管理栄養士である麻生れいみ氏によれば「HbA1cは直前の食事に左右されにくい安定した数値」であり、血糖コントロールの指標として広く用いられている。
「人間ドック・予防医療学会ではHbA1cの値が5.5%以下を基準範囲、5.6~6.4%を要注意、6.5%以上を異常と規定しています。病気にならないために、基準範囲に収まっている人は数値が上がらないように、要注意の人は5.5%以下に抑えるようにしましょう」と麻生氏は警鐘を鳴らす。
そこで注目されるのが、明治が10月14日(火)に発売した機能性表示食品「明治ヘモグロビンA1c対策ヨーグルト」。世界初(*)のヘモグロビンA1cの低下をサポートする乳酸菌入りヨーグルトで、健康な方の高めのヘモグロビンA1cの低下をサポートする「MI-2」乳酸菌を使用した商品だ。血糖コントロールには栄養バランスの良い食事や適度な運動が大切だと分かっていても続かないという人でも、ヨーグルトなら手軽で取り入れやすい。
(*)パッケージ上でヘモグロビンA1cに言及する乳製品として(2025年6月 先行技術調査およびMintel GNPDを活用した明治調べ)。
●機能性表示:本品にはL.plantarum OLL2712株(MI-2乳酸菌)が含まれます。MI-2乳酸菌は、BMIが高めの健康な方の、健常域で高めのHbA1c(血糖コントロールの指標)の低下をサポートすることが報告されています。●食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。●本品は、特定保健用食品とは異なり、機能性及び安全性について国による評価を受けたものではありません。届け出られた科学的根拠等の情報は消費者庁のウェブサイトで確認できます。●本品は、医薬品ではありません。
「カギは独自素材の乳酸菌『MI-2乳酸菌(Lactobacillus plantarum OLL2712株:ラクトバチルス・プランタルムOLL2712株)』です。明治は、HbA1cが5.6%~6.4%かつ空腹時血糖値が100mg/dL以上125mg/dLの健常な成人男女を被験者とする臨床試験を実施。126名を2グループに分けて、一方にはMI-2乳酸菌入りヨーグルトを12週間毎日1個、他方にはMI-2乳酸菌が入っていないヨーグルトを同様に摂取してもらったところ、MI-2乳酸菌入りヨーグルトを食べたグループの方が有意にHbA1cの低下が認められたのです。1日1個のヨーグルトで、こんなにも結果に差が出るのかと、私も論文を読んで驚きました」(麻生氏)
●本製品を用いたヒト試験ではありません。研究レビュー採用論文2報のうち、非摂取期間を含まない試験1報の結果を示しています。【出典】Toshimitsu et al, Nutrients 2020【試験方法】空腹時血糖値が100mg/dL以上126mg/dL未満、かつHbA1cが5.6%以上6.5%未満の健康な男女126名(MI-2乳酸菌群62名、プラセボ群64名)に対して、MI-2乳酸菌を含むヨーグルト(MI-2乳酸菌群)または通常のヨーグルト(プラセボ群)を1日1個12週間摂取させ、HbA1cの値を測定。
-
- シニアこそ「たんぱく質」で筋肉づくり 健康長寿をかなえる摂取術
-
シニア世代が特に意識したい栄養素が「たんぱく質」。近年、健康的に長生きするにはたんぱく質が重要だという認識が広がりつつあります。しかし、実際に何を、どのくらいとればいいのかについては、まだ十分に知られていません。一体、どのように摂取するとよいのでしょうか。過去の人気記事を基に、たんぱく質のとり方を見ていきましょう。
-
- 体のサビ防ぎ、老化を遠ざける! 「抗酸化生活」の極意
-
老化を進めるさまざまな要因が明らかになっている中で、大きく注目されているのが「酸化」だ。酸化によって細胞が傷つき、細胞や組織の機能を低下させ、老化を進行させてしまう。できるだけ老化を遅らせ、健康に過ごすためには、活性酸素を除去する力「抗酸化能」を高めることが肝要だ。
-
- 血管の若さが寿命を決める 100年元気に過ごす血管若返り術
-
人生100年時代をすこやかに過ごすためには、若々しくしなやかな「血管」を長く保つことが不可欠です。血管の老化予防に役立つ最新の知見を紹介しましょう。
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 20
健康・医療に関するホット・トピックスをお伝えします。
有料会員になると、鍵つき記事が全て読める&医療専門家に電話相談や名医紹介も!
-
- シニアこそ「たんぱく質」で筋肉づくり 健康長寿をかなえる摂取術
-
シニア世代が特に意識したい栄養素が「たんぱく質」。近年、健康的に長生きするにはたんぱく質が重要だという認識が広がりつつあります。しかし、実際に何を、どのくらいとればいいのかについては、まだ十分に知られていません。一体、どのように摂取するとよいのでしょうか。過去の人気記事を基に、たんぱく質のとり方を見ていきましょう。
-
- 体のサビ防ぎ、老化を遠ざける! 「抗酸化生活」の極意
-
老化を進めるさまざまな要因が明らかになっている中で、大きく注目されているのが「酸化」だ。酸化によって細胞が傷つき、細胞や組織の機能を低下させ、老化を進行させてしまう。できるだけ老化を遅らせ、健康に過ごすためには、活性酸素を除去する力「抗酸化能」を高めることが肝要だ。
-
- 血管の若さが寿命を決める 100年元気に過ごす血管若返り術
-
人生100年時代をすこやかに過ごすためには、若々しくしなやかな「血管」を長く保つことが不可欠です。血管の老化予防に役立つ最新の知見を紹介しましょう。
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 21
年をとるにつれて聴力が低下する加齢性難聴。近年は認知症のリスク要因として重要視されているが、「聞こえにくいのは年のせいだから仕方がない」と考える人は多い。そんな現状から、日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会は、加齢性難聴の周知や予防、早期の対応などを目的とした「聴こえ8030運動」を展開している。この運動の提唱者で愛媛大学大学院医学系研究科耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教授の羽藤直人氏に、加齢性難聴をめぐる現状や課題、現在の聴力のセルフチェック、予防・対応策を聞いた。
(イラスト:PIXTA)
なぜ加齢性難聴は放置してはいけない?
編集部:年をとるにつれて聴力が低下する加齢性難聴は、いわゆる老化現象で仕方がないものと思われがちです。
羽藤教授(以下、敬称略):そうですね。徐々に聞こえにくさが進行していくため、本人でも気づきにくい。気づいたとしても「年をとったせい」「仕方のないものだ」と流してしまうことも見受けられますね。しかし、加齢性難聴は、「病気」なのです。
加齢性難聴は、耳の奥に位置する蝸牛(かぎゅう)と呼ばれる部位で、音を感知する有毛細胞が加齢によって減少することが主な原因となっています。失われた有毛細胞は再生しないため、加齢性難聴そのものを改善する方法はありません。
音を感知する有毛細胞が蝸牛内部にある。有毛細胞が減少すると聴力が衰える。(図:m/stock.adobe.com)
しかし、補聴器の装用などで聞こえを良くすることは可能です。ですから、聞こえにくさを感じたら、一度は耳鼻咽喉科を受診していただきたいと思います。
編集部:加齢性難聴を放置してはいけないのですね。
羽藤:加齢性難聴は聞こえの問題だけでなく、心身や生活にさまざまな影響を及ぼします。例えば、家族や友人との会話に支障が出るとコミュニケーションがおっくうになり、社会的に孤立してうつ病を招くことがあります。外出の機会が減れば、心身の機能が衰えるフレイルを招き、要介護のリスクにつながります。さらに近年は、難聴が認知症の最大のリスク因子であるとの研究報告(*1)があり、注目を集めています。
編集部:なぜ、難聴が認知症の発症リスクを高めるのでしょうか。
*1 Lancet. 2020 Aug 8;396(10248):413-446.
-
- シニアこそ「たんぱく質」で筋肉づくり 健康長寿をかなえる摂取術
-
シニア世代が特に意識したい栄養素が「たんぱく質」。近年、健康的に長生きするにはたんぱく質が重要だという認識が広がりつつあります。しかし、実際に何を、どのくらいとればいいのかについては、まだ十分に知られていません。一体、どのように摂取するとよいのでしょうか。過去の人気記事を基に、たんぱく質のとり方を見ていきましょう。
-
- 体のサビ防ぎ、老化を遠ざける! 「抗酸化生活」の極意
-
老化を進めるさまざまな要因が明らかになっている中で、大きく注目されているのが「酸化」だ。酸化によって細胞が傷つき、細胞や組織の機能を低下させ、老化を進行させてしまう。できるだけ老化を遅らせ、健康に過ごすためには、活性酸素を除去する力「抗酸化能」を高めることが肝要だ。
-
- 血管の若さが寿命を決める 100年元気に過ごす血管若返り術
-
人生100年時代をすこやかに過ごすためには、若々しくしなやかな「血管」を長く保つことが不可欠です。血管の老化予防に役立つ最新の知見を紹介しましょう。
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 22
この記事では、今知っておきたい健康や医療の知識をQ&A形式で紹介します。ぜひ今日からのセルフケアにお役立てください!
「運動と時間の関係」についての問題
【問題】加齢により徐々に衰えていく心肺機能。心肺機能を維持・向上させるためには運動が欠かせません。しかし、運動時間がなかなか取れないという人も多いでしょう。では、運動と時間の関係について、以下のうち正しい説明はどれでしょう。
- (1)効果を出すには20分以上体を動かす必要がある
- (2)小刻みにやってもよいので、量を増やせばOK
-
- シニアこそ「たんぱく質」で筋肉づくり 健康長寿をかなえる摂取術
-
シニア世代が特に意識したい栄養素が「たんぱく質」。近年、健康的に長生きするにはたんぱく質が重要だという認識が広がりつつあります。しかし、実際に何を、どのくらいとればいいのかについては、まだ十分に知られていません。一体、どのように摂取するとよいのでしょうか。過去の人気記事を基に、たんぱく質のとり方を見ていきましょう。
-
- 体のサビ防ぎ、老化を遠ざける! 「抗酸化生活」の極意
-
老化を進めるさまざまな要因が明らかになっている中で、大きく注目されているのが「酸化」だ。酸化によって細胞が傷つき、細胞や組織の機能を低下させ、老化を進行させてしまう。できるだけ老化を遅らせ、健康に過ごすためには、活性酸素を除去する力「抗酸化能」を高めることが肝要だ。
-
- 血管の若さが寿命を決める 100年元気に過ごす血管若返り術
-
人生100年時代をすこやかに過ごすためには、若々しくしなやかな「血管」を長く保つことが不可欠です。血管の老化予防に役立つ最新の知見を紹介しましょう。
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 23
この記事では、今知っておきたい健康や医療の知識をQ&A形式で紹介します。ぜひ今日からのセルフケアにお役立てください!
有料会員になると、鍵つき記事が全て読める&医療専門家に電話相談や名医紹介も!
-
- シニアこそ「たんぱく質」で筋肉づくり 健康長寿をかなえる摂取術
-
シニア世代が特に意識したい栄養素が「たんぱく質」。近年、健康的に長生きするにはたんぱく質が重要だという認識が広がりつつあります。しかし、実際に何を、どのくらいとればいいのかについては、まだ十分に知られていません。一体、どのように摂取するとよいのでしょうか。過去の人気記事を基に、たんぱく質のとり方を見ていきましょう。
-
- 体のサビ防ぎ、老化を遠ざける! 「抗酸化生活」の極意
-
老化を進めるさまざまな要因が明らかになっている中で、大きく注目されているのが「酸化」だ。酸化によって細胞が傷つき、細胞や組織の機能を低下させ、老化を進行させてしまう。できるだけ老化を遅らせ、健康に過ごすためには、活性酸素を除去する力「抗酸化能」を高めることが肝要だ。
-
- 血管の若さが寿命を決める 100年元気に過ごす血管若返り術
-
人生100年時代をすこやかに過ごすためには、若々しくしなやかな「血管」を長く保つことが不可欠です。血管の老化予防に役立つ最新の知見を紹介しましょう。
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 24
この記事では、今知っておきたい健康や医療の知識をQ&A形式で紹介します。ぜひ今日からのセルフケアにお役立てください!
有料会員になると、鍵つき記事が全て読める&医療専門家に電話相談や名医紹介も!
-
- シニアこそ「たんぱく質」で筋肉づくり 健康長寿をかなえる摂取術
-
シニア世代が特に意識したい栄養素が「たんぱく質」。近年、健康的に長生きするにはたんぱく質が重要だという認識が広がりつつあります。しかし、実際に何を、どのくらいとればいいのかについては、まだ十分に知られていません。一体、どのように摂取するとよいのでしょうか。過去の人気記事を基に、たんぱく質のとり方を見ていきましょう。
-
- 体のサビ防ぎ、老化を遠ざける! 「抗酸化生活」の極意
-
老化を進めるさまざまな要因が明らかになっている中で、大きく注目されているのが「酸化」だ。酸化によって細胞が傷つき、細胞や組織の機能を低下させ、老化を進行させてしまう。できるだけ老化を遅らせ、健康に過ごすためには、活性酸素を除去する力「抗酸化能」を高めることが肝要だ。
-
- 血管の若さが寿命を決める 100年元気に過ごす血管若返り術
-
人生100年時代をすこやかに過ごすためには、若々しくしなやかな「血管」を長く保つことが不可欠です。血管の老化予防に役立つ最新の知見を紹介しましょう。
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 25
この記事では、今知っておきたい健康や医療の知識をQ&A形式で紹介します。ぜひ今日からのセルフケアにお役立てください!
「インターバル速歩」に関する問題
【問題】ウォーキングで手軽に体力アップをしたいと思うもの。しかし、そのハードルは意外に高いようです。そこで考え出されたのが、ウォーキングの常識を変えたといわれる「インターバル速歩」です。以下の、ウォーキングやインターバル速歩についての解説のうち間違ったものはどれでしょう。
- (1)体力を上げるには普通のウォーキングでは運動強度が低すぎる
- (2)インターバル速歩なら週60分ほどでも体力が上がる
- (3)インターバル速歩は週60分よりも長時間すればするほど効果が上がる
- (4)ややきついと感じるような運動を2分ぐらいするなら、インターバル速歩に限らずどんな運動でもいい。
-
- シニアこそ「たんぱく質」で筋肉づくり 健康長寿をかなえる摂取術
-
シニア世代が特に意識したい栄養素が「たんぱく質」。近年、健康的に長生きするにはたんぱく質が重要だという認識が広がりつつあります。しかし、実際に何を、どのくらいとればいいのかについては、まだ十分に知られていません。一体、どのように摂取するとよいのでしょうか。過去の人気記事を基に、たんぱく質のとり方を見ていきましょう。
-
- 体のサビ防ぎ、老化を遠ざける! 「抗酸化生活」の極意
-
老化を進めるさまざまな要因が明らかになっている中で、大きく注目されているのが「酸化」だ。酸化によって細胞が傷つき、細胞や組織の機能を低下させ、老化を進行させてしまう。できるだけ老化を遅らせ、健康に過ごすためには、活性酸素を除去する力「抗酸化能」を高めることが肝要だ。
-
- 血管の若さが寿命を決める 100年元気に過ごす血管若返り術
-
人生100年時代をすこやかに過ごすためには、若々しくしなやかな「血管」を長く保つことが不可欠です。血管の老化予防に役立つ最新の知見を紹介しましょう。
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 26
この記事では、今知っておきたい健康や医療の知識をQ&A形式で紹介します。ぜひ今日からのセルフケアにお役立てください!
「朝食」についての問題
【問題】「朝食抜き」が常態化すると、午前中のパフォーマンスが落ちるだけでは済まず、肥満のほか、糖尿病や高血圧といった生活習慣病、心臓や血管の病気、うつなどの病気のリスクが上がります。健康的な朝食のとり方について「間違った説明」はどれでしょう。
- (1)起床したら1時間以内に、せめて2時間以内にとるようにする
- (2)朝食は糖質をしっかりとるようにする
- (3)白米と玄米であれば、白米を食べるようにするとよい
- (4)朝のコーヒーは体内時計のリセット効果が期待できてよい
-
- シニアこそ「たんぱく質」で筋肉づくり 健康長寿をかなえる摂取術
-
シニア世代が特に意識したい栄養素が「たんぱく質」。近年、健康的に長生きするにはたんぱく質が重要だという認識が広がりつつあります。しかし、実際に何を、どのくらいとればいいのかについては、まだ十分に知られていません。一体、どのように摂取するとよいのでしょうか。過去の人気記事を基に、たんぱく質のとり方を見ていきましょう。
-
- 体のサビ防ぎ、老化を遠ざける! 「抗酸化生活」の極意
-
老化を進めるさまざまな要因が明らかになっている中で、大きく注目されているのが「酸化」だ。酸化によって細胞が傷つき、細胞や組織の機能を低下させ、老化を進行させてしまう。できるだけ老化を遅らせ、健康に過ごすためには、活性酸素を除去する力「抗酸化能」を高めることが肝要だ。
-
- 血管の若さが寿命を決める 100年元気に過ごす血管若返り術
-
人生100年時代をすこやかに過ごすためには、若々しくしなやかな「血管」を長く保つことが不可欠です。血管の老化予防に役立つ最新の知見を紹介しましょう。
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定



