失われる科学の灯:米国の変調、高まるOISTの価値
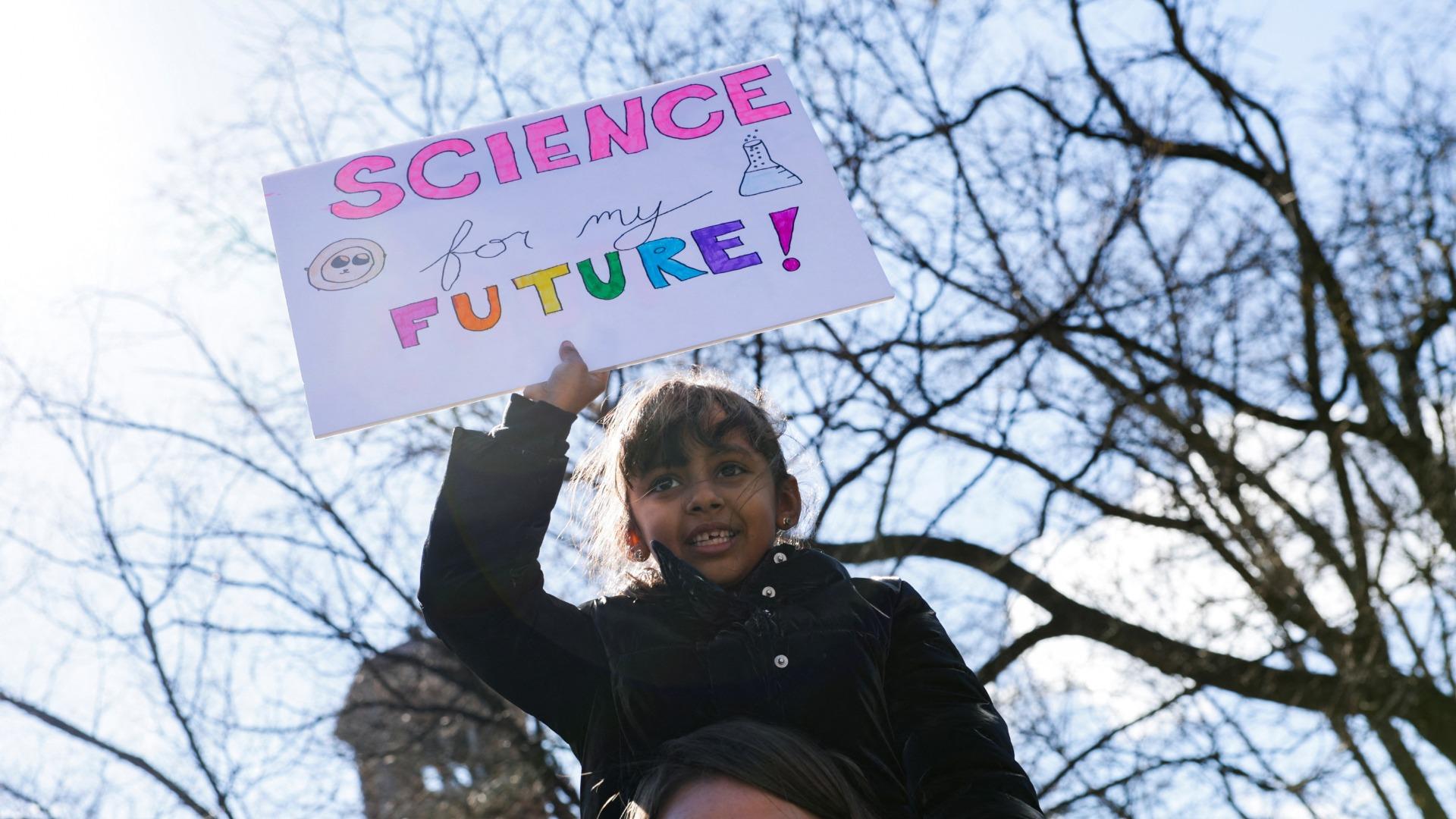
米国のトランプ大統領は、政府効率化省(DOGE)などを通じて、政府機関の人員や予算の削減を進めており、その一環として、科学研究に関連する予算や組織、人員の削減も行っている。また同政権の反エリート主義の流れから、同大統領は、同国のエリート名門大学に対して、特にDEI(多様性、公平性、包括性)政策や、トランスジェンダー選手の大会参加、反ユダヤ主義への対応などを問題視し、関連する教育方針や学内の自治を見直すよう要求し、従わない場合は補助金の凍結および留学生・研究者などのビザ停止・発給抑制などの圧力をかけている(注1)。それらの結果として、政府系の研究機関が研究を打ち切り人員削減を行ったり、大学側が妥協したりその方針を受け入れたり、研究費用などの削減・人員削減などの動きもでてきており、その方針や動きに反対する大学や研究者、妥協した大学などへの反発も生まれ、社会的に混乱が生まれていると共に、科学分野が冷遇される状況が生じている。
米各地で科学者らによるトランプ政権に抗議するデモが起きている(写真:ロイター/アフロ)米国内でのこれらの動きは、国内的混乱のみならず、同国がこれまで国際社会で築いてきた科学をリードする基盤や人材集積の機能を大きく変化させている。また、この方針・対応は、同国が科学分野でリードすることで得ていた国際的な優位性が、科学者や科学的知見の流出とともに、他国、特に科学分野に注力し世界のリーダーを目指している中国に渡る危険性などもあり、中長期的には同国のイノベーションや経済に計り知れない影響を及ぼす可能性がある。
このような状況において、研究者のなかに将来への不安および米国の政府や社会への不信感も生まれてきており、米国を離れて、他国に研究拠点を移そうとしたり、移民を希望する者も出始めているようだ。たとえば、英科学誌ネイチャーによる米研究者1600人以上を対象者とした実施した調査によれば、トランプ米政権による研究活動への締め付けを強めていること理由に「米国を離れることを検討している」と回答した割合は75%に上り、特に若手の研究者は移動を検討する傾向にあったそうだ(注2)。
このような状況を受けて、カナダや欧州などの他国は、米国研究者を受け入れる方向で動いて入るようだ(注3)。
これは、ある意味、米国以外の国々にとっては、米国の優秀な研究者を自国に呼び込んで、科学技術において大きな進展を図らせることのできる好機というか、アドバンテージをとれる機会であるともいえる。
日本は、欧米やアジアなどの他の国々と比較して安定しており、言語的なハンデはあるが、研究レベルも高くので、この機において米国の優秀な研究者を引き込み、最近科学技術のいくつかの分野での進展が遅れがちな現状を挽回し、巻き返せる好機にすることもできるはずだが、実態はそのように進んでいないようだ(注4)。これは、トランプ政権への忖度もあるかもしれないが、日本の大学などの研究機関が、国際化されていず、研究環境や外国人材の受け入れ態勢などが十分でないところが多いからである。
だが、そのような日本でも、実は非常に優位性のある場所がある。それは、「沖縄科学技術大学院大学(OIST)」だ。筆者は、OISTに滞在し、同大学について研究し、拙著『沖縄科学技術大学院大学は東大を超えたのか―日本を「明治維新の呪縛」から解放し、新しい可能性を探求する』を昨年上梓した。
OISTは、最近注目が高まっており、詳しくは同拙著を読んでいただきたいが、国際的にも高く評価される研究レベルがあり、英語が公用語であったり日本国内の大学では例外的な給与水準にあるなども含めた国際的な研究環境があり、他国の優れた研究者が着任しても、短期間で研究に専念できる環境が既にある、日本における唯一無二の研究機関・大学であるということができる。
他方で、OISTは、国際的には既に高い評価を受けているが、日本国内では、その利点や優位性が十分に活かされているとはいえない。しかしながら、正に現在のような時だからこそ、これまでおよび現在のOISTが有する利点等を、日本社会に活かすことのできる立場にあるということができる。
しかも、OISTには、東京や県庁所在地・那覇市からも離れており、基礎研究中心であり、政治的な色が薄い存在だ。その意味では、税金が投入されてはいるが私立大学であるので、日本政府が、OISTに、例えば年100億円10年間を付加投入し、ある程度の数の米国の研究者等を受け入れても、米国に対しても先端技術研究のためとの言い訳が立ちやすいのではないだろうか。
また研究の世界では、研究者は絶えずよりよい研究やその場所を求めて移動し研究活動や研究交流を行っているというのが常態であり、今回日本が受け入れても、状況が変化すれば、研究者はまた移動していくだろう。しかしネットワークでつながっていることが重要である。その受け入れにより、日本の研究水準を高く維持し続けられる、人的ネットワークおよび研究の蓄積ができるだろう。さらに、日本が、OISTを活用して、このように米国の研究者等を受け入れておけば、研究者が特定の国々に流失してしまう危険性も防げるので、結果として、同盟国等の研究水準の向上に寄与でき、それは中長期的には米国の利益にも資することができるだろう。
日本は、これまで日本社会にとって十分に利活用してきたとはいいがたい隠し資産ともいうべき、OISTを、この機会に日本および世界のために活かしてはどうだろうか。
(注1) トランプ政権の対応については、次の記事等を参照のこと。
・「トランプ政権による科学冷遇と日本の好機 #エキスパートトピ」(鈴木崇弘、Yahoo!ニュース、2025年4月16日)
・「米コロンビア大学、研究者約180人解雇へ トランプ政権が助成金削減」(AFPBB News、2025年5月7日)
またトランプ大統領は厳しい反中国の対応や政策をとっている。他方で、科学技術の基盤となってきているAI分野などの研究者の約5割が中国人といわれ、同大統領の大学対応は、その現状を抑制・変更するためだという意見もある。しかし、その対応は、短期的には中国のAI研究を抑えることができても、中長期的には、中国人人材が中国に戻ったり行ったり、留まることなどにより、かえって中国のAI研究の進展を加速させる可能性がある(いやおそらく、その可能性がさらに高まる)ことも考えるべきだろう。研究米国における中国人材の現状については、次の記事などを参照のこと。
・「世界のトップAI研究者の約50%が中国出身であることが判明」(Gigazine、2024年3月25日)
・「米国が警戒し始めた「AI人材の層の厚さで中国に敗れる日」、出遅れ日本はどうする」(中田敦、日経XTech、2025年5月9日)
・「世界のトップAI研究者、約5割が中国出身」(AAiT、2024年5月28日)
(注2)この点については、次の記事などを参照のこと。
・「米研究者、75%がトランプ政権下で国外移動検討 英調査」(日本経済新聞、2025年3月29日)
(注3)この点については、次の記事なども参照のこと。
・「仏大学などが米研究者を受け入れへ トランプ政権の予算削減で」(NHK、2025年3月27日)
・「米国を逃れる「難民研究者」第1陣、6月からフランスで勤務」(AFPBB News、2025年4月18日)
(注4)この点に関しては、次の記事などを参照のこと。
・「米国出る研究者受け入れ、鈍い日本 19大学・機関で北大のみ「検討」」(日本経済新聞、2025年5月2日)
・「米国出る研究者受け入れ、鈍い日本」(隣の経済自由人@Ameba、2025年5月4日)



