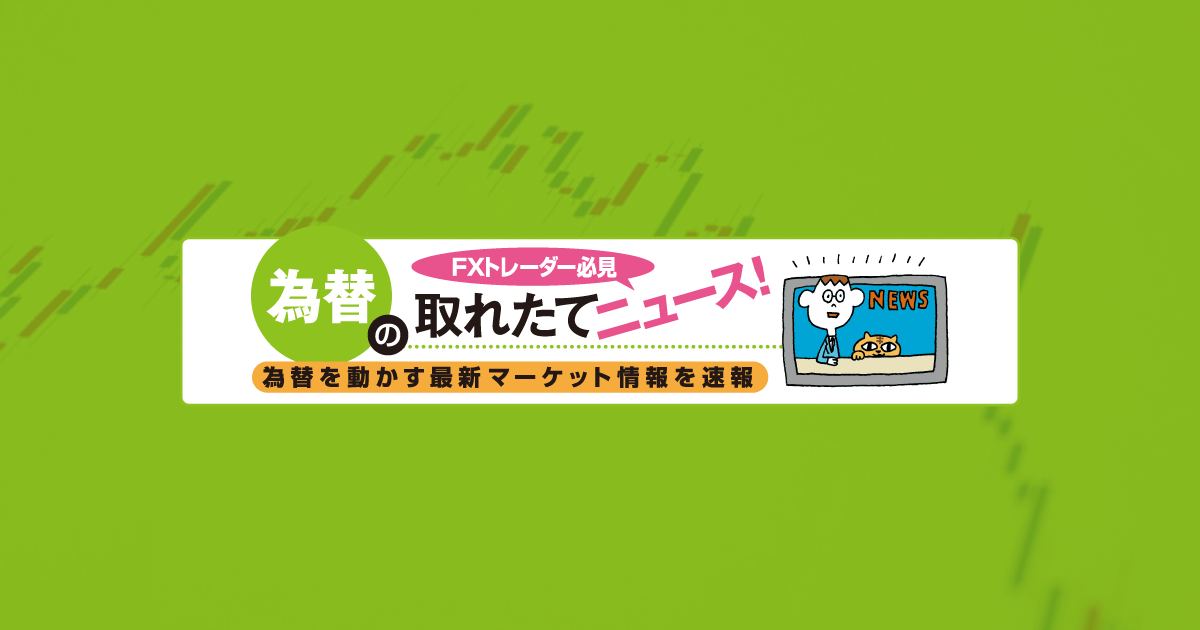高速道路でパニックブレーキをかけてしまった 日本のディーゼルはデミオで変わる? 続・アメリカの全盛時代【復刻・徳大寺有恒「俺と疾れ!!」】

2014年11月に逝去した自動車評論家、徳大寺有恒。ベストカーが今あるのも氏の活躍があってこそだが、ここでは2014年の本誌企画「俺と疾れ!!」をご紹介する。(本稿は『ベストカー』2014年4月26日号に掲載したものを再編集したものです/著作権上の観点から質問いただいた方の文面は非掲載とし、それに合わせて適宜修正しています)。
シムカ アロンド…フランスでフィアットを製造するために設立されたのがシムカでアロンドは1953年誕生のフィアット1100をベースにしながら本家より早く1951年に誕生したモデル。写真は最終型のP60と呼ばれるモデル
前回はアメリカの全盛時代だった1950年代から1960年代をざっと俯瞰したが、なかでもフォードは1960年代に世界作戦とでもいうべき欧州での攻勢に出た。
つまり1960年代のフォードはヨーロッパのモータースポーツに関心を示し、ル・マン24時間レースをはじめ、ヨーロッパのモータースポーツをドルの力で支配した時代だった。
ジム・クラークのF1チャンピオンをはじめとするロータスの全盛はフォードの資金援助によるといっていいと思う。ジム・クラークはシュアなドライバーで今もって伝説に残るドライバーであるが、フォードのドルの力はものすごく、当時のフォードは、彼をチャンピオンに押し上げることも容易にできたであろう。
当時フォードは、アメリカのビジネスが大切だったが、ヨーロッパにはイギリス、ドイツ、フランスとそれぞれにフォードモデルがあった。ヨーロッパフォードとしてひとつになるのは1968年のことである。
フランスフォードはV8、4L搭載のセダン、ヴァンドームを作っていたことがある。フランスフォードは後にシムカに吸収されてしまうが、シムカはアロンドのようなしゃれたクルマを作っていた。
1960年代はフランス国家の独自性を強調するド・ゴール大統領の時代だが、その終わり頃には多分に社会主義的な考え方が広がっていてクルマは動けばいいという超合理主義がまかり通っていたものと思われる。
まあ、自動車の歴史を考えればフランスはあの華美な時代を通ってきただけにそうそう変われるものではなかろう。
超合理主義的なフランス車と思い切って派手で華やかなカロッシ(イタリア語ではカロッツェリア)のフランス車はどちらも同じフランス車なのである。ルノー4CVがあって、ヴォワザンがあり、アルピーヌA110があって、シトローエンDSがあるのもフランスなのだ。
さてフランス車の話ついでに食い物の話をしよう。
まず私がパリについたらクーポールへ行って昼飯に何を食べるか考えよう。このモンパルナスにあるブラスリーをまず訪ねたい。パリでは凝った材料もうまいけれど、ただ牛肉を焼いただけのステーキもけっこういける。
それともシンプルにドラッグストアでサラダを中心とした軽いものでもいいね。ドラッグストアはパリにたくさんあってちょっとしたものを買うにも食べるにもとても便利だ。
ステーキには大量のフリット(フライドポテト)が付いてくる。オニオン・グラチネ(オニオングラタンスープ)もボリュームがあっていい。
パリではアメリカンスタイルのサンドウィッチも多い。フランスパンに薄いハムを挟んだだけのものを好む。パンはうまいし、3時くらいにこいつをやれば、夜の7~8時まではお腹が減らない。
そして、ディナーはキチンと取る。どこで食べるかは自由だが、ウチのかみさんに言わせればエッフェル塔のなかで食べるのもいいという。もちろんかねてより知った店ならば文句なし。日本食でもいいしラーメンもある。私は昼はオムレツ、夜はキチンとディナーを取りたいが、といって高いところへ行く必要はない。
マドレーヌ寺院の近くにいれば、近くのお店で食事を買ってホテルでやるのもいい。このカトリック教会の周辺にはとにかくうまいものが多い。夜は遊びに出かけ、腹が減れば何かを食うことになる。いわゆるスナックだ。パリはお菓子がおいしいことは皆さんご存じの通り。というわけで、パリに行くと日本に戻った時にズボンのベルトを気にする羽目になる。