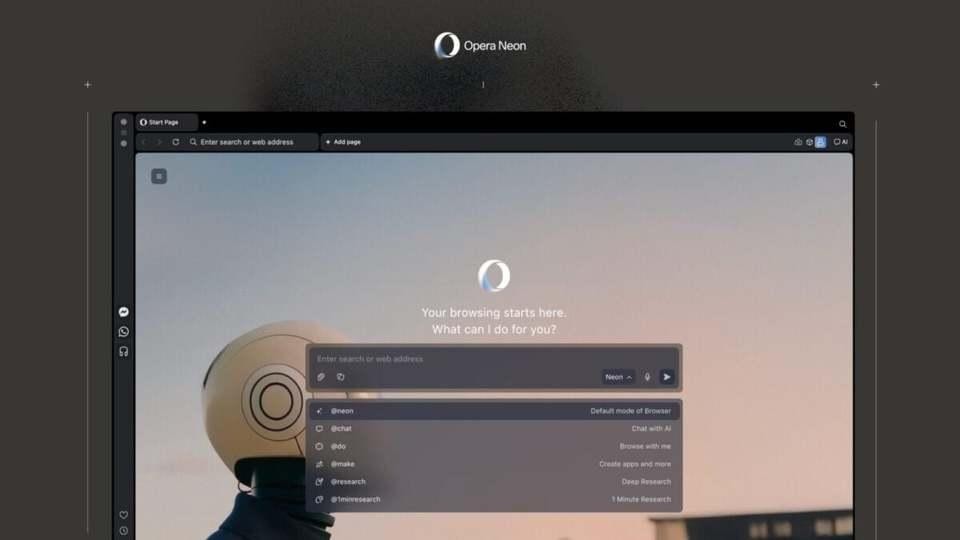なぜあのドコモが通じづらくなったのか…5Gへの移行で"著しい品質低下"が起きた3つの理由(プレジデントオンライン)

かつて世界のトップを走っていた日本の通信産業に異変が生じている。ネットワーク品質低下の舞台裏では何が起こっているのか、スマホジャーナリストの石川温氏が解説する──。 【図表をみる】au躍進の裏で、ドコモは低迷 ■「現場レベルの危機感が幹部に伝わらない」「ドコモがつながらない」 そんな書き込みが2023年春頃からSNSで散見されるようになりました。2年が経ったいまでも相変わらずつながらないところが多く見られます。 とくに、通勤中の電車内やターミナル駅など、人が多いところで電波がつながらないとの指摘が目立ちます。「全国津々浦々、つながりやすさといえばドコモ」。かつてのドコモはこのように評されていました。しかし、いまとなってはKDDIはおろか、長年「つながりにくい」と酷評されていたソフトバンクよりもドコモのネットワーク品質が低いといわれています。 品質低下が指摘され始めた当初、ドコモは専門メディアに対して「コロナ禍が落ち着き、都心部に人流が復活した影響が大きい」と理由を説明していました。 たしかに、コロナ禍が収束した23年はテレワーク中心だった働き方が変わり、都心に人が戻り始めた頃でもあります。また、渋谷駅など大規模工事をしているターミナル駅周辺では、「基地局」というスマートフォンが通信するアンテナ設備を屋上に設置しているビルが相次いで建て替えに。一時的にアンテナ設備が撤去され、通信しにくくなる状況が発生していました。 しかし、「コロナ禍収束による人流の変化」「ターミナル駅周辺の大規模工事」は、ドコモに限った話ではありません。KDDI、ソフトバンクも全く同じ条件なはず。では、ドコモだけがつながらない理由はどこにあるのでしょうか。 「現場レベルではネットワーク品質が落ちていることを十分理解し、改善するよう幹部に掛け合っている。しかし、意見が通らない」 これは、元ドコモのネットワーク関係者が23年に語っていたことです。 ドコモは、20年にNTTの完全子会社となりました。それまでドコモは競合であるKDDIやソフトバンクとネットワーク品質でもしのぎを削っていました。しかし、NTTグループの中で稼ぎ頭のドコモは、完全子会社化以降は競争力よりも収益性が重視されるように。結果として、ネットワーク品質を維持、向上させるための設備投資が抑制されたようです。 折しもコロナ禍の後押しを受けた働き方改革によって、世間ではビデオ会議が急増。また、巣ごもり需要が影響し、YouTubeやTikTokなど、スマホで動画を視聴する機会も増えました。結果として、データ通信量が莫大になり、ネットワークは混雑するようになりました。 データ通信量が増え続けるタイミングでありながら、設備投資を控えてしまったことが、ドコモが「つながりにくい」状況を引き起こした原因です。 ■競合他社と差がついた「日本代表」の事情 23年10月、ドコモはネットワーク対策に300億円を投資すると発表。24年6月には、前田義晃新社長が誕生し、さらなるネットワーク品質の向上を誓いました。 一方で、ネットワーク品質低下の背景には複数の要因が絡み合っており、単に設備投資額を増やせば解決するものではないという指摘もあります。 24年10月、ドコモが基地局の調達を見直し、これまで富士通など国内ベンダー一辺倒だったものをエリクソン(スウェーデン)やノキア(フィンランド)などの海外ベンダーに切り替えるとの報道がありました。 ドコモには、国内ベンダーとともに通信設備を開発、設計してきたという歴史があります。日本を代表する通信事業者なので、国内ベンダーと手を取り合って開発するというのは当然のことのように思います。 一方、KDDIやソフトバンクの基地局の調達はエリクソンやノキア、サムスン電子(韓国)などの海外ベンダーからが多いです。海外ベンダーは日本以外でも商売をしているため、大量生産によってコストが安い傾向です。また、世界各国の通信事業者にネットワーク設備を納入していることから、様々な国や地域のネットワーク事情に精通しています。そのため、KDDIとソフトバンクは、海外ベンダーの豊富な知見を借りながら国内のネットワークを運用することができています。 また、海外ベンダーは一つのアンテナで大量の端末と同時に通信するアンテナ技術を持っています。その技術をいち早く導入したのが、KDDIとソフトバンク。一方で、ドコモが取引する国内ベンダーは、そうした通信技術をごく一部のアンテナでしか採用できませんでした。 結果として、電波がつながらないドコモを尻目に、両社はターミナル駅などの人が多いところでも安定した通信品質を維持できたとされています。そのような経緯を踏まえて、ドコモは国内ベンダーだけでなく、海外ベンダーからも設備を調達するようにしたのです。 ■ドコモの5Gだけがつながらない理由 日本では20年から通信技術の最新規格である「5G」のサービスが始まりました。5Gには「超高速、大容量、超低遅延」という3つの特長があるといわれています。 ドコモはそれまで提供していた4Gとは全くの別モノとして、5Gの基地局を展開していました。そのため、5Gを利用可能なエリアがなかなか広がらないという状況に。一方、KDDIとソフトバンクは、これまで展開していた4Gのネットワークの一部を5Gとして運用することができる、エリクソンが持つ技術を導入しました。 この場合、ベースは4Gであるため、5Gの特長である「超高速、大容量、超低遅延」というメリットは何一つ導入されません。しかし、すでに全国で99.9%以上のエリアをカバーしている4Gネットワークにいる際に、スマホを見れば画面に「5G」と表示されます。たとえ見掛け倒しでも、ユーザーは「5Gでつながっている」という感覚になることができました。 4Gエリアなのに5Gになる技術は、通信業界で「なんちゃって5G」と揶揄されていました。ドコモはなんちゃって5Gが消費者に優良誤認を与えるとして、2社の方針を厳しく批判していました。しかし、KDDIとソフトバンクはなんちゃって5Gを運用して全国に面展開する裏で、5G本来の性能が発揮される「真の5G」も着実に普及させていきます。 一方、ドコモは5Gの基地局をスポット的、いわゆる点のように展開していました。この際、5Gエリアの端っこにおいてはつながりにくく、通信も安定しません。結果、真の5Gを展開したのはいいものの、品質の悪い部分が増えてしまったのです。 ドコモは現在、5Gの基地局を増やしたり、アンテナの角度を調整したりすることで、増大するデータ通信量を処理しようと改善を続けています。 ただ、ドコモとKDDI、ソフトバンクにおいては、もう一つ構造的な違いがあるといわれています。 KDDIには「UQコミュニケーションズ」、ソフトバンクには「ワイヤレスシティプランニング」というデータ通信に特化したグループ会社が存在します。彼らはデータ通信に強い技術を取り入れた周波数帯を持っており、auユーザーやソフトバンクユーザーが使うスマートフォンに対して、データ通信サービスを提供しています。 この2社が扱う電波は、比較的つながりやすく、また大量のデータの送受信を処理するのに向いています。KDDIとソフトバンクが「なんちゃって5G」から「真の5G」にスムーズに移行できたのは、この2社のおかげともいわれています。 実は、ドコモにはこうした会社が存在しません。莫大なデータの送受信を処理するには5Gエリアを広げ、4Gエリアで混雑するデータを5Gに移行させる必要があり、時間がかかっているのです。 ■ユーザー目線に欠けた「最高速度アピール」 通信業界は現在、イギリスの調査会社オープンシグナルが公表するデータをサービスのベンチマークとしています。24年前半まではソフトバンクがネットワーク品質で高い評価を受けていましたが、同年後半からはKDDIがトップの座に輝いています。 KDDIやソフトバンクがネットワーク品質を維持、向上するうえで参考にしているのは、ユーザーが使うアプリからの情報です。通信事業者が提供するアプリに対して、ネットワークの品質をチェック、報告する機能をあらかじめ導入しておきます。ユーザーがアプリを使う中で、速度が落ちたり、圏外になったりしたのはどこかをアプリが自動で計測します。その計測データがクラウドにアップロードされ、KDDIとソフトバンクはネットワーク品質の改善にすぐに着手するというわけです。 KDDIとソフトバンクは「通信速度」よりも「ユーザーの体感」を重視してきました。これまで通信事業者は、新しい通信技術が始まるとどれぐらい通信速度が速くなるかをアピールしていました。しかし、通信が超高速となり、2時間の映画を数秒でダウンロードできるとしても、一般的なユーザーには意味がありません。それよりも「ヤフーニュースの見出しをタッチした瞬間に記事が表示される」「YouTubeのサムネイルをタッチした瞬間に動画が再生される」ほうが快適に感じます。 KDDIとソフトバンクはこの「ユーザーの体感」を最優先に、日々ネットワークの改善を行う地道な努力を続けています。一方、ドコモはどちらかというと「最高速度アピール」に主眼を置いていた感があります。また、ユーザーが使うアプリからの情報を分析して、ネットワーク品質を改善する取り組みは、先行する2社にかなり遅れるかたちで、24年1月からようやく始めました。 ドコモの前田社長は「24年度末までにオープンシグナルの評価で1番を獲る」という方針を掲げました。NTTの島田明社長も、ドコモのネットワーク品質について「25年4月頃には改善が見られるのではないか」と語っています。しかし、業界内で信じる人はあまりいません。おそらく、もうしばらく時間がかかるのではないかと見られています。 ■日本のスマホ料金は7000円でも妥当 20年から21年にかけて、スマホ料金の値下げが相次ぎました。その背景にあるのは、「日本の通信料金は高すぎる。海外の水準まで下げるべきだ」と常々主張していた菅義偉氏が、20年9月に首相に就任したことです。 20年12月、ドコモはオンライン専用プラン「ahamo」を翌年から開始すると発表しました。20GBのデータ量を税抜き2980円(のちに税込み2970円に改定)で利用できるという破格の値下げを行ったことで業界に激震が走り、「ahamoショック」と騒がれました。 業界トップのドコモが率先してスマホ料金を値下げしたことで、他社も追随を余儀なくされます。KDDIとソフトバンクはサブブランドの「UQモバイル」「ワイモバイル」だけでなく、オンライン専用ブランド「povo」「LINEMO」を新たに投入して、ドコモに対抗しました。 また、20年4月には楽天モバイルが第4のキャリアとして新規参入し、税抜き2980円でデータ通信が使い放題というプランを展開し始めました。楽天モバイルは、参入した当初のネットワーク品質がかなり悪かったです。しかし、猛烈に全国に基地局を設置し、さらには総務省から「プラチナバンド」というつながりやすい電波を取得したことで、今日ではかなり使いやすくなってきました。最近では契約回線数が850万に達するなど、既存3社に対して競争力を上げてきています。 当時からこの一連の値下げ競争は政府による圧力、いわゆる「官製値下げ」だと指摘されていました。実際、楽天モバイルが携帯電話事業に新規参入できたのは、菅氏のおかげともいわれています。 たしかに、ヨーロッパなどの通信事業者が提供する料金プランは3000円程度でかなりのデータ量が使えるなど、安価な水準にありました。それに比べて、日本はデータ使い放題プランの料金が7000円前後と、海外よりも倍以上の設定になっていました。 一方で、菅政権の意向に対して「日本の通信料金は確かに海外に比べて高い水準にあるが、その分ネットワーク品質は高く、妥当な料金設定だ」という声もありました。 実際、フランスやドイツは料金プランこそ安価ですが、地下鉄や郊外の電車に乗ると圏外といった状況です。日本のように、どこにいてもYouTubeの動画を見ることはできません。つまり、海外のスマホ料金は「安かろう、悪かろう」という品質に見合った料金設定でもあるのです。 ドコモが率先して料金値下げをしたことと、ネットワーク品質が低下したことに直接的な因果関係があるかはわかりません。ただ、料金を値下げすれば、収益構造が悪化するわけで、幹部に「設備投資を抑えよう」という心理が生まれることは容易に想像できます。 ■通信料金値下げの大きすぎる代償とは 官製値下げが起こったことで、日本は世界でも通信料金が安価な国となりました。昨今、食料や消費財、光熱費などあらゆるものが値上げしています。その中でも、通信料金だけは据え置きを維持するどころか、ahamoが料金設定はそのままで20GBから30GBにデータ容量を増量するなど、実質的な値下げも行われています。 国民としては菅氏に感謝したいところですが、通信事業者は正直言って相当苦しい立場に追い込まれています。 KDDIの髙橋誠社長は「いま、通信事業者は本当にみんな頑張っている。通信料金を値下げしたことで、いまではアメリカの2分の1の水準まで落ちている。諸外国はどんどん値上げしている中、日本の通信事業者は設備効率を上げながら、5Gに投資を続けてきている」と、海外との格差を語ります。 特に最近、官製値下げに加えて通信業界に大きなダメージを与えているのが、電気料金の高騰です。基地局やサーバーを動かすのには当然電力が必要ですが、昨今のAIブームによって、データセンターでの電気料金が爆発的に増えると予想されています。 24年12月、ソフトバンクはシャープが所有していた大阪府堺市の工場を取得し、AIデータセンターを構築すると発表しました。北海道苫小牧市にも、大規模なAIデータセンターを建設中です。従来のデータセンターに比べて、AIデータセンターは消費する電力が桁違いです。そのため、データセンターが稼働開始すると、ここ数年右肩上がりで増え続けている電気料金の負担が重くのしかかってきます。 ソフトバンクの宮川潤一社長は「5Gへの投資も『こんなものか』と言われるのが悲しくて仕方ない。日本はただ通信料金が安いだけの国になってしまった。開発力が本当に落ちた。どこかで声を上げるつもりだ」と危機感を募らせています。 NTTは光電融合技術の開発力を武器に、世界進出を目論んでいます。一方で、国内の通信料金値下げと引き換えに、通信事業者の体力が確実に落ちています。かつて、日本の通信産業は、世界のトップを走りすぎて「ガラパゴス」と揶揄されていました。 しかし、いまでは日本の国際競争力はアメリカや中国に大きく水をあけられ、世界での存在感が希薄になりつつあります。 日本企業は5Gから6G、さらに光電融合技術で世界進出を狙っていましたが、それも厳しくなりそうです。 ※本稿は、雑誌『プレジデント』(2025年4月4日号)の一部を再編集したものです。 ---------- 石川 温(いしかわ・つつむ) ジャーナリスト 1998年、日経ホーム出版社(現日経BP社)に入社後、月刊誌『日経トレンディ』編集記者に。2003年に独立。携帯電話を中心に国内外のモバイル業界を取材し、テレビ、雑誌で幅広く活躍。 ----------
ジャーナリスト 石川 温