「生物進化の謎」の一端を解明する「ジャンピング遺伝子」とは。名古屋大学などの研究(石田雅彦)
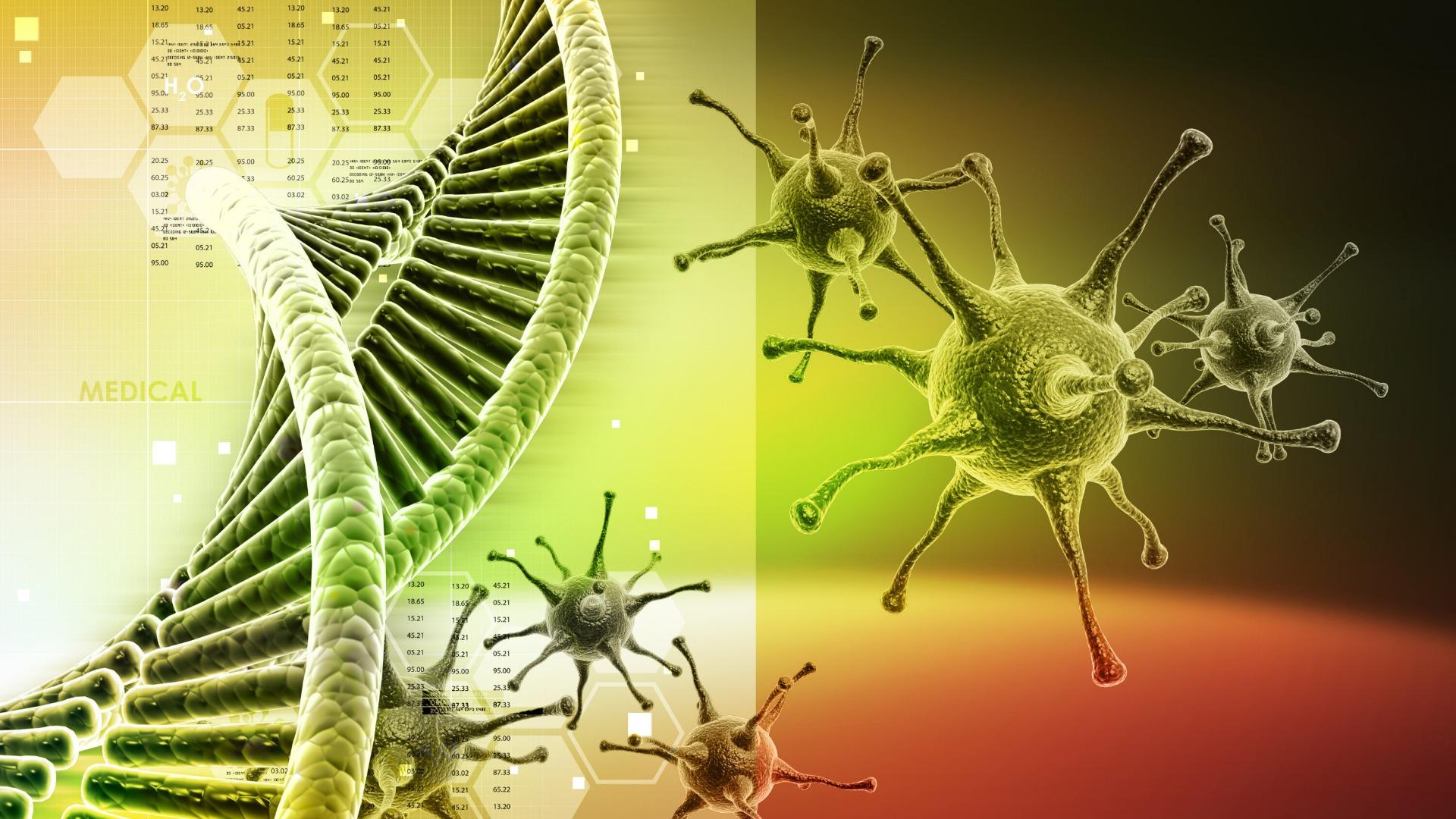
生物の進化には、内因外因を問わず、多くの要素が複雑に関連しているが、その要素の一つが「ジャンピング遺伝子」と呼ばれる遺伝子配列だ。名古屋大学の研究グループは、このジャンピング遺伝子の一つが生物進化にどのように作用したのか、その仕組みの一端を明らかにした。
ジャンピング遺伝子とは
地球上の生物は、互いに影響をおよぼし合い、あるものは絶滅し、あるものは別の種に分岐し、あるものは進化し、生物の多様性を生み出している。過去から現在、そして未来へ生物の遺伝子は受け継がれていくが、多様性に関係してるDNA配列がジャンピング遺伝子(トランスポゾン)と呼ばれる部分だ。
通常、遺伝子のDNA配列はゲノムの中や染色体の間を移動しないが、ジャンピング遺伝子は移動するため、こう名付けられている。ジャンピング遺伝子は、特に脊椎動物の進化の過程で感染したレトロ・ウイルスのDNA配列の残骸と考えられ、宿主と一種の共生をしてきた。
ジャンピング遺伝子は、転移酵素によって自分自身のDNA配列を切り出して他のDNA配列に挿入(カット&ペースト)したり、自分自身と同じDNA配列を合成し、他のDNA配列に転移(コピー&ペースト)したりする。ジャンピング遺伝子が他のDNA配列にどう挿入したり転移したりするのかは、宿主の都合などに関係なく「利己的」に起こす。
こうしたジャンピング遺伝子の振る舞いにより、DNA配列が変化して病気の発生や老化などに関係するとともに、常にDNA配列に変化を与えて突然変異を引き起こすなどして生物の進化に影響をおよぼす、ポジティブにもネガティブにも機能する存在ということがわかってきた。ただ、ジャンピング遺伝子の仕組みが、どのように生物の進化に影響をおよぼしてきたのか、その歴史や役割についてまだよくわかっていない。
現在の多種多様な生物のゲノム(全DNA配列)情報(全遺伝情報)が明らかになりつつあり、分子生物学の進歩によって遡及的に生物の系統の分子解析が可能になった。地球上の生物は全て共通祖先から枝分かれし、進化してきたと考えられているため、遺伝情報をたどっていくと、それぞれの種がどれくらい前に共通祖先から分岐したのかなどがわかるようになったというわけだ。
哺乳類にはない種類のジャンピング遺伝子の融合
そのため、名古屋大学の研究グループ(※1)は、多様な脊椎動物の遺伝子情報を解析し、LINE-1(L1)というジャンピング遺伝子(トランスポゾン)に着目した結果、このジャンピング遺伝子が新たなタンパク質を生み出すことを発見した。そして、このタンパク質を、哺乳類は持たず、鳥類や爬虫類が保持し、進化や多様化の仕組みに関係している可能性を示す論文を国際的な遺伝学雑誌に発表した(※2)。
このLINE-1というジャンピング遺伝子は、ヒトのゲノムの中で全ゲノムの約17%という最も大きな割合を持つ代表的なトランスポゾンという。LINE-1はヒト以外にも脊椎動物のゲノムに存在しているものの、LINE-1が他のDNA配列にどう挿入や転写しているのかについて、ほとんど研究されていない。
そのため、同研究グループは、鳥類と爬虫類、約600種のゲノムを解析し、LINE-1が他のDNAへ挿入や転写するために必要なORF1pというタンパク質について調べた。その結果、ミオシン軽鎖4(Myosin light chain4、MYL4)という心臓で働くタンパク質の遺伝子にLINE-1による遺伝子進化の痕跡を発見したという。
遺伝子の情報によってタンパク質を合成する配列(ブロック)をエキソンというが、ミオシン軽鎖4は6つのエキソンに分割され、本来なら順番に連結されることで正しいタンパク質の情報が完成する。
同研究グループは、鳥類や爬虫類ではジャンピング遺伝子のLINE-1が新しいエキソンとして挿入することでLINE-1とミオシン軽鎖4が融合したタンパク質の情報ができることを発見した。哺乳類のミオシン軽鎖4のエキソン領域にLINE-1は挿入されていない。
同同研究グループは、この融合したエキソンの領域をLINE-1とミオシンを合わせた「ライオシン(Lyosin)」と名付け、その働きをより詳しく調べた。その結果、ある種(4種類、ワニ類、カメ類)の爬虫類では、心臓で本来のミオシン軽鎖4のエキソンの正常な組み合わせが生じる一方、精巣ではミオシン軽鎖4にLINE-1が転写されてライオシンとして働くことがわかった。
エキソンは、その組み合わせによって複数のタンパク質を作ることができるが(選択的スプライシング)、鳥類や爬虫類が持っているライオシン(LINE-1とミオシン)の各エキソンが、ある種の爬虫類の心臓ではLINE-1を排除した組み合わせになり、精巣ではLINE-1がミオシン軽鎖4のエクソンに連結した組み合わせ、ライオシンとなるというわけだ。
ライオシン(LINE-1とミオシン軽鎖4)のエキソン。ある種の爬虫類における選択的スプライシングによる、心臓でのミオシン軽鎖4のみの組み合わせ、精巣でのLINE-1とミオシン軽鎖4のエキソンの組み合わせを示す。これは、選択的スプライシングによる仕組みによってLINE-1というジャンピング遺伝子によるミオシン軽鎖4との融合タンパク質が生まれる現象についての初めての報告だという。名古屋大学のリリースよりライオシンは哺乳類との共通祖先の分岐後か
では、LINE-1が挿入したミオシン軽鎖4、つまりライオシンはいつ鳥類や爬虫類で生まれたのだろうか。ライオシンは、哺乳類や両生類には存在せず、鳥類や爬虫類のゲノムにだけ存在している。ただ、ライオシンは、鳥類や爬虫類でも特にワニ類とカメ類で残され、ヘビ類とダチョウなどを除くほとんどの鳥類(新顎類鳥類)で失われている。
現在の鳥類や爬虫類の共通祖先が分岐したのは約2億8000万年前のペルム紀とされているので、同同研究グループはライオシンはそれ以前に獲得され、受け継がれてきたのではないかと考えている。哺乳類や両生類の共通祖先はそれ以前に分岐しているので、鳥類や爬虫類と同じように獲得したがその後に失われたのか、それともそもそも獲得しなかったのかについてはまだわからないという。
ただ、本来は心臓で発現する標準的なミオシン軽鎖4が、ワニ類やカメ類の精巣でライオシンとして発現していることが、その疑問を解明するヒントになるのではないかと同研究グループは考えている。
生物の系統樹とライオシンの有無。脊椎動物では、両生類との共通祖先がまず分岐し、その後に哺乳類との共通祖先が分岐した。鳥類や爬虫類の共通祖先が分岐したのが約2億8000万年前なので、ライオシンはその後にゲノムに存在したと考えられる。名古屋大学のリリースよりまた、ジャンピング遺伝子のLINE-1が、ミオシン軽鎖4以外に融合しているかどうか調べたところ、ナマズ類、クマ類、アフリカ獣類から1遺伝子ずつ、3例を同定したという。同同研究グループは、一部の生物にしか存在しないようなLINE-1ジャンピング遺伝子によって発現する融合タンパク質が、もっとあるのではないかと予想している。
ジャンピング遺伝子は正常なDNA配列を壊すなどして病気を引き起こすことも多く、常に宿主側とジャンピング遺伝子との攻防が繰り返されてきた。今回の研究成果は、ジャンピング遺伝子がどう生物の進化を促し、多様性を生み出すのか、そのメカニズムを解明する一歩になるだろう。
※1:北尾晃一(名古屋大学大学院生命農学研究科、日本学術振興会特別研究員PD)、一柳健司(東海大学医学部教授)、中川草(東海大学医学部准教授)ら
※2:Koichi Kitao, et al., "Birth of protein-coding exons by ancient domestication of LINE-1 retrotransposon" Genome Research, Vol.35(5), 8, May, 2025



