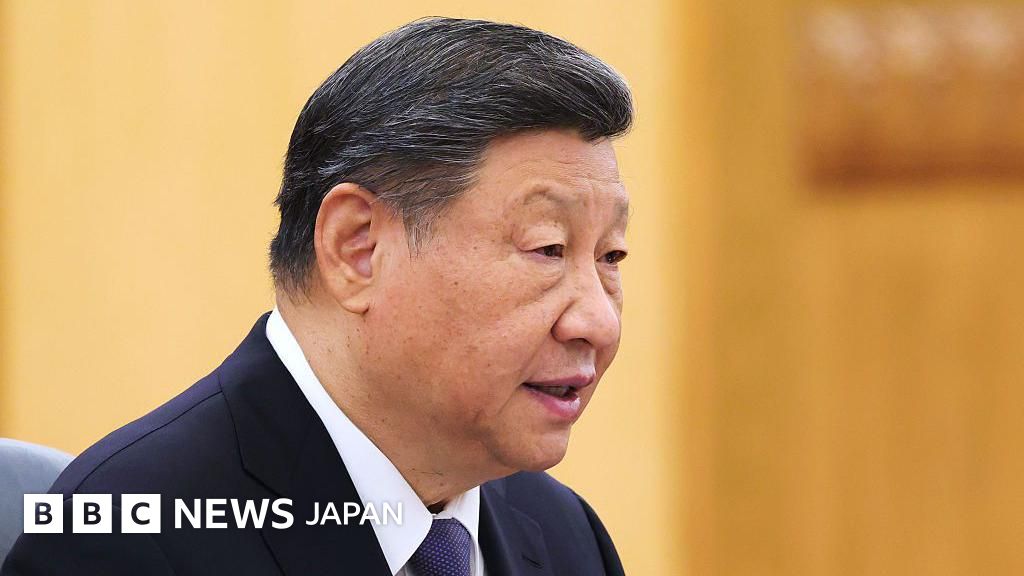地球から見えているのは片側のみ。月のこっち側とあっち側ってどう違う?

月が地球に見せている面は、いつも同じというのは常識。これは月の自転周期と公転周期が同じだからです。では、私たちからふだん見えない月のあっち側はどうなっているのでしょう?
宇宙探査で月のあっち側の画像は撮影されており、研究は進んでます。が、最新研究では、あっち側が思ってたよりこっち側と違うらしいことが明らかに。なんでもあっち側の方が冷たいんですって。
こちら側とあっち側
その昔、月のこちら側とあっち側には大差ないと考えられていました。それが60年以上月の表面を研究していくうちに、地質学上の違いがあることが判明。
例えばあっち側にはたった1%しか月の海(色が濃い部分)がないのに、こちら側には31%もあります。観測を重ねるうちに、月に転がる岩を構成する物質も、こちらとあちらでは違うようだということもわかってきました。また、NASAの月探査機Grailによって、あっち側の地殻はこちら側よりも平均20kmほど分厚いことも明らかになりました。
こっちとあっちの違いは、月の形成、進化に深く関わりがあり、ひいては地球の歴史にも関係します。ゆえに月の二面性の違いを調査することは、地球誕生の解明にもつながるのです。
温度差の背景
論文共同執筆者で、北京大学とユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドンで地球惑星科学の准教授を務めるYang Li氏は、プレスリリースにてこう語っています。
「これは月の最大のミステリーの1つで、私たちは月の二面性と言っています。
こちら側とあちら側の温度差は長く仮説としてありましたが、今回、リアルなサンプルを使い始めてその証拠を提供することができました」
今回の研究でチームが解析したのは、2024年打ち上げ嫦娥6号が採取したあっち側の石サンプル。28億年前の石の化学成分が示したのは、月の奥深く温度1,100℃にもなる溶岩から形成されたということ。こっち側の石サンプルと比べ、100℃も温度が低いのです。
あくまでも溶岩形成時の話ではありますが、この温度差は長く(もしかしたら今日まで)続いている可能性もあります。放射性崩壊時に、ウランやトリウムなど熱を放出する物が少なく、結果としてあちら側の内部はこちら側よりも温度が低いという仮説をチームは立てました。
過去の研究では、あっち側とこっち側の違いは隕石衝突の影響でこっち側の物質密度が高くなったという説、月誕生初期にまったく異なる温度の小さな星とぶつかりミックスして形成されたという説、はたまた地球の重力が影響している説もあります。
なぜこっちとあっちで地殻温度が大きく異なるのかは、まだ解明されていないものの、嫦娥6号の活躍によって一歩正解に近づいたのかもしれません。
研究論文はNature Geoscienceに掲載されています。