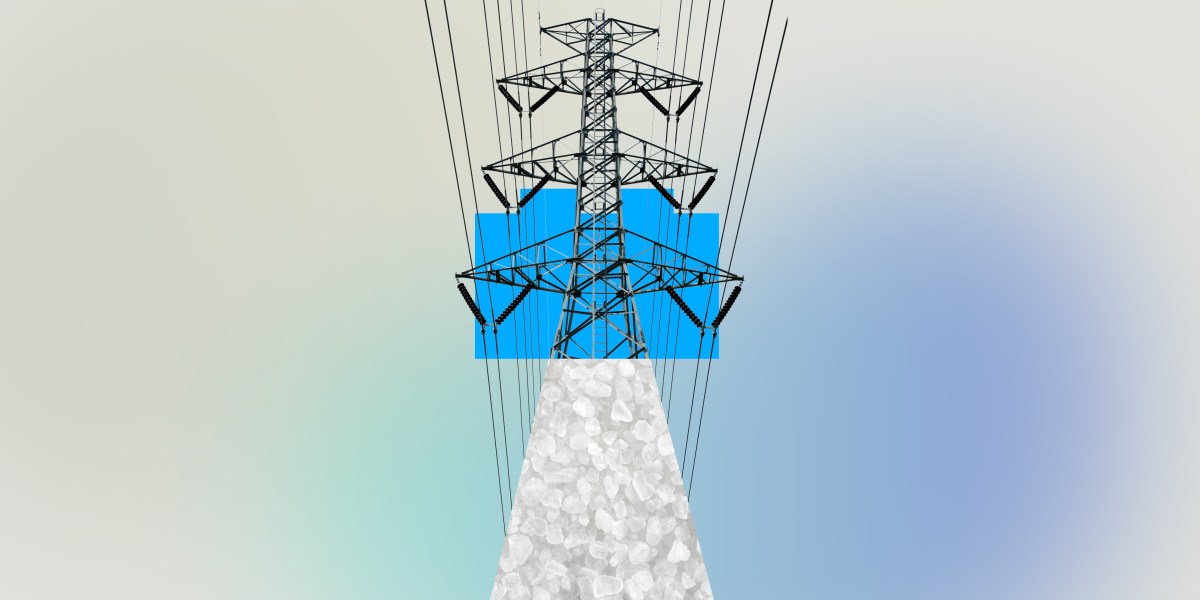“細胞のリサイクル”で老化にブレーキ?50代の新習慣「オートファジー」超入門(HALMEK up)

「同じ生活なのに疲れやすくなった」「体型が戻りにくい」——50代になると、そんな小さな老化の兆候を実感する方が増えます。 老化とは、全身の細胞の機能が十分に働かなくなってしまうことによって、様々な病気になりやすくなることです。 実はその機能維持のために働いているのが、細胞の“リサイクル機能”=オートファジー。 日々少しずつ分解・リサイクルし新しいものと入れ替えたり、有害物を除去したりして、細胞を若々しい状態に保つ仕組みです。 この研究は2016年に日本人研究者・大隅良典氏がノーベル生理学・医学賞を受賞したことでも注目を集めました。ノーベル賞研究から生まれた知見が、私たちの日常習慣に役立つのは大きな魅力です。
50代は更年期の影響でホルモンバランスが大きく変化する時期。 ・睡眠の質が下がる ・筋力が落ちやすい ・代謝が落ちる こうした変化は生理的老化といわれ、病気ではありませんが、オートファジーの低下が関係している可能性があります。 実際に、加齢とともにオートファジーの働きは低下。そして歳を取ってもオートファジーを活性化すると、運動量が回復することが動物実験で分かっています。 さらにオートファジーが低下すると細胞の中に本来あるべきでないもの(老廃物や有害物)が処理されず、認知症や糖尿病、心血管疾患などの加齢性疾患リスクが高まることが分かってきています。動物実験ではオートファジーの活性化によりこれらの疾患が抑えられます。 だからこそ、生活習慣で細胞をメンテナンスし、認知症予防や健康寿命の延伸につなげる視点が大切になります。
次の項目、いくつ当てはまりますか?3つ以上〇がついたら、今日からオートファジー習慣を取り入れるチャンスです。 ・食後はつい満腹になるまで食べてしまう ・夜更かしやスマホで睡眠時間が短くなりがち ・最近、運動不足を感じている ・ストレス発散の時間があまりない ・人と会う機会が減ってきた ・加工食品や出来合いのお惣菜をよく利用する ・朝から晩まで「お腹が空いた」と感じる時間がほとんどない 〇が多い人ほど、オートファジーが低下しているサインかも。 まずはできそうな習慣を1つから試してみましょう。
Page 2
難しいことは不要。次の7つの習慣のうち、できるものから取り入れてみましょう。 1.「プチ空腹」の時間をつくる 食事の間隔を少しあけたり、夕食を軽めに。週末ブランチにして自然に空腹時間を作るのもおすすめ。 2.腹八分目でとどめる 「あと一口食べたい」でストップ。小皿を使うと実践しやすいです。 3.軽い運動で細胞に刺激を エスカレーターを使用せずに階段に、買い物ついでに寄り道して歩数を増やすなどでOK。 4.良質な睡眠を“細胞の修復時間”に 就寝90分前に入浴したり、寝室を20〜22℃に整えると質が上がります。 5.オートファジーを助ける食材を食卓に 納豆や味噌、緑茶、鮭、ナッツ、エキストラバージンオリーブオイルなど。無理なく献立にプラス。 6.ストレスを受け流す習慣を持つ 推し活や趣味に10分没頭するだけでも心身リセットになります。 7.人とのつながりを大切に 友人とのお茶会や地域活動は、心だけでなく細胞にも良い影響が期待されています。
研究で注目されている「オートファジーを高める可能性のある食材」をまとめました。スーパーで買える身近なものが中心です。 ・大豆製品(納豆・味噌・豆腐・豆乳) ・ぶどう・赤ワイン(※飲みすぎ注意) ・ザクロ・ベリー類 ・ナッツ(アーモンド・くるみなど) ・鮭・えび・かに ・緑茶・紅茶 ・エキストラバージンオリーブオイル ・玉ねぎ・アスパラガス・サニーレタス 例:朝は納豆ご飯と味噌汁、昼はサラダにエキストラバージンオリーブオイル、夜は鮭のムニエルに赤ワイン1杯(適量)など、日常の献立に取り入れやすい組み合わせです。
オートファジーは、加齢による“なんとなく不調”を緩やかにする可能性を持つ細胞の仕組み。難しいことはなく、7つの習慣と14の食材から一歩を始めるだけでOKです。 ・極端な断食は不要。プチ空腹の範囲で十分です。 ・アルコールは適量に。赤ワインは1日1杯程度までを目安にしてください。 ・持病や服薬中の方は主治医に相談を。 「週末は朝食を遅めにしてみる」「夕飯を腹八分目に」——そんな小さな工夫から、未来の自分を変えていきませんか? アンチエイジング習慣としても、見た目も気持ちも若々しさを保つ秘訣になります。 ※効果には個人差があります。試してみて異変を感じる場合はおやめください。 監修:UHA味覚糖「オートファジーな習慣」プロジェクト 監修指導(学術):大阪大学名誉教授 吉森保氏
HALMEK up編集部