職場で広がる「距離」と「沈黙」を変えるには 分断を越える5つの鍵と対話の4ステップ
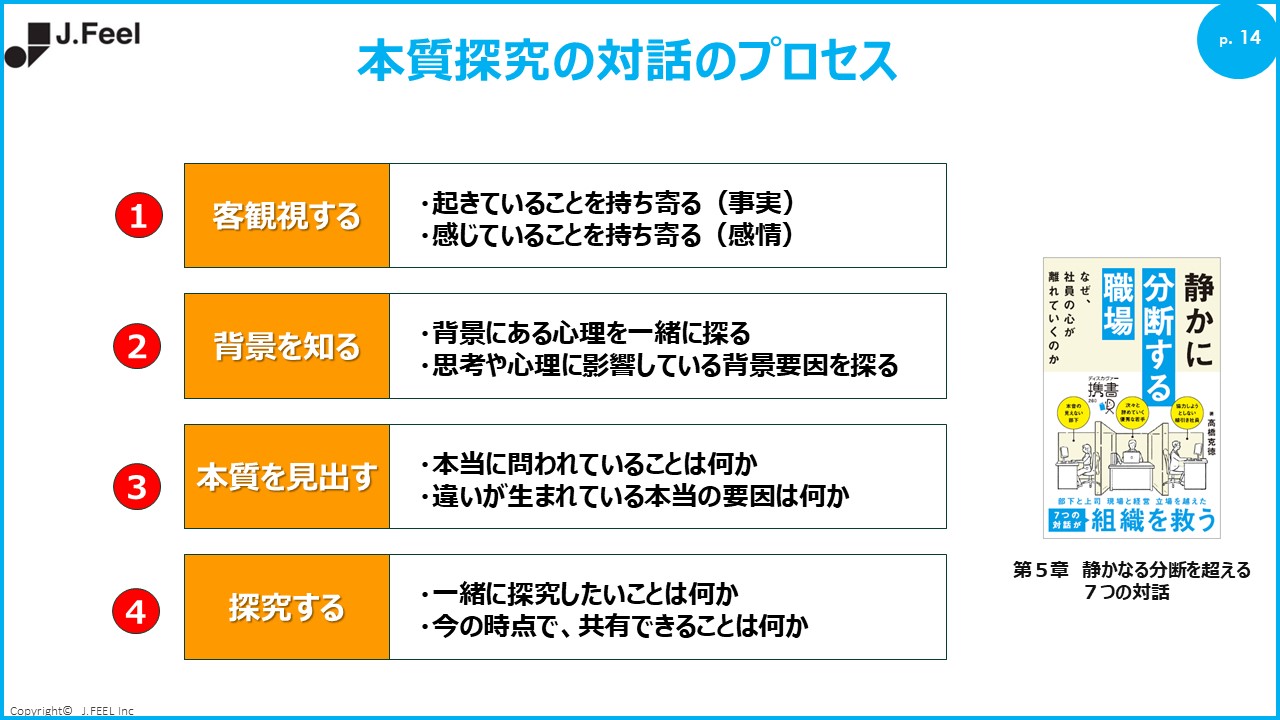
高橋克徳氏(以下、高橋):いやいや、大学生に「仕事にやりがいを求めますか。それとも働きやすさを求めますか」と言ったら、もうほぼ9割ぐらいの子は「働きやすさのほうが大事で働きがいは求めません」と回答したんですよね。
「なんで」と聞いた時に、やはり自分が働きがいを持って生き生きしている姿のイメージが持てないんですよ。学生時代もみんなでがんばって何かを達成したとか、特にコロナ世代の子たちはあまりそういう経験がない。みんなで一緒にやる中で、ものすごく生き生きした自分に出会えたという経験が少なかったり。あと20代の子に聞いても「そんな先輩、どこにもいません」というのがやっぱり多いんですよ。だからそうやって見た時に、「やりがい持って会社に入っていくよね」というのは、たぶんもう山中さん世代が言うことで。山中:(笑)。
高橋:もう、前提、出発点が違うんじゃないかなと。
青木美帆氏(以下、青木):私はやる気がありましたよ(笑)。
高橋:そうなんだ、当時、僕もありましたよ。でもやっぱりちょっとそこは変わってきている気がするけどなぁ。
山中:問題は、働きがいがイメージできないことなんでしょうね。でも入社してから、失敗したりしながら働いていく中で、イメージってできていくものが大きいのかなとも思ったりするんですよね。
働く前って別に「これが、働きがいが」ということよりも……どうなんだろう。高橋:「仕事っておもしろいじゃん」って言ってくれる先輩がいるかいないかが、環境の中でやっぱり大きい気がする。
だからその人たちが疲弊しているだけでね。もう5時になったらみんな帰って、飲み会が減ったのは僕はいいことのような気もするし。でも一方でそういう場で話してくれた大切な思いみたいなものを聞かされることもなくなっていく。そうなるとやっぱり思いは育たないじゃない? っていう気はするけど、どうだろうね。山中:やっぱりその経験も少ないのかなとはちょっと思っています。実際に会社に入って、そこで新しいことやいろいろなことにチャレンジしていく中で、周りとの関係性がしっかりできていたら、そこに対してフォローがあったり、フィードバックがある中で一歩踏み出せたり、がんばれたりできます。
さらにはそこできちんと認知してもらえることによって「これでいいんだ」とか「あ、がんばれているんだ」みたいなものがあると、その分やりがい・働きがい経験みたいなものがあるような気がするんですけど。それが生まれにくくなっているのかなというのは、僕も本の中でも書いたので、あるかもしれないと(思います)。青木:あと、ネガティブな情報もすごく多くなっているなと思っています。私はSNSが大好きなのでいろいろなSNSを使っているんですが、例えばInstagramだとやっぱりプライベートがものすごく充実している人こそ輝いて見えたり、Xだと「こんなに大変で鬱になりました」とか「こういうことをやると鬱になります」という情報が蔓延していたりするので、そういう影響もあるのかなぁとは(思います)。特に若い子たちは、社会に出る前にそういう情報に触れる機会が増えているので、ネガティブな認識だったり、「自分を守らなきゃ」という状態で(会社に)入っているというのはあるかもしれないですね。高橋:そういうネガティブな気持ちになってしまうような社会環境があるから、将来に対する不安もけっこうあると思うんですね。それに会社という場所に入ったら意外といい感情ではあまり交流しなくて、ネガティブな感情だけはなんとなく見え隠れしている。
こうなっていくとやっぱりそこに思いを持てなかったり、働く意味や意義を実感できなかったり。なんとなくわかる、わかるんだけど。次にちょっと考えたいんですけど、この状態は本当に良くないんでしょうか。たぶん若い人たちからすると「いいじゃないですか」ってね。「やっぱりある意味、人との距離感が近すぎたんです」「近いとストレスもかかるし、負荷もかかる。だったら一定の距離を置いて働いたほうがいいですよね」というような答えがたくさん返ってくる気がするんです。実際僕も、「こんなの今更。静かな分断している職場がいいに決まってるじゃないですか」という書評を見ました。高橋:良くないと言い切っていいのかわからないけれど、いろいろなことに対して、ちょっとこのままで続けていいのかなと思うんですが、どうですか?……(笑)。青木:相手と向きあうことを諦めるとか、対人的な距離、心理的な距離が開いたという話があったと思うんですね。コロナでそれが一気に加速したと思っています。これは、心理学的に見ると、短期的には対人関係のストレスをかなり減らすというポジティブな側面も確かにあるんです。なので、すべてがネガティブではないとは思っています。
ただ、じゃあこのままでもいいのかというと、そうとは言い切れないなと私は思っています。やっぱり長期的に見ると、人と人との距離がかなり広がってしまっているので、人それぞれが孤立しやすい。そうするとメンタルヘルス不調という問題にもなってきます。個人の問題としては(ポジティブな)ピアサポート、ピアラーニング、ピアプレッシャーといった良い相互作用が失われているんですよね。問題は必ず起きるじゃないですか。起きた時に援助希求をしにくくなってしまっています。対人関係のストレスが減った反面、何かが起きた時に悩ましい時間が増えてしまったり、問題解決にすごくエネルギーが必要になってしまったり、結局個人個人が困ったりということもあると思います。また、例えば今、組織や社会全体を見ても、イノベーションを起こそうみたいなことがすごくあると思います。イノベーションに必要な創造性という点で、やっぱり良好な人間関係が一番必要と言われているんですね。しかし分断が起きてしまっていると、人間関係の質が保てなくなってしまったり、イノベーションが起こりにくかったり、社会全体としての活気を失ってしまったりということにもつながっていくんじゃないかなと思っています。高橋:なるほど。今の話、心理的な観点ですが、日本の生産性が低い原因は何かと言った時に、無駄が多い、無駄なことをやっていると言われています。その無駄な時に一番多いと言われてるのが、手が止まっている。つまり、相談したいのにできなくて自分で抱え込んでいる時間がすごく多いんです。「ちょっと聞けば」とか「ちょっと教えてもらえば」とか、相談できれば済むことができないと思って、ためらっている時間が1日の中ですごく多いんだって。これってやっぱり、日本人の働き方の要因として一番変えなきゃいけない部分の1つかなと思うんですよ。そこの根幹にあるのは、先ほど言ったように、ちょっと距離感が生まれて、みんなも忙しそうだし、声かけていいのかなとか、自分がわかってないと否定されるんじゃないかとか。そういう心の抵抗感があるとますます距離を取ってしまう。そのほうが楽だよと言われて閉じこもってて、気がついたら相談に乗ってくれる相手がいない。助けてくれる人がいない。高橋:自分の目の前の仕事ができているうちはいいけれど、そうじゃない時に急に止まってしまう。ここからどんどん悪循環に入っていっちゃう気がするんですよね。山中さんはどう思う?山中:ご存じの方もいるかもしれませんが、関係の質によって思考の質が変わって行動の質が変わって結果の質が変わるという成功循環モデルかなと思うんです。
今の話って、マイナスから0と、0からプラスの話かなと思うので、相談しあえる関係があったら仕事を止めている時間がなくなって思考の質が上がるというサイクルだと思います。先ほどのイノベーションみたいな話も「本当はこうおかしいんだけどな」とか「こうやったらもっといいのかな」と思っていることを気軽に言えるかどうかって、すごく大事だと思うんです。お互いに諦めている状態だと「言っても仕方ないな」ってなると思うんですよ。そうすると、何かを変えていったり、新しいものを生み出していくきっかけが生まれない。0からはプラスは生まれない。そんな話なんだろうなと思って聞いていました。高橋:なんか言いたそう?……(笑)。
青木:そうですね、イノベーションのところでちょっとまた別の話をしたくて。
高橋:いいよ、いいよ。
青木:ちなみになんですけど、生産性を高める時には、相手の人の新たな発想にお互いが気づきあえるかというのも、すごく重要らしいんですね。やっぱりある程度お互いを見ている、関わっている、注意を向けているという状態がベースにないと、(生産性が)生まれないというのはすごくわかっています。先ほどのネガティブをあまりにも避けるという傾向も、実はイノベーションを起こしにくい状況を作っています。なぜかというと創造性を高めるのにもう一つ必要なのが危機感なんですよね。なので、危機感を避けていってしまうと、イノベーションを加速させる要因を失うというところにつながっているなと思って。高橋:生産性って、目の前の効率を上げていくことみたいに言われるんですが、本当は効率性×創造性ですよね。
要するに何をやるかとか、やり方を変えるということがないと生産性は本当は上がらない。今のやり方をとにかくもっとスピーディにするとか、一人ひとりもっとがんばりなさいというのがなんとなく生産性のように聞こえるんだけど、それは効率性の問題なんですよ。より良く働いていくためにも、そういう意味で創造性を、もっと日常的に発揮できなきゃいけないと思うんです。じゃあどうしたら創造性は高まるかというと、やはりいろいろなやり方があるということを知らなきゃいけないし、そうは言ってもいろいろな矛盾や壁があるわけですよ。それをどうやったら超えられるかという対話がない、あるいはそういう思考がないと新しいやり方は見つからないはずです。そこを避けてしまうと、結局今やることをずっとやり続けなきゃいけないし、その中で生産性と言われると結局効率を上げるしかない。これが今起きていることなんじゃないかなと(思います)。そういう中で狭くなって、今、自分が知っている範囲の中でどうやってより良くするかをひたすら毎日やり続けていくとなっていくと、やはり心を閉じちゃうよね。いろいろなものとつながることで実は助けてもらえたり、知恵が出てきたり、いろいろなやり方を発見できたりする可能性があるのに自分から諦めてしまうことにならないのかなと。そんな感じがすごく強くします。



![[プロモーション]【500人調査】片付けが進まない背景に 「捨てるかどうか」の判断疲れ 「片付け・整理整頓に関する意識調査」を実施](https://image.trecome.info/uploads/article/image/458d3fbb-219e-40fc-a458-1b7a90a07fa8)