「ぼーっとする時間」が記憶の定着率を上げる。短期記憶を長期記憶にする方法
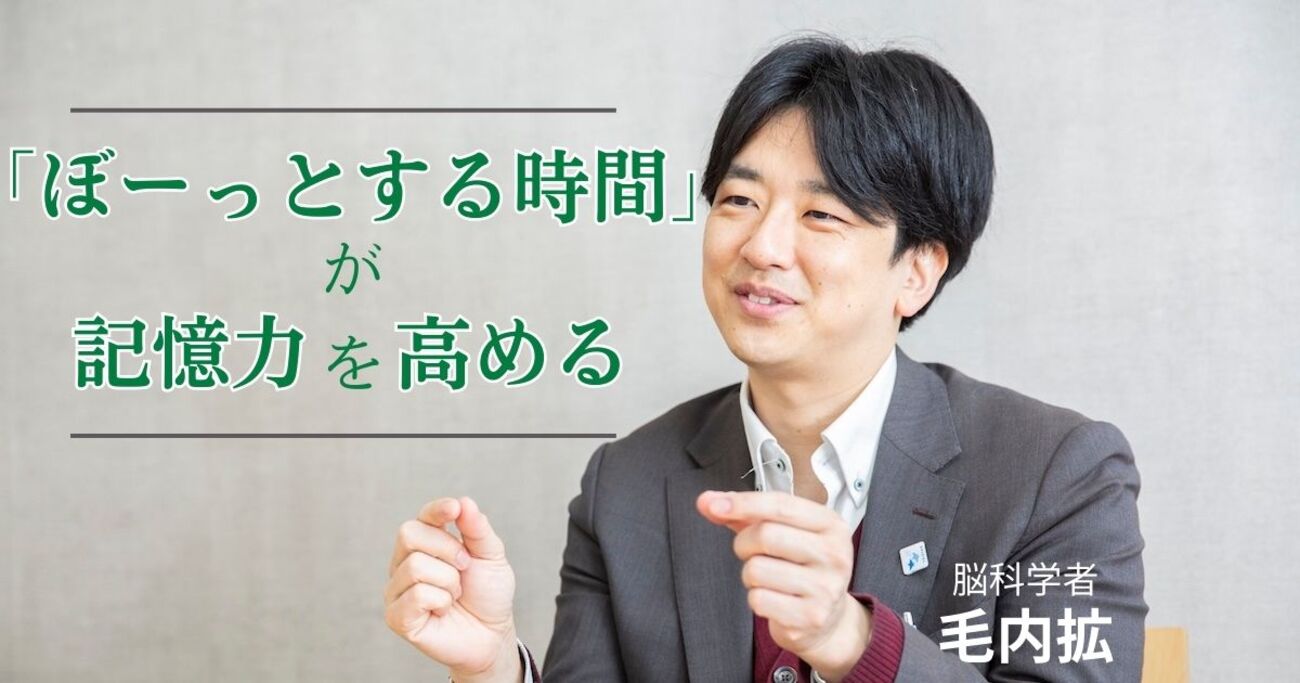
インプットした知識や経験を活かすには、それらを思い出せることが前提になります。せっかくなにかを学んでも、記憶に残らなければ意味がありません。記憶の定着率を高めるには、どうすればいいのでしょうか。お茶の水女子大学基幹研究院自然科学系助教である脳科学者の毛内拡先生は、「記憶の仕組み」を知って活用することが重要だと言います。
構成/岩川悟 取材・文/清家茂樹 写真/石塚雅人
【プロフィール】毛内拡(もうない・ひろむ)1984年生まれ、北海道出身。お茶の水女子大学基幹研究院自然科学系助教。2008年、東京薬科大学生命科学部卒業。2013年、東京工業大学大学院総合理工学研究科博士課程修了。博士(理学)。日本学術振興会特別研究員、理化学研究所脳科学総合研究センタ一研究員を経て、2018年より現職。生体組織機能学研究室を主宰。脳をこよなく愛する有志が集まり脳に関する本を輪読する会「いんすぴ!ゼミ」代表。「脳が生きているとはどういうことか」をスローガンに、マウスの脳活動にヒントを得て、基礎研究と医学研究の橋渡しを担う研究を目指している。『心は存在しない』(SBクリエイティブ)、『なぜか自信がある人がやっていること』(秀和システム)、『運のいい人がやっていること』(秀和システム)、『「気の持ちよう」の脳科学』(筑摩書房)、『すべては脳で実現している。』(総合法令出版)、『脳研究者の脳の中』(ワニブックス)、『面白くて眠れなくなる脳科学』(PHP研究所)など著書多数。
記憶にはいくつもの種類がある
ひとことで「記憶」と言っても、その種類はさまざまです。記憶を分類する大きな軸のひとつに、「言語化」できるかどうかがあります。言語化できる記憶のうち、歴史の年号や数学の公式のように、普遍的事実などに関する記憶は「意味記憶」と呼ばれます。これは、いわゆる「知識」のことです。
また、言語化できる記憶には、「あのときはあんなことがあったな」「あれを食べたな」「あんな気持ちだったな」というように思い出す、「エピソード記憶」もあります。
一方、言語化できない記憶のなかには、たとえば一度自転車に乗れた人はしばらく乗っていなくても自転車に乗れるように、「体が覚えている記憶」もあります。これは、「手続き記憶」と呼ばれています。
ほかには、「プライミング記憶」というものもあります。「たこ焼き、道頓堀、吉本新喜劇」という字を見たあとに「大○」と見ると、なぜか「阪」の字を入れたくなりますよね。これが、直前に見聞きしたものが記憶の想起に影響を与える、プライミング記憶と呼ばれるものです。
ただ、こういった記憶のすべての入り口は、「短期記憶」です。ワンタイムパスワードのような数字を一時的に覚えて、用が済んだらすっかり忘れてしまうような、文字通り短期的にしか残らない記憶です。
その短期記憶のなかで、脳が「これは重要だ」「きちんと覚えておこう」と判断したものが、ずっと覚えている記憶である「長期記憶」になります。
物事を覚えたあとに思い出すための「フック」を増やす
ビジネスパーソンとしてより重要なのは、言うまでもなく長期記憶でしょう。いくら読書をしても内容をすぐに忘れてしまっては時間と労力の無駄ですし、斬新なアイデアを生むようなひらめきも、それまでに脳内に蓄積された情報どうしの組み合わせによって起こります。
短期記憶を長期記憶にする、記憶の定着率を高めるためのコツのひとつが、物事を覚えたあとに思い出すための「フック」を増やすことです。と言うのも、脳は見聞きした情報をそのまま覚えるのではなく、なんらかのカテゴリーに分類し、そのなかで情報どうしを関連づけて記憶するからです。
たとえば「歌手」というカテゴリーを脳がつくったとして、そのなかで「スイートピー」なら「松田聖子」、「マリーゴールド」なら「あいみょん」というように、情報どうしを関連づけて覚えます。そのため、関連づけて覚える、あるいは関連づけて思い出すために、例のような花の名前のほかにも「フック」となる情報が多ければ多いほど覚えやすい、思い出しやすいということになるのです。
勉強で成果を挙げるには、毎日違うカフェで勉強するのがいいという話を聞いたことはありませんか? その根拠も、フックが増えることにあります。いつも自宅のデスクで勉強していると、なにか特別な出来事が起きることはほとんどありません。
一方、毎回違ったカフェで勉強すれば、「この勉強をしたのは、雨に降られて初めてのカフェに駆け込んだときだった」「ほかの店にはないこんな飲み物を飲んだ」「隣の人がこんな奇抜なファッションだった」というように、覚えたいことと関連づいてフックになる情報が増え、その結果として記憶の定着率が高まるのです。
短期記憶が長期記憶に変わるのは、脳が休んでいるとき
また、記憶の定着率を高めるには、「休む」ことも非常に重要です。休んでいるときにこそ、脳が短期記憶を長期記憶にしているからです。
自分が起きていて能動的になんらかの行動をしているときには、その目の前の作業に脳も集中しています。すると、短期記憶を長期記憶にするという作業に脳がリソースを割けません。
対して、眠っているときや、休憩してなにも考えずにぼーっとしているようなときに、脳は短期記憶のなかで「さっき入力された情報はどのようなものだったかな?」「これはもう必要ないから忘れてしまおう」「これは重要だからきちんと覚えておこう」と選別しています。
「休む」とか「ぼーっとする」と言うと、「サボっている」というようにネガティブな認識をする人もいるかもしれません。でも、休むからこそ記憶できるのですから、記憶力を高める観点から見ると、適切にきちんと休むことは最重要事項だと言ってもいいくらいです。
日本では、「働き方改革」の推進もあって、データ上では労働時間は減少傾向にあります。しかし一方では、人手不足の問題等により、仕事をもち帰ったり勤務時間外にも仕事をしたりと、「見えない労働時間」が増えているケースもあります。そのような状況のなかで記憶力を高め、ひいては仕事で成果を挙げるためにも、自らの「休み方」についてあらためて考えることも大切なのだと思います。
【毛内拡先生 ほかのインタビュー記事はこちら】「IQが高い人ほど頭がいい」は時代遅れ。本当に頭のいい人の脳には特徴があった脳科学者が明かす「脳の持久力」の高め方。「失敗したほうがいい」って本当?(※近日公開)
【ライタープロフィール】清家茂樹(せいけ・しげき)
1975年生まれ、愛媛県出身。出版社勤務を経て2012年に独立。ジャンルを問わずさまざまな雑誌・書籍の編集に携わる。



