【RSウイルス】出産前に知りたい基礎知識 2歳までにほぼ全員が初感染、乳児は重症化しやすく将来ぜんそくの発症の可能性も〈PR〉
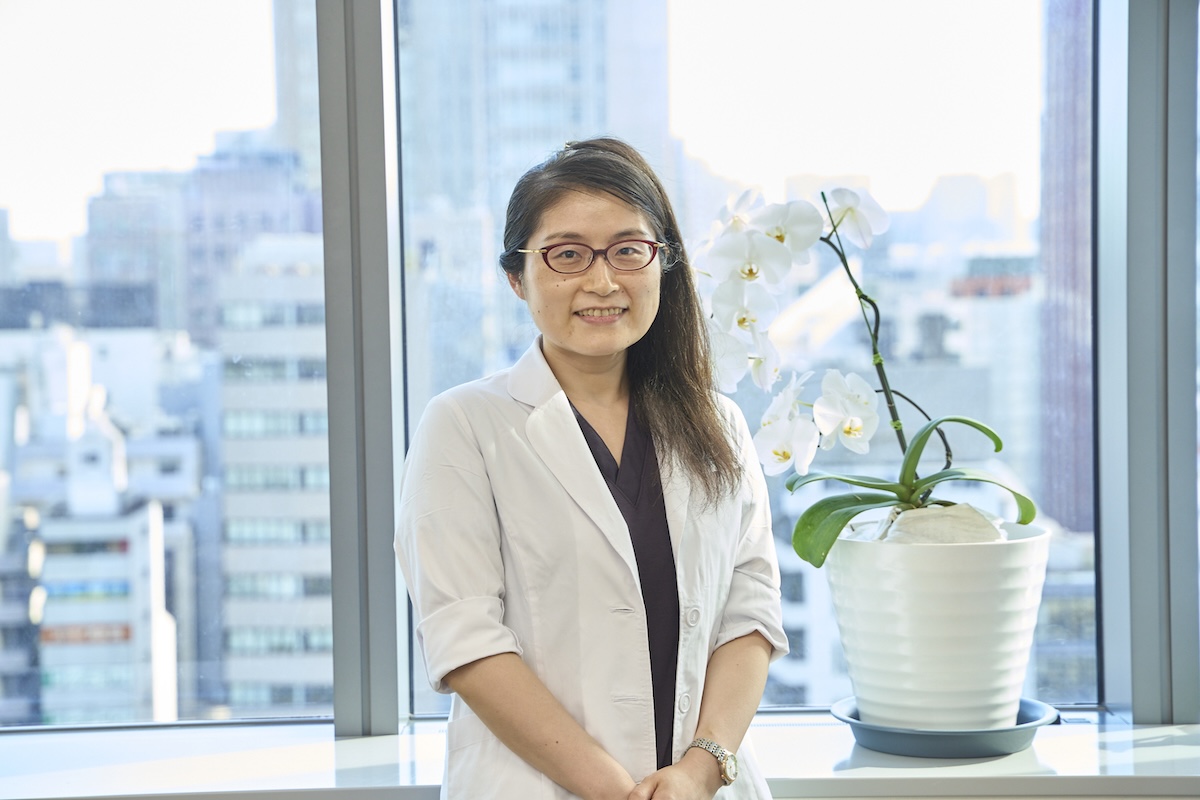
―RSウイルスは乳幼児が入院するおもな原因となるウイルスと聞きました。まずはRSウイルス感染症はどんなものか教えてください。
羅ことい先生(以下、羅先生) 「RSウイルス感染症」は、RSウイルスに感染することによっておこる呼吸器の感染症の一つ。くしゃみや咳による飛沫感染、ウイルスが付いたものを触ることなどによる接触感染でうつります(※3)。世界中のどこにでもいるごくありふれた風邪ウイルスで、1人が感染するとまわりにいる3人程度に感染が広がるといわれ、集団感染を起こしやすい(※4)です。また、生後1歳までに半数以上、2歳までにほぼ全員が感染する(※5)ことがわかっています。
―感染するとどんな症状が現れるのでしょうか?
羅先生 4〜5日の潜伏期間の後、高齢者を除く大人の場合は発熱、鼻水などの風邪症状で良くなるケースがほとんどですが、乳幼児では重症化することがあります。重症化した場合は、気管支炎や肺炎のほか、強いせきやゼーゼーとした呼吸、呼吸困難などが現れることがあります(※5)。
実際に、RSウイルスは全世界的にも乳幼児が肺炎や気管支炎になって入院する主な理由の一つであり、乳幼児の肺炎の5割を占める(※6)と言われています。国内では2歳未満でRSウイルス感染と診断される子どもは毎年10万人以上と推定されていて、その4人に1人は入院を経験しています(※1)。
一度かかったからといって二度と感染しないということはなく、誰もが何度でも感染する可能性があります。一方でRSウイルス感染症に対する確立した治療法はありません。そのため症状を和らげる対症療法や呼吸困難を助ける治療が主体となります。
6カ月未満で感染すると重症化しやすい
―乳幼児は特に重症化の可能性が高いのですね。
羅先生 そうです。なかでも重症化の可能性が高いのが、初めて感染する生後6カ月未満の赤ちゃんです。実際に入院した2歳までの子どもの月齢分布を見ると、6カ月未満の割合が多く、入院のピークは生後1〜2カ月でした(※1)。低月齢で重症化した場合は、無呼吸発作や急性脳症を起こしたケースも確認されています(※3)。そのほか早産・低体重で生まれてきた赤ちゃんや、肺や心臓に病気があったり、生まれつき免疫不全やダウン症のお子さんのほか、基礎疾患を持つ成人、高齢者でも重症化する危険性が高くなることが知られています(重症化する可能性がある因子=重症化因子)(※1)(※7)。
子どもは成長過程で少しずつ免疫を手に入れる
―小さな赤ちゃんが重症化しやすいのは、免疫力がまだ弱いからでしょうか?
羅先生 それも理由の一つです。赤ちゃんは成長の過程で感染を繰り返すなかで、少しずつRSウイルスに対する免疫が作られていきます。そのため、免疫を十分に持たない赤ちゃんでは重症化しやすいのです(※1)。また赤ちゃんの気管支は小さく細いため、炎症が広がりやすいことも理由と考えられます。
―赤ちゃんはお母さんからもらう自然の免疫で守られているから病気をしないと聞きますが…。
羅先生 確かに、生まれたばかりの赤ちゃんは、「母児免疫(母子免疫)」といって、胎盤を通して妊娠期間中にお母さんから譲り受けた免疫で守られています。けれどこの母児免疫(母子免疫)は万能ではなく、全ての病気から守ってくれるわけではないのです。さらに人の免疫力には個人差があり、お母さんがもともと免疫力が弱い場合などは、赤ちゃんに伝わる免疫が少なくなることもあります。
重症化すると、将来のぜんそく発症のリスクも
―RSウイルス感染症は、ぜんそく発症のリスクにも関連があると聞きました。
羅先生 そうなんです。海外の研究では、乳児期にRSウイルス感染症により入院した経験があるお子さんは、そうでないお子さんと比較して7歳児においてぜんそくを発症する確率が高かったことが報告されています(※2)。
7歳児におけるぜんそく発症率の比較(※2)
対象:1989年12月~1990年4月にRSウイルス感染による細気管支炎で入院した乳幼児47例と性別、年齢、居住地域を合わせた対象乳幼児93例 方法:患者及びその家族に対する7歳時点の追跡調査によって喘息の発症状況を検討した。3回以上の気管支閉塞を医師が確認 した場合を喘息と定義した。
また、ご家族への影響も見逃せません。先ほどお話ししたとおり、入院する乳幼児の9割は基礎疾患がないため、ご家族が重症化に対する心の準備がないまま突然入院するケースも少なくないのです。さらに日本では親が付き添い入院を求められることも多いため、精神的・身体的な負担だけでなく、仕事の調整などの経済的な負担、兄弟姉妹の育児への影響もあります(※8)。このようなご家族の社会活動に影響を与えることも、大きな課題だと感じています。
RSウイルス感染症による保護者・家族への負担(医師による評価)(※8)
目的:小児科医のRSウイルス感染症の診断・治療・予防に対する現場の認識を把握する。 対象・方法:2022年11月27日~12月5日に、過去1年間に3名以上のRSウイルス感染症患者の治療経験があり、外来、入院、または救急科で現在治療を行っている日本人小児科医300名を対象として、RSウイルス感染症による負担や影響に関するアンケート調査をwebにて実施した。 本研究の限界:①本調査の参加者の募集は特定のサービスを定期購読している集団であり、国内の小児科医全体を代表していない可能性がある。
②保護者への負担は小児科医の視点から回答した内容であり、実際に保護者が感じている負担とは異なる可能性がある。など。



