幼少期のトラウマは脳を物理的につくり変える──心理学者が解説する2つのメカニズム(Forbes JAPAN)
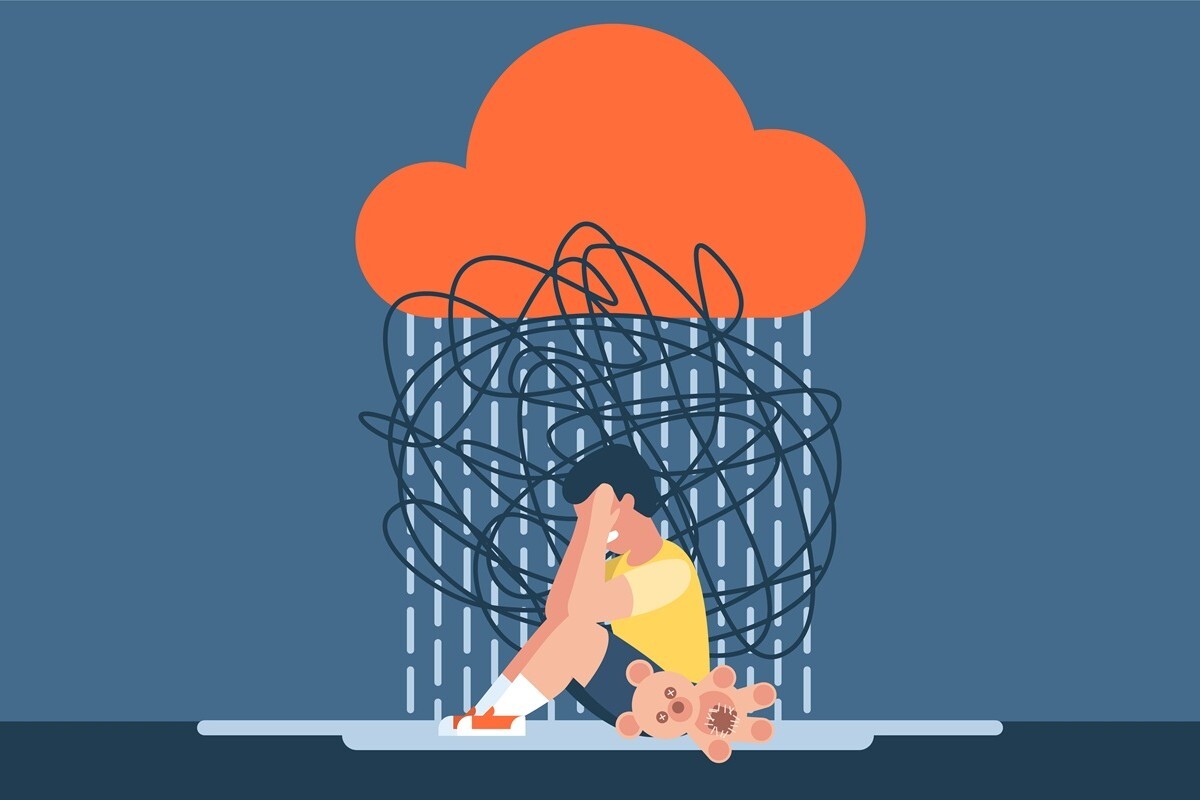
■2. トラウマは、脳の白質を疲弊させる 慢性炎症が何を引き起こすかを理解するには、脳を個別の部位の寄せ集めではなく、街のようなものと考えるとわかりやすい。この街は、主に2つの素材でできている。白質と灰白質だ。 ごく単純にいえば、白質は脳を円滑に機能させる役割を担っている。白質は無数の長い繊維からなり、脳の最も重要な部分(灰白質)同士が相互にコミュニケーションをとることを可能にしている。 街のたとえでいえば、灰白質は街の地区にあたり、ここにはあなたの思考や感情が「住んでいる」。白質は、思考や感情が移動に利用する幹線道路だ。 先述の2022年の研究において、幼少期に困難を経験した双極性障害患者には、脳の白質に混乱の兆候がはっきりと見てとれた。具体的には脳スキャンの結果、拡散異方性(fractional anisotropy; FA)が低レベルであることが判明したのだ。拡散異方性とは、白質を構成する神経線維がどれだけ明瞭に構造化されているかを定量化する指標だ。 端的にいえば、先に説明したような慢性炎症が、白質の永続的損傷を引き起こし得るということだ。たいていの場合、これは脳内のコミュニケーションシステムが、トラウマをもたない人のそれと比べて効率的に機能しないことを意味する。 損傷がなく、整然と構造化されている白質は、適切に設計されメンテナンスされた幹線道路のように機能する。つまり、情報が迅速かつ効率的に脳内を移動できる。しかし、白質のつながりが途絶えたり、絡まったり、損傷したりすると、シグナル伝達の遅延や誤送信が起こる。いわば、車が通行する道路に陥没穴や亀裂があり、路面標示がかすれているような状態だ。 幼少期に頻繁にトラウマにさらされた脳は、まさにこのような状態になる。荒れた道路が相互につながりあい、車の行き来が難しくなるのだ。このような、脳の幹線道路網が「荒れた」状態は、実生活における機能に悪影響を及ぼす。 先の研究によれば、白質の構造的均一性が損なわれることで、脳の主要部位のあいだのコミュニケーション不全が生じる可能性がある。これにより、脳内の情動中枢と、論理的思考や行動制御を司る部位のあいだのコミュニケーションが困難になり、以下のような機能に問題が生じかねない。 ・情動制御 ・睡眠と覚醒のサイクル ・脅威の検出 ・高次の思考(計画、衝動抑制、意思決定など) 結果として、こうした問題を抱える人は、理由もわからないまま、常に緊張状態に置かれるかもしれない。論理的には安全だと判断すべき理由がすべて揃っている状況でも、気持ちを落ち着けることができないのだ。そして、心身ともに疲労困憊しているにもかかわらず、夜に横になるとひどく目が冴えてしまう。 どんなに小さな、取るに足らない意思決定でさえ、耐えがたい重荷に感じられるかもしれない。それは、健康な状態であればこうしたプロセスを何の労力もいらない容易なものにする脳内の回路に、遅延や回り道が頻発するせいだ。 残念ながらこうした反応は、トラウマから長い月日が経ち、大人になったあとも長く残ることがある。 だからといって、これは脳が「壊れて」いるとか、「機能不全」に陥っていることを意味しない。脳が危険と炎症に対して、設計に組み込まれた唯一の方法で順応しただけのことだ。すなわち防御回路を強化し、自らを守ったのだ。 トラウマに直面したとき、脳は柔軟性よりも生存を優先するという思い切った決断を下す。たとえそのせいで、のちの人生において日常の機能が、少しばかり困難になるとしても。 これは脳の回復力を示唆するものであり、けっして故障ではないのだ。
Mark Travers



