東大合格者が紹介!子どもに「勉強なんてなんの役に立つの?」と言われたらおすすめしたい本5冊(東洋経済オンライン)
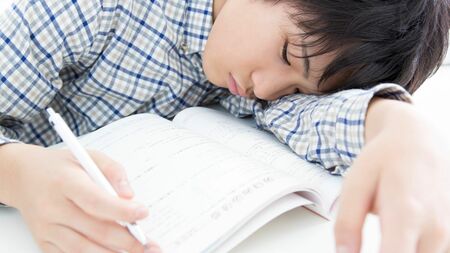
■「勉強は意味がない」と言う子におすすめしたい本5選 今回は、「勉強する意味がない」と感じている子どもにこそ読ませたい、あるいは親子で一緒に読みたい“処方箋のような本”を5冊紹介します。 学校で学ぶ意味を、社会に出てからのリアルな視点で教えてくれるラインナップです。 1. 『親子で学ぶ どうしたらお金持ちになれるの? ――人生という「リアルなゲーム」の攻略法』 小学生や中学生の子どもに、科目ではない「社会」を知ってもらうための1冊目としておすすめしたいのが、『親子で学ぶ どうしたらお金持ちになれるの?』です。タイトルの通り親子で読める構成になっているので、読みやすい本だと言えます。この本では、「お金」「社会」「勉強」を“人生の仕組み”として楽しく学べる本です。
たとえば、「なぜ銀行にお金を預けると利息がつくの?」「働くってどういうこと?」といった、子どもが抱きやすい疑問に対して、論理的に、そしてやさしく説明してくれます。 大人が読んでも、「なるほど、そういう構造だったのか」と納得できる内容で、家庭の“経済教育”にも最適です。 また、この本の良さは、勉強=知識の積み重ねではなく、世界を読み解くための武器だと気づかせてくれるところだと思います。知識量を得るためのものなのではなく、世の中をしっかりと深く理解し、社会の仕組みを読み解く前提になるのが勉強である、というのをしっかり説明してくれます。子どもが社会に興味を持ち、「知ることが楽しい」と思えるきっかけになる一冊だと言えます。
Page 2
2. 『東大の先生! 文系の私に超わかりやすく数学を教えてください!』 中高生向けですが、イラストが多いので賢い子なら小学生でも読めるかもしれないのが、この『東大の先生! 文系の私に超わかりやすく数学を教えてください!』です。タイトルの通り、東京大学の西成活裕教授が、「数学の考え方がどう社会に生きるのか」をやさしく語っており、「文系だから数学苦手でいい」と思っている高校生や大人に対しても刺さるような面白い一冊です。
ここでは、数学は「正解を出す学問」ではなく、「筋道を立てて考える学問」だと説明されています。数学の論理構築力が、いったいどんなことに役に立つのか。論理的に推論を積み重ね、答えへの階段を積み上げていくような「多段的な思考」を教えてくれる一冊です。 “文系”と“理系”を分ける境界線を軽やかに越えて、誰もが「考えることの楽しさ」を感じられる内容になっているので、「数学なんて役に立たない」と言う子どもにこそ読ませたい一冊です。
3.『学校教育は最強のビジネススキルである』 次は中高生向けの一冊で、社会に出てから活躍して、年収の高い職業に就きたい! と考えているような人向けの一冊です。 タイトルからして衝撃的ですが、「勉強=社会人の基本」であり、仕事ができる人は結局、学校の勉強をしっかりと応用することができている人だ、ということを教えてくれる一冊です。ビジネスの現場で解決を求められるシチュエーションを紹介して、実はそれが、学校で学ぶ内容と驚くほど一致している、ということが語られています。
たとえば、営業で相手のニーズがわかる人は、国語で“文の構成”を理解している人。「数字に強い人」は、数学で“前提条件を整理して筋道を立てる力”を鍛えてきた人だ、などなど。 つまり、学校の勉強は“科目の知識”そのものではなく、「考え方の訓練」だったということを教えてくれます。この本を読むと、子どもも大人も「勉強の延長線上に仕事がある」という実感を持てるようになれます。ぜひ読んでみてください。 4. 『戦わずして売る技術 クリック1つで市場を生み出す最強のWEBマーケティング術』
Page 3
中高生で、数学が苦手な人に対して読んでもらいたいのがこの一冊です。「戦略的思考=数学的思考」だと気づかせてくれる本になります。別に学校の勉強について触れられているわけではないのですが、先ほどの『学校教育は最強のビジネススキルである』と併せて読むと、「ああ、自分の今学んでいることは社会に出てからモノを売るのに役立つんだな」という実感を持たせてくれると思います。 この本の著者の木下氏は、競争を避け、視点を変えて“戦わずに勝つ”方法を説きます。これはまさに、数学で学ぶ“場合分け”や“マトリクス思考”そのものです。
さらに、数字を数字として終わらせて、「伸びた」「売れた」というような短絡的な思考で完結させるのではなく、数字の裏にある、「顧客の置かれた状況」「何がうまくいっていないのか」などを正しく分析していくための思考も書かれており、数学の一歩先には何があるのかということを感じさせてくれます。 「勉強で培った考え方が、社会でどう応用されるか」を生きた事例で教えてくれるという意味で、おすすめの一冊です。 5. 『地政学が最強の教養である』
最後は、中高生のなかで、「社会の勉強なんて、暗記ばかりでつまらない」と感じている子どもに読ませたい一冊です。『地政学が最強の教養である』は、「なぜこの国とこの国が対立しているのか」「なぜ戦争は起こるのか」といった“リアルな社会の構造”を解き明かしてくれます。 社会の教科書で学ぶことは、世界のニュースを理解するための前提知識です。為替の変動も、資源の争いも、歴史や地理の知識があって初めて「なぜ」が見えてくるものです。この本は、社会の勉強が単なる暗記ではなく、“世の中を生きる力”になることを体感させてくれる一冊になっています。
また、地理学だけではなく、歴史的な背景も踏まえた上での知識を教えてくれるというのもこの本が面白いポイントです。「過去の出来事から考えると、今後こうなっていく可能性が高い」というような、歴史を踏まえた未来の予測の立て方を教えてくれて、これからのニュースを読み解く上でいかに歴史の勉強が必要なのかを教えてくれる一冊です。 ■勉強とは生きる力を育てるもの 言うまでもなく、勉強の意味とは、「テストで点を取ること」ではなく「自分の頭で考える力を鍛えること」だと言えるでしょう。
ですから、子どもが「勉強なんて意味ない」と言うとき、それは“目に見える成果”しか勉強の価値として感じられていないからそういう発言をしている可能性が高いわけです。けれど、社会に出てから求められるのは、正解を覚える力ではなく、「考える力」「整理する力」「仮説を立てる力」ですよね。 今回紹介した5冊は、その“見えにくい学力”を、社会の文脈からわかりやすく示してくれます。親子で一緒に読むことで、「勉強とは生きる力を育てるものだ」という原点に気づけるはずです。ぜひ読んでみてください。
西岡 壱誠 :ドラゴン桜2編集担当



