明日使える“論文の雑学” ちょっと変わった論文たち 「本文0文字」「ネコが書いた」「著者が5000人超」など
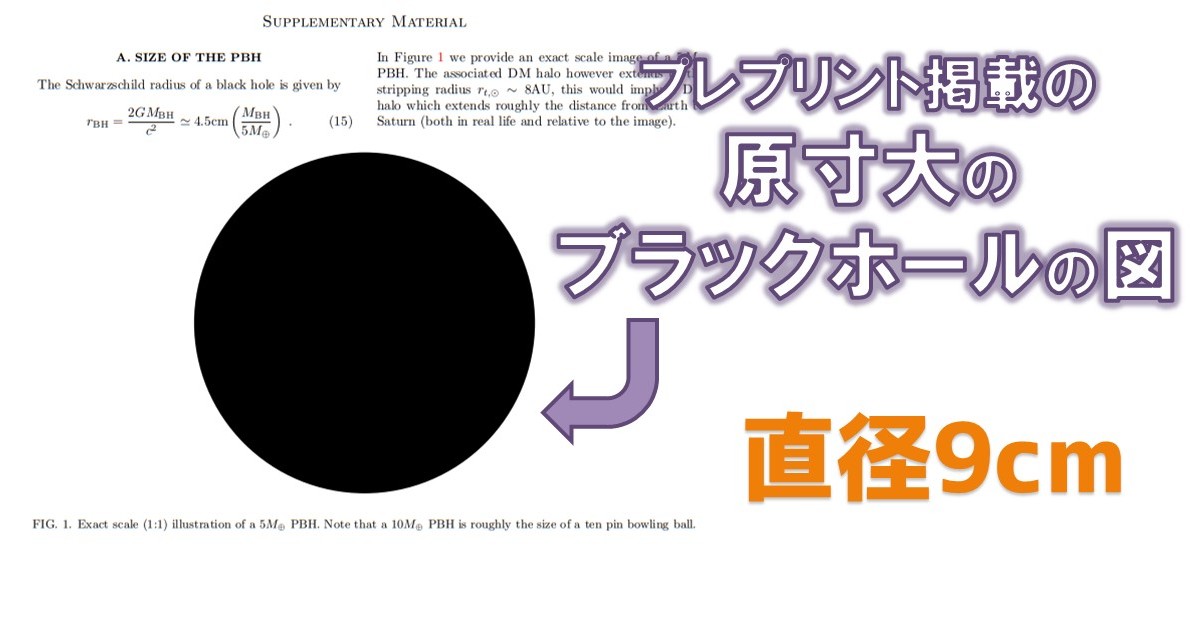
論文には、その研究に関わった人が著者として名を連ねています。論文の著者に載るかどうかは、研究に対する貢献度や業界・研究室によってさまざまであり、あまり一律な基準があるとはいえませんが、現在では著者が1人であるケースは少なく、特に自然科学分野ではかなり貴重です。 5人以下であればかなり少ない方であり、10人以上が名を連ねていることも珍しくありません。最近では研究結果の妥当性の主張のため、大量のデータを取得したり、とても1人では運用不可能な巨大な実験機器を使ったりするケースも珍しくなく、著者が100人を超えるケースもよくあります。 とはいえ、さすがに著者が1000人を超えるようなケースは少ないため、時々話題になります。冒頭で挙げたGemini 2.5のプレプリントに3295人の著者が載ったケースはまさに典型例でしょう。 では、著者が最も多い論文は何か。筆者が知る限り、それは2015年に科学雑誌「Physical Review Letters誌」に掲載された論文「ATLAS実験とCMS実験において、重心系エネルギー7~8兆電子ボルトの陽子同士の衝突において複合測定されたヒッグス粒子の質量」 (Combined Measurement of the Higgs Boson Mass in pp Collisions at √s = 7 and 8 TeV with the ATLAS and CMS Experiments)です。 タイトルは難しいものの、この論文は物理学において重要です。ただしそれ以前に、著者の人数がとんでもないという点で有名なのがこの論文です。なんと5154人もの著者が載っています。あまりにも多すぎるため、全33ページのうち、タイトルと本文が9ページ目前半まで、9ページ目後半から24ページ目までが著者、25~33ページ目までが所属などの注釈リストになっているなど、全体の7割が著者に関する情報となっています。 なぜここまで極端なのでしょう? この論文は、質量が生じるメカニズムに関わる「ヒッグス粒子」そのものの質量を測定するための実験結果について述べています。このために世界最大の円形加速器であるLHC(大型ハドロン衝突型加速器)を運用し、膨大な実験データを取得するため、これだけでも人数が膨大となります。 この研究の場合、2つの国際研究チームが共同で論文を発表しているため、もともと多い人数がさらに膨れ上がりました。これには2つの理由があります。まず、ヒッグス粒子の質量は現在の理論では正確に予測できないため、他の素粒子物理学の研究とは異なり、実験結果の妥当性を検証する手段が乏しいという事情があります。 また大量のデータを取得し処理すると、偶然にも誤った結果が現れる可能性が高まるという統計学的な性質があります。この研究の場合、ヒッグス粒子の質量という物理学の根幹的な部分に関わる内容のため、2つの研究チームが独立して、異なる検出器によるデータ取得と処理を実行することで、お互いの結果を検証するクロスチェック的な側面がありました。 最終的には同じ結果を得られたため、このような膨大な人数での共同発表となった経緯があります。 参考文献 G. Aad et.al. (ATLAS Collaboration, CMS Collaboration). “Combined Measurement of the Higgs Boson Mass in pp Collisions at √s = 7 and 8 TeV with the ATLAS and CMS Experiments”. Physical Review Letters, 2015; 114(19)191803. DOI: 10.1103/PhysRevLett.114.191803



