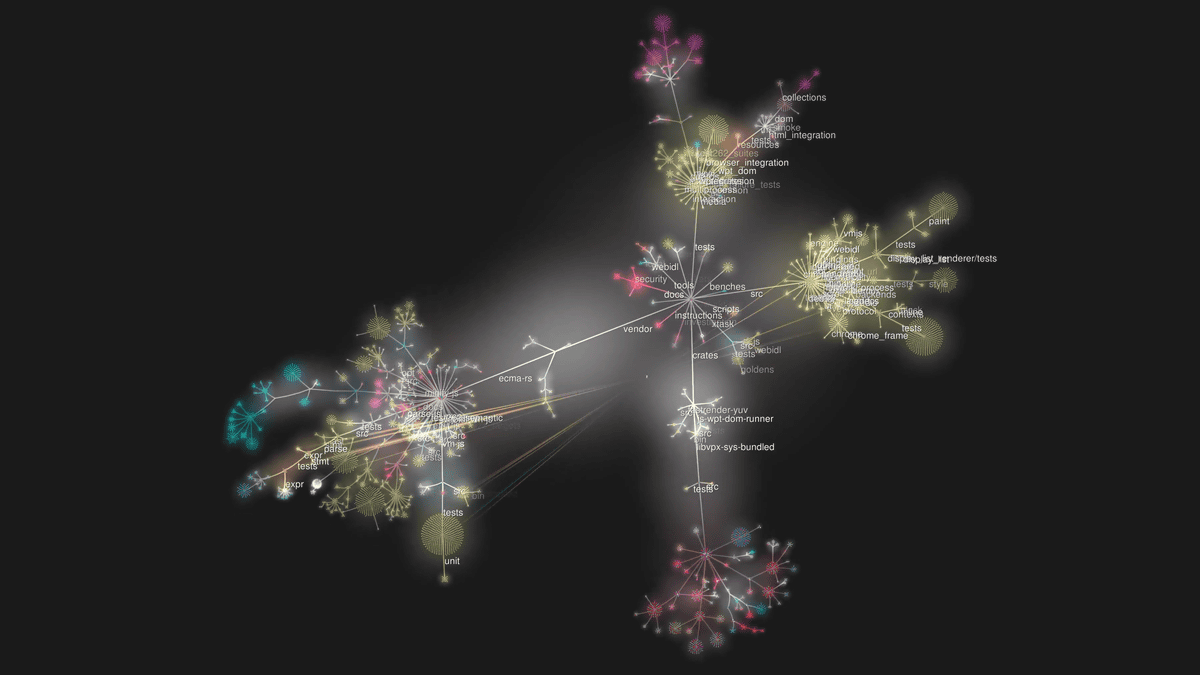まるで成長していない。「USB4」になっても呼び名が混乱している件。Gen 2とか相変わらず分かりにくいまま

アクセスランキング
Special Site
PC Watch をフォローする
最新記事
Impress Watchシリーズ 人気記事
おすすめ記事
USBという規格が複雑怪奇であることは、PCやスマホに詳しいユーザーに限らず、いまや一般の人にも知れ渡りつつある。誰にでも使いやすいことを目指して策定され、頭文字に「ユニバーサル」の「U」を据える業界標準規格が、ややこしいものの代表格として認知されているのは、非常に残念なことと言えよう。
USB規格の混乱は、最新の「USB4」の登場で、ある程度は改善されると思われていたが、現在の状況を見る限り、必ずしもうまくいっていないようだ。 今回はそうした、呼び名を中心とした現状のUSB規格について、2025年8月時点での状況をまとめてみた。
なお、この種の解説記事では、細かい例外事項を盛り込み過ぎて分かりづらくなることも多いため、本稿では注釈は割り切って最小限としている。本職の方から見ると「大筋では合っているが説明を端折りすぎている」というポイントは少なからずあるはずだが、ご了承いただきたい。
USBは規格の登場以来、バージョンアップを重ねて現在にいたっている。かつては最大480Mbpsの転送に対応したUSB 2.0が一般的だったが、2008年にはUSB 3.x系列、そして2019年にはUSB4系列が登場し、速度は最大80Gbpsまで向上している。
これらが「USB3」「USB4」といった、小数点もバージョンもないシンプルな表記であればよかったのだが、USB 3.xでは「USB 3.0」「USB 3.1」」「USB 3.2」というバージョン表記に加えて、「Gen 1」「Gen 2」「Gen 2x2」など、いわゆるGen(世代)表記が付与され、見た目が煩雑になった。それ以前はUSBのバージョンごとの最大転送速度をある程度把握していたが、この頃からさっぱり分からなくなった人も少なくないはずだ。
中でもややこしいのは、表記が違うだけで、実際には同じものを指しているケースが含まれていることだ。USB 3.0が3.1に進化する時点で、従来の「USB 3.0」を「USB 3.1 Gen 1」に改名し、USB 3.1の1つとして取り込むなど、1つ前の規格を名前を変える前例ができてしまったことで、混乱に拍車がかかることになった。具体的には以下の表の通りだ。
周辺機器やケーブルの仕様としてこの名前のどれを使うかはメーカーに委ねられているため、弊誌PC Watchのようなニュースサイトで複数のメーカーの製品を並べて表記する時、各社の表記ルールが異なると、中身が同じなのにスペックに相違があるように見える問題が生じる。かと言って表記を揃えると、メーカーが発表しているスペック表記と、ニュース記事上のスペック表記にズレが生じることになる。実に頭が痛い問題だ。
そうした中、USBの規格を策定するUSB-IF(USB Implementers Forum)では、2022年10月にマーケティング名なる表記のルールを公表した。これはシンプルに「USB + 速度(Gbps)」で表示するというルールで、たとえばUSB 3.2 Gen 1は転送速度が最大5Gbpsなので、マーケティング名では「USB 5Gbps」となる。
従来は「USB 3.x」のように後ろに小数点以下の表記をつけたり、またGen表記を用いていたが、ユーザーにとって真に必要なのは速度表記であるという考え方に基づいて、記載を省略することになったというわけだ。
結果として、現行の「USB4」および「USB 3.x」では以下の5種類が存在することになる。USB4なのか、USB 3.xのどれなのかは、このマーケティング名からは分からないが、それはあまり重要な問題ではないというわけだ。ちなみにUSB 2.0以前はマーケティング名はなく、従来のままとされている。
最初からこうであればよかった、というのは簡単だが、後からできる措置としては、十分に反省が生かされている。速度主体の表記であるため、USBのそのほかのスペック、具体的には充電の容量や、ディスプレイ接続に使えるか否かといった違いは分からないが、それはまた別の問題だ。
余談だがGen表記では、その手前に書かれているUSBのバージョンが3.0であろうが3.1であろうが、転送速度は共通という特性がある。具体的には以下の通りで、Gen 1はどれも5Gbps、Gen 2はどれも10Gbps、Gen 3はどれも40Gbpsといった具合だ。とはいえマーケティング名が一般的になれば、最初から転送速度で区別されるため、こうした豆知識は不要になる。
と、ここまでの内容は、過去の記事でも何度か紹介してきているのだが、現時点では残念ながら、うまくいっているとは言いにくい。
まずはバージョン表記。「USB 40Gbps」というマーケティング名からは、USBの具体的なバージョンは読み取れないわけだが、それらを補完する形で、「USB4 40Gbps」「USB4(40Gbps)」などといった具合に、USBが「4」であることを独自に追記している例はちらほら見かける。
もっともこれは当のUSB-IFが、前述のマーケティング名の策定以前に「USB4 40Gbps」というブランド名を用いていた時期があるので、現行の表記ルール上は正しくないものの、まだ理解はできる。そもそもバージョンの記載までなくしてしまうのはかなりドラスティックな変更でもあり、付け加えたくなるのは分からなくはない。
一方で、少々擁護が難しいのは「USB4(Gen 3x2)」「USB4 Gen 4」のように、転送速度の表記をせず、いまだにGen表記を用いているケースだ。USB-IFが推奨命名法を定めてGen表記を引っ込めたのは、「消費者の混乱を避けるため」であり、その主旨ごとガン無視しているのは理解に苦しむ。大手のケーブルメーカーでも、こうした表記はいまだに後を絶たない。
火種はまだある。USB4は2022年9月に最大80Gbpsの転送速度を持つ新しい「USB4 Version 2.0」が登場し、それ以前のUSB4を「USB4 Version 1.0」として区別するようになったが、これは実質的に「USB4.1」「USB4.2」にすぎない。USB4登場時には、小数点以下の表記は用いないと表明しているのだが、それを反故にしたと言われないために、表現を変えて煙に巻いただけ、と言われてもおかしくない。
この「USB4 Version x」は、前述のGen表記と同じく技術的には必要な表現であり、マーケティング名に表示が一本化されれば表に出ることはないので、そう大きな問題はないのだが、Amazonで「USB4 Version 2.0」で検索すると、USB 80Gbpsケーブルの検索用ワードとして埋め込まれている例があったりと、またしてもおかしな方向へと行きつつある。
以上が現状なのだが、これらの混乱に対してユーザーが貢献できることがあるとすれば、表記ルールを遵守して正しい情報提供を行なっているメーカーの製品を優先して選ぶことだろう。USB-IFの表記はあくまで「推奨」でしかないという理屈で、わざと表記に揺れを持たせているメーカーは、混乱の片棒を担いでいる側と言って過言ではないからだ。
最後に、USBについてはもう1つ、コネクタ形状についても触れておこう。かつてはUSB Standard-AとUSB Standard-Bの2種類しかなかったUSBコネクタだが、より小型化したUSB mini-B、さらに薄型化したUSB micro-Bが登場し、その後はUSB Type-Cへと刷新されて現在にいたっている。
「USB 3.x」「USB4」など、後ろに続く数字は転送速度を表しているのに対して、コネクタはあくまで物理的な形状でしかなく、速度とは関係がない。なので両端ともにUSB Type-Cコネクタのケーブルがあったとしても、それはUSB4の場合もあれば、USB 2.0の場合もある。このあたりは混乱しやすいポイントなので、大前提として押さえておきたいところだ。
ただし最新のUSB4がサポートするコネクタ形状はUSB Type-Cのみであるほか、急速充電のUSB PDはUSB Type-Cでのみ動作。またディスプレイ接続に使えるUSBケーブルは両端USB Type-Cのケーブル(の一部)に限定されるなど、USB Type-Cでしかサポートされない機能は多い。名実ともに標準となりつつあるのが、現在の状況だ。
一方、USB Type-Cで逆にややこしくなったのは、データおよび充電が行なわれる向きが、見ただけでは判別できなくなったことだ。以前ならば「データはAからBの方向に流れる」だったのが、両端USB Type-Cケーブルでは、どちらからどちらにデータが流れるのか、また給電がどちらからどちらの方向に行なわれるのか挿すまで分からず、また抜き差しのたびに方向が変化する場合もある。
たとえば2台のスマホをUSB Type-Cで接続したとして、両者ともにリバース充電機能を搭載していれば、先につないだ側からあとにつないだ側に充電が行なわれる場合もあれば、接続順序とは無関係にバッテリ残量で充電方向が決定される場合もある。このように、USB Type-Cポートに汎用性を求めすぎたことで逆にややこしくなった面はある。
とはいえ、古い世代のUSB Standard-BとUSB mini-B、およびUSB micro-Bは、時間の経過とともに順調に姿を消しつつあり、ポート形状が乱立して分かりづらい問題は解消に向かいつつある。USB Standard-AとUSB Type-C、この2つに収斂していく傾向は今後も変わらないはずで、前述の表記ルールのややこしさと比べると、好ましい方向に向かっていると言えるだろう。