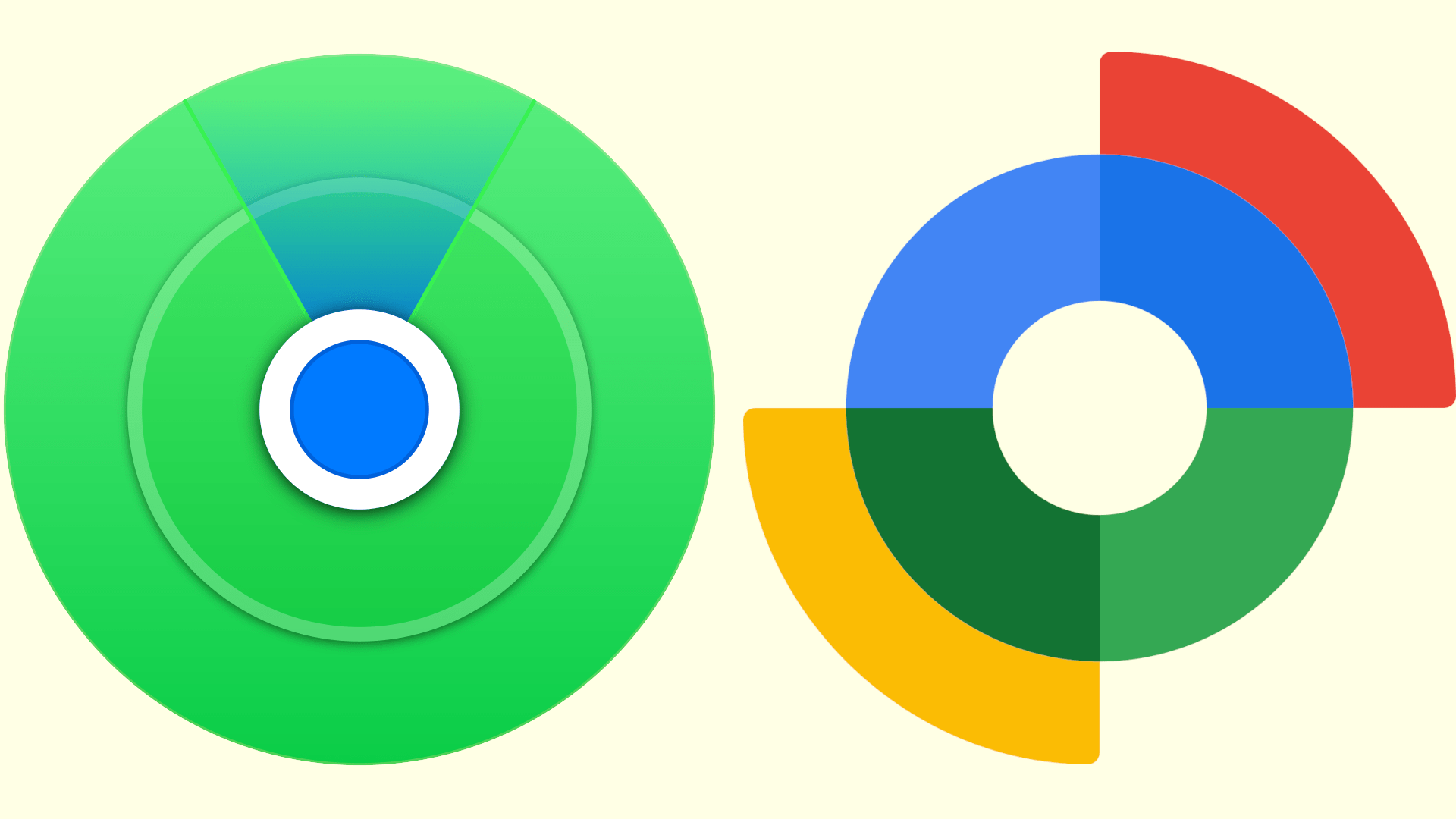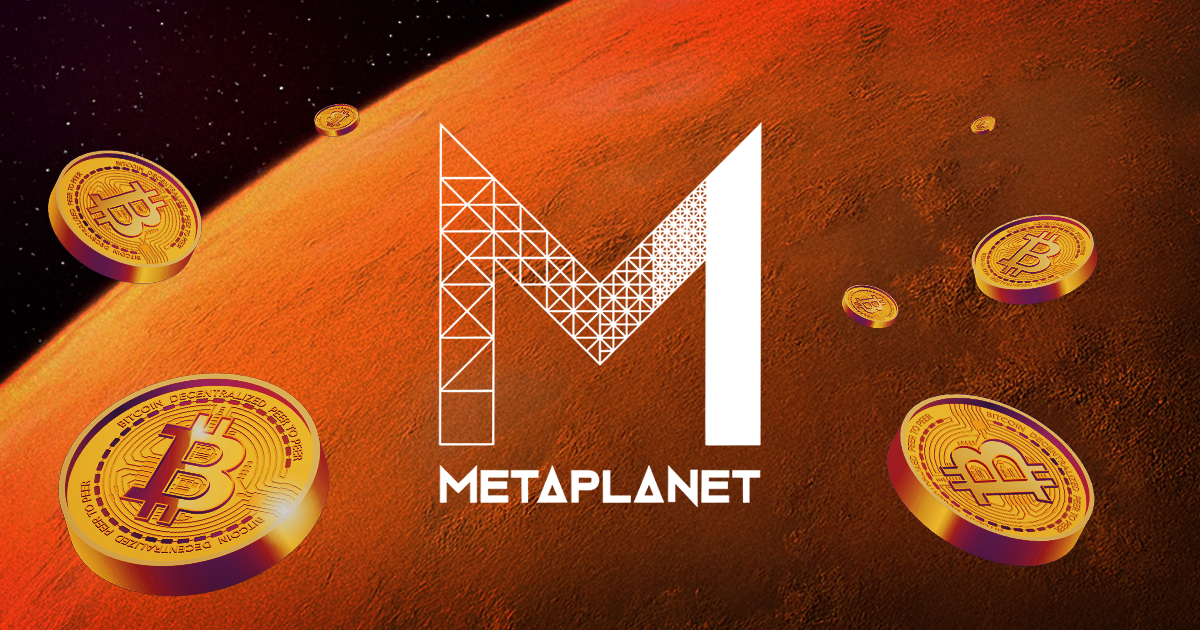「AIに現代詩の創作がどこまで可能なのか」福岡の詩人たちが実験したら…高度な詩作ができたが「課題」も(読売新聞オンライン)

参加したのは、詩人の渡辺玄英さん(65)、松本秀文さん(45)、石松佳さん(40)、緒方水花里さん(27)。10月に福岡市でシンポジウムを行い、それぞれ対話型AIサービスを用いて書いた詩を報告し、批評したり意見を交わしたりした。
石松さんの報告では、米オープンAIの「チャットGPT」を使い、まず「8行で秋の詩を書いて」と指示。チャットGPTは〈柿の実は しずかに熟れ/遠い鐘の音が 胸を揺らす/虫の声 夜の底へと沈み〉(部分)との詩を回答した。
従来の叙情詩の範囲に収まった詩句に対し、石松さんが「異質な要素を入れて」と求めると、〈公園に置き去られたマネキンの腕〉という行が追加された。さらに「『感覚の自明性』を疑う要素を入れて」「逆説を展開して」などの指示を追加すると、次のような詩に変化した。
〈柿の実は しずかに熟れ 口にすると酸っぱく/遠い鐘の音は 胸を揺らすが心は動かない/ベンチの下に転がるマネキンの腕/白く 指先に小さなひびが走るが/握ろうとすると 何もつかめず/落ち葉がその手の甲に積もるほど軽い〉(部分)
石松さんは「解釈の余地が生まれ、孤独感や寄る辺なさがにじむ詩となった」と評価しつつ、「こうした作品はすでに多く作られてきた。AIはデータの蓄積で詩を書くというのが致命的だ。歴史の中で蓄積されてきた叙情を批判的に継承することを積み重ねて、現代の個人につながる表現ができる」と語る。
緒方さんは「気持ちの悪い詩」についてAIに創作させた。その狙いを、「触覚こそが人間の世界認識のベースとなっており、身体を持たないAIには生理的な気持ち悪さがわからないのではないか」と説明した。
Page 2
米グーグルの「ジェミニ」は〈鏡に映る、自分の顔 目の中に小さな蟲が湧いている〉といった詩句を創作。身体的に繊細な不快感よりも、恐怖や不気味さが前面に出た表現だった。
緒方さんは「例えばAIは風邪の時の熱の上がり具合などを感覚として知らない。言葉にできない感覚を言葉にしていくことが詩作なので、人の心に届くような詩作はAIには難しいと思う」と話す。
詩作と身体感覚の関連については、石松さんも触れた。自身の詩「雪」から〈skin/風邪をひいても、/背中を撫でてやれば大丈夫なはずだ〉の一節を挙げて、「skinは雪と(ukiの音韻から)音が似ていると思い継ぎ足した言葉。なくても意味は通じるが、身体よりもっと微細な口触りによる言葉の質感はAIでは到達できない」と語った。
松本さんは、グーグルで「オバマ」と検索し、表示されたウェブ記事の切り貼りで作られたという山田亮太さんの詩「オバマ・グーグル」(2009年初出)を紹介。膨大な情報や言葉があふれるネット文化の強みが表れた作品だと評価した上で、「AIの時代にみんなが同じようなものを創れるようになると、内面より、言葉そのものの面白さといったコンセプトが重要になる。AIとともに可能性を考えたい」と語った。
定型や形式にとらわれない現代詩は、従来の意味や文法を変化させるなどして、言葉の可能性を広げてきた。一方のAIは、膨大な言語データをもとに、人々に受け入れられやすい表現を導き出すことが得意だ。
双方異なる方向性を持つ中、シンポジウムを主催した渡辺玄英さんは「詩とは何か、詩を書くこととは何かといった問題に向き合うことにもあった」と実験の狙いを説明する。
課題が挙がったAIは国内外で巨額の投資が進み、飛躍的な進化と普及が見込まれる。渡辺さんは「詩は、詩的なものと反詩的なもののせめぎ合いから発展してきた。AIによって、詩とは何かという根源的な問いが、これまで以上に深まっていきそうだ」と述べた。