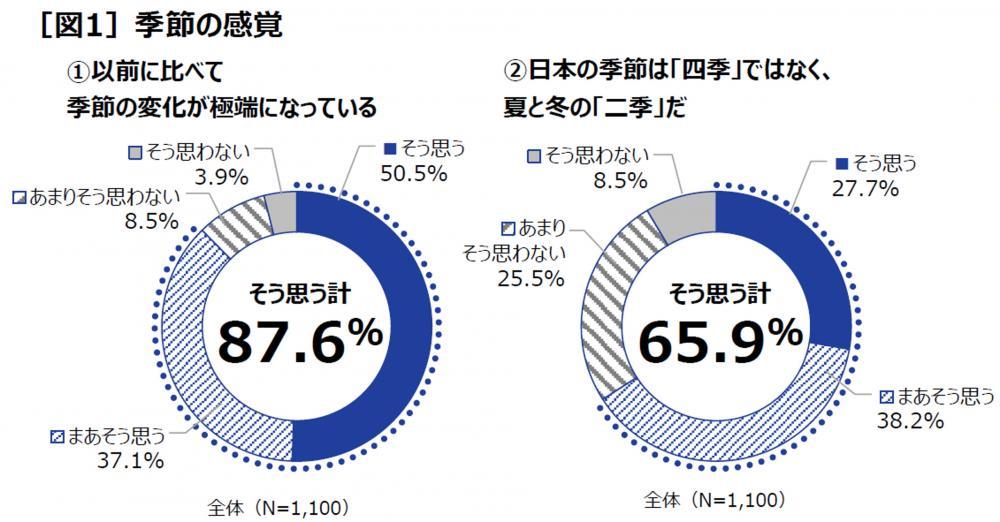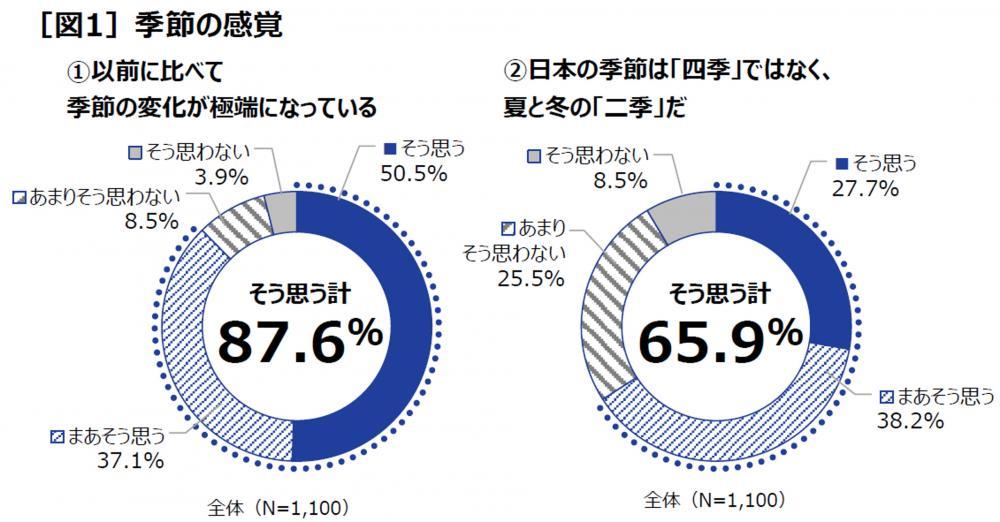10月特集のお知らせ(予告)

10月の特集記事や注目連載をご紹介! 「マイドクター会員」のご登録で、最新記事も過去の記事もすべて読み放題! 健康本のオンライン閲読や電話相談など、盛りだくさんのサービスもご利用できます。
マイドクター会員(有料)とは → ご案内はこちら
\健康長寿に役立つ記事が満載!/ (1カ月無料、まずはお試しください!)
【10月の特集】
賢い「健診&人間ドック」活用術(10月前半公開予定)
健診や人間ドックは病気を早期に見つける大切な機会――「なんとなく受けているだけ」になっていませんか? 賢い受け方、選び方、結果の読み解き方をまるっとお伝えします。ぜひ今から自分の健康状態を把握しましょう。
- 第1回 医師が直伝「健診結果」の読み方 多くの人が軽視しているポイント
- 第2回 進化を続ける人間ドックの賢い活用法、オプションの選び方
- 第3回 がん検診を受診しよう―どんな人がいつ受けたらいい?
科学的に正しい認知症予防(10月後半公開予定)
認知症は予防・治療できる時代になる?――2024年には認知症予防の最新エビデンスが発表され、適切な対策を打てば発症リスクを減らすことが可能だとされました。さらに初期段階でも手を打てば健康な状態に戻れることも。最新事情をお伝えします。
- 第1回 認知症の発症リスクは45%減らせる! 予防研究で分かったこと
- 第2回 「脳をお掃除」認知症予防3つの行動 とっとり方式のプログラム
- 第3回 LDLコレステロール対策は認知症予防! 脳の機能維持にやるべきこと
【テーマ別特集】
10月のテーマは「たんぱく質」(10月前半公開予定)
【健康Q&A】
あなたの疑問に専門家が回答! 健康Q&A「歯・口腔」のお悩みに新谷悟先生が答えます(10月後半公開予定)
【注目の連載】
「100年元気」を目指すアンチエイジング学(10月前半公開予定)
古武術式! 日常動作の極意(10月後半公開予定)
快眠の科学(10月前半公開予定)
Dr.ひらまつの「知っておきたい“老化”と“目”の話」(10月後半公開予定)
野口緑の「職場の健康」Q&A(10月後半公開予定)
【健康ブック】
10月1日から、以下の書籍をオンライン閲読できます。 健康ブックの詳細はこちら
50歳からの心の疲れをとる習慣<日経Goodayの本>
50歳を過ぎると、体力が衰えて、疲れが抜けなくなってくるだけでなく、心も疲れやすくなってきます。ちょっとしたことでイライラしたり、傷つきやすくなったり、気分の浮き沈みが大きくなったり……。人生100年時代では、50歳はその「折り返し地点」。残りの長い「人生の後半」は、心の疲れをきちんとケアすることが何よりも大切になってきます。
本書では、日経Gooday連載でもおなじみの元・陸上自衛隊の心理カウンセラーである下園壮太さんが、あなたの心と体に寄り添う「メンテナンス習慣」をお教えします。
名医が教える 高血圧の治し方
放っておくと心筋梗塞や脳卒中など、重大な事態を引き起こす高血圧と動脈硬化。自覚症状なく進んでしまう油断のならないサイレントキラーです。
わが国では推定4300万人もの高血圧患者さんがいるといわれており、高血圧が原因となって死亡する人の数は、年間10万人は下らないと見積られています。その多くは自覚症状がないことから取り返しのつかない事態に陥っているのです。しかし、高血圧は決して治せない病気ではありません。対処が早いほど改善のきく症状なので、高血圧について正しく知っていただくことが何よりも大切です。
やさしいカラー図解 乳がん
女性の罹患率がもっとも高いがんは乳がんですが、一方で、早期発見がかない、適切な対処を施せば、治して日常生活を取り戻しやすいがんであるともいえます。
乳がんの最新の基礎知識から、検査や診断、がん細胞がもつ性質によって分類したサブタイプ、温存の可否など治療法選択の考え方、術後の療養やリハビリ、再発リスク低減のための工夫まで、乳がんに関する「すべて」を1冊にまとめました。オールカラーの豊富な図解と詳しい解説で分かりやすく紹介します。
*日経Goodayのコンテンツを許可なく複製、編集、翻訳、翻案、放送、出版、販売、貸与、公衆送信、送信可能化などに使用することはできません。日経Goodayで提供しているコンテンツの著作権についてはこちらをご覧ください。
Page 2
有料会員になると、鍵つき記事が全て読める&医療専門家に電話相談や名医紹介も!
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 3
この記事では、今知っておきたい健康や医療の知識をQ&A形式で紹介します。ぜひ今日からのセルフケアにお役立てください!
有料会員になると、鍵つき記事が全て読める&医療専門家に電話相談や名医紹介も!
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 4
期待の新薬、治療ガイドラインの改訂、革新的な医療機器の登場―。今、医療の様々な分野で注目されている最新の治療トレンドを、専門医が分かりやすく解説します。
有料会員になると、鍵つき記事が全て読める&医療専門家に電話相談や名医紹介も!
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 5
ビジネスでも、プライベートでも、「酒」が同席する機会は少なくない。ましてや日本の文化に「酒」はなくてはならないもの。祝い酒、嬉し酒、やけ酒、涙酒…。「アルコールはガソリン!」という“超・左党”たちから、「アルコールとは時々仲良し」という“準・左党”たちまで、皆に役立つ酒と健康の最新科学を贈る! (タイトル題字:葉石かおり)
有料会員になると、鍵つき記事が全て読める&医療専門家に電話相談や名医紹介も!
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 6
日経Goodayでは日々、新しい健康・医療情報をお届けしています。その中で、読者のみなさまが今、最も気になっているテーマ、例えば、「大腸がん」「脂肪肝」「痛風・尿酸値」「男性ホルモン」などに関する多数の記事の“エッセンス”をすばやく知りたい――。そんなニーズにお答えする新サービスを開始します。
それが「テーマ別特集」です。毎月、読者のみなさまの関心が高かったテーマをチョイスし、特に好評だった記事のポイントを編集部でピックアップしてお届けします。そのテーマ、ジャンルについて知っておくべきことが、この記事を読むだけですべて把握できます。さらに、そのテーマに関する記事一覧もご用意しました。ご活用ください。
有料会員になると、鍵つき記事が全て読める&医療専門家に電話相談や名医紹介も!
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 7
近年、老化研究が進む中で、老化を進めるさまざまな要因が明らかになってきた。中でも注目されているのが「酸化」だ。酸化とはいわゆる「サビ」のこと。酸化によって細胞が傷つき、細胞や組織の機能を低下させ、老化を進行させてしまう。老化を遅らせるには、活性酸素を除去する力「抗酸化能」を高めることが肝要だ。本記事では、酸化ストレスの脅威の実態とその対策を、これまでの人気記事をもとに分かりやすく紹介する。
テーマ別特集「酸化ストレス」 この記事の主な内容 体をサビつかせる犯人「活性酸素」とは? 抗酸化能を高める「食事」のポイント ビタミンEは脂質やたんぱく質の酸化を防ぐ オリーブオイルとニンニクは抗酸化食品の優等生 適度な運動は抗酸化能を上げるが、過度な運動は逆効果年を取ることで進む「加齢」という自然現象には誰も逆らうことができない。だが、加齢に伴って体の機能が低下する「老化」にあらがうことはできるのではないか――。こうした考えから、近年、「老化は病気」として扱われるようになってきた。世界保健機関(WHO)でも、「加齢関連」という病気の枠組みが作られ、老化を病気とする考えはグローバルスタンダードとなっている。老化が病気の一種なら、先手で予防したり、治療したりすることも可能となる。
老化は病気の一種で、予防したり、治療したりすることも可能となるという考え方が定着してきた。(写真はイメージ:PIXTA)
老化は、食生活の乱れや運動不足など、さまざまな要因が絡み合って進行する。その中でも注目されている要因に「酸化」がある。今回は酸化にフォーカスして、過去の人気記事をもとにその脅威や対策を紹介していこう。
酸化はいわゆる「サビ」のことで、酸素が物質と結合する化学反応を指す。金属や、古くなった野菜・果物が茶色く変色するのと同じように、酸化は私たちの体の中でも起こる。例えば、紫外線を浴び続けた皮膚の細胞がダメージを受け、シミやシワができるのも酸化の仕業だ。このように、酸化によって細胞が傷つき、有害な作用が生じることを「酸化ストレス」と呼ぶ。酸化ストレスは、細胞や組織の機能を低下させ、老化を進行させる。
金属や野菜、果物などは、酸化により劣化する。これと同じことが体内で起こると、細胞が傷み、老化が進んでしまう。(写真はイメージ:PIXTA)
実は、酸化ストレスは、皮膚のような見た目の変化だけでなく、老化に関連するあらゆる病気とも深く関わっている。酸化ストレスに詳しい、同志社大学大学院生命医科学研究科教授の市川寛氏は、「認知症をはじめ、がんやサルコペニア(加齢に伴う筋肉量の減少)、生活習慣病など、老化に伴うすべての病気の上流に酸化ストレスがあると言っても過言ではありません」と話す。老化に伴う多くの病気を防ぐため、酸化ストレスから体を守ることが不可欠だ。
体をサビつかせる犯人「活性酸素」とは?
酸素を使って生きる以上、私たちは酸化と一生付き合っていかなければならない。生きていくために必要なエネルギーは酸素を材料にして作られていて、その過程で発生する「活性酸素」という物質が酸化のもとになるからだ。活性酸素には他の物質を酸化させる強い力があるため、過剰になると細胞にダメージを与え、さまざまな病気の引き金となってしまう。
ただし幸いなことに、人間には活性酸素を除去する力、「抗酸化能」も備わっている。活性酸素は生命維持に必須の物質でもあるため、極端に減ることなく、なおかつ増え過ぎないように制御しなければならない。抗酸化能を高めてこのバランスを維持できれば、細胞を活性酸素から守り、老化に伴う病気を予防・改善することにつながる。
活性酸素と抗酸化能のバランスが大切
活性酸素が発生しても、それを消す抗酸化能が働けば、健康な状態を保つことができる。だが、バランスが崩れて活性酸素を消去しきれなくなると、細胞が傷ついていく。
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 8
日経Goodayでは日々、新しい健康・医療情報をお届けしています。その中で、読者のみなさまが今、最も気になっているテーマ、例えば、「大腸がん」「脂肪肝」「痛風・尿酸値」「男性ホルモン」などに関する多数の記事の“エッセンス”をすばやく知りたい――。そんなニーズにお答えする新サービスを開始します。
それが「テーマ別特集」です。毎月、読者のみなさまの関心が高かったテーマをチョイスし、特に好評だった記事のポイントを編集部でピックアップしてお届けします。そのテーマ、ジャンルについて知っておくべきことが、この記事を読むだけですべて把握できます。さらに、そのテーマに関する記事一覧もご用意しました。ご活用ください。
有料会員になると、鍵つき記事が全て読める&医療専門家に電話相談や名医紹介も!
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 9
白内障手術は日本で年間180万件以上も行われる、最も多い手術だ。治療が進化した今、手術により近視・遠視・乱視・老視も治り、メガネなしで快適な生活を送る人もいる。しかし、そうしたことを知らない人はまだ多い。知識不足や医師とのコミュニケーション不足から、手術で期待通りの効果を得られない人もいる。また、意外な原因が白内障を進めることが分かっており、日常生活で注意するべきこともあるという。「白内障手術なんてまだ関係ない」と思っても、人は高齢になれば必ず白内障になる。一生に一度の手術だからこそ、後悔しないための基礎知識を備えておこう。
佐々木洋(ささき ひろし)氏 金沢医科大学眼科学講座 主任教授
有料会員になると、鍵つき記事が全て読める&医療専門家に電話相談や名医紹介も!
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 10
「腰曲がり」はもう少し年をとってから気にすべきこと、と思っていないだろうか。実は、加齢や生活習慣が原因で進んでいく背骨の変形は60代の4割、80代になると7割に起こっているという報告や、70歳以上は腰曲がりが進行するという話もある。たかが姿勢、と甘く見てはいけない。腰曲がりは見た目の老化に直結するだけでなく、将来的な介護リスクとも密接に関わり、「健康寿命」を左右することが分かってきた。本特集の第1回では、腰曲がりを改善するために有効な対策を研究する北海道千歳リハビリテーション大学健康科学部リハビリテーション学科教授の世古俊明氏に、腰曲がりはなぜ起こるのか、腰曲がりのサインの見分け方を聞く。
世古俊明(せこ としあき)氏 北海道千歳リハビリテーション大学健康科学部リハビリテーション学科理学療法学専攻教授
有料会員になると、鍵つき記事が全て読める&医療専門家に電話相談や名医紹介も!
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 11
「腰曲がり」はもう少し年をとってから気にすべきこと、と思っていないだろうか。実は、加齢や生活習慣が原因で進んでいく背骨の変形は60代の4割、80代になると7割に起こっているという報告や、70歳以上は腰曲がりが進行するという話もある。たかが姿勢と甘く見てはいけない。腰曲がりは老け見えに直結するだけでなく、将来的な介護リスクとも密接に関わり、「健康寿命」を左右することが分かってきた。本特集の第1回では、腰曲がりはなぜ起こるのか、腰曲がりのサインの見分け方を紹介する。
背骨の変形は60代には始まっている
「久々に同窓会に参加。背が高かった同級生と立ち話をしていたら、何か違和感が…そう、自分よりも背が低くなっていました。とても驚きました。よく見たら、背中が丸くなっていて」そう話すのは60代の男性だ。
身近な人に「最近、背中、丸くなっていない?」と指摘されたり、ショーウインドーに映り込む自分の姿にがくぜんとしたりした経験がある人もいるかもしれない。
60代を過ぎる頃から、はっきりと「老けて見える人」と「若々しい人」に分かれるような気がするが、それはなぜだろうか。若々しさに直結する「見た目のシルエット」を形作るのは、背骨の弯曲(カーブ)の角度だ。
「背中が丸くなるのは年齢のせいだから仕方がない」と思うのは甘い。姿勢が悪いと気づいてそのたびに背すじをピンと伸ばして正しても、気休めにしかならない。背骨の変形は徐々に進み、放置すると「腰曲がり」に発展していくからだ。
「腰曲がり」は言葉の響きもあり、「10年、20年先の高齢になったときの話」と考えがちだ。しかし、骨盤の傾きと第7頸椎(けいつい)の角度を用いた指標によって背骨の変形を評価した国内の研究では、背骨が変形している人の割合は60代で4割もいて、年齢を重ねるごとに増えていくことが分かっている(*1)。背骨の変形は、60代にはもう始まっているのだ。
図1 背骨の変形は60代で4割の人に発生している
1121人を対象に、骨盤の傾きと第7頸椎の角度を用いて立ち姿勢での背骨の変形(脊椎アライメント)を評価した。背骨の変形が起こっている人の割合は、50歳未満では19%だったが、50代で29%、60代で40%、70代で54%、80代以上では69%と年齢が上昇するとともに高くなった。(Sci Rep. 2023 Jul 22;13(1):11862.より改変)
70歳以上は腰曲がりが進行 早期対策がカギ
医学的には、胸椎が40度以上後弯(こうわん)すると「過度な後弯」とされ、いわゆる脊柱後弯変形(腰曲がり)に該当することが多い(詳しくは後述)。胸椎後弯の平均角度は60代で約45度、70歳以上では約50度と報告されており(*2)、高齢になるにつれて多くの人が自然に腰が曲がってくることが分かっている。腰曲がりは決してひとごとではない。
「加齢とともに腰曲がりの程度は大きくなっていきます」と説明するのは、理学療法士として健康増進の社会実装のためのリハビリテーションを考案、地域住民に提供するなどして、その効果の検証を進める北海道千歳リハビリテーション大学健康科学部リハビリテーション学科教授の世古俊明氏だ。
「18歳以上の椎体に異常のない280人を年代別に調べた米国の研究では、男女ともに加齢とともに腰曲がりの角度は増加し、65歳以上では女性は3分の2、男性は半数が腰曲がりと判明しました(*3)。私も、臨床現場で50~70代の腰曲がりの人と会う機会が多いです。腰曲がりは、将来的な介護リスクや健康寿命にも関わるため、早めの対策が重要です」(世古氏)
世古氏は「腰曲がりを進める要因は、主に4つあります(詳しくは後述)。早めに気づいて対策することで、悪化を抑制していくことが可能だということを私たちは研究によって確認しています」と話す。
本特集では、腰曲がりのメカニズムやその原因、有効な対策を紹介していく。今回は、腰曲がりの仕組みや腰曲がりを進行させる4つの要因について見ていき、腰曲がりに気づくために見逃せないサインについても詳しく解説する。
*3 AJNR Am J Neuroradiol. 2005 Sep; 26(8): 2077-2085.
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 12
「腰曲がり」はもう少し年をとってから気にすべきこと、と思っていないだろうか。実は、加齢や生活習慣が原因で進んでいく背骨の変形は60代の4割、80代になると7割に起こっているという報告や、70歳以上は腰曲がりが進行するという話もある。たかが姿勢、と甘く見てはいけない。腰曲がりは見た目の老化に直結するだけでなく、将来的な介護リスクとも密接に関わり、「健康寿命」を左右することが分かってきた。本特集の第1回では、腰曲がりを改善するために有効な対策を研究する北海道千歳リハビリテーション大学健康科学部リハビリテーション学科教授の世古俊明氏に、腰曲がりはなぜ起こるのか、腰曲がりのサインの見分け方を聞く。
世古俊明(せこ としあき)氏 北海道千歳リハビリテーション大学健康科学部リハビリテーション学科理学療法学専攻教授
有料会員になると、鍵つき記事が全て読める&医療専門家に電話相談や名医紹介も!
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 13
年齢とともに背骨が変形し、徐々に進行していく「腰曲がり」は、つらい肩こりや腰痛などの体の不調につながるだけでなく、フレイルやサルコペニア、さらには介護リスクといった「健康寿命」にも関わることが分かってきた。いつまでも若々しく自立した生活を送るには「背骨の維持」が大切なのだ。特集第2回では、簡単にできる腰曲がりのチェック方法や、腰曲がりが私たちの健康に及ぼす悪影響、腰曲がりにつながるNG習慣と背骨の維持に大切なOK習慣を、北海道千歳リハビリテーション大学健康科学部リハビリテーション学科教授の世古俊明氏に聞いていく。
実は健康長寿に欠かせない「背骨」
背骨が丸まる、老け見え姿勢の代表格と言える「腰曲がり」。胸椎が過剰に後弯(こうわん)し、背中が丸くなる状態を脊柱後弯変形(いわゆる腰曲がり)と呼ぶ。
「背骨の変形」を放置すると腰曲がりに発展するが、背骨の変形は60代の4割に見られるという報告がある。さらに、腰曲がり自体も65歳以上では女性は3分の2、男性は半数に見られるという報告もあり、決してひとごとではない。「腰曲がりはだいぶ先のことで、自分にはまだ関係ない」と甘く見てはいけないのだ。
北海道千歳リハビリテーション大学健康科学部リハビリテーション学科教授の世古俊明氏は「腰曲がりは、筋力低下、筋肉の柔軟性の低下、骨や骨を支える組織の老化、生活習慣における偏った姿勢など4つの要因(詳しくは第1回)が総合的に関わって起こり、進行していきます。腰曲がりが進むとフレイル(加齢による心身の衰え)やサルコペニア(筋肉減弱症)につながるほか、介護リスクが高まることが分かってきました。老け見えにつながるだけでなく健康寿命とも密接に関わっており、いつまでも自立して若々しく過ごすには、実は『背骨の維持』が欠かせないのです」と説明する。
腰曲がりは、肩こりや腰痛を起こすほか、進むとフレイルやサルコペニアにつながったり、介護リスクとも関連したりすることが分かってきた。老け見えや体の不調だけでなく、健康寿命とも密接に関わり、「背骨の維持」は自立した生活を送るのに欠かせない。(写真はイメージ:PIXTA)
背骨の変形を放置すれば、日常生活に支障を来し、健康寿命にも悪影響を及ぼす可能性がある。「たかが姿勢」と思わずに、早めの対策が重要だ。
医療現場で使われる簡単チェック法
知らず知らずのうちに進む腰曲がりの兆候に気づくには、「鏡に映る自分の姿の変化」や、人から背中が曲がっていることを指摘されるといった「見た目で気づくサイン」がある、と第1回でお伝えした。
特集第2回では、腰曲がりのチェック法と健康に及ぼす悪影響について見ていく。また、腰曲がりを進ませるNG習慣と背骨の維持に大切なOK習慣についても詳しく解説する。次ページからは、まずは自分が腰曲がりかどうかを知るための、簡単で信頼性の高い方法を紹介する。腰曲がりになっていないかを確認してみよう。
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 14
何歳になっても活動的で、「若々しいね!」と言われたい。そのためには、背骨がすっときれいに伸びた状態であることが大切だ。腰曲がりを予防・改善する体操を開発し、指導する北海道千歳リハビリテーション大学健康科学部リハビリテーション学科教授の世古俊明氏は、腰曲がり予防のためにアプローチすべきは「体幹の前側のストレッチと、背すじを伸ばす後ろ側の筋肉の強化」だという。今回は、実際に「背すじが伸びる」効果を導き出した4つの体操を紹介する。さらに、腰曲がりと同様に起こりやすい「カメ首」を改善する運動も紹介。どれもシンプルで心地よさも抜群。毎日の習慣にして若々しい姿勢を手に入れよう。
エビデンスに基づく「4つの体操」で若々しい姿勢に!
いつまでも若々しく活力ある体を維持したい──。誰もがそう願っていることだろう。そんなときに気になるのが若々しさに直結する「背骨のライン」だ。年齢を重ねるにつれ、背骨のラインが崩れていく人が多い。背骨の後弯は少しずつ進み、やがて「腰曲がり」が起こると、腰痛や肩こりだけでなく、転倒や自立度低下リスクなど健康寿命にも関わることが分かっている(第2回)。
北海道千歳リハビリテーション大学健康科学部リハビリテーション学科教授の世古俊明氏は「腰曲がりは、加齢にともなう筋力低下、筋肉の柔軟性の低下、骨粗しょう症による椎体骨折や椎間板の変性、さらに偏った姿勢や座りっぱなしなどの生活習慣などが関わり合って悪化していきます」と説明する(第1回)。
筋肉の質の低下も問題だ。やせた筋肉の隙間に脂肪が入り込む、いわゆる「脂肪筋」状態になっている人では姿勢が崩れやすいことも最近の研究で分かってきた(第2回)。
だが、「加齢とともに筋肉や組織が老化していくのは仕方がないこと」と諦めるのは早い。「実は、腰曲がりに関わる筋肉はどの部位の筋肉なのかが特定されていて、それぞれの筋肉にピンポイントにアプローチすることで姿勢の改善が可能です」と世古氏は話す。
世古氏は、中高年から高齢者を対象に、サルコペニア(加齢にともなう筋肉量の減少と筋力低下)やフレイル(加齢による心身の衰え)などの改善のためのリハビリプログラムを開発し、社会実装へと橋渡しする研究を実施している。そこで本特集の最終回は、世古氏が実施した「健康増進教室(腰曲がり予防教室)」で実際に効果が得られた「4つの体操」を紹介しよう。
下の図1を見てほしい。「腰曲がり予防教室」の結果を基に姿勢のビフォーアフターを再現したものだ。同教室では、参加者の自然立位(普段通りの立位姿勢)での脊柱後弯角度が5度有意に改善することを確認した(中央値)。2つの画像を見比べてみると、受ける印象が異なる。左は背中が丸く、頭が前に突き出て老けて見えるのに対して、右は若々しく見える。
図1 「腰曲がり予防教室」実施前後の姿勢ビフォーアフター
腰曲がり予防教室で、自然立位(普段通りの立位姿勢)での脊柱後弯角度が5度(中央値)有意に改善した姿勢を、北海道千歳リハビリテーション大学のスタッフが再現したもの。5度改善すると、目に見えて姿勢が若返ることが分かる。(画像:世古氏提供)
「腰曲がりの予防や改善を目指すときに、運動の内容はもちろんのこと、有効な運動の頻度や期間を実践する人たちが現実的に達成できることがカギとなります。そのためには分かりやすく、正しく、再現しやすいメニューに絞り込むことも重要です。私たちは、それらを踏まえたプログラムを開発しました」(世古氏)
次ページからは、腰曲がりを予防・改善するためにアプローチしたい筋肉部位や体操のやり方のほか、体操の詳細なエビデンスも紹介する。この体操を実施して、いつまでも若々しさをキープしたい。
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 15
誰もがいつかは「白内障」を発症すると言われ、日本では年間180万件以上の白内障手術が行われている。濁った水晶体と交換する人工の「眼内レンズ」が次々と開発され、裸眼の生活を取り戻すことも夢ではなくなった。さらに、左右の目に異なるタイプの眼内レンズを入れるなど、新しい方法も出てきている。今回はそんな眼内レンズの種類と特徴を紹介しよう。眼科選びに苦労した患者による体験談も必読だ。
白内障手術は「目の若返り手術」と言っても過言ではない
80代になると100%近い人が発症する「白内障」。印象派の画家、クロード・モネも患者の1人で、代表作「睡蓮」のぼやけた描写が、まさに白内障の見え方だと言われている。モネが手術を受けた1920年代は現在と大きく異なり、手術後は分厚いメガネをかけて生活したそうだ。
今や白内障手術は広く普及し、視界をくもらせる「水晶体」を人工の「眼内レンズ」に取り換える手術が全国で行われている。眼内レンズには、1カ所にしっかりピントが合う「単焦点レンズ」と、複数箇所にピントが合う「多焦点レンズ」がある(下表)。新しい眼内レンズが次々に開発され、老眼や近視、乱視も一度に改善し、メガネいらずの生活を取り戻す人もいる。
眼内レンズの主な種類とメリット・デメリット
単焦点レンズ 多焦点レンズ 遠くに焦点が合う場合 近くに焦点が合う場合 3焦点・連続焦点 焦点深度拡張型 メリット
- ピントが合う1カ所のコントラストが良く、鮮明に見える
- 単焦点レンズと同様に鮮明に見える
- 遠くから近く(50cmくらい)まで裸眼で見える
- 夜に不快な光が見えることは少ない
ト
- 単焦点レンズほど鮮明度が高くない
- 夜、不快な光が見える現象が出やすい
- 近く(30~40cm)が少し見えづらく、老眼鏡を使う人もいる
方
遠く ◎ ✖ 〇 ◎ 中間 △ △ 〇 ◎ 近く ✖ ◎ 〇 △5万件以上の白内障手術を行ってきた金沢医科大学眼科学講座主任教授の佐々木洋氏は、70~80代の人が白内障手術を受けた場合を例に、レンズの違いを次のように説明する。
「70~80代の人が白内障手術を受けるとすれば、従来の単焦点レンズは、白内障のない60代の見え方に戻るイメージ。具体的には、『遠くは鮮明に見えるが、近くは見づらい状態』になります。最近スタンダードになってきた新しいタイプの単焦点レンズは、従来の単焦点レンズより近くが見えやすく、50代後半の見え方のイメージ。そして、最新の多焦点レンズなら、老眼になり始めた40代の見え方になることも可能になりました。手元はやや見にくいものの、遠方から50cmくらいまでは裸眼で見える状態です。こう見ていくと、白内障手術は目の若返り手術と言ってもいいでしょう。メガネが不要になれば地震などの災害時も安心です」(佐々木氏)
見え方のイメージ
レンズの選び方によっては、遠くから近くまで鮮明に見えるようになる。(元画像:PIXTA)
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 16
白内障手術は日本で年間180万件以上も行われる、最も多い手術だ。治療が進化した今、手術により近視・遠視・乱視・老視も治り、メガネなしで快適な生活を送る人もいる。しかし、そうしたことを知らない人はまだ多い。知識不足や医師とのコミュニケーション不足から、手術で期待通りの効果を得られない人もいる。また、意外な原因が白内障を進めることが分かっており、日常生活で注意するべきこともあるという。「白内障手術なんてまだ関係ない」と思っても、人は高齢になれば必ず白内障になる。一生に一度の手術だからこそ、後悔しないための基礎知識を備えておこう。
佐々木洋(ささき ひろし)氏 金沢医科大学眼科学講座 主任教授
有料会員になると、鍵つき記事が全て読める&医療専門家に電話相談や名医紹介も!
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 17
体の老化とともに最近、脳の老化も気になる――。「ほら、あれあれ!」と固有名詞がどうしても出てこなかったり、変化の激しい仕事環境についていけなかったりすることも増えてくる。本連載では、公立諏訪東京理科大学工学部教授で脳科学者の篠原菊紀さんに、脳にまつわる素朴な疑問や悩みの解決法について聞いていく。
有料会員になると、鍵つき記事が全て読める&医療専門家に電話相談や名医紹介も!
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 18
公立諏訪東京理科大学工学部教授で脳科学者の篠原菊紀さんに、脳の活性化術を聞いてきた連載も今回で最終回。世界で進んでいる「スーパーエイジャー」研究の最新成果と、年齢とともに増える「うっかりミス」を防ぐ予習のコツ、これからの脳をできるだけ若く保っていく心構えを聞いた。
若い脳を維持するスーパーエイジャー研究で分かったこと
この連載では、会話の端々に「あれ」「それ」が増えていき、ややこしい作業をすることが苦手になっていく中高年世代の「脳の使い方」について解説いただいてきました。最終回の今回は「脳の若さの維持の仕方」について伺いたいと思います。今、高齢になっても脳の若さを維持している「スーパーエイジャー:Super Agers」という研究が世界で進められているそうですね。
篠原さん:スーパーエイジャーについて、研究者たちは「80歳を越えても、20~30歳年下の人と同程度の優れた記憶力を維持したまま晩年を迎える人たち」と定義しています。
このスーパーエイジャーを多角的な視点で分析したスペインのマドリード工科大学の研究が2023年に発表されました(*1)。この研究は、認知機能テストの成績によってスーパーエイジャーとされた64人の男女(平均年齢81.9歳)と、一般レベルの認知機能だった55人の男女(平均年齢82.4歳)を最大6年間追跡したものです。脳画像、生活習慣、認知症の血中バイオマーカーなどをまとめて解析した結果、スーパーエイジャーに特徴的だったのは、「同年齢の高齢者に比べて脳の容積の減少が少ない」こと、また、「運動速度の速さ、精神的健康度の高さ」でした。
なるほど、認知機能が低下した人を調べたのではなく、「高齢になっても認知機能を維持している人には何が起こっているのか」を比較的長期間観察した研究なのですね。スーパーエイジャーは脳の容積の減少が少ない、というのは具体的にはどういうことでしょう。
篠原さん:脳の部位でいうと、「内側側頭葉」の灰白質の容積が大きく、一般の高齢者と比べて萎縮が緩やかだったということです。「内側側頭葉」とは、大脳の両横にあり、ちょうどこめかみから耳の後ろぐらいの範囲にあります。内側側頭葉には、記憶に関わる「海馬」も存在します。
(元イラスト:gotooo/stock.adobe.com)
ちょっと話は飛びますが、この内側側頭葉と海馬の情報のやりとりをしているのが内側側頭葉の最も内側にある「嗅内野」なのですが、この部位も極めて記憶にとって重要な役割を果たしています。米国ノースウェスタン大学は、スーパーエイジャーが亡くなった後にその脳を分析し、スーパーエイジャーでは嗅内野のニューロン(情報伝達を行う神経細胞)が、20~30歳若い人よりも大きく、萎縮していないことを確かめました(*2)。
*1 Lancet Healthy Longev. 2023 Aug;4(8):e374-e385. *2 J Neurosci. 2022 Nov 9;42(45):8587-8594.
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 19
体の老化とともに最近、脳の老化も気になる――。「ほら、あれあれ!」と固有名詞がどうしても出てこなかったり、変化の激しい仕事環境についていけなかったりすることも増えてくる。本連載では、公立諏訪東京理科大学工学部教授で脳科学者の篠原菊紀さんに、脳にまつわる素朴な疑問や悩みの解決法について聞いていく。
有料会員になると、鍵つき記事が全て読める&医療専門家に電話相談や名医紹介も!
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 20
強い痛みや水ぶくれを伴う発疹が出る「帯状疱疹」。体内に潜伏する水ぼうそうのウイルスが、数十年を経て暴れ出す病気だ。早期の抗ウイルス薬で治まりやすいが、後遺症が残ることもある。そこで、発症はもちろん、重症化や後遺症も最低限に抑える切り札として期待されるのが、2025年4月より定期接種となった帯状疱疹ワクチンだ。帯状疱疹ワクチンや抗ウイルス薬の選択肢、かかりやすい人の傾向や症状などについて、中野皮膚科クリニック(東京都)院長の松尾光馬氏に聞いた。
(写真:PIXTA)
水ぼうそうと同じウイルスが帯状疱疹の原因に
帯状疱疹はどんな病気なのでしょうか。典型的な症状の出方を教えてください。
松尾氏(以下敬称略):帯状疱疹の原因は、水ぼうそう(水痘)と同じ「水痘・帯状疱疹ウイルス」です。このウイルスは、子どものころにかかった水ぼうそうが治った後も神経の根元(神経節)に潜んでいます。40~50年を経て何らかのきっかけで再び活性化し、発症するのが帯状疱疹です。単純ヘルペスウイルス1型や2型により口唇や性器などに症状が出る「単純ヘルペス」と似ていると思うかもしれませんが、また別の病気です。
帯状疱疹の症状は、ピリピリ、チクチクする前駆痛から始まります(図1)。3~4日経つと、そこに水ぶくれを伴う赤いぷつぷつとした発疹も加わります。痛みと発疹に時間差があるのは、ウイルスが活性化して増殖する時間と、ウイルスが神経から皮膚の表面まで移動するのにも時間がかかるからです。
図1 帯状疱疹が発症する仕組み
(原画:PIXTA)
帯状疱疹の症状は1~2週間で治まるのが一般的ですが、高齢になると痛みが残りやすくなります。3カ月以上続く痛みは「帯状疱疹後神経痛」と呼ばれ、50歳以上の患者さんの約2割に見られる後遺症です。
帯状疱疹の症状は体のどこに出やすいのでしょうか。
松尾:ウイルスが潜む神経節は、胸や背中、腹部、腰などの「体幹」に多く存在しています。そのため、帯状疱疹の症状も体幹によく現れます。しかし、高齢になると、若い人の10倍くらい、三叉(さんさ)神経がある顔面に出現することが増えてきます。
痛みや発疹が体の片側だけに、神経に沿って現れるのが帯状疱疹の典型例です。体幹に痛みがあると整形外科を受診する人が多いのですが、痛みに続いてその部位に発疹が出たら早めに皮膚科を受診しましょう。
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 21
期待の新薬、治療ガイドラインの改訂、革新的な医療機器の登場―。今、医療の様々な分野で注目されている最新の治療トレンドを、専門医が分かりやすく解説します。
有料会員になると、鍵つき記事が全て読める&医療専門家に電話相談や名医紹介も!
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 22
葉石かおり=エッセイスト・酒ジャーナリスト
年をとるにつれ、肌などの見た目はもちろん、筋肉や内臓などの機能も少しずつ低下していく。「老化」を進める大きな要因に「酸化」がある。鉄がサビるように、体内の細胞が傷ついて老化を進め、さまざまな病気の火種になる。酸化を進める要因はいくつかあるが、その1つに飲酒があるという。実際にどのくらいの影響があるのだろう。酒飲みとしては気になるところだ。酸化ストレスの研究者である同志社大学大学院生命医科学研究科教授の市川寛氏に直撃して話を聞いた。
私事だが、来年はいよいよ還暦。第3のお年頃(初老)ともなると、気になるのが「老化」である。顔はもちろん、気づけば首や腹回りがシワッとしており、自慢だった体力にも陰りが見え始めていた。目をそむけ、耳をふさぎたくなる「老化」というワード。だがありがたくも最近では老化研究がより進み、さまざまなことが分かるようになってきた。その中でも老化の要因として知られているのが「酸化」である。紫外線に当たりすぎて「老け見え」するのも酸化の影響が大きいらしい。
実は筆者もゴルフをやめて過度な日焼けから遠のき、それに加え徹底的に節酒するようになったところ、すこぶる肌の調子がいい。先日も美容皮膚科で「以前より肌の水分量が上がり、柔軟性が出ている」とドクターから言われたばかりである。
これはもしや、酒も酸化に関係しているのだろうか? 気になって調べたところ、「飲酒は酸化を進める要因」という一節を目にした。酒好きとして、これはもう放っておけない。そこで同志社大学大学院 生命医科学研究科 教授で、酸化ストレス研究の第一人者である市川寛氏に酒と酸化の関係について話を伺った。
「酸化」は、老化はもちろんさまざまな病気の引き金に
先生、まず老化の原因である「酸化」について教えてください。
「酸化とは、酸素によって体の細胞や物質が“サビる”こと。身近な例でいうと、切ったりんごを放置しておくと茶色くなる、釘がサビるなどが挙がります。実は私たち人間の体の中でも酸化が起こっています。酸化を引き起こす原因はさまざまありますが、例えば紫外線を浴び続けた皮膚の細胞がダメージを受け、シミができるのも酸化によるものです。このように酸化によって細胞が傷つき、有害な作用が生じることを“酸化ストレス”と呼びます」(市川氏)
(写真はイメージ:PIXTA)
先週レーザーで取ったばかりのシミも酸化の仕業だったのか。しかし、なぜ私たちの体の中で酸化が起こってしまうのだろう? そのメカニズムが気になる。
「酸化の主因は活性酸素です。活性酸素とは、酸素を含んだ反応性の高い分子の総称で、他の物質を酸化させる強い力を持っています。反応性が高く、体内のたんぱく質や脂質と反応して細胞にダメージを与え、老化を進めるほか、さまざまな病気の引き金となってしまうのです」(市川氏)
なんと恐ろしい…。だが、原因が活性酸素なら、活性酸素を遠ざけるように対策をすれば大丈夫ということだろうか。
市川氏は、実は酸化は体の中で常に起こっていることなのだという。「私たちは空気中の酸素を取り込んで生きていますよね。細胞内にあるミトコンドリアは体に取り込んだ酸素を使ってエネルギーを作っています。そのプロセスで取り込んだ酸素の1~2%が活性酸素となるのです」(市川氏)
ミトコンドリアと活性酸素の関係
ミトコンドリアは、酸素を使ってエネルギーを作り出す細胞小器官。ミトコンドリアでは、使用する酸素の1~2%にあたる活性酸素が副産物として発生する(原図:PIXTA)
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 23
ビジネスでも、プライベートでも、「酒」が同席する機会は少なくない。ましてや日本の文化に「酒」はなくてはならないもの。祝い酒、嬉し酒、やけ酒、涙酒…。「アルコールはガソリン!」という“超・左党”たちから、「アルコールとは時々仲良し」という“準・左党”たちまで、皆に役立つ酒と健康の最新科学を贈る! (タイトル題字:葉石かおり)
有料会員になると、鍵つき記事が全て読める&医療専門家に電話相談や名医紹介も!
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 24
テレビ界きっての多趣味人で、博識の石原良純さん。人生により磨きをかける日々の中で感じている、カラダのこと、天気のこと、そしてニッポンのこと。何事も前向きに生きれば、日々是好転! (タイトル写真:岡﨑健志)
石原良純(いしはら よしずみ) 俳優・気象予報士
有料会員になると、鍵つき記事が全て読める&医療専門家に電話相談や名医紹介も!
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 25
日本古来の古武術には、日常生活においても体に負担をかけず、楽に動くためのヒントがたくさん隠されている。筋トレなどで体を鍛えなくても、今日から身軽に動ける上に、腰や膝を傷めにくくなる。そんな「古武術」式の日常生活動作をここでマスターしよう。講師は、理学療法士・介護福祉士として古武術を応用した合理的な体の使い方を研究する岡田慎一郎さんだ。
岡田慎一郎(おかだ しんいちろう)氏 理学療法士、介護福祉士、介護支援専門員
有料会員になると、鍵つき記事が全て読める&医療専門家に電話相談や名医紹介も!
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 26
従業員の健康管理を経営的視点でとらえ、戦略的に実践する「健康経営」を推進する動きが企業の間で活発化している。その一方で、「何から始めればいいのか分からない」「取り組んではいるものの、成果を実感できない」といった経営者・担当者の声も聞かれる。そこで本連載では、有識者や先行企業への取材から、健康経営に取り組む上での悩みや疑問を解決に導くヒントを探っていく。
有料会員になると、鍵つき記事が全て読める&医療専門家に電話相談や名医紹介も!
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定