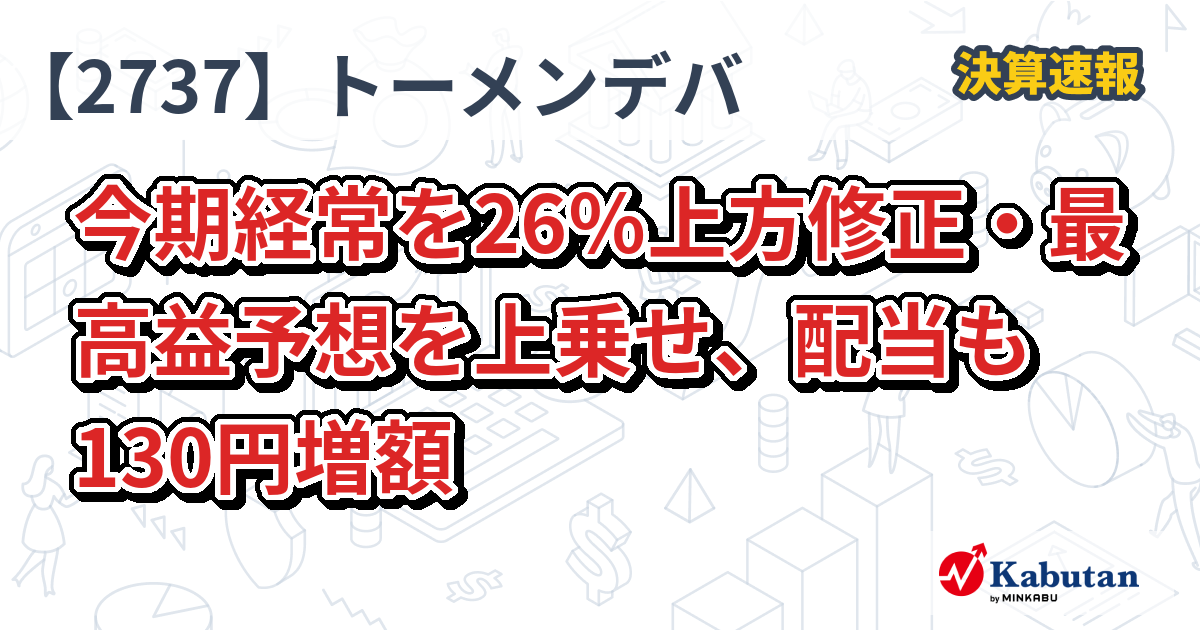約1億5000万円! 日産「すごい"GT-R"」実車展示! 曲線美まとった「ワイド&ロー」デザイン! 720馬力を誇る"特別な"「GT-R50 by イタルデザイン」とは

会場内の主催者特別展示では、「ニッサンとイタリアンデザインのクリエーション」をテーマに、デザインや生産などの面でイタリアと深い関わりを持つ日産車が4台展示されていました。
そのひとつが、2021年モデルの「GT-R50 by イタルデザイン」です。
このモデルは、イタリアの名門カロッツェリア「イタルデザイン」が創立50周年を迎えた2018年と、日産が2019年に3代目スカイライン(通称ハコスカ)に設定された高性能モデル「スカイラインGT-R(PGC10型)」のデビュー50周年を迎えることを記念して製作された特別な1台です。
2018年6月には、イギリスの「グッドウッド・フェスティバル・オブ・スピード」で初披露され、世界限定50台の発売が発表されました。同年12月に受注を開始し、2021年から生産がスタートしています。
価格は約1億5000万円という超高額モデルであったことから、世界中のクルマ好きを驚かせ、大きな話題を集めました。
GT-R50 by イタルデザインのベースとなったのは、その車名が語る通り日産が誇るスポーツカーのR35型GT-Rです。
外観は、GT-Rのアイコンとも言える縦長のヘッドライトやフロントの大きな開口部、特徴的な形状のウィンドウグラフィックやルーフのイメージを残しつつ、さらにシャープな印象に。
ボディサイズはR35型GT-R(全長×全幅×全高)と比べて、全長が94mm、全幅では91mm大きくなっていますが、全高は54mm、も下げられており、伸びやかでワイドなプロポーションを実現しています。
車重は未公表ですが、ボディパネルの多くは、カーボンファイバーとアルミニウムを採用しており、軽量化に貢献しているものと思われます。
リアにはフローティングタイプの可動式リアスポイラーを装備。スカイラインとGT-Rの象徴ともいえる丸型4連テールライトは、大きくアレンジを加えられながらもGT-R50 by イタルデザインにもしっかりと受け継がれています。
搭載されるエンジンは、GT-Rではおなじみの3.8リッターV型6気筒 DOHCツインターボ「VR38DETT型」です。
しかしGT-R50 by イタルデザインでは専用チューニングが施され、最高出力は720ps・最大トルクは652Nmへと向上しています。
この数値はFIA(国際自動車連盟)のGT3規定に沿って開発されたレース仕様モデル「GT3」よりも高く、エクステリアに見合う性能を誇ります。
イタルデザインは、正しくは「イタルデザイン・ジウジアーロ」と称し、1968年に名だたる名デザイナーのジョルジェット・ジウジアーロ氏によって設立されました。
「フィアット・パンダ(初代)」や「フォルクスワーゲン・ゴルフ(初代)」といった実用車から、「ロータス・エスプリ」、「マセラティ・メラク」、「デロリアンDMC-12」といったスポーツカー、さらには小型3輪トラック「アペ」に至るまで、イタルデザインは多岐にわたる自動車のデザインを手がけてきました。
2010年以降はフォルクスワーゲングループの傘下に入り、現在もその活動を続けています。
ここまで説明すると、GT-R50 by イタルデザインは「デザインを行なったのはイタルデザインで、生産は日産」と思うかもしれません。
実際、GT-R50 by イタルデザインのスタイルはイタリアン・エキゾチックカーを彷彿とさせる迫力と美しさ、そしてほどよいエキセントリックさを併せ持っています。
ところが意外なことに、内外装デザインを手がけたのは日産側で、開発・生産はイタルデザインが担当。
イタルデザインはデザインだけでなく研究開発部門や生産拠点も有しており、GT-R50 by イタルデザインは、同社の3箇所の工場で部位ごとに生産を行なっています。
生産はほぼ手作りで、栃木工場を出荷後空輸でイタリアに運ばれたGT-R NISMOは、イタルデザインの工場で分解され、ボディの骨格の上に新たにボディパネルが組み立てられていきます。
1台作るのに半年以上かかり、内外装の仕様をフルオーダーで選べるということなので、1億5千万円という価格は納得です。
なお会場に展示されていたGT-R50 by イタルデザインは、マット仕上げの青をまとっていました。
※ ※ ※
日本にも数台から十数台が上陸しているとされるGT-R50 by イタルデザイン。
一般道で見かけることはほとんどないであろうドリームカーですが、イベント会場では間近でじっくりと鑑賞できるのが嬉しいポイントです。
こうした希少車に出会えるのも、オートモビルカウンシルというイベントの奥深さを改めて実感させてくれる瞬間でした。