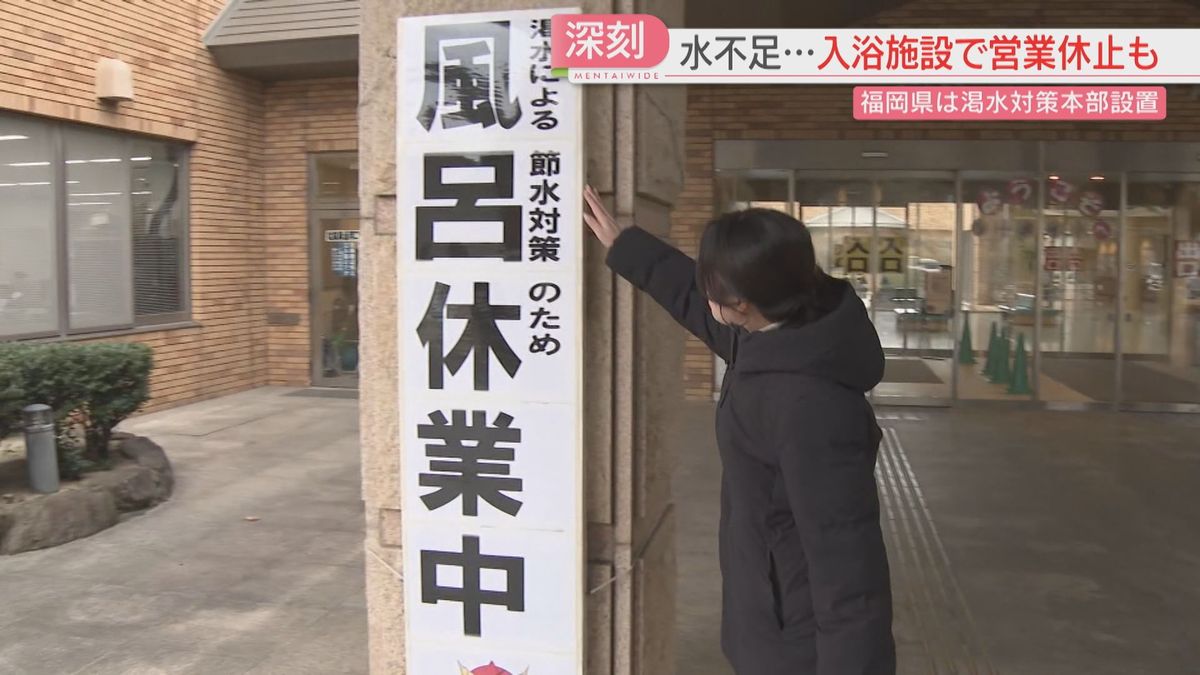Dialogue for People

記事中に戦没者の方のご遺骨の写真を掲載しています。
「遺骨には、戦死者には、人と会う権利がある。あなたが撮った写真の掲載されたものが、偶然、遺族の元に届くことだってあり得る。生まれた家のテレビに映されたり、その居間で新聞が開かれたりするかもしれない。写真を通してこの人が家に帰れるようにと、念じながら撮って下さい――」
2021年4月、沖縄戦の戦没者遺骨収集を続ける「ガマフヤー」代表、具志堅隆松さんの活動現場を初めて訪れたときのことだ。旧日本軍の壕から次々と掘り出される遺骨を前に、私がシャッターを切ることを躊躇していると、具志堅さんがこう、語りかけてきた。
その後も具志堅さんと共にガマや壕に入るとき、必ずこの言葉を心に刻みなおすようにしている。伝える者として、そして「本土」に生まれ育ち、今なお沖縄に負担を押しつけている側にいる者として、忘れてはならない畏怖だと思うからだ。
4年前に具志堅さんと訪れたのは、沖縄本島、糸満市・束辺名(つかへな)グスク近く(旧喜屋武村)の山中にある日本軍の構築壕だった。今年4月、この壕からほど近い斜面で、ほぼ全身の、それも埋葬された可能性の高い遺骨が見つかった。具志堅さんは発見後、警察と状況を確認の上、周辺を含めた捜索を継続している。
「埋葬された全身遺骨、珍しい」情報提供呼びかけ
「ここに来ているのは、戦争で亡くなった方の姿を世の中に伝えたいと思っている方です。どうか見ること、会うことを許して下さい」
しゃがみ込んで手を合わせた具志堅さんが、ビニール製の雨合羽をそっとどかすと、地中に横たわった「その人」が姿を現した。
具志堅さんが発見した全身遺骨。(安田菜津紀撮影)
身長は160センチ前後とみられ、歯にはほぼ摩耗した痕跡がない。他の骨の状態からも、推定で15歳から20歳前後ではないかと具志堅さんは見ている。
この周辺でも激戦が展開されたと見られ、近くの構築壕の壁には火炎放射を受けた跡が残るほか、今回発見された遺骨の周りからも、日本軍、米軍双方の薬莢なども見つかっている。
顔面の鼻骨周辺は陥没し、上あごの歯も内側にめり込んでいた。口の中には、片手にすっぽりとおさまるほどの石が残されている。
「おそらく近くで砲撃があって、その破裂で飛んできた石が顔を陥没させたんでしょう」
顔面が陥没した頭部。(安田菜津紀撮影)
具志堅さんが全身かつ埋葬されたらしい遺骨を見つけるのは、那覇市真嘉比で開発前に捜索を行った2009年以来だという。しかも真嘉比では、埋葬されたとみられる遺骨はほぼ上官とみられるものだった。若い兵士が埋葬された状態で見つかるのは、非常に珍しいという。だからこそ少しでも身元の手がかりを集められないか、具志堅さんは情報提供を呼びかけている。
遺骨と一緒に見つかった軍服のボタン。真鍮製や鉄製のものではなく、ベークライト製のものだという。(安田菜津紀撮影)
今に継がれる激戦の証言
「その人」は一体、誰なのか。
束辺名に築かれた壕については、かつて県立第二中等学校(二中)三年生で、学徒通信兵として動員された山城寛則さん(当時15歳)の証言が残る。石原昌家著(1984年)『証言・沖縄戦: 戦場の光景』(青木書店)によると、山城さんがその壕にたどり着いたとき、兵士と学徒兵約300人がいたという。米軍の進撃に応戦したのは、6月20日前後と記してある。
「壕の中から機関銃を撃ちまくるので、壕内はガンガン反響していました」
「敵は爆雷とか火焔放射器を壕内に浴びせて、さらに爆雷で壕出入口をふさいでしまったのです。壕内には硝煙がたちこめました」
「防毒マスクを持っている兵隊はそれをはめるが、敗残兵なんかはそういうのは持っていないので、ガスでやられてバタバタ倒れるのです」
「名城さんという牧志(那覇市)で薬局をしていたひとが、榊原軍医と行動をともにしていました。このかたが私のそばにいて、10センチくらいの厚みのガーゼを手渡してくれたのです」
『証言・沖縄戦: 戦場の光景』より
その後、三々五々に壕から脱出し、国頭(くにがみ)へと向かおうとしたときには、諸見里ヤスヒロさん、上原さんが一緒だったと山城さんは記憶している。
「その人」は学徒だったのか、地元の兵なのか、それとも沖縄ではないところから派兵された日本兵なのか――。これまでに掘り出された手がかりだけでは断定は困難だ。
遺骨のもとを離れる前、具志堅さんはまた「その人」に祈りを捧げた。
「私たちは戦争で殺された人たちの被害を現代に伝え、二度と戦争が起きないようにしたいと思っています。みなさんのこの姿を通し、戦争の実相を伝えていきます」
束辺名の山中を歩く具志堅さん。(安田菜津紀撮影)
「記憶」引き合いにした西田議員の発言
前述の山城さんの姉は、ひめゆり学徒隊(日本軍に動員された沖縄師範学校女子部・県立第一高等女学校の生徒222人と教師18人)であり、この壕周辺が激戦となる前、その姉が自分を訪ねてきたとも記されている。
「半時間ほど話しましたが、姉とはここで別れたっきりです」
『証言・沖縄戦: 戦場の光景』より
2025年5月3日、自民党・西田昌司参院議員が、那覇市内で開かれた「憲法シンポジウム」(県神社庁など主催、自民党県連共催)で、ひめゆりの塔を20年以上前に訪れた当時の「記憶」を引き合いに、こんな発言をした。
「何十年か前、国会議員になる前にお参りに行きましたが、あそこ、酷いですね」
「あの説明のしぶり、日本軍がどんどん入ってきて、ひめゆりの隊が死ぬことになっちゃったと。そして米国が入ってきて、沖縄が解放されたと、そういう文脈で書いているじゃないか。亡くなった方々は本当に救われませんよ。歴史を書き換えられると、こういうことになっちゃうわけですね」
「(京都でも)ここまで間違った歴史教育はしていません」
「自分たちが納得できる歴史を作らないといけないと思います」
こうした発言や態度に対し、具志堅さんは言葉にしきれない思いを抱えているという。
「(西田議員は)沖縄の教育は無茶苦茶というけれど、被害を受けた地域には、被害を受けたことに対する教育があって当然だと思っています」
ひめゆりの塔の前で。(安田菜津紀撮影)
こうした発言をする議員は、具志堅さんの現場をなぜ訪れないのか――? そう私が尋ねると、具志堅さんはこう答えた。
「もし来たとしても、亡くなった人を英霊だと褒めたたえてもらいたくないんです。その人には家族がいたかもしれない、遺された家族は苦労したかもしれない。戦争から逃れることができない人を褒めたたえるのは誰の視点になるんでしょうか?」
「この人たちはここで死ななければならなかった存在なんでしょうか?」
「尊ぶ」ことが答えなのか
この日、ひめゆり平和祈念資料館には、多くの修学旅行生が訪れ、熱心にメモを取って周っていた。
ひめゆりの塔のすぐそばには、小さな慰霊塔がある。壕の中でひめゆり学徒らと犠牲になった民間人の大田さん一家の名が刻まれている「赤心之塔」だ。ここには、時間をかけ、見なければならないものがある。
大田さん一家の名が刻まれた「赤心之塔」(安田菜津紀撮影)
けれども西田議員は、発言後の一度目の会見(5月7日)で、ひめゆりの塔を再び訪れるつもりはあるとしながらも、「この前行きたかったんですけどね、とにかく遠いでしょ、私もそれなりに忙しいですから」と苦笑いして見せた。結局、どこまでも「他人事」なのではないか。ここで奪われた人たちの命は、自らの論を補強するための道具ではない。
時折、一部政治家が掲げる「尊い犠牲」という言葉に強い違和感を抱く。「尊ぶ」が今を生きる私たちの答えだろうか。なぜその命は奪われていったのか、それは国として防ぐことができなかったのか、むしろ国が犠牲を生み出した責任はどこへ行ったのか――。公権力者に求められているのは、その問いに向き合うことではないのだろうか。
ひめゆり平和祈念資料館のエントランスで。(安田菜津紀撮影)※許可を得て撮影しています。
1987年神奈川県生まれ。認定NPO法人Dialogue for People(ダイアローグフォーピープル/D4P)フォトジャーナリスト。同団体の副代表。16歳のとき、「国境なき子どもたち」友情のレポーターとしてカンボジアで貧困にさらされる子どもたちを取材。現在、東南アジア、中東、アフリカ、日本国内で難民や貧困、災害の取材を進める。東日本大震災以降は陸前高田市を中心に、被災地を記録し続けている。著書に『国籍と遺書、兄への手紙 ルーツを巡る旅の先に』(ヘウレーカ)、他。上智大学卒。現在、TBSテレビ『サンデーモーニング』にコメンテーターとして出演中。
あわせて読みたい
これからも、世界の「無関心」を「関心」に変えるために、Dialogue for Peopleの活動をご支援ください。
寄付で支える新着コンテンツやイベント情報、メルマガ限定の取材ルポなどをお届けしています。
LINEでも、新着コンテンツやイベント情報をまとめて発信しています。
友だち追加