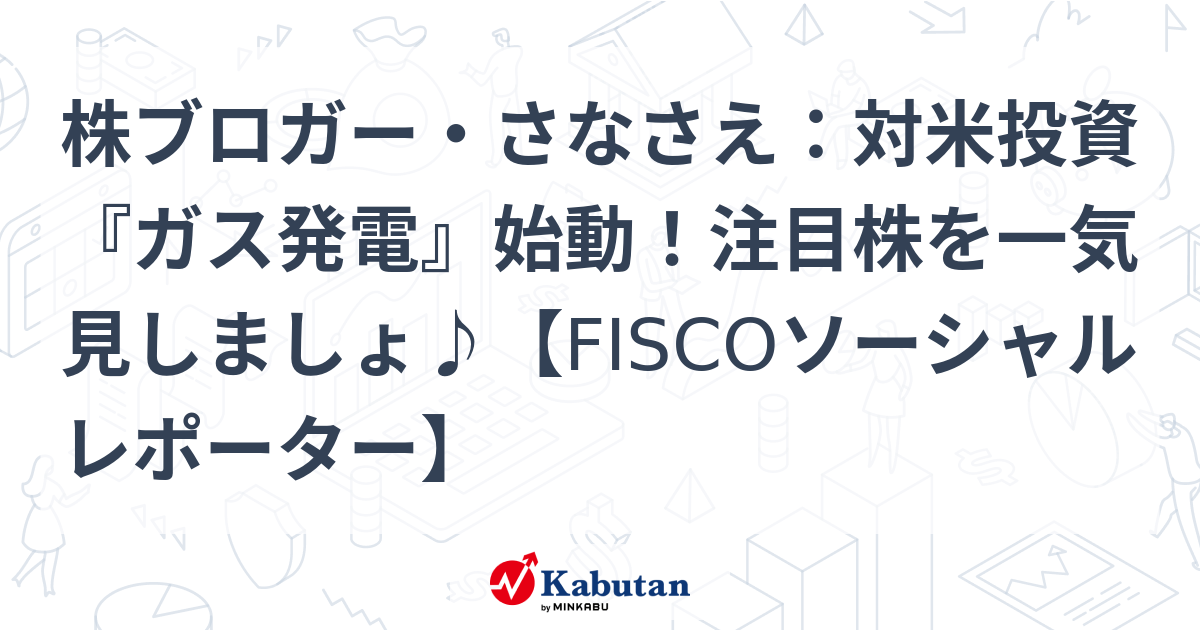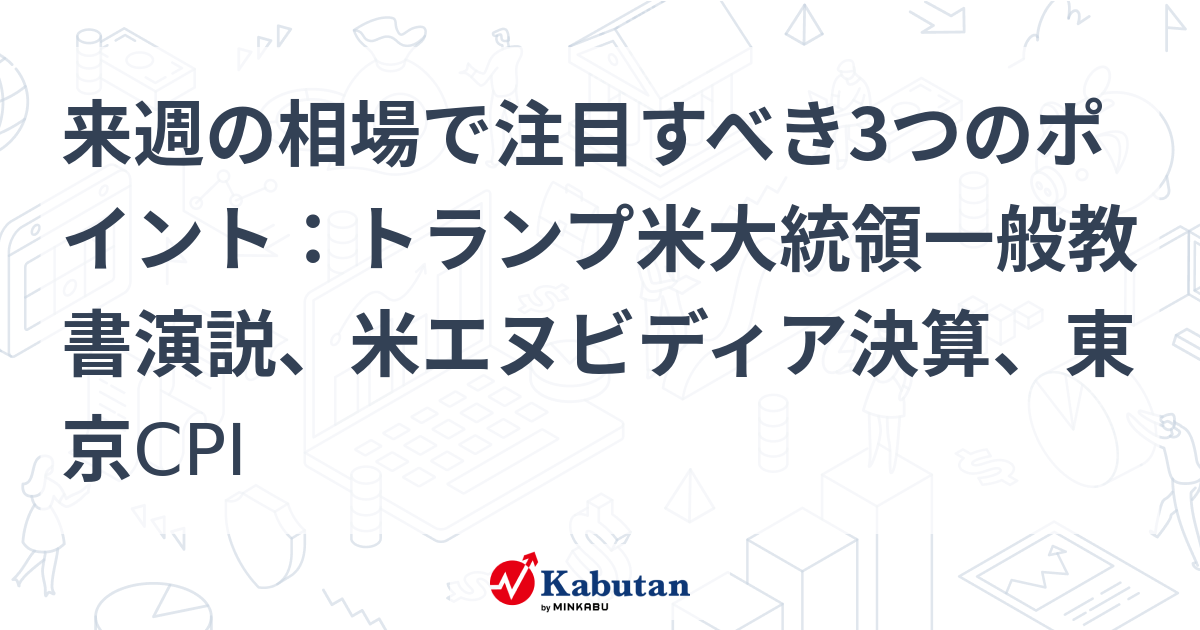コラム:難点だらけの年内利上げ、日銀は強行できるか=上野泰也氏

[東京 18日] - 8月1日に日銀から公表された「経済・物価情勢の展望」(展望レポート)の全文で、末尾近くの「各国の通商政策の動きとその影響:アップデート」に次の記述があった。
「米国の関税引き上げによる直接・間接の影響により、今年度のわが国企業収益は減益となる可能性が高まっている」
これは、前日7月31日に公表された展望レポートの基本的見解に、「経済の中心的な見通し」として「輸出や生産は、海外経済の減速を背景に、弱めの動きになると見込まれる。こうした動きを受けて、企業収益も、高水準ながらも減少するとみられる」と日銀が記したことと対応する内容だが、よりダイレクトな書きぶりである。
レポートでは上記の文章に続けて、次の説明がなされた。
「2025年6月短観で今年度の経常利益計画をみると、非製造業は底堅く推移する一方、製造業は、加工業種を中心に減益計画となっている。このような見通しが実現する場合には、先行きの賞与やベースアップなど企業による賃金設定行動にも影響を与えうるだけに、今後の動向を注意してみていく必要がある」
8月8日にピークを迎えた上場企業の25年4-6月期決算発表でも、25年度(26年3月期)通期は減益に転じる見通しである。主因は、「トランプ関税」によるコスト増に直面する自動車メーカーだ。米国の自動車関税が最初に提示された25%ではなく15%にとどまっても、今期収益への下押し圧力は大きい。
企業収益に生じているこうした変調を、どのように受け止めて動くか。株式市場と日銀では、動き方に大きな違いがあるように見える。
3連休明けの8月12日の東京株式市場で、日経平均株価は大幅続伸。前週末比の上げ幅は一時1100円を超え、昨年7月11日に記録していた史上最高値を塗り替えた。
日米関税交渉妥結と、合意内容が不明確だった部分の赤沢亮正経済再生相の訪米によるフォローアップをうけて、25年度の企業業績の悪化幅にまつわる不透明感が解消された。
「もはや最悪期は脱した」というムードの強まりが、株価急騰に結びついたと言える。25年度はこのまま減益になるとしても、次の26年度は増益に十分転じ得るという見方も、市場では広がったようである。
一方、日銀の場合は、企業業績の減益転換について、株式市場とは異なる反応の仕方にならざるを得ない。
植田和男総裁は7月31日の記者会見で、識者の一部から批判が出ている「賃金と物価の好循環」という言い回しを意識して避けていたように筆者には見えた。
だが、それに代わる新たな言い回しである「賃金と物価が相互に参照しながら緩やかに上昇していくメカニズム」が次の26年春闘に向けて維持されるかどうかは、日銀が利上げを進めようとする上で非常に大きな「要確認事項」である。
したがって、冒頭で引用した通り「今年度のわが国企業収益は減益となる可能性が高まっている」とした上で、「企業による賃金設定行動にも影響を与えうる」ため今後の動向を注意してみていく必要ありとしたことには、日銀の政策運営上、重い意味合いがある。
報道に出てきた匿名の日銀関係者による発言には、「(25年6月の日銀短観には)関税の影響は反映されなかった可能性が高い」、「影響は後ずれして出るのでは」、「今秋以降、思った以上に(企業の業況などの)弱い数字が出てもおかしくない」(毎日新聞)――といったものがある。
日銀短観の今後の発表予定は、次の9月調査が10月1日、12月調査が12月15日、26年3月調査が4月1日である。「トランプ関税」の悪影響が、上記の指摘の通りに後ずれして出てくるなら、悪影響の度合いをしっかり見きわめるためには9月調査のチェックだけでは足りず、12月調査まで日銀短観を最低でも2つは見きわめる必要があるだろう。
さらに、筆者が本欄を含めて以前より指摘している通り、企業収益が減少に転じる中での賃上げが26年春闘でどのような姿になるのかを手堅く確認するには、26年3月中旬の春闘集中回答日と、それを受けた連合による回答集計結果を待つ必要がある。
今年10月中旬あたりに連合が26年春闘での賃上げ要求水準を正式に決めて以降は、「25年春闘の好結果」から「26年春闘の見きわめ」へと、追加利上げに向けた視点は切り替わる。
日銀が26年の賃上げ率集計結果が手に入るのを待つことなく、もっと早く利上げに動きたい場合でも、年明け1月の日銀支店長会議の結果、特に、地方支店から上がってくる賃上げ状況についての報告は、最低限待つべきだろう。
このように整理すると、日米関税交渉妥結という好機に飛びつくことなく、おそらく参院選後の国内政治情勢見きわめの必要性を重視して7月末の金融政策決定会合での利上げを見送った日銀が、「あちら立てればこちら立たず」という難しい立場に追い込まれたことがわかってくる。
実現する可能性は現時点では小さそうだが、9月2日の氷見野良三副総裁による講演・記者会見での「地ならし」を経て、同月18、19日の金融政策決定会合で日銀が仮に追加利上げに動くなら、25年春闘の好結果を理由の一つとして前面に出すことはまだできる。その一方で、「トランプ関税」の影響見きわめに関し、短観9月調査の結果さえも確認していない点が批判される恐れは十分にある。
また、仮に自民党総裁選の前倒し実施が濃厚になる中で石破茂首相が辞意を表明し、総裁選が9月中下旬ごろに実施されることが決まる場合には、政治情勢見きわめの必要性から、日銀は9月の会合でも様子見継続を余儀なくされる可能性が高くなる。
次の10月29、30日の金融政策決定会合で日銀が利上げに動こうとするケースでは、短観9月調査の結果、および秋の支店長会議で地方から上がってくる報告を確認できるという利点がある。
とはいえ、視点が切り替わったばかりで、26年春闘の行方について不透明感がかなり強いにもかかわらず、見切り発車的に10月に利上げに動くことはリスクを伴う。
また、秋に召集されるとみられる臨時国会で連立政権の枠組み拡大問題がどうなるかなど、国内政治情勢がまだ十分落ち着いていない可能性もある。仮に「反利上げ」の議員が首相や財務相に就任するようなら日銀の追加利上げが政治的に封印されかねないことは、以前に本欄でも述べた通りである。
その次の12月会合での利上げを日銀が模索するケースはどうか。9月調査に12月調査が加わって、短観を2つ確認できることは利点である。
だがこのケースでも、26年春闘の行方を見きわめないまま拙速に利上げに動く形になることは、見逃し得ない弱点である。特に「なぜ年明けの1月会合まで少しだけ待って26年春闘の手ごたえを確認しないのか」と問われた際に、十分な説得力を持つ理由を見いだすのは難しい。
以上のように整理すると、次の利上げのタイミングとして、今年9月、10月、12月は、いずれも難点があることがわかる。
それでも日銀が年内に追加利上げを強行する場合には、理由の説明や政治への対応でかなりの苦労をすることは避けられそうにない。
市場との対話は円滑に行われにくく、金融市場では不規則な値動きが生じ得る。
編集:宗えりか
*本コラムは、ロイター外国為替フォーラムに掲載されたものです。筆者の個人的見解に基づいて書かれています。
*上野泰也氏は、経済・金融市場に関する情報を発信する「マーケットコンシェルジュ」の代表。会計検査院を経て、1988年富士銀行に入行。為替ディーラーとして勤務した後、為替、資金、債券各セクションにてマーケットエコノミストを歴任。2000年から25年6月までみずほ証券のチーフマーケットエコノミスト。25年7月より現職。
*このドキュメントにおけるニュース、取引価格、データ及びその他の情報などのコンテンツはあくまでも利用者の個人使用のみのためにコラムニストによって提供されているものであって、商用目的のために提供されているものではありません。このドキュメントの当コンテンツは、投資活動を勧誘又は誘引するものではなく、また当コンテンツを取引又は売買を行う際の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。当コンテンツは投資助言となる投資、税金、法律等のいかなる助言も提供せず、また、特定の金融の個別銘柄、金融投資あるいは金融商品に関するいかなる勧告もしません。このドキュメントの使用は、資格のある投資専門家の投資助言に取って代わるものではありません。ロイターはコンテンツの信頼性を確保するよう合理的な努力をしていますが、コラムニストによって提供されたいかなる見解又は意見は当該コラムニスト自身の見解や分析であって、ロイターの見解、分析ではありません。
私たちの行動規範:トムソン・ロイター「信頼の原則」, opens new tab
筆者は「Reuters Breakingviews」のコラムニストです。本コラムは筆者の個人的見解に基づいて書かれています。