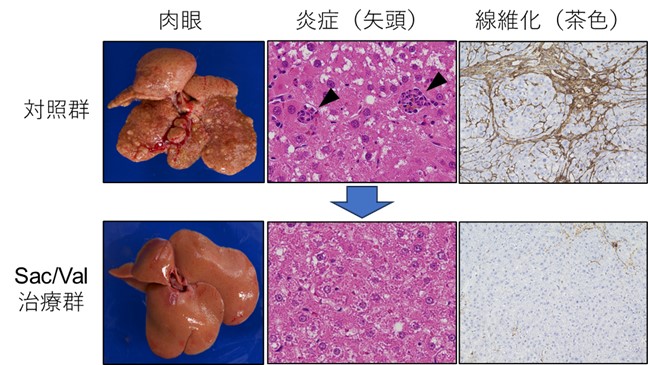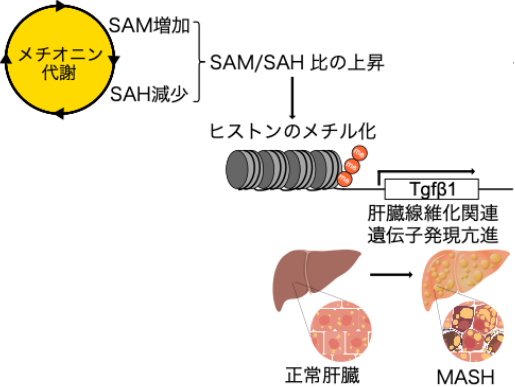遺伝子組み換え作物 - びお編集部 | びおの珠玉記事

びおの珠玉記事
第203回
※リニューアルする前の住まいマガジンびおから再掲載しました。 (2013年04月15日の過去記事より再掲載)
草木が萌え、周囲に緑が増えてきました。 植物は地球上で唯一の生産者であり、人間を含めた多くの生き物の直接の糧になっています。 直接の食物だけでなく、食肉の生産にも飼料としての植物が必要です。
酸素の供給も含めて、植物がなければ今の地球はなりたちません。
農業は、そんな植物の生産を自然に任せず、人の手で行うようにしたものです。 農業は英語でagriculture、文化を意味するcultureと同じ、ラテン語のcolere(耕す、育む)を語源にしています。
人間以外の生き物はみな、自然の環境下にあるものからエネルギーを得ています。コアラがユーカリを、パンダが笹を食べるように、そこにあったものを食べる、という生き物に進化していきました。
人はなぜそのようにせず、植物を栽培するようになったのでしょうか。 知恵を獲得したから、とも言えますが、そうしなければ食べ物が手に入らなかった、ということもあるのかもしれません。
農業を営むようになって徐々に増えてきた人口は、産業革命を経て爆発的に増えていきます。先進国の人たちは、「そこら辺にあるもの」を自力で穫ることを諦めて、代わりに生活習慣病を手に入れました。下のコラムは「住まいを予防医学する本」から、肥満という現代病の話です。
私たち人類も、野生動物と同じように飢餓にそなえるしくみを持っています。先進諸国では食料獲得にほとんどエネルギーを使うことがありませんが、からだには飢餓に備えるしくみがありますから、どんどんエネルギーがたまっていきます。これが現代型の肥満です。
肥満を最初に生み出したアメリカでは、その肥満人口は全人口の30%とも50%ともいわれています。
ハンバーガーに代表されるファストフードや炭酸飲料など、カロリー(熱量)の高い食事を大量摂取し、車社会によって運動することもなく、アメリカは肥満大国となりました。ファストフード企業に対して、“自分が太ったのはハンバーガーを食べさせた企業の責任だ”、という訴訟は、極端ではありますが、現代アメリカを象徴するエピソードです。
そしてアメリカ化を望む諸国は肥満をも輸入、日本もいまや肥満大国への道を歩みつつあります。
一方で、肥満先進国アメリカでは、肥満に対して規制する動きをみせています。学校の自動販売機で清涼飲料水を販売することを禁止する州が現れ、ニューヨーク市では、市内のレストランに対して肥満の原因となるトランス脂肪酸の使用中止を指導、また各ファストフードチェーンも、トランス脂肪酸の少ない油脂への切り替えを始めています。
これらの取り組みが、肥満増加の抑制に効果を上げられるのか、そもそもの生活スタイルが変わらなければ焼け石に水なのか、いろいろな見方がありますが、現代型肥満を生み出したアメリカが、今度はその解決方法も生み出せるのであれば、各国もまた、それにならうのでしょうか。
日本では、肥満の定義として、BMI(Body Mass Index:体格指数)が よく用いられます。BMIはあくまでも体重と身長の単純計算のため、筋肉太りなのか脂肪がついているのかまでは判断できませんが、日本では25を、アメリカでは30を超えると肥満とされています。
また、体脂肪率による診断も定着してきました。年齢にもよりますが、男性の場合は25%、女性は30%を超えると肥満とされることが多いようです。
肥満の原因となりやすいのは、炭水化物(糖質)と脂肪です。炭水化物は体内で糖分となり、からだを動かすエネルギーとなったり、グリコーゲンとしてからだに蓄積され、必要に応じてエネルギーとして使われます。
しかし、余剰分は脂肪となってからだにたまります。つまり、たんぱく質とは異なり、余剰分は排出されずに蓄積されますので、肥満の原因となるのです。
脂肪は、エネルギー源としての働きのほかに、細胞やホルモンを構成する成分となります。この脂肪を、エネルギーとしてもからだの成分としても使わずに、蓄積した結果が肥満です。
「メタボリックシンドローム」は、内臓脂肪型の肥満に、高血圧、高血糖、脂質異常(高脂血症)を併発した状態を指します。これらの危険要素は、動脈硬化を促進し、心臓病や脳卒中などを起こすといわれています。LDLコレステロール(俗にいう悪玉コレステロール)が活性酸素と結びついて血管を痛め、動脈硬化を促進します。
また、脂肪細胞からは、血液中の糖分を分解する作用を持つインシュリンの働きを阻害する物質が分泌されるため、すい臓がインシュリンを過剰に生産し、結果的にインシュリンが枯渇、糖尿病をまねきます。睡眠中に呼吸がとまる睡眠時無呼吸症候群も、肥満との関係がいわれている病気です。肥満によって咽頭や胸部が圧迫されることによって生じます。
さらに、体重によって軟骨を摩耗させる変形性膝関節症などもあり、まさしく内科的にも外科的にもさまざまな疾患を引き起こします。
肥満のメカニズムは簡単です。消費するカロリーと摂取するカロリーのバランスがとれていれば肥満は起こりません。すでに肥満の人は、摂取カロリーよりも消費カロリーが上回るようにすれば当然やせます。
しかし、誰もが鉄の意志をもって実行できる訳でもありません。ましてや、テレビや雑誌で紹介されるダイエット法のような、魔法のように何かでぐんぐんやせる、というのも、ねつ造番組などもあり、信憑性の面で眉唾ものです。脂肪吸収を押さえる飲み物がヒットしているのは、予防という観点よりも、むしろ免罪符のように使われているのでは、という気もします。
鉄の意志も持てず、魔法も利かない、そうであるのならば、肥満を生んだ社会的背景、生活スタイルを考え、それをあらためていくことが、結果として肥満の予防につながりましょう。
肥満の多くは、生活スタイルの欧米化・近代化に起因しています。高カロリーな食事と、車の普及による運動不足が背景にあります。予防のヒントになるのは、肥満が日本に輸入される前の生活です。今までより少し粗食にしてみる、今よりももうちょっと機械任せの部分を減らす、というのが、よく言われていますが、結局のところそれが、健康的な肥満予防の糸口であり、有効な解消法です。
遺伝子組み換えの表示について
農業の話になると、現在焦点があてられているのが、TPPによる「聖域」です。 関税の撤廃による「安い農作物」が入ってくると、日本の農業は壊滅的なダメージを受ける、という主張があります。「聖域」がいつのまにか「センシティブな品目」に変わってしまいましたが、関税の他にも、気になることがあります。
今年3月、アメリカで包括予算割当法案が可決されました。その中に、「モンサント保護法」と揶揄される条項があり、話題になっています。
モンサント社※1は、アメリカに本社を置く化学メーカーです。除草剤ラウンドアップと、その除草剤に耐性を持つ遺伝子組換え作物の両方を売るなどして、現代の農業(と、それ以外にも)に大きな影響力を持つ企業です。
この法案の735条に、遺伝子組み換え作物が原因と思われる健康被害があっても、因果関係が証明されなければ法的な差し止めは出来ない、という条項があります。 アメリカでは従来も、遺伝子組み換え作物の表示がありません(アメリカ流にいえば、遺伝子組換え食品を食べてもらう自由、なのでしょうか)。
一方、EUは遺伝子組換えに対する規制が日本以上に強く、これに対してアメリカから報復措置をするように働きかけた文書がウィキリークスに公表されています。
こうした動きはモンサントの強力なロビー活動によるものだといわれています。
TPPに関連して、日本の非関税障壁の一つとして、こうした遺伝子組換えに対する表示義務があげられています。
遺伝子組み換えでない場合の表示(大豆)。小麦は表示対象外ですが、モンサントは小麦の組み換え品も開発中。いずれは小麦も? その前に表示自体がなくなるのか?
F1種と遺伝子組換え
以前、「びお」で「固定種」の話を取り上げました。 固定種とは、昔からある遺伝的に安定した品種です。それに対してF1種とは、栽培に適した性質をもった交配種という、栽培に適した性質をもった一代限りの雑種です。F1から出来た種(F2)は、育てやすく売りやすいF1とは別の性質を持っていることが多いため、自家採種では、別の性質をもった作物が出来てしまいます。安定した出荷のためには、F1の種をまた買う必要があります。
F1種は珍しいものではない、どころか、固定種のほうが、もうずっと珍しくなってしまっています。スーパーマーケットで野菜を買おうとすれば、それはもう全部F1種といっても過言ではありません。 F1種か固定種かの表示義務はありません。
こう聞くと、何か操作された食べ物のような気がして、遺伝子組み換え食品と勘違いをする方もいるのですが、F1種、という表現は、あくまで一代限りの性質をもった交配種を指します。
これに対して、遺伝子組み換え作物は、明確な目的をもって遺伝子を操作してつくられたもの。有名なのは、バチルス・チューリンゲンシスという、本来その植物が持たない殺虫作用をもったタンパク質を作る遺伝子を組み込み、害虫への抵抗力を持たせたものです。
遺伝子組み換え食品は危険なのか、という議論はつねにつきまといます。長期的な徴候を見ようと思っても、食品は、それだけを食べ続けるわけでもないので、正確なところはまだわからない、といっていいでしょう。遺伝子組み換えによって収穫量が増える、農薬の量が減らせる、というメリットをいう人もいます。そして反対する側の心理には、疑わしきは遠ざけたい、という予防原則が働いています。
作り手側からすれば、「安いもの、安定したもの、年中食べられるもの」を求めたのは消費者だ、と文句のひとつも言いたくなるかもしれません。遺伝子組み換えだけでなく、食品添加物等、食の安全に関わる項目はたくさんあります。
アメリカで遺伝子組み換えの表示義務がなく、そしてTPPという名のもとに、同様の基準を日本にも、という機運が盛り上がるのかもしれません。確かに日本の遺伝子組み換えの表示は、ちょっとぐらい入ってても「遺伝子組み換えでない」と表示できたりしてしまうなど、甘いところもありますが、それでも消費者は表示に基づいて一定の選択をすることができるはずです。 危険かどうかの判断をしようにも、その事実さえ知らせてもらえない社会に、突入しようとしているのでしょうか。仮に生産者に戸別補償をしたところで、その疑念は晴れません。遺伝子組み換え作物そのものもいざしらず、こうした風潮自体が、よほど危険だと感じます。