幼少期のトラウマは脳を物理的につくり変える──心理学者が解説する2つのメカニズム(Forbes JAPAN)
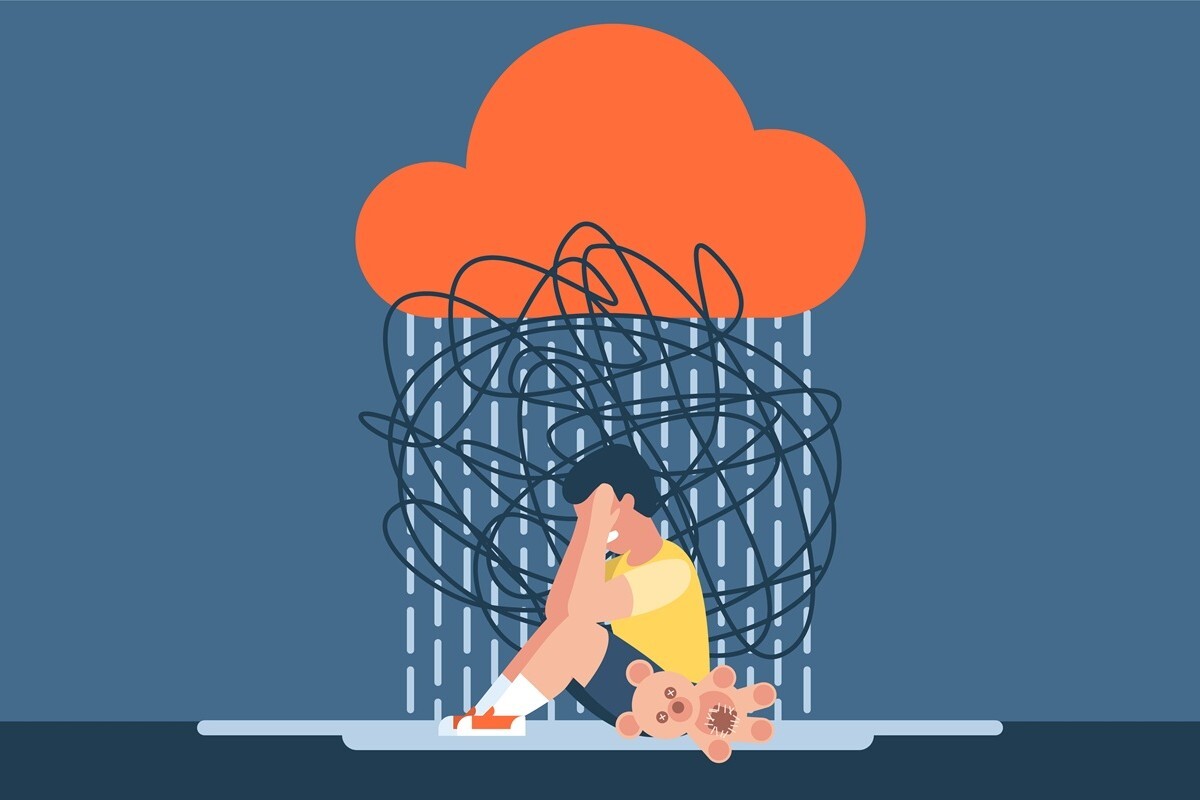
幼少期のトラウマ(心的外傷)体験は往々にして、成長したあとに深刻なメンタルヘルスの問題として顕在化することを、見識ある人の多くは知っている。しかし、トラウマが具体的にどのように精神的疾患を引き起こすのかを知る人は、ほとんどいない。 なかにはこうしたつながりを、感情的瘢痕(はんこん)、つまり精神的にのみ存在する「心の傷」によるものとして説明する人もいる。けれども、2022年に学術誌『Brain, Behavior, & Immunity - Health』に掲載された論文によれば、こうした傷はけっして単なる比喩ではない。トラウマは脳に対して、裂傷ややけど、骨折と同じように、本物の物理的損傷を与え得るのだ。 幼少期のトラウマが脳を物理的に再構成し、生物学的な意味で個人をつくり変えてしまう、主要な2つのメカニズムを、以下に紹介しよう。 ■1. トラウマは、身体と脳を恒常的な厳戒態勢に置く 繰り返し脅威にさらされると、子どもの身体と脳は、否応なしに適応を強いられる。こうした場合、真っ先に反応する身体機能の一つが免疫系だ。 ご存知の通り免疫系の主な機能は、高リスクと知覚される状況で私たちを守ることだ。該当する状況は通常、病気やけが、感染、ウイルス、細菌といったものだが、ストレスフルな状況も含まれる。免疫系は、こうした多岐にわたる脅威をどれか一つでも感知すると、いつでも反応できるよう態勢を整える。 しかし幼少期に虐待やネグレクト、あるいは不安定な環境が常態化していると、免疫系が活性化した「臨戦態勢」が維持される。身体は、こうした長期的環境ストレスにうまく対処できない。具体的、局所的、短期的な脅威に反応するようにはいかないのだ。恒常的な脅威には、恒常的な警戒が必要となる。 免疫系は、自身が常にリスクにさらされていると認識するため、常にフル稼働の状態となる。化学的シグナル、具体的には炎症関連分子を産生し、身体を感染症や負傷から守ろうとするのだが、その産生量が過剰となるのだ。 回復させるべき身体的損傷がないため、この炎症関連分子の過剰生産は慢性炎症につながる。トラウマ経験者では驚くべきことに、当該の体験から数年、さらには数十年を経ても、炎症マーカー分子のレベルが高いままであることが、先述した2022年の研究からわかった。 これらの炎症関連分子は通常、血流に乗って必要な箇所に運ばれる。健康な人の場合は、血液脳関門(BBB)によって炎症関連分子が脳に侵入することを防ぐ。だが、トラウマへの曝露が長期化すると、炎症関連分子が血液脳関門を通過しやすくなることがある。 その結果、炎症関連分子が本来到達するはずのない脳内に侵入し始める。いったん血液脳関門を突破すると、炎症関連分子は重要な神経機能に干渉するようになる。これにより、子どもの気分や記憶、注意力に悪影響が及ぶのだ。 特に重要なのは、子どもが絶え間なくトラウマにさらされ続け、「もう安全だ」というメッセージを身体がずっと受け取れないままでいると、こうした厳戒態勢の長期化によって、深刻なメンタルヘルスの問題を発症する可能性があることだ。そして重篤なケースでは、知覚された脅威への対処として、脳の物理的構造が変化し始める。



