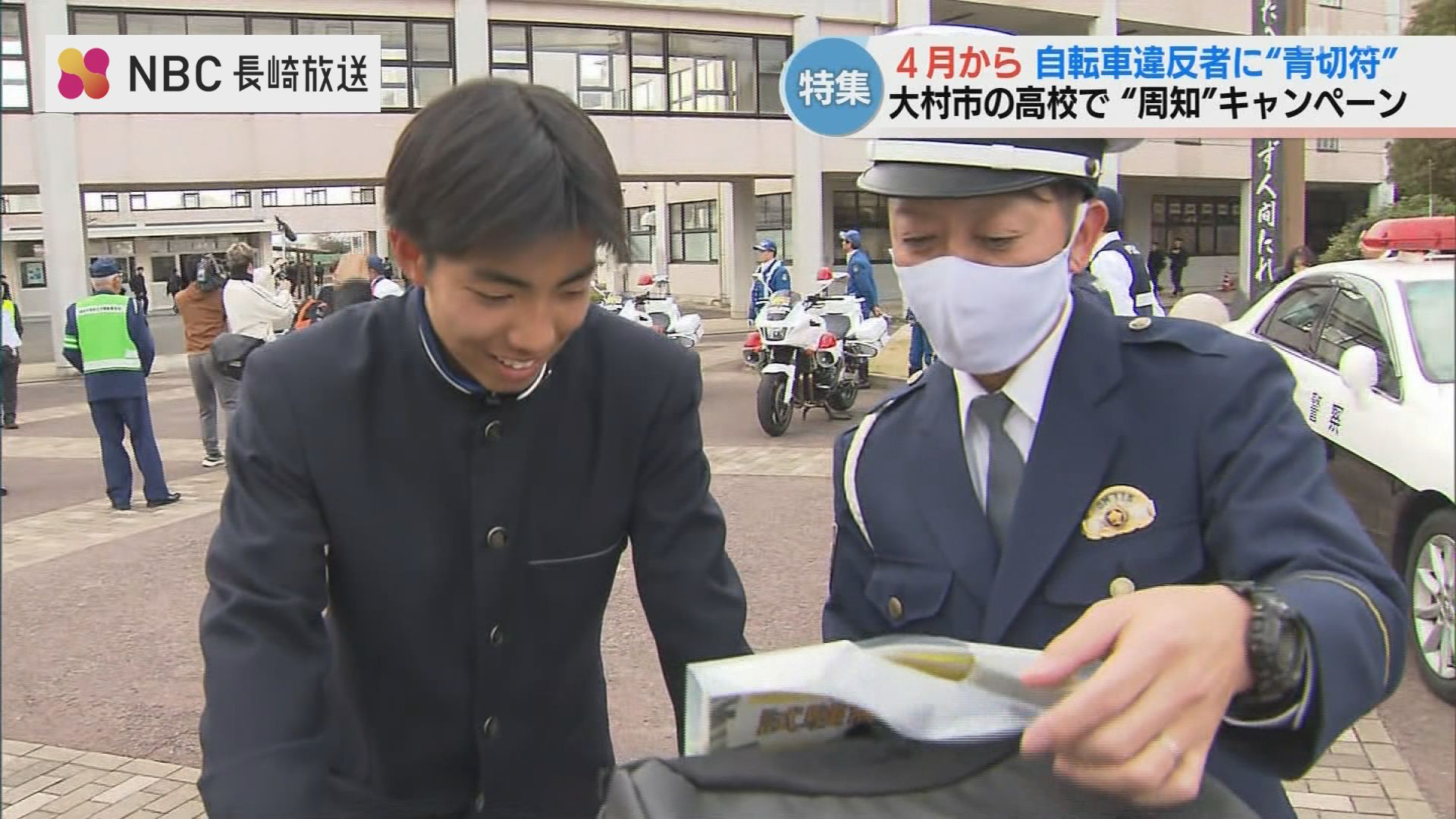AIが書いた怪談小説が面白い 2分に1本のペースで出力されるのは驚異的

最新のAIで書いた短編小説の出来が良いと話題になっています。AIによる小説執筆がどこまで進んだかを紹介します。 【もっと写真を見る】
最新のAIで書いた短編小説の出来が良いと話題になっています。SNS(X)でバズっていたのが、花笠さんの「AI怪談」です。7月7日にnoteにアップロードした「3週間で100話の良質なAI怪談を生み出した手法とプロンプトについて」という作成テクニックを解説した記事が人気を集めました。グーグルの「Gemini 2.5 Pro」を使って作成されたショートショートはどれも完成度が高く、普通に読めてしまいます。AIによる小説執筆がどこまで進んだかを紹介します。 怪談の短編小説、3週間で100本 花笠さんは、6月から約3週間で100本ものAI生成したAI怪談をnoteに投稿しています。それぞれは約2000字の短編で、内容もバラエティに富んでいます。例えば、「黒い夢」は2~3メートル先しか見えない暗闇を進み続ける夢の先に待ち受けている老人との意外な出会い、「心霊写真」では生成AIを使って亡くなった息子の心霊写真を作り続けた夫婦の悲劇、「AI面接─ラストバトル」ではAIデバイスを使って企業面接を受けると相手の面接官もAIデバイスを用意し、その性能バトルに発展する様子がユーモラスに描かれています。 品質も高く、オチもちゃんとあるため、引き込まれてしまいます。AIが作成したとの情報がなければ、人間が作成したかどうかはすでに区別がつかないレベルです。 花笠さんは、ホラー系の画像を定期的にXに投稿しているホラー好き。その延長線上で、ホラーの短編小説を作るプロンプトを作っていったそうで、その生成された結果に“唖然”としたそうです。「あまりに好み。あまりに面白い。短い文章の中に伏線を張り、にやりと、ほろりと、ゾクッとする感情を、見事に描き出すのです」(花笠さん)。そのために生成するのをやめられなくなり、100話のAI怪談を投稿するまでに至ったとか。また、「本業で何冊もエンタメ書籍をプロデュース」する経験を持つことから、「私が読んでも、ちゃんと、面白い」と紹介されています。 公開されたプロンプトで作ってみた ところが、公開したAI怪談には、ほとんど反響もなかったそうです。そこで作って楽しむ人がもっと増えないかと、プロンプトの公開とその解説に踏み切ったということでした。AI怪談の100話目「※この話はAIのハルシネーションです」は、それ自体がプロンプトになっています。 このプロンプトは、100話の試行錯誤のなかで作成されたと思われる様々な工夫が凝らされています。テーマを「恐怖」だけでなく、「滑稽さ」「皮肉」「哀愁」「切なさ」に広げたり、「自分の身にも起こるかもしれない」と感じさせるリアリティラインの遵守、読者への問いかけといった安易な結末の回避といったものが細かく設定されています。それにより、幅の広い優れた短編が出てくるように練られています。 この花笠さんのプロンプトを使い、実際にグーグルのGemini Pro 2.5に小説を書いてもらいました。タイトルは「代筆」。AIにアシスタントとして執筆作業を手伝ってもらっていたフリーライターが、使用する過程でその本音を学習されてしまい、AIに追い込まれていってしまうという展開です。文字数は約2200字で、生成にかかったのは2分程度。本文にはまったく手を加えていない状態ですが、展開からオチまできれいにまとまっており、AIの執筆能力が上がっていることを実感できます。 今年1月にChatGPT-o1で長文小説が書けることを紹介しましたが、現在はこうした能力はあまり強くサポートされていないようです。4oやo3で試してみたのですが、文字数は1400字と指定よりも少なめにしか書かないことが多く、文章の品質的にも面白さはイマイチという印象でした。また、現在は、以前のように長文小説を一度に生成させることは難しくなっているようです。(参考:AIの書いた小説が普通に面白い ChatGPT「o1」驚きの文章力) Anthropic「Claude」は文章力が高い 一方で、日本語の文章の作成能力が高いと言われているのが、Anthropicの「Claude 4(クロード)」です。Gemini Proよりもさらに繊細で、なめらかな文章を書いてくれます。 花笠さんのプロンプトを使い、心霊写真とAIのようなものを混ぜたテーマを指定して1作品「学習データの向こう側」を作成してみました。存在しないはずの女性が、AIを使うことによって日常世界の中にじわじわと侵入してくる感じはゾクッとする展開になっており、唸らされました。あまりに面白かったので、続きを書いてもらったりしたのですが、短編にもかかわらず、次々に犠牲者が出ていく過程が、和風現代ホラー感をうまく表現しており、続きを興奮しながら読みました。 Claude 4は文章の生成が非常にうまく、他のAIではまだ実現されていない文体表現の機能も持っています。例えば、「1980年代の日本の田舎町を舞台」の小説の冒頭を書かせてみました。「村上春樹風」、「司馬遼太郎風」、「藤沢周平風」などと指定すると、それなりにその作家に似た雰囲気の文章を出してくれます。特に、司馬遼太郎風はその土地についての説明から入る事が多い特有の文体の癖がよく出ているように感じました。 さらに文章を読み込ませて、文体学習をさせることができます。試しに、筆者の過去のこの連載記事を5本読み込ませ、Claudeに筆者の文体の癖を解説させたところ、筆者の文体には3つの特徴があるとしてきました。そのうえで、筆者の文体で、この冒頭の文章を書き直させてみたのですが、筆者の記事向けの文体では、小説といったものはあまり向かないということでした。まあ、技術解説記事が大半だからですね。 しかし、「代筆」をこの連載風の文章に書き直させたところ、なかなかうまい文章を書き上げてきました。この連載風に「AIライティングアシスタントの深層学習が引き起こした異常事態 TypeFlowとの3週間検証レポート」というタイトルをつけてきました。全体的な文章も、あくまで筆者風にとどまるのですが、それでも、なんとなくこの連載のノリで出力されるのは面白いところです。 さらに、Claude 4の優秀さを感じさせるのが、この記事を元にして、ノベルゲーム風の会話のやり取りに変換してほしいと指示したところ、それもすぐに出力してくれたところです。地の文で解説していた文章は、田中と佐藤というキャラクターを登場させ、対話形式のセリフへと変換することで、スムーズな流れで物語が進行するようにしています。ベースとなる物語の骨子ができあがれば、コンテンツとしての応用はかなり自由にできますね。 2分で1本の小説が書けるのは驚異的 ただし、AIによる文章がうまいからといって小説として面白いかどうかはまた別の話です。そして、さらに読んでもらえるのかというのも、さらに高いハードルがあります。 小説はそもそも読むために高い注意力を求めるのに、最初の段階ではすぐに面白いかどうかがわからないため、なかなか関心を持ってもらうこと自体が難しいメディアです。私自身も、「AIが書いた」というのはアピールにならないと感じています。個人的にも、よほど評価を集めた作品でなければ積極的に読みたいとは思いにくいです。人間はAIが作ったものより、同じ人間が作ったものに惹かれるという側面は明確にあると思います。 AI単体による小説執筆の能力は確実に上がってきていますが、まだ足りません。花笠さんの100本のAI怪談も、個々の短編はちゃんとまとまっていて、実際おもしろいのに、筆者の場合は、何十本も読もうという気持ちまでにはなりませんでした。星新一氏のショートショートのように、今でもなんとなく読み始めると、文庫本の短編を最後まで次々に読んでしまうような読書体験までは得られません。まだ、乗り越えなければならない質的な差が存在するのだろうと思われます。急激に発展していますが、今後さらにAIが発展していくことで、その溝が埋まってくるのかは、今の時点ではわかりません。 それでも、“読める”レベルの物語を、2分に1本というペースで出力できることは驚異的です。今後は、100本生成して、その面白さを評価させて優れた数本だけを残していくことで質を確保していくというような、これまでと違う小説の書き方も登場してくるのかもしれません。 筆者紹介:新清士(しんきよし) 1970年生まれ。株式会社AI Frog Interactive代表。デジタルハリウッド大学大学院教授。慶應義塾大学商学部及び環境情報学部卒。ゲームジャーナリストとして活躍後、VRマルチプレイ剣戟アクションゲーム「ソード・オブ・ガルガンチュア」の開発を主導。現在は、新作のインディゲームの開発をしている。著書に『メタバースビジネス覇権戦争』(NHK出版新書)がある。 文● 新清士