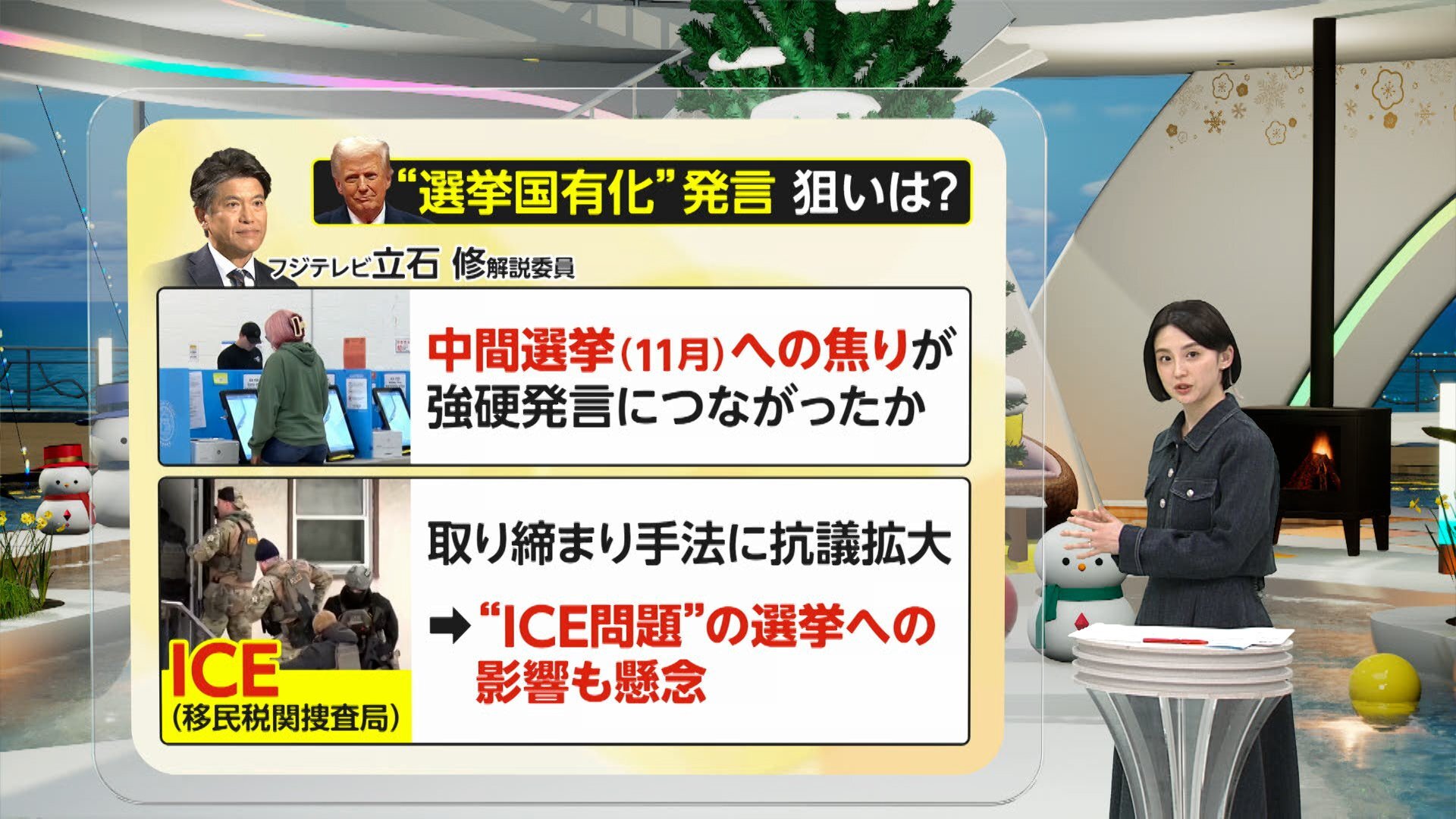イースター島のモアイ像、人々は労働命令ではなく自律的に作っていた

かつてのイースター島は、今よりよっぽど持続可能で平和的な社会だった。
世界遺産となっているイースター島のラパ・ヌイ国立公園にあるモアイ像。約900体あるという謎多き巨大な石像の製作方法については、たくさんの研究がされてきました。新たな研究で、モアイ像がどうやって太平洋のこの孤島(チリから約3,700km沖)に並んでいるのか、これまでの仮説が覆されるかもしれません。
モアイ像とは?
モアイ像は、13世紀にポリネシアの人たちによって彫刻されたと考えられています。最大で高さ20m、重さ90トンにもなる巨大な像を彫り、その上運搬までとなると、ものすごく高度な技術です。こうした作業が何らかのしっかりとした管理体制なしに行なわれたとは想像しにくいのですが、PLOS One誌で発表された研究では、実際に階級的な管理体制ではなかったのではないかと示唆されています。
ラパ・ヌイには、階層的な組織に代わる洗練された仕組みが存在したことを示しています。労働は命令ではなく、自律的に組織化されていました。
と研究論文の筆頭著者であり、ビンガムトン大学人類学教授のCarl Philipp Lipo氏が米Gizmodoにメールで語っています。
古代の技術が現代のテクノロジーで明らかに
Lipo氏の研究チームは、モアイ像が多数ある採掘エリア「ラノ・ララク」で1万1000枚以上の画像をドローンで収集しました。その後、その画像に2D画像を重ね合わせて、構造・運動解析フォトグラメトリーを用いて、遺跡の3Dモデルを作成。ラノ・ララクには、さまざまな製作段階のモアイ像が数百体ありますが、モデルの分析によるとここは30の異なる採掘ゾーンが存在し、それぞれが明確な境界を持つ独立した採掘エリアとして機能していたことがわかりました。
Image: Lipo et al., 2025, PLOS One独立した作業区画には、岩盤を最初に切り出す段階から仕上げの彫刻に至るまで、制作工程全体が各ゾーン内で完結していたことを示す証拠があったとのこと。分析ではさらに、ゾーンごとに製作技術、モアイ像の比率、様式的特徴に違いが見られ、独自の伝統が異なる社会集団によって維持されていたことがうかがえたそうです。
これは、すなわちモアイ像の制作が中央政府によって統括されていたわけではなく、小さなコミュニティが自主的に作業を進めていたということになります。
ラパ・ヌイの歴史を再考
研究結果は、モアイの製作がこれまで理解されていたラパ・ヌイの人々の姿に合致していることを示しています。考古学的証拠から、このラパ・ヌイの社会は政治的に統一されていたのではなく、小規模で自立した家族集団から構成されていたとみられています。
各採石ゾーンは、拡大家族(※)あるいは領域コミュニティが自律的に作業していたことを示しているようです。実験考古学によると、運搬に必要な少人数(18〜20人)は、拡大家族の規模と完全に一致します。
(※)拡大家族…核家族(夫婦と未婚の子ども)に、祖父母や親族などが同居、または密接に交流する家族形態
とLipo氏は述べています。
階層に頼らず協力できる社会だった
同時に、この研究はラパ・ヌイ社会が1600年頃に崩壊したという長年の説を覆す証拠の一つにもなっています。島全体の森林消失や未完成のモアイは、人口が資源を使い果たし衰退した証拠と解釈されてきましたが、今回の研究では違う視点が出てきています。Lipo氏は以下のように説明しています。
今回のラノ・ララクでの発見と我々が過去25年間行なってきた研究で、ラパ・ヌイの歴史の流れについて従来の考え方を大きく変える必要があることがわかりました。これまでラパ・ヌイ社会は一度繁栄したあと急に衰退し、崩壊したと説明されてきましたが、実際には島の人たちはずっと状況に合わせて適応しながら、社会を続けていたのです。ラノ・ララクの未完成のモアイ像は、突然何か大きな災害が起きて作業が止まったわけではなく、単に日常的な採石作業の途中段階を示しているだけなのです。
この研究が持つ重要性は考古学の範囲を超えて、人間がどのように協力し合い、どんな仕組みで社会を作り上げるのかという根本的な問題にも光を当てている点にあります。Lipo氏によると、今回の成果は人類は階層組織に頼ることなく、大きな仕事を達成できること、また社会が力で統制されなくても、持続可能で平和的で、しかも文化の豊かさを保ちながら発展していくことができるのだということを明らかにしているのです。