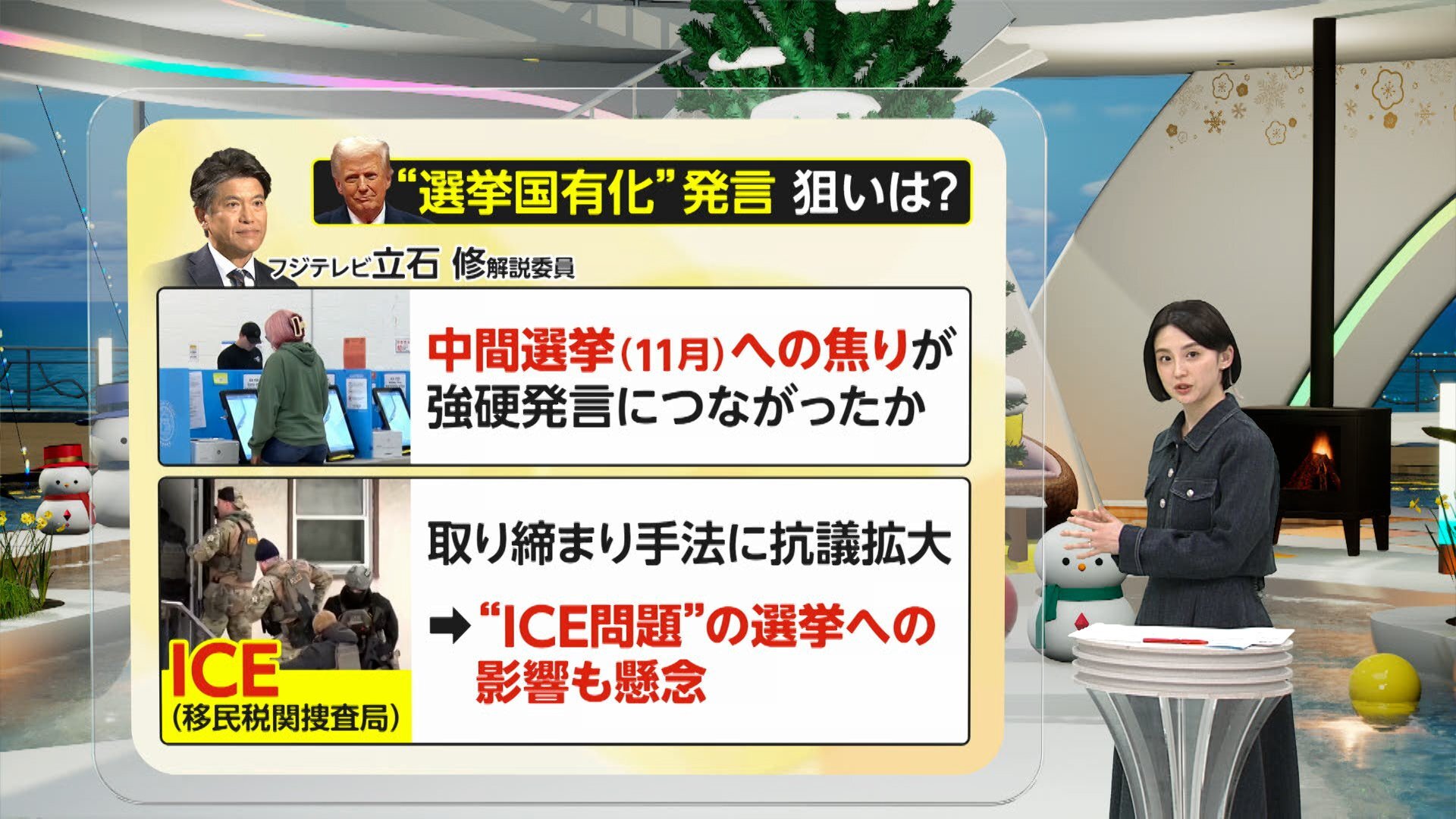橘玲「ハーバード大学がやっていることはトランプの主張と同じ」 『ティッピング・ポイント』が暴く“リベラルの欺瞞”

アメリカを蝕むオピオイド中毒、新型コロナウイルスの感染爆発、なぜハーバード大学には「女子ラグビー部」があるのか? 『超新版 ティッピング・ポイント 世の中を動かす「裏の三原則」』(飛鳥新社、以下本書)は、一見、無関係に思える数々の出来事を、ある一つの法則で鮮やかに解き明かしていく。
「ティッピング・ポイント」は、ある小さな変化が一定の条件下で急激に加速、拡大する際の境界を指し、「転換点」「限界点」とも訳される。薬物中毒の蔓延も、感染症の世界的流行も、特定犯罪の急増も、富裕層の子女たちが次々と自殺する謎めいた事件もーーその原因は、本書によれば「ティッピング・ポイントを超えてしまったから」だ。
著者でジャーナリストのマルコム・グラッドウェルは2000年の著作でティッピング・ポイントの理論を世に広め、25年後の今年、続編として本書を上梓した。日本社会や世界情勢が「転換点」を迎えつつある今、本書は私たちにどのような示唆を与えてくれるのか。解説を担当した作家の橘玲氏に語ってもらった。(島袋龍太)
本来ならハーバード大学はアジア系だらけ?
ーー本書はティッピング・ポイントを切り口に、新型コロナウイルスの感染爆発をはじめ、さまざまな社会的事象を分析していく構成です。橘さんが特に印象に残ったエピソードはありますか。
橘玲氏(以下、橘):ハーバード大学のアファーマティブ・アクションと、アメリカのオピオイド危機の2つでしょうか。
ーーハーバード大学のアファーマティブ・アクションの章では、2023年にアメリカ最高裁判所が下した違憲判決と一連の裁判が扱われています。
橘:発端は、ハーバード大学の入試におけるアファーマティブ・アクションに対して、「アジア系学生を差別している」という訴訟を白人の保守派団体が支援したことです。黒人やヒスパニックが優遇され、アジア系の学生には不当に高い合格ラインが設けられているという訴えでした。
裁判に提出された資料によれば、たしかに人種間で合格ラインに差がありました。しかも、アジア系が合格するには、2400点満点の試験でヒスパニックより270点、黒人より450点高い点数を取る必要があった。2400点満点中の450点ですから、あまりにも極端な差です。白人保守派が「アファーマティブ・アクションは黒人やヒスパニックの特権であり、逆差別だ」と主張すると、「レイシスト」のレッテルを貼られます。“有色人種”であるアジア系を矢面に立てることは渡りに船だったのでしょう。その結果アメリカ最高裁が、大学入試における人種を考慮したアファーマティブ・アクションは違憲であるとの判決を下しました。
しかし著者のグラッドウェルは、ハーバード大学のアファーマティブ・アクションは人種マイノリティではなく、むしろ白人を優遇していると喝破します。この洞察は非常に鋭いと思いますね。
ーー本書はハーバード大学がアファーマティブ・アクションを隠れ蓑にして、白人学生が多数派になるように人種の比率をコントロールしていたと指摘しています。
橘:入試でのアファーマティブ・アクションを実施していないカリフォルニア工科大学では、アジア系学生の比率は約45%にのぼります。対してハーバード大学では、ごく最近まで白人学生の比率は50~60%程度で推移していました。入試の点数だけで学生を選抜すると、特定の人種の学生数が圧倒的多数になってティッピング・ポイントを超え、大学の文化やキャンパスの雰囲気が変容するのをおそれているのです。
「アメリカの理想のキャンパス」であるべきハーバードをはじめアイビーリーグの大学にとっては、アジア系学生ばかりになることはどうしても避けたいでしょう。だから、アファーマティブ・アクションやスポーツ推薦などの制度を巧妙に組み合わせることで、黒人やヒスパニックに配慮しているように見せかけながら、白人学生が多数派になる操作を行なっていたわけです。
ーー本書では、ティッピング・ポイントを超えないための意図的な操作である「ソーシャル・エンジニアリング」についても取り上げています。
橘:ハーバード大学のアファーマティブ・アクションは、ソーシャル・エンジニアリングの分かりやすい例です。しかもこの「人種による選別」を、レイシズムを批判するリベラルが率先して行なっている。これはもちろん欺瞞ですが、「白人中心主義の傲慢」と切って捨てられない面もある。
共同体のなかでマイノリティの比率が急激に増えると、既存の秩序が崩れて分断や治安悪化を招くおそれがあります。アメリカでは、黒人をはじめとしたマイノリティの大規模な移住をきっかけに、白人の住人が生まれ育った街を捨てる「ホワイトフライト」が古くから社会問題化していました。最近でも、シリコンバレーのパロアルト周辺では、中国系の住民が増えすぎて白人の転出が相次いでいるといいます。しかもこれは、差別意識による転出というよりも、中国系の子どもたちの成績が良すぎて、白人の子どもたちが劣等感でドロップアウトしてしまうというのが理由のようです。そうした事例を踏まえると、一定の多様性は確保しつつ、白人中心のキャンパスを恣意的な操作で維持しようとするのは、理解できなくはありません。
ーー多様性を確保するためのアファーマティブ・アクションが、白人の地位を温存するために用いられているのは皮肉ですね。
橘:ハーバード大学がやっているのは、「ここはアメリカの大学なのだから、アメリカファーストで学生数を調整するのは当然だ」ということですから、トランプの主張と同じです。ただしリベラルはその事実を受け入れられないので、アファーマティブ・アクションを自己正当化に使ってきた。その矛盾をトランプ政権に攻撃されるのは、当然だと思います。
リベラルの論理でいえば「マジョリティはマイノリティに資源を分配すべき」となるわけですが、そこには「どこまで分配すればいいのか」や「誰に分配すべきか」といった問題が付いて回ります。
アファーマティブ・アクションについても、どの人種をどの程度の比率で合格させるかを決めるのは容易ではありません。完全な平等が実現できない以上、どこかで欺瞞を孕みます。しかしリベラルは、自分たちのわずかな過ちすら認めようとせず、綺麗事のスローガンで糊塗してきたので、その矛盾が露呈すると大きな反発を喰らってしまいます。第二次トランプ政権以降に顕著になった多様性(ダイバーシティ)に対するバックラッシュは、リベラルの側にも原因があります。
「解決できる問題は、すでに解決されている」
ーー本書では、昨今、アメリカで社会問題化している処方鎮痛薬のオピオイド中毒の蔓延についても分析しています。
橘:オピオイド中毒の蔓延は、米製薬大手のパーデュー・ファーマによるオピオイド系鎮痛薬「オキシコンチン」の販売がきっかけです。しかも、極めてごく一部の医師と営業担当者がスーパースプレッダー(超感染拡大者)となって、史上類を見ないOD(オーバードーズ、薬物の過剰摂取のこと)危機を巻き起こしてしまいました。
この問題も経緯は複雑です。もともと、オピオイドは慢性疼痛などへの処方を目的にしていました。特定の原因がないのに体に痛みが続く慢性疼痛は治療が困難で、患者のQOLを著しく低下させます。オピオイドはがんのターミナルケアのように完治の難しい痛みを緩和するのに有効で、1990年代には疼痛の専門医などを巻き込んで、オピオイド系鎮痛薬の規制緩和を求める社会運動が起こっています。
ーー適切に摂取すれば依存性の少ない薬剤だったわけですね。
橘:その意味では一概に否定できるものではありません。ただし、どんな薬剤も乱用されるリスクはありますし、パーデュー・ファーマの過剰な販売戦略がオピオイド依存症の蔓延を加速させたということもあるでしょう。
話がさらに複雑になるのは、パーデュー・ファーマが批判を受けて、乱用を防ぐためにオキシコンチンを改良していることです。依存症者たちは、従来型のオキシコンチンの錠剤を砕いて鼻から吸引していました。そのためパーデュー・ファーマは、グミのように粘度が高くて砕けない錠剤を開発したのですが、それによって蔓延が収まったかといえば、結果は真逆です。オキシコンチンを乱用できなくなった依存症者たちは、ヘロインよりもさらに強力な合成オピオイドのフェンタニルが混入したストリートのドラッグを摂取するようになり、ODによる死亡者数が全米で激増してしまいました。
ーー昨今、アメリカでのフェンタニルの蔓延がよく報道されています。
橘:グラッドウェルも本書のなかで「オキシコンチンの中毒のほうがマシだった」と嘆いていますね。フェンタニルには粗悪品も多く、「史上最悪の麻薬」とも呼ばれます。たしかに、主に密売で流通しているフェンタニルよりも、処方薬であるオキシコンチンのほうがはるかにマシです。しかし、パーデュー・ファーマがオキシコンチンを改良しようとしたときに「そんなことをしたら状況がさらに悪化する」と制止できた人物がいたでしょうか。
ーーなかなか答えの出ない問いですね。
橘:それが本書の魅力かもしれません。現代社会は複雑なので、世の中は解決できない問題で溢れています。そもそも、解決できる問題であれば、すでに解決しているはずです。解決の難しい問題が、どのような経緯や対立のなかで生まれてきたのかを知るうえで、本書はよい教科書になるのではないでしょうか。現代社会の仕組みや争点を理解できる一冊だと思います。
■書誌情報 『超新版ティッピング・ポイント 世の中を動かす「裏の三原則」』 著者:マルコム・グラッドウェル 翻訳:土方奈美 価格:2,500円 発売日:2025年6月5日
出版社:飛鳥新社