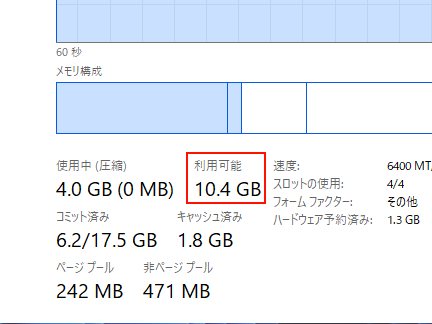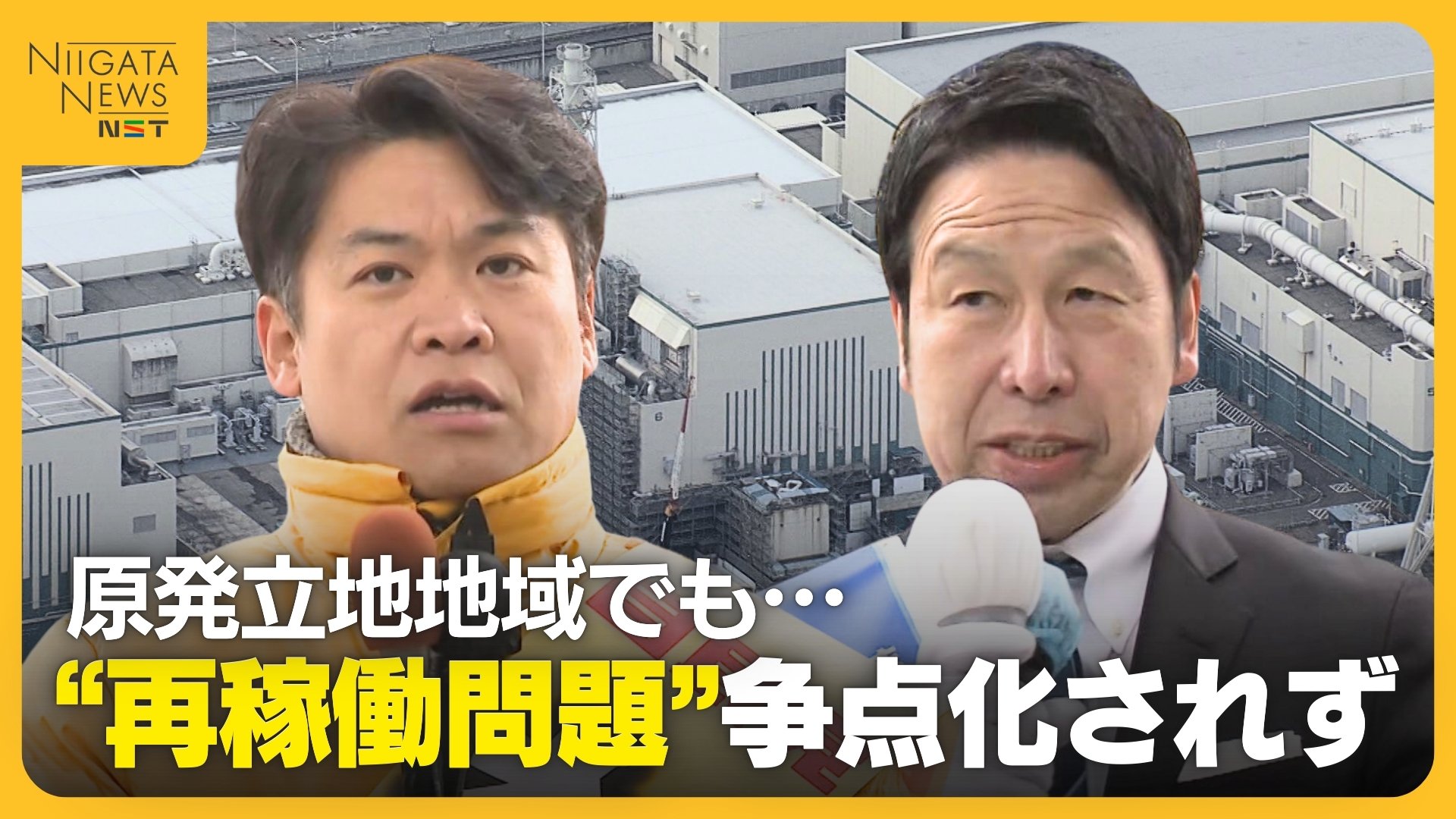「コンデジ復活」は本当なのか?(ITmedia NEWS)

他方でレンズ交換できないながらも、ボディの質感や独特の写真の仕上がりを武器に、ハイエンドカメラとして再起動しようという動きも出てきている。 24年発売の富士フイルム「X100VI」は、アナログの操作感を前面に押し出し、撮影する高揚感を演出した。同社の強みであるフィルムテイストで撮影できる機能も、それを後押しした。市場価格30万円超えの高級機だが、写真上級者を中心に大ヒット商品となった。 フィルムカメラの時代には、普段は一眼レフを使うプロも、サブカメラとしてコンパクトカメラを常用した人も多い。OLYMPUS XAなどは、そうした時代の名器である。こうしたポジションにハマった、とも言える。 さらに富士フイルムが今年仕掛けた「X half」は、35mmフィルムを半分使って2倍撮影できた「ハーフカメラ」をデジタル的に再現したことで、こちらもまた爆発的なヒット商品となった。もちろん操作感だけでなく、撮影された写真もフィルムテイストだ。 ソニーが今年8月に発売した「RX1R III」は、前作から実に9年半という時を超えて復活したコンデジだ。単焦点レンズにフルサイズセンサー、市場想定価格は66万円前後という、もはやコンデジなどと気軽に呼んではいけないウルトラハイエンドモデルである。どれぐらい売れているのか気になるところだが、発売間もないこともあってまだデータは出ていないようだ。 これらの高級カメラは、若い人が背伸びして買うものではなく、定年や引退した人が「一生もの」として買うカメラ、ということだろう。筆者も引退したら、残りの人生を楽しむため、最後にいいカメラを買いたいという気持ちはある。言い換えれば、Leica以外にも選択肢ができた、ということである。 こうしてみると、昨年から今年の「コンデジ復活」は、複数の要因が絡み合って生まれたトレンドであり、今後このまま伸び続けると見るのは危ういように思える。特にレトロブームにおける「エモい」文脈は水ものであり、いつ収束してもおかしくない。 Vlog路線は堅調だが、これはコンデジでなくても構わない。コンパクトミラーレスも好調だし、アクションカメラやDJI Osmo Pocketなどもこの文脈に入ってくる。むしろ拡張性がないコンデジ路線は次第にウケなくなるとも考えられる。 一方で金銭的余裕のある人をターゲットとしたレトロハイブランド路線は、堅調に推移するものと見ていいのではないだろうか。毎年新モデルを投入して数を捌く商売から、1モデルを何年もかけて丁寧に売っていくという商売への転換は、合理性よりもめんどくさいお作法が存在する方がやりやすい。何がいいのかわららないという人には、レンズの埃を拭いながら、「いや、これはわかる人にしかわからんのです」でいいのだ。 この答えは、あと2~3年で出るのではないだろうか。
ITmedia NEWS