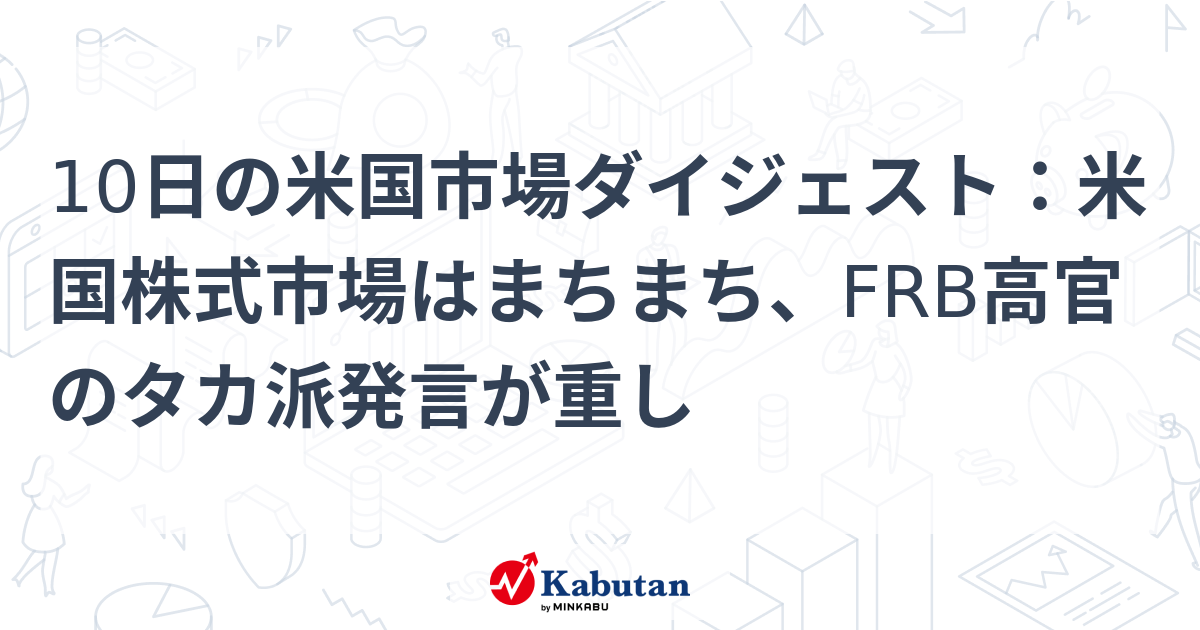コラム:米国経済次第の日銀利上げ、中立金利が意外に高くなる可能性=門間一夫氏

[東京 7日] - 消費者物価の前年比上昇率は、日銀の目標値である2%を41カ月連続で上回っている。物価で機械的に判断すれば利上げは待ったなしである。それでも日銀が利上げをしばらく休止しているのは、米国経済の下振れリスクが気になっているからだ。
米国経済は今のところ堅調である。しかし、米国企業が駆け込み輸入で対応したからという面もあり、トランプ関税の悪影響が出てくるとすればこれからだ。実際、日銀の植田和男総裁は10月3日の講演で、今後の見通しは「米国経済の展開によって大きく変わる可能性がある」とし、最近の米国雇用者数の変調にも警戒感をにじませた。日銀が米国の動向を気にするのは、それ次第では国内企業が「物価上昇を賃金に反映させる動きが弱まる可能性がある」(植田総裁)からである。
一方、9月の金融政策決定会合では、2名の政策委員が利上げを主張した。そのうち高田創委員は「2%物価目標はおおむね達成された」との認識を示した。その認識はおそらく間違いではないと思うが、あと2-3カ月待てば、来年の賃上げがどうなりそうかもわかってくる。その間に米国経済に関する追加情報も蓄積される。
そんなメリットがある「2-3カ月待ち」もできない場合があるとすれば、物価の上振れリスクが喫緊の課題という場合だろう。実際、9月会合で利上げを主張したもうひとりの田村直樹委員は、「物価の上振れリスクが膨らんでいる」ことをその理由とした。しかし、物価には下振れリスクもあるというのが植田総裁の認識であり、田村委員とは温度差がある。
<高市トレードで大幅円安なら利上げ>
自民党総裁選の結果が10月利上げに与える影響は微妙である。新総裁となった高市早苗氏は「金融政策に責任を持つのは政府」として、政府・日銀の緊密なコミュニケーションを求めている。新政権の発足が今月中旬とすると月末の日銀会合までにあまり日がなく、それは10月利上げの確率をさらに低下させる要因となる。その一方、高市トレードで円安が大きく進めば、植田総裁も物価の「上振れリスク」を重視せざるをえなくなる。物価高への国民の不満は大きく、円安は高市政権にいきなり打撃となりかねない。円安を止めるための利上げなら高市氏も容認するだろう。
以上を総合すると、10月29-30日の会合で利上げが決まるかどうかは微妙である。ただ、いずれにせよ遠くない将来に日銀が利上げに向かう可能性は高い。最近の長期金利上昇は、そういう市場の認識を反映している面がある。だとすれば次の焦点は、日銀がどこまで利上げを進めるかである。
<米国次第で日本の中立金利は2%に>
政策金利が最終的に落ち着く水準は「中立金利」と言われる。中立金利とは、景気に対して刺激的でも抑制的でもない金利水準のことである。物価目標が安定的に達成された状態なら、それ以上の緩和も引き締めも必要ないので、政策金利は中立金利の水準で据え置かれることになる。だから中立金利は、長期金利の適正水準を考えるうえで大事な概念だ。
ただ、中立金利は直接観察できず、推計するにしてもその誤差は大きい。そのため日銀は、中立金利を1-2.5%と広いレンジで捉えている。現在0.5%の政策金利について、少なくとも中立金利下限の1%までは上がると市場は見ているが、その先は誰にもわからない。
日銀が示すレンジの上限付近、すなわち2%程度まで上がるという見方は今のところ少ない。しかし、「日本経済は強くないので金利もそんなに上がらない」という予断は持たない方が良い。そもそもここまでの利上げも、日本経済が強くなったから行われたというわけではない。日銀が利上げを始めた理由は、世界的なインフレと、それがもたらした海外金利の上昇および円安である。日本経済とは関係ない。
したがって今後も、日本の金利を大きく左右するのは、世界とりわけ米国のインフレ圧力や金利動向である。米連邦準備理事会(FRB)は9月に利下げを再開した。インフレが総じて落ち着いたままで利下げが今年、来年と順調に進むなら、為替はドル安・円高に向かい日銀の利上げは限定的となるだろう。
しかし、筆者はどちらかと言えば、米国のインフレ圧力は意外に根強いのではないかと見る。その場合、FRBは年内あと1-2回の利下げができたとしても、来年の利下げは進まなくなる。下手をすれば利上げに転じる可能性もあり、ドル高・円安圧力が強まる。
日銀の2%物価目標がおおむね達成されつつある中で、強い円安圧力が加わった場合、日銀はこれまで利上げに慎重であった分も含めて、来年以降は足早の利上げを余儀なくされる。気がついてみたら中立金利は2%、となる確率はテールリスク(可能性は低いが起きれば影響が大きいリスク)というほど小さくはない。
<設備投資増加と人手不足が米国のインフレ圧力に>
では、米国のインフレ圧力が根強いと考えられる理由は何か。活発な設備投資と労働力不足である。米国では人工知能(AI)の開発や活用がブームの様相を呈しており、テック大手の「GAFAM」を中心にデータセンターなどの設備投資が急増している。その波及効果で電力インフラなど周辺分野にも投資が広がる。
さらに、トランプ政権の国内回帰方針のもとで、製造業の設備投資が全般に押し上げられていきそうだ。関税が米国内での生産を促す方向に働くうえ、関税交渉の過程で日本、欧州連合(EU)、韓国などから巨額の対米投資を取り付けた。
一方、トランプ政権は移民の統制を強化している。建設業、農業、食品加工業など移民への依存度が高い産業を中心に、人手不足への懸念が高まっている。先月には南部ジョージア州にある韓国系の自動車用バッテリー工場で作業員が不法就労の疑いで拘束されるなど、外国人就労への制約も強まっている。こうした外国人材受け容れの厳格化も、人手不足に拍車をかける可能性がある。
短期的には労働市場悪化のリスクが意識されており、それがFRBによる利下げ再開の主たる理由である。しかし、やや長い目でみた場合、設備投資を促す政策と労働供給の制約を強める政策の組み合わせは、根強いインフレ圧力につながる可能性が高い。加えてグローバル市場の分断、地政学リスクの高まり、地球温暖化の影響など、2020年代に入って明らかになった世界的なインフレ圧力は、今後も構造要因として残るとみられる。
FRBは中立金利を3%程度とみており、それに比べると現在の政策金利水準(4-4.25%)はかなり高い。そのことも利下げ再開の一因である。しかし中長期的なインフレ圧力の根強さが顕在化してくれば、3%近辺まで利下げを進めるのは難しいだろう。結果的に中立金利の水準は切り上がり、もしかするとそれは4%に近いかもしれない。
ただし、今の議論の前提となる人手不足の先行きについては、不確実性が大きいことも確かである。最大の不確実性は、AIが全体として米国経済にどのような影響をもたらすかだ。前述の通りAIブームは旺盛な投資需要をもたらしているが、一方でAIの活用が人員の削減につながる面もある。若年層の採用環境が厳しくなっているなど、既にその兆候が見られるとの指摘もある。移民政策の影響などがあったとしても、全体として人手がむしろ余剰気味になっていく可能性も否定できない。
底流にあるグローバルなインフレ圧力は今後もあまり変わらないとして、そこに加わる製造業強化、移民政策、AIブームという3つのトレンドが米国の総需要と総供給のバランスをどう変えていくのか。それが米国の中立金利に影響し、ひいては日本の中立金利を大きく左右することになる。
編集:宗えりか
*本コラムは、ロイター外国為替フォーラム向けに執筆されたものです。筆者の個人的見解に基づいて書かれています。
*門間一夫氏は、みずほリサーチ&テクノロジーズのエグゼクティブエコノミスト。1981年に東京大学経済学部を卒業後、日本銀行に入行。86年に米ウォートンビジネススクール留学。調査統計局長、企画局長を経て、12年に日銀理事(13年3月まで金融政策担当、以降、国際担当)を歴任。16年に日銀を退職し、みずほ総合研究所エグゼクティブエコノミスト。21年4月から現職。
*このドキュメントにおけるニュース、取引価格、データ及びその他の情報などのコンテンツはあくまでも利用者の個人使用のみのためにコラムニストによって提供されているものであって、商用目的のために提供されているものではありません。このドキュメントの当コンテンツは、投資活動を勧誘又は誘引するものではなく、また当コンテンツを取引又は売買を行う際の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。当コンテンツは投資助言となる投資、税金、法律等のいかなる助言も提供せず、また、特定の金融の個別銘柄、金融投資あるいは金融商品に関するいかなる勧告もしません。このドキュメントの使用は、資格のある投資専門家の投資助言に取って代わるものではありません。ロイターはコンテンツの信頼性を確保するよう合理的な努力をしていますが、コラムニストによって提供されたいかなる見解又は意見は当該コラムニスト自身の見解や分析であって、ロイターの見解、分析ではありません。
私たちの行動規範:トムソン・ロイター「信頼の原則」, opens new tab
筆者は「Reuters Breakingviews」のコラムニストです。本コラムは筆者の個人的見解に基づいて書かれています。