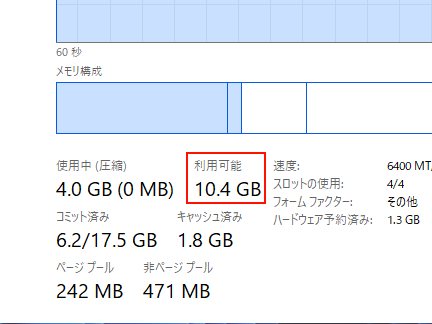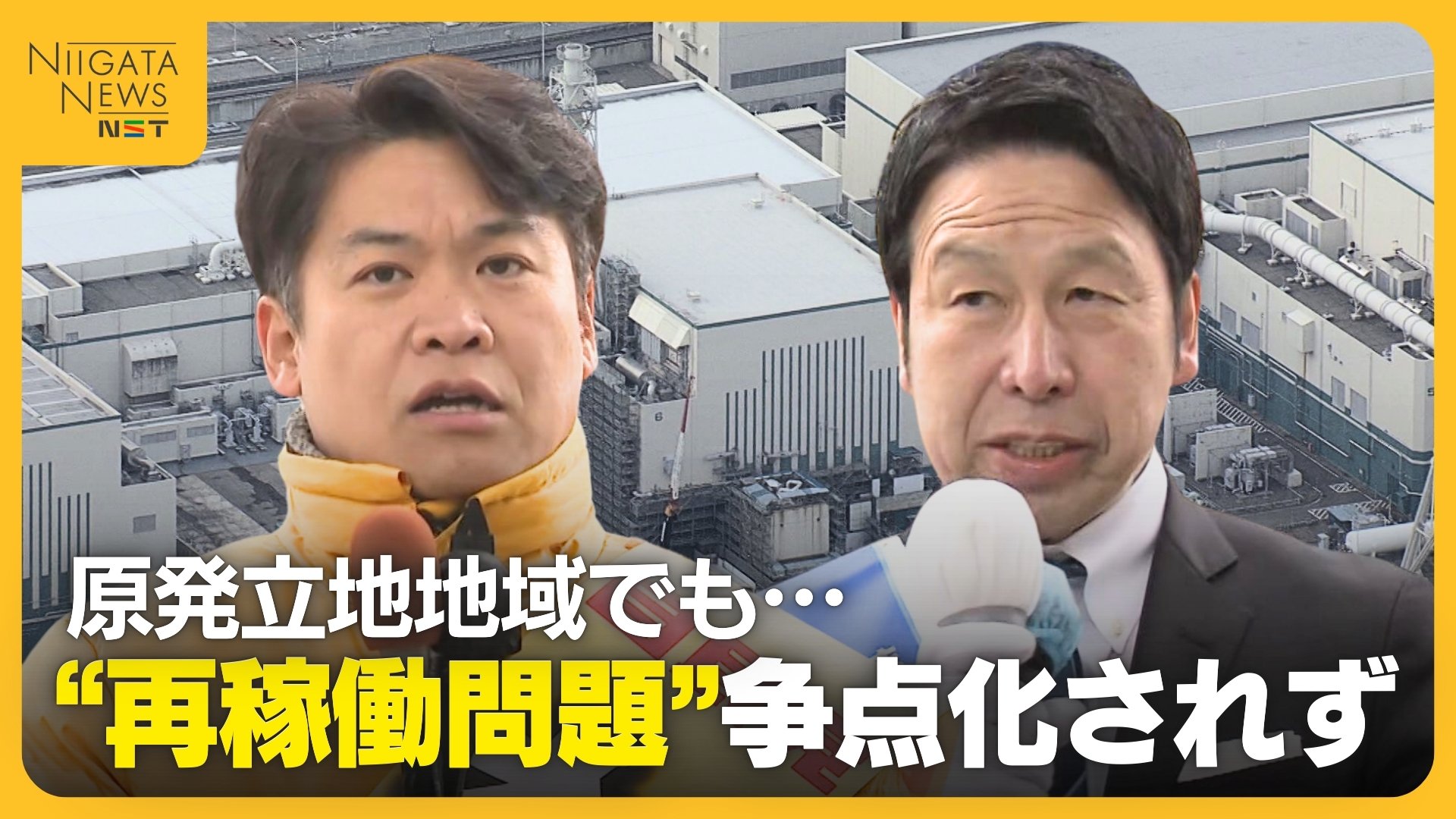AIで生産性は上がるのに、なぜ社員の“やる気”は下がるのか?(TBS CROSS DIG with Bloomberg)

■生産性向上の罠 今、AIやデジタル技術の活用がビジネスのあらゆる分野に広がっている。その中でも生成AIは、仕事の効率を飛躍的に上げる切り札として、大きな期待を集めている。 【写真を見る】AIで生産性は上がるのに、なぜ社員の“やる気”は下がるのか? 資料作成からデータ分析、お客様対応まで、AIを業務に積極的に活用することにより、従来の作業プロセスが効率化され、働き方は根本から変わろうとしている。 多くの会社の経営者がAI導入によるコスト削減と業務効率化に期待を寄せている。 しかし、現場で働く個人にとっては、必ずしも良いことばかりではない。 ここに「生産性向上の罠」とでも呼ぶべき矛盾がある。 たとえば、AIを活用して8時間かかっていた仕事が6時間で終わるようになったとしよう。 その結果として生まれる2時間の余裕は、果たして個人のゆとりや創造的な活動に使えるのだろうか。 多くの会社では、その空いた時間に対し、すぐに新しい仕事が割り振られるのが現実ではないだろうか。 生産性を上げた結果、労働時間は変わらず、むしろ仕事の量が増え、密度が高まるという状況は、従業員のやる気を削ぐ。 これは、AI導入が本来目指すべき「より価値の高い仕事への転換」という理想を意味のないものにしてしまいかねない。 本レポートでは、AI活用による業務効率化が進む中で、従業員の労働時間や仕事量にどのような変化がもたらされるのか、組織は生み出された余裕時間をどう活用すべきかという課題を取り上げる。 生成AIが実際に驚くほどの生産性向上をもたらすという事実を学術研究のデータを使って客観的に説明したうえで、この「生産性向上の罠」を乗り越え、AIと人間が本当に共存共栄するための組織のあり方について考察する。 ■AIは本当に生産性を上げるのか? スタンフォード大学とマサチューセッツ工科大学の研究チームが発表した論文「GENERATIVE AI AT WORK」は、実際の職場で生成AIがもたらす効果を5,172人の従業員データから分析した研究である。