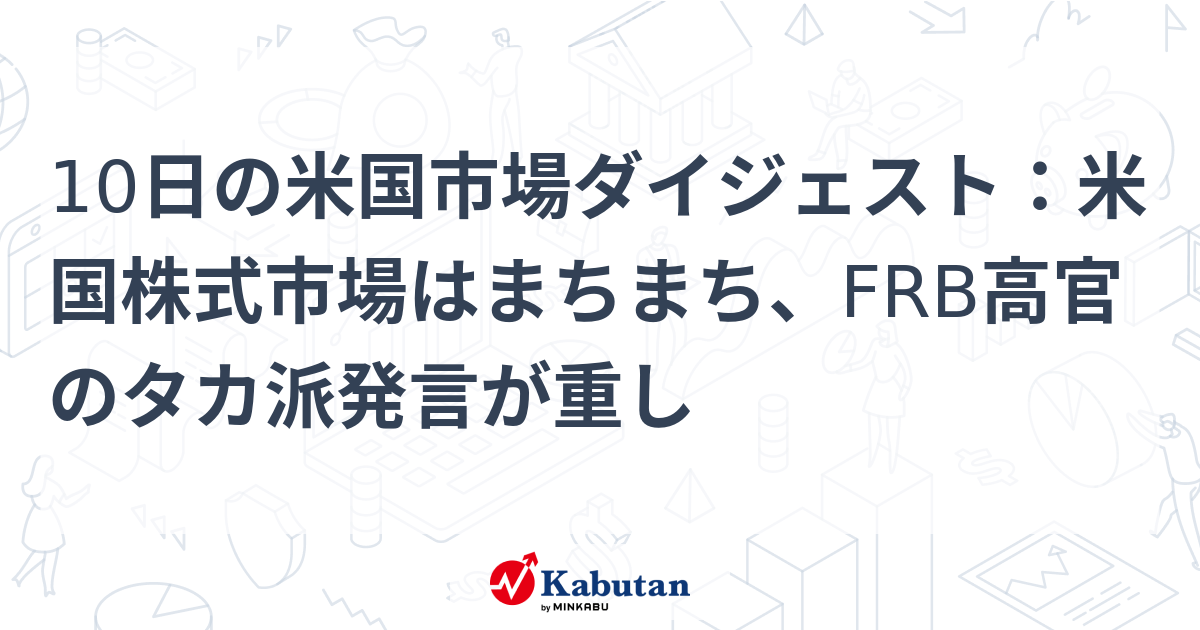「高市トレード」って何、円安・株高・債券安の一辺倒に実はあらず

自民党総裁選で高市早苗前経済安全保障担当相が予想外の勝利を収めたことを受け、為替・株式・債券の各市場で「高市トレード」と呼ばれる動きが再び注目を集めている。
株式では景気刺激策への期待から上昇が見込まれる一方、円安と超長期金利の上昇(価格は下落)が同時に進むとの警戒も広がり、さっそく6日の日本市場で動きが見られた。ただ、「高市トレード」は必ずしも円安・株高・債券安の3点セットだとは限らない。いったい何を意味し、どのような投資心理が背後で働いているのだろうか。
なぜ市場が反応したのか
総裁選前の市場では、報道各社や海外予測市場の情報を材料に小泉進次郎農林水産相の勝利が有力視されていた。小泉氏は財政規律を重視し、日本銀行の政策正常化を後押しするとみられており、投資家の間では利上げを意識したポジションが広がっていた。
一方で、高市氏は安倍晋三元首相の「アベノミクス」路線を継承し、財政支出や減税などを通じた景気刺激を重視、利上げには慎重な立場を取る。このため、金融緩和を志向する高市氏が予想外に勝利したことは、市場にとって織り込みの反動を伴うサプライズとなった。
「高市トレード」とは
「高市トレード」とは、高市氏の政策スタンスを手がかりに、為替・株式・債券が連動して動く市場の反応を指す。 典型的な形は、円安・株高・債券安(長期金利上昇)の3点セットだ。
同氏が掲げる緩和的な金融・財政政策が意識されると、景気刺激策への期待から株式が上昇し、国債は増発懸念で超長期債が売られ、日銀の利上げ観測が後退して円安が進むという構図が描かれる。
明確な定義はあるのか
高市氏の政策スタンスが変化すれば、市場の反応も変わるため、実は明確なルールや数値基準はない。「アベノミクス相場」などと同様に、市場参加者が高市氏の政策スタンスを手がかりに相場を語る際の略称的な表現として使われているにすぎない。
そのため、時期や状況によっては円高や株安など、異なる反応を含めて語られる場合もある。つまり「高市トレード」という言葉自体が円安・株高・債券安を意味するのではなく、市場心理を映す柔軟な概念といえる。
どんな市場の反応があったのか
6日の東京外国為替市場では円が約2カ月ぶりの安値となる150円台に下落した。日経平均など主要株価指数は史上最高値を更新し、景気刺激的な政策への期待が株式相場を支えた。
一方で、債券市場では財政拡張への思惑が強まり、超長期国債に売り圧力がかかった。短期金利との差が広がり、利回り曲線(イールドカーブ)がより急になる「金利スティープ化」が進んだ。スワップ市場が織り込む10月利上げ確率は5割強から2割程度に急低下している。
今後の焦点は
高市氏の政策がどこまで実行されるか、また誰が財務相に就任するかなど、政権運営次第で市場の反応は変わる可能性がある。財政規律を重視する人事が行われれば債券市場は落ち着くが、積極財政が進めば超長期金利が一段と上昇する展開もあり得る。
「高市トレード」は、政策への期待と警戒のバランスの上に成り立つ。高市氏の政策スタンスや日銀の対応が変われば、相場の方向は逆転する可能性もある。アベノミクスを想起させる政策と、財政拡張への懸念が交錯するもろはの市場現象として、各種政策への思惑や期待の持続性、実現可能性を含めて当面の市場の衆目を集めることになりそうだ。
— 取材協力 Issei Hazama