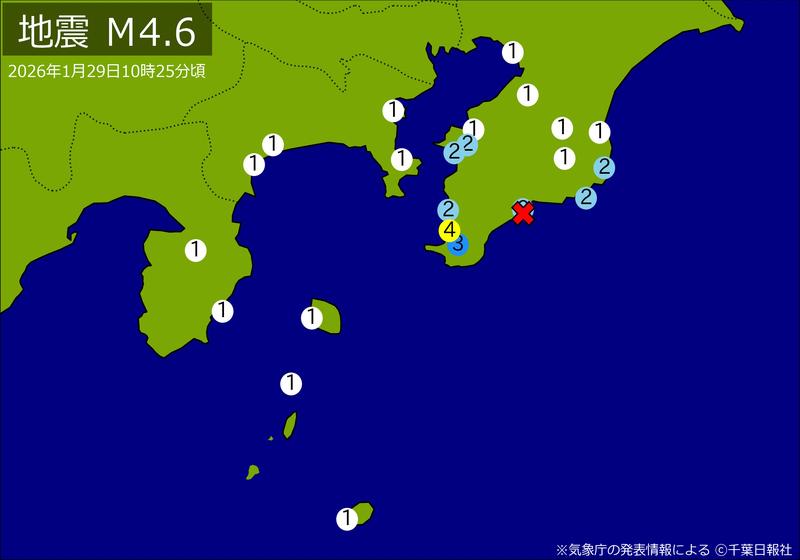「迷わず列車を止める」の理念裏腹 JR西日本の「組織にゆがみ」脱線事故遺族の深い憂慮 企業体質は変わったか JR福知山線脱線事故20年㊦

「緊張感が足りないのではないか」。JR福知山線脱線事故で妻=当時(62)=と妹=同(55)=を失った浅野弥三一(やさかず)(83)はJR西日本の現状をこう批判する。脱線事故を組織の問題と位置付け、時に遺族の立場を封印して、高次の安全の実現をJR西に迫ってきた。その浅野が今になってまた嘆息するのだ。「もとに戻ってしまったのでは」
繰り返される問題
同社の安全管理体制に疑念を生じさせた近年の事例に、平成29年12月に起きた新幹線のぞみの台車亀裂問題がある。亀裂は破断寸前まで達し、運輸安全委員会が新幹線初の重大インシデントに認定した。
複数の関係者が異音や異臭に気づきながら3時間以上も運転を続けた。「列車を停止させる必要が本当にあるなら相手がいってくるだろう」。運輸安全委の報告書は判断を他人任せにする「相互依存」があったと指摘。異常に接しても平穏を保とうとする心理傾向「正常性バイアス」が働いた可能性にも言及した。
JR西はのぞみのトラブルの反省から、同社の安全指針である「鉄道安全考動計画」に「迷わず列車を止める」の文言を盛り込み、これが経営陣のメッセージだと強調することで、社員の意識改革を促した。
だが問題は繰り返された。令和5年1月、京都を中心に起きた大雪トラブルがそれだ。「10年に1度」といわれた大寒波を前に、JR西は計画運休を行わず、降雪の見込みが基準値以下だとして融雪器も作動させなかった。結果、東海道線の一部区間で電車15本が立ち往生、約7千人が最長10時間近く車内に閉じ込められた。乗客の降車判断に躊躇(ちゅうちょ)し、「迷わず-」の理念とは裏腹の事態を招いた。
判断ルール化困難
「乗務員判断でいろいろやれというが、運転指令が『待て』となったらどうするのか。こちらには運転士と車掌しかいないのに」。JR西の40代の男性運転士が率直に明かす。
現場で直面する状況は千差万別である以上、運行停止の判断をルール化することは困難だ。「迷わず止める」の理念はいい。だが現場任せでも、指示待ちでもいけない。
「一人一人の能力、組織的な対応力が落ちていると感じる。リスクとは何かを常に考え、そのためにどうするかを考える組織にならないといけないのに」。浅野は、経営層と現場をつなぐ中間の機能に特に問題を感じているという。鉄道事業者とは人と技術によって成り立つ一つのシステムだ。「そのゆがみがまた大きくなっているのでは」といぶかしむ。
浅野は、JR西が脱線事故後に国土交通省航空・鉄道事故調査委員会に情報漏洩(ろうえい)を働きかけた不祥事で、有識者らで構成する検証メンバー・チームに名を連ねた。
またJR西の「安全フォローアップ会議」にも参加。事故の遺族と加害企業の幹部が同じテーブルで安全性向上を議論するというわが国初ともいわれた会議体で、誰よりも同社の企業体質と向き合ってきた。
安全フォローアップ会議が報告書をまとめたのがちょうど11年前。浅野はその末尾に「こんな事故は二度と惹き起してはならない、と叫びたい」(原文ママ)と書いた。
その叫びはなお、切実な響きを失っていない。(敬称略)
=おわり(秋山紀浩、黒川信雄、原川真太郎)